詳報 働き方部会の中間まとめ案
中教審の学校における働き方改革特別部会は、11月28日の第8回会合で、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)」(案)を出した。教員の長時間労働の是正や多忙化の解消に向け、国、教委、学校が取り組むべき方策を示した。主な内容は次の通り。
■国が取り組むべき方策
国に対しては、学校・教師が担うべき業務の範囲を具体的に示した上で、その業務の範囲を学校現場や地域、保護者が共有できるよう、学校管理規則のモデルを作成するよう求めた。また、学校・教師が主として担う必要のない業務に関しては、責任の所在も明確に示すようにする。
教委・学校における業務改善の事例を収集・周知し、研修などで活用しやすいような配慮もしながら、全国の教委・学校の業務改善の取り組みを促す。また、教委における学校の業務改善の取り組み状況については、実効性を担保するために、市町村別の実施状況の公表も検討する。
文科省には、教職員の業務量を一元的に管理する部署を設置する。今後、同省が学校に新たな業務を加えるような制度改正を行う場合は、教職員の正規の勤務時間や人的配置、業務改善の取り組みなどの状況を踏まえ、既存の業務との調整や義務付けの必要性について検証を行い、関係部署と調整する体制を築く。
■教委が取り組むべき方策
教委は、所管する学校に対して、時間外勤務の削減に向け、数値目標も含めた業務改善方針・計画を策定し、PDCAサイクルに基づく業務改善の取り組みを支援する。
「チームとしての学校」として、事務職員の参画をこれまで以上に強化し、学校事務の共同実施などの事務処理の効率化も積極的に行う。また、学校徴収金など、これまで学校が担ってきた業務で、域内で統一して実施できるものは、できる限り市町村や教委が担うようにする。
ICTの利活用による業務の効率化も求められた。統合型校務支援システムを導入するなどし、学習評価をはじめとした業務の効率化、教材の共有化などを積極的に進めていく。
■各学校が取り組むべき方策
管理職は、学校の重点目標や経営方針を策定する際に、教職員の働き方に関する視点も盛り込み、学校全体で取り組む必要があるとした。教職員間で業務見直しを話し合う機会を設けるなどし、校内の業務の適正化を図れるような学校組織の雰囲気づくりも重要だとした。
地域・保護者とも連携を図るよう努め、学校経営方針の共有を図るため、保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する学校運営協議会制度や地域学校協働活動の活用を推進する。
■従来の業務の役割分担の見直し
これまで学校や教師が担ってきた代表的な業務について、各業務の役割分担や適正化、業務改善に関する方策も示した。挙げられた業務は①登下校に関する対応②放課後から夜間にかけての見回りや児童生徒が補導された際の対応③学校徴収金の徴収・管理④地域ボランティアとの連絡調整⑤調査・統計への回答⑥児童生徒の休み時間における対応⑦校内清掃⑧部活動⑨給食時の対応⑩授業準備⑪学習評価や成績処理⑫学校行事の準備・運営⑬進路指導⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応――。
①の登下校に関する対応では、学校が安全指導の観点から通学路の設定・安全点検などを行っており、保護者や関係機関との連携を行う必要性があるものの、登下校時の見守り活動に関しては、必ずしも教師が担わなければならないものではないとした。
通学路における登下校の見守りの日常的・直接的な実施は、基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく、市町村や保護者、地域住民など「学校以外が担うべき業務」であるとした。また、登下校時間についても、教職員の勤務時間を踏まえた合理的な時間を設定すべきとした。
②の夜間などの見回りや、児童生徒の補導時の対応については、地域や学校の実情に応じて、教委が実施の必要性を含め精査した上で、警察や地域ボランティアの協力の下で実施すべきであるとした。児童生徒が補導された際の対応については、第一義的には保護者が担うべきであり、基本的には「学校以外が担うべき業務」だとした。
③の、学校給食費や教材費、修学旅行費などの学校徴収金の徴収・管理は、銀行振込や口座引き落としが増えているものの、依然として手渡しによる例もある。今後は銀行振込・口座引き落としを原則とする。学校給食費については文科省がガイドラインを作成するなどし、全国的に公会計化する方針。未納金の督促も「学校以外が担うべき業務」であり、市町村が担っていくべきだとした。
④の地域ボランティアとの連絡調整については、地域学校協働活動推進員などが中心となって行い、主幹教諭や事務職員を学校側の地域連携担当として校務分掌上に位置付けるなどの対策を行う。
⑤の調査・統計などへの回答業務は、前述のように文科省が負担軽減に向けた精査を行うとともに、関係団体にも理解を求める。
「学校が担わざるを得ない業務」であるが、教育課程の編成・実施や生徒指導など、教師の専門性に深く関わるもの以外の調査については、事務職員が回答するなど、可能な限り「教師以外の者が担うべき業務」だとした。
⑥の児童生徒の休み時間の対応については、安全確保や児童生徒の理解、健康観察などに効果があるため、「学校が担うのが現実的」であるとした。
ただし、休み時間における児童生徒の事故を防止する注意義務については、児童生徒の発達段階や学校の状況等に応じて責任体制を明確にするなどした上で、事務職員や地域ボランティアなどの協力も得ながら、教師は輪番制で対応するなどの負担軽減策を求めた。
⑦の校内清掃は、日本では清掃指導を通じて勤労の意義や奉仕の精神などを学んでいるため、教育的効果があるとしつつ、各学校において合理的に回数や範囲を設定し、地域ボランティアの協力や民間委託の検討なども求めた。
日常的な環境衛生の維持・改善活動は「学校が担うべき業務」ではあるものの、学校環境の日常点検はできる限り教師に行わせないように努めるべきだとした。
⑧の中学校・高校における部活動では、運動部・文化部にかかわらず、教師の負担軽減が必要だとした。
部活動は教育課程外ではあるが、学校教育の一環として、学校の業務と位置付けられるとしつつ、「教師の中には、部活動にやりがいを感じている者もいる一方で、協議等の経験がなく部活動の指導に必要な技能を備えていない教師等が部活動の顧問を担わなければならない場合には負担を感じている」と指摘した。
部活動の顧問については、各校長が教師の専門性や校務分担の状況、専門性の有無などを踏まえ、部活動指導員をはじめとした外部人材の活用を積極的に行う。大会への引率なども責任の所在を明確にし、スポーツ庁が作成する予定の「運動部活動の在り方に関するガイドライン」を遵守するなどした上で、外部人材が担えるようにすべきだとした。
また、少子化により、部活動が維持できなくなっている学校については、複数の学校による合同部活動や、総合型地域スポーツクラブとの連携などを積極的に行う。
教委は、教師の負担軽減だけでなく、生徒のバランスの取れた成長の確保などの観点からも、保護者の理解を得るよう努める。将来的には地域で部活動に代わり得る質の高い活動機会を提供できる体制を整え、部活動を学校単位から地域単位の取り組みに移行させる。
⑨の給食時の対応は、給食指導と食物アレルギーへの対応が求められているが、栄養教諭とも連携し、学級担任の負担を軽減していくべきだとした。また、学級単位の給食指導から、ランチルームなどでの複数学年一斉の給食の提供などの工夫を行うよう求めた。
⑩の授業準備は、教師の本務である授業に必要不可欠であるが、実験の準備や片付け、教材の印刷などは、スクールサポートスタッフなどの活用を積極的に進めるよう求めた。また、ICTなどを活用した、広域での教材や指導案の共有化も求めた。
⑪の、テストの問題作成や採点、通知表や指導要録の作成などの学習評価や成績処理は、「教師が行うべき業務」であるが、提出物や宿題の提出状況の確認、漢字・計算ドリルの丸付けなどの補助的業務はスクールサポートスタッフの積極的な活用を検討すべきだとした。
⑫の学校行事等の準備・運営では、学校行事の企画・運営、児童生徒への指導は教師が担うべき業務だとしたが、準備などが教師の過度な負担とならないよう、精選や見直し、簡素化などを進めるよう求めた。
さらに、本来の教科の学習に相当する内容の一部が学校行事として行われている場合は、積極的に教科の授業時数に含めるべきだとした。
また、学校行事の物品の準備や職場体験活動の受入企業との日程調整、修学旅行の運営などは、事務職員や民間委託などの外部人材が担うべきだとした。
⑬の進路指導では、特に高校の場合、就職先などが多岐にわたり、必ずしも教師がその専門性を持っているとは言い難く、事務職員や民間企業経験者、キャリアカウンセラーなどの外部人材の活用を進めるべきだとした。
⑭の、支援が必要な児童生徒・家庭への対応では、児童生徒が抱える課題が複雑化・多様化しているため、教師の専門性とは異なる、より高度な専門性が求められる。
そのため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、日本語指導の支援員などが中心となって担うべき問題もあるとした。
さらに、保健室登校への対応なども増えているため、養護教諭の負担軽減も検討課題とされた。











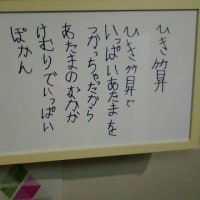






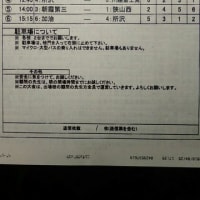
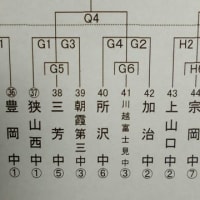
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます