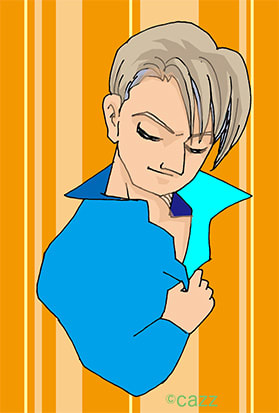『チチ』(ガルバ)の困惑
ハヤトがトヨと共に『神月』にお呼ばれする話が公式になり、ぐんぐんと近づいて行く。
楽しみが膨らむ一歩で、ハヤトはどこかで気が進まなかった。
楽しみなのは家を離れてトヨとしばらく過ごせること。滞在するのはトヨの親戚の経営する旅館らしい。ハヤトには知識はあったが、実際に旅館というものに泊まるといことは初めてだったので、ごくごく普通の6歳の子供としてワクワクする心を抑えられなかった。
それとは反対に、気が進まないのは恐れからだ。神月に常駐しているという正規軍の知識は与えられず、白紙で臨むようにと取りはかられている・・・果たして正体を見破られずにうまくできるだろうか。もしも、できなかったら・・。
ハヤトは認めなかっただろうが、『チチ』が着々と『ハハ』の排斥の布石を打っていることも彼の憂鬱に少しは関係しているのかもしれない。
『チチ』は『ハハ』が廃人であるかのように吹聴した為に、旅支度はトヨと共にトヨの両親によって行われている。4月最後の日曜日、トヨの父と3人で買い物に行き、必要なものを買い揃えた。最初は自分の欲しいものを素直に選ぶことに慣れなかったハヤトだが、次第にあれこれとものを買うことは楽しいと思うようになる。ちなみに費用は『チチ』から渡されていた。デパート内のフードコーナーでトヨの父は何でも食べたいものをおごってくれる。次々と面白い発掘の話を聞かせてくれて、子供達をワクワクさせたり笑わせたりする。陽気で気さくで、それでいて頼もしい。本来の父親というものは、こういうものなのだろうか。
家に帰る前には必ず、トヨの家での夕飯をご馳走になる。トヨの母親が夕飯はカレーしか作れないとハヤトがトヨに言っていたせいかもしれない。それはほぼ事実だった。トヨの母親の料理は『ハハ』のとはヴァリエーションといい味といい比べものにならないことがハヤトにも痛いほどわかる。『ハハ』から料理といえば、あとは朝に目玉焼きを作るくらいだから。
今までトヨと自分の境遇に対して何も感じていなかったハヤトだった。そんなハヤトも考える。
もしこの家族と暮らせるのなら。
次第にこの星の文化、考え方が染み込んできたのだろうか。
『チチ』と『ハハ』と別れて、トヨとその両親と『家族』になる。それは考えただけで気持ちが良い。もちろん、『チチ』とは完全におさらばにはならないんだけれど。
『ハハ』にはもう2度と会うことはなくなるのだ。それもいいかなとハヤトは思うことにする。
痩せた肩や悲しそうに見つめる目を考えまいと思う。
そしてとうとう、トヨの父が入院する妻の為に長期休暇を取った日。
『神月』が翌々日に迫っていた。
「何か、企んでいるのかな。」田町裕子の家の中では、ガルバがつぶやいていた。
一番最初に弁護士が来た時はインターホン越しの対応で済ませたのだ。
それであっさり引き下がったので、大した問題ではないと思っていた。
(注:弁護士が屋敷政則に田町裕子に会った時の経緯を事細かに述べていたのは、相手を煙に巻き有利に進めるための彼流の盛りに盛った嘘であった)
ハヤトの父親の再婚相手に関する弁護士との問題はガルバにとってはそれでもう終わっていた。
しかしすぐに、ハヤトに実の父親が接蝕する問題が浮上した。
ハヤトに直接、接触してくるとは予想外の展開だ。あの男が捨てた妻子に興味を持つ理由が見当たらなかった。もとより父と子の関係などというものは宇宙人類に分かりようがないが、あのような男が原始星人特有の父性愛なる本能を持っているというデータは、皆無だったはず。考えられるとすれば、愚かな所有欲ぐらいだろうか。
「あの弁護士のせいなのか。いったい、あの父親にどんな話をしたのだ?」疑いが生まれた。
そしてとうとう、屋敷政則自身が田町邸に現れる。
チャンスだった。裕子の記憶と彼の記憶を照らし合わせ、さらに二人とも描き変えることもできる。彼がベルを押すことを今か今かと待っていたと言ってもいい。
なのに屋敷は直前で『あの弁護士』に止められ、そのまま彼に連れられて行ってしまった。
「あの弁護士・・・何が目的なのだ?」
再婚した相手との話し合いがまだもつれているのか、というような発想がガルバにあったならば彼も少しは安心できただろうか。
サーチした肉体の素性分析からあの弁護士は宇宙遊民ではないとわかっている。だが
「何かを企んでいるとしか思えない。」
ガルバはこの『果ての地球』に入ってから、初めて不安を持つ。
それは久しぶりに覚える心を鼓舞するジレンマというものだ。
彼は連邦とカバナの抱える様々な事情から極力、目立たないようにしている。カバナ政府、あるいは軍部からの正式な対連邦向けの『不法侵入者』であったならばもっとバックアップがあっただろう。とりあえず、表向けにあるのは彼自身の肉体と道具である子供だけというのは極めて例外的なことだ。しかし、それは彼の目的には沿っている。
屋敷政則自身にとって幸いだったことに、彼は自分の息子がわからなかった。
どっちみちハヤトの父親はハヤトの母親がそのうち殺すから問題はない。
そう安心仕切っていたことが後々、致命的となって帰ってくる可能性もある。
すでにこの星に定着している遊民組織からの何らかの邪魔が入っているとは考えられないか。
そして今日。これが三度目だ。
最初はシルバーの不信な動きをする車。屋敷政則の所有車だ。まだ未明のうちから何回か通り過ぎ、どこかへ消えた。その次は弁護士の黒い高級車。その車は今、路地の角に停車している。
ガルバは振り返り、先ほど起きてきたハヤトを見る。屋敷裕子が作った朝ごはんを食べていた。準備をし、これから登校するのだ。
またハヤトがターゲットなのだろう。ガルバは思案する。
「どうかした?」ハヤトが聞く。下等な原始星人に普通に気遣われたことへのいらだち。
「どうもしない。早く行け。」
しかし、ハヤトは反抗的に『ハハ』にトーストに塗るジャムを求めた。
子供にかいがいしくジャムを塗ってやる屋敷裕子はごく普通の『この星の母親』にしか見えない。このかりそめの母子の心中に全く関心のないガルバにはわからなかったが、『ハハ』の服はいつもの着たきりではなく真新しいものだ。数日ぶりに体も髪も洗っている。
ハヤトはいち早く、それに気がついてそのことを洗面所でタオルを差し出す彼女に告げていた。
裕子と彼の心が弾んで、『チチ』を恐れないのはその所為なのかもしれない。
ガルバはホムンクルスの上から滑り落ち、隣室の小部屋に向かう。
ハヤトが驚いたようにそれを見ている。『チチ』が自力で移動するのを初めて見たからだ。
『チチ』の周りは重力が調整されているので浮いているようにも見える。
「しばらく、邪魔をするな。お前はいつも通りに行動しろ。」
返事を待たずにドアが閉じられる。ハヤトは『ハハ』に肩をすくめ『ハハ』は微笑んで子供を見返す。登校前の平和な光景。
隣室はもともとは四畳半の仏間だ。かつてあった仏壇は屋敷の親のもので今は何もない。
「一度、あの弁護士に・・・ぶつけてみるか。」
ガルバの内部の何かが騒ぎ、一時、彼はその対応に集中する。彼の内部にみっしり詰まった・・・有機物でできた内臓の偽物たち。
不意にガルバの歪んだ体に何かが生じる。穴だ・・・黒々とした深い闇。量子次元が開いたのだ。と、いうことはガルバの奇異に見える肉体の中は機械が次元がみっしりと詰まったワープ装置でもあるのか。
これでは有機人形に過ぎないホムンクルスに乗り込む、ガルバ自身の改造された肉体内部すらも空と言ってもよい。脳も様々な仕掛けで穴だらけなのか。
現れたのは黒々とした影だ。それが床に流れ出て丸く固まる。はるばるカバナリオン・ボイドから運ばれた思念体のボールだ。
『だから、切り貼り屋とかいうペテン師を生かしておけばよかったのだ。』
声ではない、誰かの思考の塊が意見をのべ始める。
『動き回れないお前に変わって色々と雑用をこなすためにだ。失策だったな。』
「あの男はそんなに簡単に動かせる駒ではない。洗脳にも耐性があることは明白・・・何せ、ペルセウスから無傷で帰った男なのだ。」『それが羨ましくて殺したのかな。』
体に穴を開けたままのガルバの口が黙る。図星か。
『話は簡単だ。その弁護士とやらも父親とやらもみんな消してしまえばいいのだ。』
「何でも簡単に排除しろという・・・ここはリオンではないのだ。」
ガルバは苦々しく。「頼んでいた・・・スペアはあるか。」
『ここにな。』バレーボールほどの黒い塊から足が生えてきた。白い子供の足だ。
『この子供は使えないんじゃないのか。』
青白い裸体の子供が畳の上に、ぐったりと横たえられる。目を閉じた顔はハヤトによく似ている。「なんとでもなる。」『我々の協力者たちの命令が行き渡っていれば、上陸部隊はあの子供を黙認するしかないだろう。その隙に・・・お前一人の潜伏ならば容易い。』
「いや、上陸部隊の動きはやはり知っておかなくてはいけない。彼らが探しているもののことは連邦では秘密でも何でもないのさ。」『・・・星殺しか』「連邦はカバナにもあると今も信じているからな」『ボイドに都市を作る条件が星殺しの引渡しだったことは我々貴族の絶対の秘密・・』「だから子供は必要だ。スペアでもなんでも。それと・・・考えがある。ホムンクルスをもう一台だ。」『リオンにいる同胞の人使いが荒いな。』「お互い様だ。」
足から現れたもう一つのそれが床の上に並んで立ち上がると、思念体はガルバへと収まり次元の穴は閉じられた。
「行ってきます。」ハヤトの声がする。
ガルバにではない、『ハハ』に言っているのだ。
「まぁ、原始人だから仕方がない。簡単に愛着を持つとは。」今はまだ目覚めないオビトを見下ろし唇のない口が歪む。
「所詮、あれも捨て駒だ。」