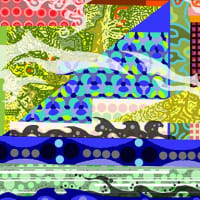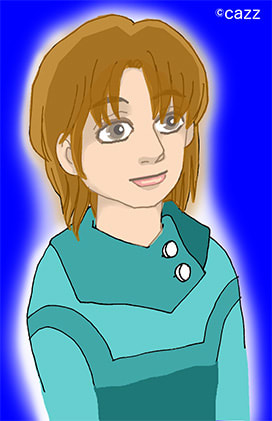
とよ
変わった印象の子供だと思った。
勿論、自分を除いてだけど。
ただし、相手もその小学生にしか見えない外観にもかかわらず自分を子供だとは思っていないようだった。そして最初に会った時から、僕のことも同様に。
「ハヤト君はさぁ。」その『変わった子供が』振り向く。
「遠くからから来たんだよね、それもとてもとても遠くから、ね?。」
「遠く?」
鸚鵡返しすると、ことも無げに空を指差したんでさすがの僕もドキリとした。
「つまり、遠い遠い・・・ズバリ、宇宙、ってこと!。違う?」
「まさか!」反射的に返しながら、僕は自然に見えるように笑う。
「何言ってんだよ、僕は、ずっと君の近所に住んでるんじゃないか。」
「そうだっけ?」「そうだよ、年長さんからずっと一緒だろ。」
「まぁ、ハヤトが望むなら、そういうことにしてもいいけどね。」
もともと相手は6歳にしては言葉が立つ、神童とかささやかれている所以だ。
しかもすごく整った顔をしているという。
僕にはまだこの星の美醜がよくわからないから、判断は保留だ。
大きな目がじっと僕を見返す。
内心の動揺を押し隠すと、僕は手近な石に手を伸ばした。
今は学校の休み時間。どういうわけか、人気者の彼の周りにいたのは珍しく僕だけだった。かしましい幼稚な子供があふれている校庭の端っこで、僕らは並んでしゃがんでいる。互いに捕まえた大きなダンゴムシを競争させることに、さっきまで熱中していたはずなのだが・・・いつの間にこんな展開になったのか。
少なくとも周りからは子どもらしい遊びに興じる二人に見えてるはずだ。
「怒られないかしらね?」横で彼が言う。
「僕にばれたって知れたら・・・新しいお父さんにさ?」
「嫌いだ。あいつ、大嫌い!」つい反射的に答えてしまった。
「大丈夫、僕は誰にも言わないから。」
僕を彼を見る。形のいい口がくっと笑った。
「どっちも、言わない。」
「なんで・・・わかるんだよ?」
否定しなきゃとわかっていた。わかっていたけれど、彼に心を読まれているような気持ちがそうさせなかった。それに。もしも、言ったところで6歳の子供の発言なんて誰が本気にする?そんな確信もある。冗談にすり替えてしまうのも子供にはよくある遊びだ。
勿論、それはオレが『チチ』を嫌いな件の方ではない。
「なんでかな?・・・」彼は老成した表情でうなづく。「お母さんは僕が誰に何をいうのか、心の中でいつも心配しているの。でも、仕方がないよ、わかるんだから。」
それから少し逡巡する。
「何?なんだよ。」
「うーん、あのね、ちょこっとあることがあってさ・・・僕は変わったの。急に赤ちゃんじゃなくなったっていうか、すごく頭の中がすっきりしったっていうのかな。」
「あること?」
「夢の中でね、いや、夢じゃないのかな。現実なんだけど、ある人に会って、知らないけど知っているっていうか・・・うーん、うまく説明できないよ。でもハヤトにはそのうち必ず言う。ちゃんと整理したらね。」はぐらかすように笑った。
「なんだよ。すごく、気になるなぁ。気になるぞ!」
その場でくわしく話を聞きたかったけど、その時、休憩時間の終わりを告げるチャイムが鳴ってしまった。全く小学校とは不自由キマワリない。
「トヨ!ハヤト!遅れんなよ!」何人かが声をかけて、ふざけながら校舎に走っていく。
僕もゆっくりと腰を上げ、背を伸ばした。視線が周りの住宅地から一段低い校庭を囲む桜を撫でる。ここに来て初めて、僕が心から綺麗だと思った花はもう散っていて、若い葉の間から日差しが目を射た。
「あっ。あいつ、またいる。」
それはグランドを囲むフェンスの向こうからこちらを見ている影。葉に隠れているが靴とスーツの色でいつものあの男だということはわかる。たぶん、ちりちりパーマの痩せたメガネだ。
「ロリコンの変態かな?こういう時は普通、先生に言った方がいいんだろ?。」
たぶんこの星では。
「ほっといていいよ。」トヨはちらりとも見ずに肩をすくめた。
「あいつが見てるのはどうせ僕だから。」
「・・・!。そうなの?」さすがに驚いた。それにトヨの平然とした態度にも。
「それで・・・いいの?なんで?怖いじゃないか。」
「別に大丈夫なんじゃない?」スタスタと足早に歩き出した後を追う。振り向けば男はまだこちらを見ている。「だって、登校する時、よく家からついてくるの。そういう日は帰りもついてくる。今のところ、それだけしかしないもん。」
「そりゃ、そういう時は・・・普通は、親に言わなきゃ、ダメなんじゃ?。」この星では。「そうだよ、この星では。」白い歯を見せる。「親に言ったら大騒ぎになると決まってるんだ。学校にも送り迎えするって言い出すし、ハヤトと遊ぶこともできなくなる。そんなの嫌だ。大丈夫、気をつけるから。それに何もできやしないよ、僕にはね。だけど」
鈴木トヨは僕の手を強く引く。
「ハヤトはあいつに近づいちゃだめだよ。剣呑なやつだから。」
「剣呑?」難しい言葉を知っている。
「危険だってこと。・・・やっぱわからないかな。」「剣呑ぐらいわかるよ。」
僕は頭の中にこの星のあらゆる辞書があるんだ。トヨは首を振る。
「違うよ、あいつの持ってるやばい雰囲気だよ。」
僕にはわからなかった。「子供が好きだから・・・やばいおじさんってことなんだろ?」
「血の匂いがする。」吐き捨てるように言った。「あいつからプンプン臭ってくるよ。」
僕は新ためてもう一度、思う。
『やっぱ変なやつ・・・ほんと変わったガキ。』
この星の他の子供と、あまりにかけ離れている。
でも、だから僕は・・『最初、この任務を聞かされて心配した時よりも、実際、退屈してない。退屈するどころか・・こいつといることが楽しいかも』
二人で校舎に続く渡り廊下に戻る。もう周りに生徒は誰もいない。
「ハヤト、いそがなきゃ!」トヨが無造作に僕の手を取る。
僕は久しく他者から触られていなかった。
ただでさえ、僕らは肌と肌が触れ合うことに慣れていない。
並んで走りながら、僕は少し動揺していた。
だけど不思議と嫌ではない。むしろ、暖かい、懐かしい感じがする。
僕たちの世界では失われた感情の1つ。
「遅刻だね、僕ら怒られるのかな?」トヨが階段を登りながら振り向く。
胸の奥がざわつくような不思議な笑みだった。