
「『山猫』でカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞。この時期から晩年は一転して没落する貴族や芸術家を描いた耽美的な作品を多数発表する。特に、クルップ製鉄財閥をモデルとした『地獄に堕ちた勇者ども』、マーラーをモデルにした(トーマス・マンの原作では作家に設定を変えてあるものを作曲家に戻している)『ベニスに死す』、バイエルン王ルートヴィヒ2世を描いた『ルートヴィヒ』は、19世紀後半~20世紀前半のドイツ圏の爛熟と崩壊を遡る形で描いて『ドイツ三部作』と呼ばれファンが多い」。
この三部作を取り上げる前に、ヴィスコンティの映画を語る上で押さえておかなければならないのは、「ネオレアリズモ」という運動です。以下、ウィキペディアから再編集して引用します。
ネオレアリズモ(イタリア語表記:Neorealismo)とは、「イタリアにおいて、1940年代から1950年代にかけて特に映画と文学の分野で盛んになった潮流。イタリア・ネオリアリズムとも言われる。リアリズムの方法で現実を描写する傾向は、当時のイタリアで支配的だったファシズム文化への抵抗として、また頽廃主義の克服として、1930年代ごろすでにあらわれ始めた新たな社会参加から生まれた」。
「知識人は歴史的責任を自ら引き受けなければならず、人々の要求を代弁しなければならないという考え方が、この時期広まっていた。このため、ネオレアリズモの作家・映画人たちは、日常語を模範とした平易で直接的な言語を採用した」。
「ネオレアリズモが確固たる地位を得たのは1943年から1950年にかけてである。この時期はファシズムとナチズムに対する抵抗の時期であり、また戦後の混乱期であった。この間多くの作家が、初めはパルチザン闘争に、次いで政治的議論に関わりあった。パルチザン闘争、労働者の要求、市民の暴動といった主題が、この時期のネオレアリズモ映画やネオレアリズモ文学によく現れる」。
「山猫」(伊語Il gattopardo)(1963年/イタリア・フランス合作映画)
出演:バート・ランカスター、アラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレ

「原作はヴィスコンティと同じくイタリア貴族の末裔である、ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサの長編小説。王制の終焉を迎え、没落していくイタリア貴族を描いた作品で、ランペドゥーサ自身の体験を基に描いたフィクションである。映画では全8章のうち第6章までを取り上げている」。
「第6章の舞踏会の場面が全編のおよそ3分の1を占める。同シーンに貴族の役で登場している多数のエキストラたちは、3分の1が実際のシチリア貴族の末裔たちである。また、スタンリー・キューブリック監督『バリー・リンドン』などと同様、人工の光源を排除して自然光のみで撮影されている。室内での撮影で不足した光量を補うため多数の蝋燭が点火されたが、そのためにセット内は蒸し風呂のような暑さとなった。劇中でキャストがしきりに扇を仰いでいたり、汗に塗れていたりするのは演技ではない」。
「この作品はヴィスコンティのフィルモグラフィーのちょうど中間に位置し、イタリアン・ネオレアリズモの巨匠と謳われたヴィスコンティが初めて貴族社会を取り上げた、後の作品に続く転機となった作品である。また自身の血統であるイタリア貴族とその没落を描いた意味で、『ヴィスコンティが唯一自身を語った作品』と評された」。
「ベニスに死す」(Morte a Venezia)(1971年/イタリアとフランスの合作映画)。
1971年度・第24回カンヌ国際映画祭で、25周年記念賞を受賞した。トーマス・マン作の同名小説の映画化。
出演:ダーク・ボガード、ビョルン・アンドレセン、シルヴァーナ・マンガーノ

「静養のため訪れたヴェネツィア(ベニス)で老作曲家は、ふと出会った少年に理想の美を見出す。以来作曲家は浜に続く回廊を少年を求めて彷徨う。疫病に罹っても尚、死化粧をその顔に施させ、ヴェネツィアの町を徘徊し、やがて疲れた体を海辺のデッキチェアに横たえる。波光がきらめく。満足の笑みを浮かべつつ涙し、化粧は醜く落ちていく…」。
「マーラーの交響曲第5番の第4楽章アダージェットは、もともとは作曲者が当時恋愛関係にあったアルマにあてた、音楽によるラブ・レターである。この映画の感情的表現において、ほぼ主役ともいえる役割を果たした。この映画を鑑賞した、あるハリウッドメジャーの社長は、『今度の新作映画では、マーラーにテーマ音楽を作らせよう』と語ったと言う」。
「原作者トーマス・マンは、この小説を執筆するに当たって、主人公を老作家としていた。しかし監督のルキノ・ヴィスコンティは、原作者の真の意図を汲み、主人公の『グスタフ・アッシェンバッハ』をマーラーらしき人物に『再転換』している。また、同時代の作曲家であり、マーラーと親交のあったアルノルト・シェーンベルク(アルフレッド)をも登場させ、二人の『美』についての論争は、この映画全体に満ち溢れる『対比』の主体軸である」。
「ルートヴィヒ」については、2006年11月2日付の記事「ルードウィヒ/神々の黄昏(原題 Ludwig)」(イタリア、西ドイツ、フランス/1972)で取り上げているので割愛。

ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti、1906年11月2日-1976年3月17日)は、「イタリアの映画監督、舞台演出家、脚本家。華麗で美術性の高い作風が特徴である。難解で高尚で文芸的な雰囲気もある。全盛期の作品は発表当時、映画通の人気が高く、ベストテンのトップあたりに来ることもしばしばだった。映画館の上映の終了時に、試写会でもないのに観客の拍手が鳴り止まない事もあった。イタリア・ミラノの名門ヴィスコンティ家出身の伯爵」。
「裕福な家庭に生まれ、幼少の頃より芸術に親しむ。その身分にも関わらず、イタリア共産党に入党する。30歳よりジャン・ルノワールのアシスタントとして映画製作に携わるようになる。彼をルノワールに紹介した人物はココ・シャネルであった。生涯に渡りバイセクシュアルであることをオープンにしており、アラン・ドロンとの関係の噂もあった。ヘルムート・バーガーに至っては、死後に自らを実質的な未亡人と称したことすらある。父親もバイセクシュアルであったという」。
「愛用の香水は英国のPenhaligon's(ペンハリガン)のHamman Bouquet(ハマム・ブーケ)。ルイ・ヴィトンの鞄を愛用していたが、当時は同社が有名ではなかったので、出演者が勘違いして、『さすがはミラノの御貴族だけある。トランクの生地すらにイニシャル(偶然の一致で同じL.V)を入れてオーダーするとは』と感嘆したという逸話がある」。
「1943年の『郵便配達は二度ベルを鳴らす』で映画監督としてデビュー。この衝撃的なデビュー作は彼が後にロベルト・ロッセリーニらとともにその主翼を担ったネオレアリズモ運動の先駆け的な作品であり、ヴィスコンティはロッセリーニ、ヴィットリオ・デ・シーカなどと共にイタリアン・ネオリアリズモを代表する監督とされる。その後数年は舞台演出、オペラ演出に専心したのち、南イタリアの貧しい漁師たちを描いた『揺れる大地』で映画復帰。このネオレアリズモ期の彼の代表作とされる。この頃に共産党から離党する」。
この三部作を取り上げる前に、ヴィスコンティの映画を語る上で押さえておかなければならないのは、「ネオレアリズモ」という運動です。以下、ウィキペディアから再編集して引用します。
ネオレアリズモ(イタリア語表記:Neorealismo)とは、「イタリアにおいて、1940年代から1950年代にかけて特に映画と文学の分野で盛んになった潮流。イタリア・ネオリアリズムとも言われる。リアリズムの方法で現実を描写する傾向は、当時のイタリアで支配的だったファシズム文化への抵抗として、また頽廃主義の克服として、1930年代ごろすでにあらわれ始めた新たな社会参加から生まれた」。
「知識人は歴史的責任を自ら引き受けなければならず、人々の要求を代弁しなければならないという考え方が、この時期広まっていた。このため、ネオレアリズモの作家・映画人たちは、日常語を模範とした平易で直接的な言語を採用した」。
「ネオレアリズモが確固たる地位を得たのは1943年から1950年にかけてである。この時期はファシズムとナチズムに対する抵抗の時期であり、また戦後の混乱期であった。この間多くの作家が、初めはパルチザン闘争に、次いで政治的議論に関わりあった。パルチザン闘争、労働者の要求、市民の暴動といった主題が、この時期のネオレアリズモ映画やネオレアリズモ文学によく現れる」。
「山猫」(伊語Il gattopardo)(1963年/イタリア・フランス合作映画)
出演:バート・ランカスター、アラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレ

「原作はヴィスコンティと同じくイタリア貴族の末裔である、ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサの長編小説。王制の終焉を迎え、没落していくイタリア貴族を描いた作品で、ランペドゥーサ自身の体験を基に描いたフィクションである。映画では全8章のうち第6章までを取り上げている」。
「第6章の舞踏会の場面が全編のおよそ3分の1を占める。同シーンに貴族の役で登場している多数のエキストラたちは、3分の1が実際のシチリア貴族の末裔たちである。また、スタンリー・キューブリック監督『バリー・リンドン』などと同様、人工の光源を排除して自然光のみで撮影されている。室内での撮影で不足した光量を補うため多数の蝋燭が点火されたが、そのためにセット内は蒸し風呂のような暑さとなった。劇中でキャストがしきりに扇を仰いでいたり、汗に塗れていたりするのは演技ではない」。
「この作品はヴィスコンティのフィルモグラフィーのちょうど中間に位置し、イタリアン・ネオレアリズモの巨匠と謳われたヴィスコンティが初めて貴族社会を取り上げた、後の作品に続く転機となった作品である。また自身の血統であるイタリア貴族とその没落を描いた意味で、『ヴィスコンティが唯一自身を語った作品』と評された」。
「ベニスに死す」(Morte a Venezia)(1971年/イタリアとフランスの合作映画)。
1971年度・第24回カンヌ国際映画祭で、25周年記念賞を受賞した。トーマス・マン作の同名小説の映画化。
出演:ダーク・ボガード、ビョルン・アンドレセン、シルヴァーナ・マンガーノ

「静養のため訪れたヴェネツィア(ベニス)で老作曲家は、ふと出会った少年に理想の美を見出す。以来作曲家は浜に続く回廊を少年を求めて彷徨う。疫病に罹っても尚、死化粧をその顔に施させ、ヴェネツィアの町を徘徊し、やがて疲れた体を海辺のデッキチェアに横たえる。波光がきらめく。満足の笑みを浮かべつつ涙し、化粧は醜く落ちていく…」。
「マーラーの交響曲第5番の第4楽章アダージェットは、もともとは作曲者が当時恋愛関係にあったアルマにあてた、音楽によるラブ・レターである。この映画の感情的表現において、ほぼ主役ともいえる役割を果たした。この映画を鑑賞した、あるハリウッドメジャーの社長は、『今度の新作映画では、マーラーにテーマ音楽を作らせよう』と語ったと言う」。
「原作者トーマス・マンは、この小説を執筆するに当たって、主人公を老作家としていた。しかし監督のルキノ・ヴィスコンティは、原作者の真の意図を汲み、主人公の『グスタフ・アッシェンバッハ』をマーラーらしき人物に『再転換』している。また、同時代の作曲家であり、マーラーと親交のあったアルノルト・シェーンベルク(アルフレッド)をも登場させ、二人の『美』についての論争は、この映画全体に満ち溢れる『対比』の主体軸である」。
「ルートヴィヒ」については、2006年11月2日付の記事「ルードウィヒ/神々の黄昏(原題 Ludwig)」(イタリア、西ドイツ、フランス/1972)で取り上げているので割愛。

ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti、1906年11月2日-1976年3月17日)は、「イタリアの映画監督、舞台演出家、脚本家。華麗で美術性の高い作風が特徴である。難解で高尚で文芸的な雰囲気もある。全盛期の作品は発表当時、映画通の人気が高く、ベストテンのトップあたりに来ることもしばしばだった。映画館の上映の終了時に、試写会でもないのに観客の拍手が鳴り止まない事もあった。イタリア・ミラノの名門ヴィスコンティ家出身の伯爵」。
「裕福な家庭に生まれ、幼少の頃より芸術に親しむ。その身分にも関わらず、イタリア共産党に入党する。30歳よりジャン・ルノワールのアシスタントとして映画製作に携わるようになる。彼をルノワールに紹介した人物はココ・シャネルであった。生涯に渡りバイセクシュアルであることをオープンにしており、アラン・ドロンとの関係の噂もあった。ヘルムート・バーガーに至っては、死後に自らを実質的な未亡人と称したことすらある。父親もバイセクシュアルであったという」。
「愛用の香水は英国のPenhaligon's(ペンハリガン)のHamman Bouquet(ハマム・ブーケ)。ルイ・ヴィトンの鞄を愛用していたが、当時は同社が有名ではなかったので、出演者が勘違いして、『さすがはミラノの御貴族だけある。トランクの生地すらにイニシャル(偶然の一致で同じL.V)を入れてオーダーするとは』と感嘆したという逸話がある」。
「1943年の『郵便配達は二度ベルを鳴らす』で映画監督としてデビュー。この衝撃的なデビュー作は彼が後にロベルト・ロッセリーニらとともにその主翼を担ったネオレアリズモ運動の先駆け的な作品であり、ヴィスコンティはロッセリーニ、ヴィットリオ・デ・シーカなどと共にイタリアン・ネオリアリズモを代表する監督とされる。その後数年は舞台演出、オペラ演出に専心したのち、南イタリアの貧しい漁師たちを描いた『揺れる大地』で映画復帰。このネオレアリズモ期の彼の代表作とされる。この頃に共産党から離党する」。












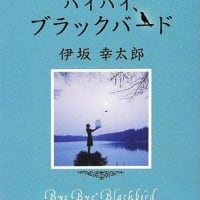







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます