
主な登場人物は、失踪したた広瀬ゆかり、かつて担任だった元教師・波多野和郎、元妻・手塚雅子、その母映子、都内の名門校・敬愛女学園の創設者・故金子英隆、その娘・故夏江、彼女の女婿・故金子美篤(よしあつ)、現理事長でその息子・英明、現学園長・神山節雄、学園の常務理事・池辺忠賢(ただまさ)、その運転手・大森幸生、学園の元経理部長・角田良幸、神山学園長の秘書・木村美紀。
読んでいてまず思ったのは、登場する関係者同士の連絡が実にとり難いストーリー展開だな、ということ。思えば、平成になっての作品といっても16年前。携帯電話がない時代なのです。携帯電話が普及するのは、1990年代の後半からなんですね。ウィキペディアに、携帯電話と文学作品の関係について次のように記述されています。
「『電話番号さえ知っていれば、いつでも携行者と直接話せる』機械である携帯電話の出現により、少なからぬフィクション作品のジャンルは、その描写に大きな変化を余儀なくされた。例えば推理小説やサスペンスなどの多くでは、外界との連絡が絶たれた状況で惨劇が発生するのが常であるが、手元に携帯電話があれば少なくとも、外部の誰かに連絡を取る事は出来るからである――通話のための電気と電波が確保出来ていればの話ではあるが」。
「それとは逆に、『離れている恋人や家族同士が、日常の様々な場所から互いを確かめ合い(時にはすれ違い)語り合うための道具』として携帯電話が登場するシーンは、現在では小説・漫画・映画・ドラマといったジャンルを問わず、すでに当り前のものとして広く受け入れられている。また、新たなツールが世に登場した時は常にそうであったように、近年では携帯電話にまつわる新たなホラー・怪談といったものも登場している」。
作品としては楽しめました。ただ、16年の時の経過がこのミステリーを少し陳腐化してしまったかという思いも残ります。志水辰夫さんの作品は今回初めてになりますが、帯になった冒険三部作「飢えて狼」「裂けて海峡」「背いて故郷」は読んでみようと思っています。
 志水辰夫
志水辰夫
1936(昭和11)年、高知県生れ。1981年、『飢えて狼』でデビュー。巧みなプロットと濃密な文体で、熱烈なファンを獲得する。1985年『背いて故郷』で日本推理作家協会賞を受賞。1991(平成3)年『行きずりの街』で、日本冒険小説協会大賞を受賞する。さらに、2001年『きのうの空』で、柴田錬三郎賞を受賞。ほかに『情事』『暗夜』『生きいそぎ』『男坂』『約束の地』『青に候』など、多くの著書がある。(新潮社)
読んでいてまず思ったのは、登場する関係者同士の連絡が実にとり難いストーリー展開だな、ということ。思えば、平成になっての作品といっても16年前。携帯電話がない時代なのです。携帯電話が普及するのは、1990年代の後半からなんですね。ウィキペディアに、携帯電話と文学作品の関係について次のように記述されています。
「『電話番号さえ知っていれば、いつでも携行者と直接話せる』機械である携帯電話の出現により、少なからぬフィクション作品のジャンルは、その描写に大きな変化を余儀なくされた。例えば推理小説やサスペンスなどの多くでは、外界との連絡が絶たれた状況で惨劇が発生するのが常であるが、手元に携帯電話があれば少なくとも、外部の誰かに連絡を取る事は出来るからである――通話のための電気と電波が確保出来ていればの話ではあるが」。
「それとは逆に、『離れている恋人や家族同士が、日常の様々な場所から互いを確かめ合い(時にはすれ違い)語り合うための道具』として携帯電話が登場するシーンは、現在では小説・漫画・映画・ドラマといったジャンルを問わず、すでに当り前のものとして広く受け入れられている。また、新たなツールが世に登場した時は常にそうであったように、近年では携帯電話にまつわる新たなホラー・怪談といったものも登場している」。
作品としては楽しめました。ただ、16年の時の経過がこのミステリーを少し陳腐化してしまったかという思いも残ります。志水辰夫さんの作品は今回初めてになりますが、帯になった冒険三部作「飢えて狼」「裂けて海峡」「背いて故郷」は読んでみようと思っています。
 志水辰夫
志水辰夫1936(昭和11)年、高知県生れ。1981年、『飢えて狼』でデビュー。巧みなプロットと濃密な文体で、熱烈なファンを獲得する。1985年『背いて故郷』で日本推理作家協会賞を受賞。1991(平成3)年『行きずりの街』で、日本冒険小説協会大賞を受賞する。さらに、2001年『きのうの空』で、柴田錬三郎賞を受賞。ほかに『情事』『暗夜』『生きいそぎ』『男坂』『約束の地』『青に候』など、多くの著書がある。(新潮社)










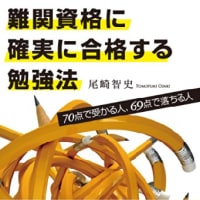
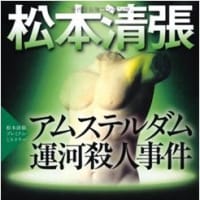
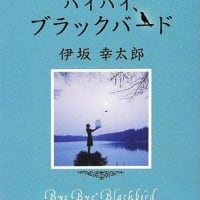

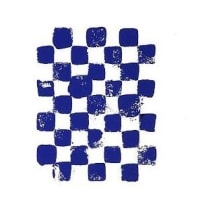
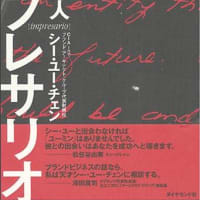



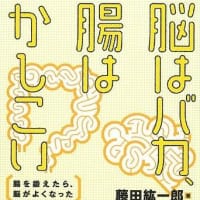
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます