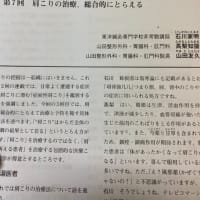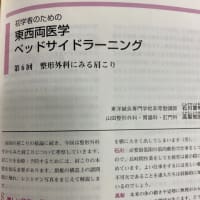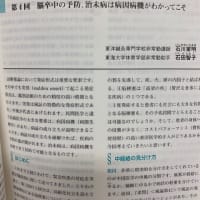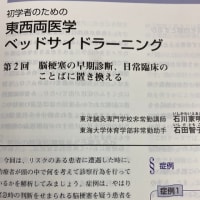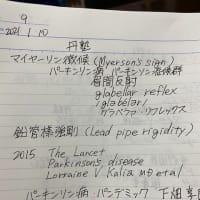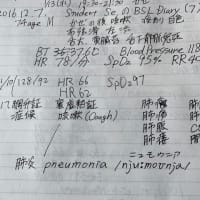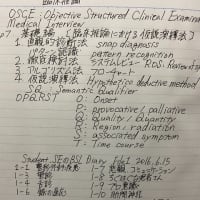『針灸大成』の水分に関する記述は以下である。
『鍼灸大成』「水分(一名,分水):下カン下一寸、臍上一寸、穴当,小腸下口。至是,而泌別清濁、水液,入膀胱、渣滓,入大腸、故曰,水分。『素註』鍼一寸。『銅人』鍼八分、留三呼、瀉五吸。水病,灸大良。」
これは、明らかに、東洋医学の「小腸」の概念である。
つまり、清濁の分別を主る。胃から送られてきた水穀の精微を、液体を膀胱に送って小便とし、固形分を大腸に送って大便とする。
この「小腸」概念の問題については、浅川要先生が『針師のお守り』(東欧学術出版社)の「尿の生成」(前掲書134ページ)という論考で詳述されている。
東洋医学の尿の生成ルートは、
胃による水穀の精微の腐熟
↓
小腸による清濁の分別→→→固形分は大腸で伝導され、大便として排出される。
↓
水液は膀胱に注ぎ滲入する。膀胱より小便として排泄される。
となる。
臨床的には、 神闕(CV8)の塩灸や水分(CV9)の灸、陰交(CV7)の灸などは利尿作用があり、下痢に効果がある。これは、「小腸」の機能を高めて、小便の量を増やすことで、結果的に大便を固めるという「分利小便」の方法論である(漢方では五苓散など)。
『鍼灸大成』の論述から言えば、任脈の下かん(CV10)は胃が終わり、小腸がはじまる「小腸の上口」である。
『鍼灸大成』「下カン:建里下一寸、臍上二寸。穴当,胃下口、小腸上口、水穀,於是,入焉。」
そして、任脈の陰交(CV7)は、小腸が終わり、膀胱が始まる部分である。
『鍼灸大成』「陰交(一名,横戸):臍下一寸、当膀胱,上際。」
つまり、『針灸大成』の描く小腸は、下かん(CV10)から陰交(CV7)にいたるゾーンとなる。さらに飛び地のように、任脈には小腸の募穴である関元(CV4)もある。
東洋医学における小腸の問題は、心熱移熱小腸や小腸実熱、小腸気痛のような臓腑弁証、あるいは小腸経の経絡弁証も併せて、とても深い問題であると思う。