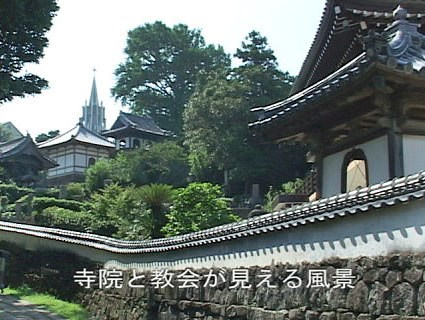砂が積み上げられた場所も見られました。

(砂が)
後ろには、相浦発電所が見えました。

(相浦発電所)
大きなガントリークレーンも見えました。

(大きなガントリークレーン)
前を大きな船が横切っていきました。砂を運ぶ船でしょうか。

(大きな船が)
後方には、相浦発電所の煙突と小さな富士山の形をした山が見えました。愛宕山のようです。

(煙突と小さな富士山の形をした山)
前方に高島が見えてきました。

(高島)
(写真撮影:2015.02)

(砂が)
後ろには、相浦発電所が見えました。

(相浦発電所)
大きなガントリークレーンも見えました。

(大きなガントリークレーン)
前を大きな船が横切っていきました。砂を運ぶ船でしょうか。

(大きな船が)
後方には、相浦発電所の煙突と小さな富士山の形をした山が見えました。愛宕山のようです。

(煙突と小さな富士山の形をした山)
前方に高島が見えてきました。

(高島)
(写真撮影:2015.02)