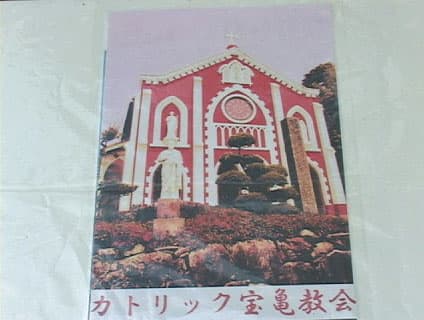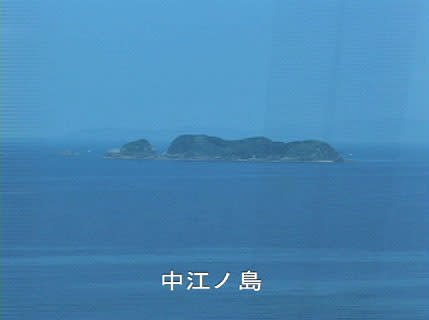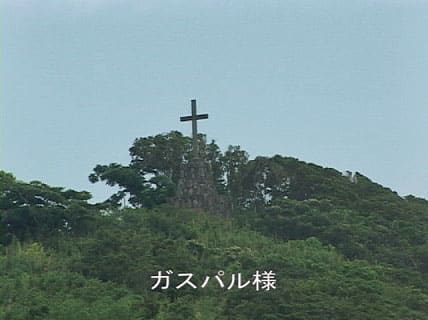定番の「聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂」へ向かいました。この教会は、天文19年(1550)に平戸を訪れたフランシスコ・ザビエルを記念して、昭和6年に建てられた聖堂です。この周りには寺院も多くあり寺院と教会が同居する平戸独特の風景を作っています。



(聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂)
平戸独特の風景を作っている坂道に向かいました。その途中に、松浦隆信(宗陽)の墓がありました。松浦家28代 松浦隆信(1591年~1637年)は、平戸が最も繁栄した頃の領主だったようです。


(松浦隆信(宗陽)の墓)
寺院と教会がみえる坂を下りました。

(寺院と教会がみえる坂)
(写真撮影:2005.8)



(聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂)
平戸独特の風景を作っている坂道に向かいました。その途中に、松浦隆信(宗陽)の墓がありました。松浦家28代 松浦隆信(1591年~1637年)は、平戸が最も繁栄した頃の領主だったようです。


(松浦隆信(宗陽)の墓)
寺院と教会がみえる坂を下りました。

(寺院と教会がみえる坂)
(写真撮影:2005.8)