昨日の大学院ゼミは、接触場面の規範についての考察第4回ということで、ファン,サウクエン(1999)「非母語語者同士の日本語会話における言語問題」『社会言語科学』2-1 pp.37-48を取り上げました。
非母語話者同士のインターアクションの場面は第三者言語接触場面と呼ばれていますが、使用している日本語の母語話者がいないために、基底規範が弱く、その他の言語バラエティの規範はもちろん、社会的規範もまた目立ってきます。参加者は日本語能力に差があったとしてもどちらも同じようなストラテジーを使って会話協力をしていきます。
論文では最後の問題提起として、なぜ第三者言語接触場面は内的場面と類似したストラテジーを使うのか?接触場面の代表とされる相手言語接触場面(母語話者と非母語話者によるインターアクション)とは、母語規範が強調される場面ではないか、といった興味深いポイントが提出されています。
よく接触場面では日本語の規範が緩和されるというのですが、しかし接触場面で自分の規範を強く意識することも同時に起こります。したがって、規範は強められると同時に緩和されるというへんなことが起きていることになります。私はこうした現象は2つの異なる規範のシステムが関連している可能性を追求したい気がしています。つまり、母語(基底)規範と普遍規範という2つのシステムを考えてみたいのです。
非母語話者同士のインターアクションの場面は第三者言語接触場面と呼ばれていますが、使用している日本語の母語話者がいないために、基底規範が弱く、その他の言語バラエティの規範はもちろん、社会的規範もまた目立ってきます。参加者は日本語能力に差があったとしてもどちらも同じようなストラテジーを使って会話協力をしていきます。
論文では最後の問題提起として、なぜ第三者言語接触場面は内的場面と類似したストラテジーを使うのか?接触場面の代表とされる相手言語接触場面(母語話者と非母語話者によるインターアクション)とは、母語規範が強調される場面ではないか、といった興味深いポイントが提出されています。
よく接触場面では日本語の規範が緩和されるというのですが、しかし接触場面で自分の規範を強く意識することも同時に起こります。したがって、規範は強められると同時に緩和されるというへんなことが起きていることになります。私はこうした現象は2つの異なる規範のシステムが関連している可能性を追求したい気がしています。つまり、母語(基底)規範と普遍規範という2つのシステムを考えてみたいのです。


















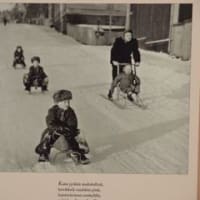







当時は今みたいにコンピューターとネットワークが今みたいに普及されてないため、卒業後先生たちとの連絡がたちました。
帰国してもう九年経ちまして、時々懐かしい気持ちになり、インターネットで当時の先生たちの消息を見つけようとしたり。
今日担当の猪崎先生の名前で検索したらこちらのサイトにたどり着きました。猪崎先生がすでに他界されたと知り、非常にショックを受けています。
そちらは猪崎先生と直接かかわっていないかもしれませんが、もし差し支えがないなら、先生がいつ頃、そしてどの国で晩年を過ごされたかを教えていただけないでしょうか。
メールアドレスはCharyu@gmail.comです。ご連絡をお待ちしております。
乱筆乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします