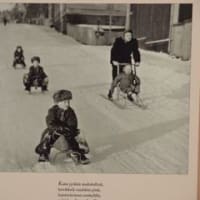外部から委託されていたやっかいな仕事がようやく片付いて、やっと水面から顔をだした気持。自転車で走ると海岸沿いから富士山がみごとに白く東京湾の向こうに見える。
大学院では東海大の加藤さんの著書をもとに、いろいろ議論に花が咲いた。以下、わかりずらい話で恐縮ですが、覚え書きとして残しておくことにする。
接触場面の研究において、規範は文法規則のようなものではない。ACTFLなどの日本語の会話能力評価では、母語話者の持っている規範意識を分類して、それらをもとに学習者の逸脱を指摘していく手法をとるが、接触場面における規範はその実際の場面で、そこに参加する当事者同士によって設定される規範(基底規範basic norm)を意味している。つまり、母語話者がもっている(と信じられている)規範や規則の固定的なイメージではなく、その場の情報(あらたまった場面、くだけた場面など)や相手に対する認知(日本語が上手そう、こわい顔をしている、外国人っぽい、話をしやすそう、専門知識がないかもしれない)などをもとに相互承認のもとで設定される動的な性格をもっているわけだ。
日本での接触場面で日本語が基底規範として設定されることが多いとしても、その基底規範は場面ごとに異なるし、相手との相互作用によっても変化する。逸脱の留意というのは、こうして構築され、流動する基底規範から逸脱した外来性に気づくことを意味する。正確に言うなら、決して固定的な母語規範から逸脱を留意するわけではない。
もう1つ議論したのは、はたして言語管理モデルは有効なのかというもの。フォローアップ・インタビューなどでデータ収集をしても、5つの段階(規範からの逸脱、逸脱の留意、評価、調整、調整実施)がかならずしも跡づけられるわけではなく、さて本当にこのプロセスがあるのかと思ってしまうことになる。このあたりの疑問もよく言語管理に対する批判として出てくるものだ。
しかし、ぼくらは「モデル」とはどのようなものなのかを忘れないようにしなければならない。モデルはすべての現象がそのモデルに当てはまらなければならないわけではない。ある現象がモデルに反していると言っても、それによってモデルを否定することはできない。モデルを採用して研究を行う場合には、もし現象がモデルに適さないとか観察されないときはその不適、不在の理由をモデルとの関係でさらに追求していくことになる。もしも現象の説明にモデルが本当に適さないことがわかれば、そのモデルを放棄して、別のモデルをつくるしかない。
だから、じつはモデルを批判することはたんに非生産的で意味がない活動なのだと思う。
大学院では東海大の加藤さんの著書をもとに、いろいろ議論に花が咲いた。以下、わかりずらい話で恐縮ですが、覚え書きとして残しておくことにする。
接触場面の研究において、規範は文法規則のようなものではない。ACTFLなどの日本語の会話能力評価では、母語話者の持っている規範意識を分類して、それらをもとに学習者の逸脱を指摘していく手法をとるが、接触場面における規範はその実際の場面で、そこに参加する当事者同士によって設定される規範(基底規範basic norm)を意味している。つまり、母語話者がもっている(と信じられている)規範や規則の固定的なイメージではなく、その場の情報(あらたまった場面、くだけた場面など)や相手に対する認知(日本語が上手そう、こわい顔をしている、外国人っぽい、話をしやすそう、専門知識がないかもしれない)などをもとに相互承認のもとで設定される動的な性格をもっているわけだ。
日本での接触場面で日本語が基底規範として設定されることが多いとしても、その基底規範は場面ごとに異なるし、相手との相互作用によっても変化する。逸脱の留意というのは、こうして構築され、流動する基底規範から逸脱した外来性に気づくことを意味する。正確に言うなら、決して固定的な母語規範から逸脱を留意するわけではない。
もう1つ議論したのは、はたして言語管理モデルは有効なのかというもの。フォローアップ・インタビューなどでデータ収集をしても、5つの段階(規範からの逸脱、逸脱の留意、評価、調整、調整実施)がかならずしも跡づけられるわけではなく、さて本当にこのプロセスがあるのかと思ってしまうことになる。このあたりの疑問もよく言語管理に対する批判として出てくるものだ。
しかし、ぼくらは「モデル」とはどのようなものなのかを忘れないようにしなければならない。モデルはすべての現象がそのモデルに当てはまらなければならないわけではない。ある現象がモデルに反していると言っても、それによってモデルを否定することはできない。モデルを採用して研究を行う場合には、もし現象がモデルに適さないとか観察されないときはその不適、不在の理由をモデルとの関係でさらに追求していくことになる。もしも現象の説明にモデルが本当に適さないことがわかれば、そのモデルを放棄して、別のモデルをつくるしかない。
だから、じつはモデルを批判することはたんに非生産的で意味がない活動なのだと思う。