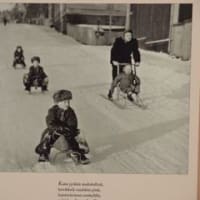秋が深まる。
大学院はRajendra Singh, Jayant K. Lele and Gita Martohardjono (1996) Communication in a multilingual society: Some missed opportunitiesの紹介。この論文は最初、Language in Societyに出たものだが、論文集としても批判の対象となっているGumperzの論文の後ろに掲載されたり、Singhが自分で編集した"Towards a Critical Sociolinguistics"にも掲載している重要論文。モントリオール大学の教授でインド英語の形態論や言語接触を専門にするが、批判的言語学の一翼を担ってもいるようだ。
この論文で、Singh等はGumperzに代表される異民族間相互作用の社会言語学を、支配の側からの解釈に甘んじていることと、分析の道具的な合理主義に関して、厳しい批判をしている。Gumperzの有名なdiscourse strategiesについて、異民族間のコミュニケーションの誤解は、discourse strategiesが民族間で異なることに直接に由来するのか、と問う。もしそうならdiscourse strategiesを取り替えるようにすれば問題は解決するかもしれない。日本語教育の論文がしばしば似たような主張を前提にしているように。
しかし、Singh等はそのような道具主義に警告を発する。確かにGumperz等はdisoucrse上の相違の場所を見つけたが、だからといってそれが誤解の原因であるとは限らない。誤解は権力、偏見などが生まれる社会的文脈にもあるかもしれないという。discourseだけを見ることが必ずしも正しくないというわけだ。(言語管理から見れば、留意した逸脱を人はどのような規範から評価するのか?という問題になるだろう。)
うまく説明できていないのだけど、とにかく、この批判はとてもぼくのところにまで響いてくる。似たようなことをしているかもしれないのだ。しかし、ここ10年ほど進めてきた研究で、ぼくは少なくとも非母語話者だったり多言語使用者だったりする、主流派ではない側の声を理解しようとしてきたと思う。だから彼らがこの単一言語社会でどのように自分なりの相互作用と生活を作り上げているかを、そしてそこにはそれなりの合理的な理由があることを語ろうとしてきたつもりだ。
しかし、それでもやはり似たり寄ったりだったかもしれない。彼らが、異文化に対して柔軟さを持っていると考える人々の博愛主義には自文化中心主義がこびりついていると批判しているのを読むと、そろそろちゃんと内省しろと言われている気がする。
大学院はRajendra Singh, Jayant K. Lele and Gita Martohardjono (1996) Communication in a multilingual society: Some missed opportunitiesの紹介。この論文は最初、Language in Societyに出たものだが、論文集としても批判の対象となっているGumperzの論文の後ろに掲載されたり、Singhが自分で編集した"Towards a Critical Sociolinguistics"にも掲載している重要論文。モントリオール大学の教授でインド英語の形態論や言語接触を専門にするが、批判的言語学の一翼を担ってもいるようだ。
この論文で、Singh等はGumperzに代表される異民族間相互作用の社会言語学を、支配の側からの解釈に甘んじていることと、分析の道具的な合理主義に関して、厳しい批判をしている。Gumperzの有名なdiscourse strategiesについて、異民族間のコミュニケーションの誤解は、discourse strategiesが民族間で異なることに直接に由来するのか、と問う。もしそうならdiscourse strategiesを取り替えるようにすれば問題は解決するかもしれない。日本語教育の論文がしばしば似たような主張を前提にしているように。
しかし、Singh等はそのような道具主義に警告を発する。確かにGumperz等はdisoucrse上の相違の場所を見つけたが、だからといってそれが誤解の原因であるとは限らない。誤解は権力、偏見などが生まれる社会的文脈にもあるかもしれないという。discourseだけを見ることが必ずしも正しくないというわけだ。(言語管理から見れば、留意した逸脱を人はどのような規範から評価するのか?という問題になるだろう。)
うまく説明できていないのだけど、とにかく、この批判はとてもぼくのところにまで響いてくる。似たようなことをしているかもしれないのだ。しかし、ここ10年ほど進めてきた研究で、ぼくは少なくとも非母語話者だったり多言語使用者だったりする、主流派ではない側の声を理解しようとしてきたと思う。だから彼らがこの単一言語社会でどのように自分なりの相互作用と生活を作り上げているかを、そしてそこにはそれなりの合理的な理由があることを語ろうとしてきたつもりだ。
しかし、それでもやはり似たり寄ったりだったかもしれない。彼らが、異文化に対して柔軟さを持っていると考える人々の博愛主義には自文化中心主義がこびりついていると批判しているのを読むと、そろそろちゃんと内省しろと言われている気がする。