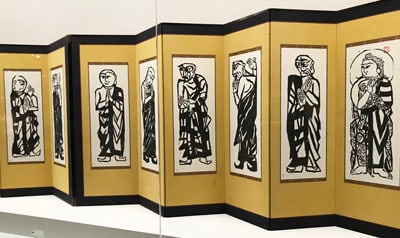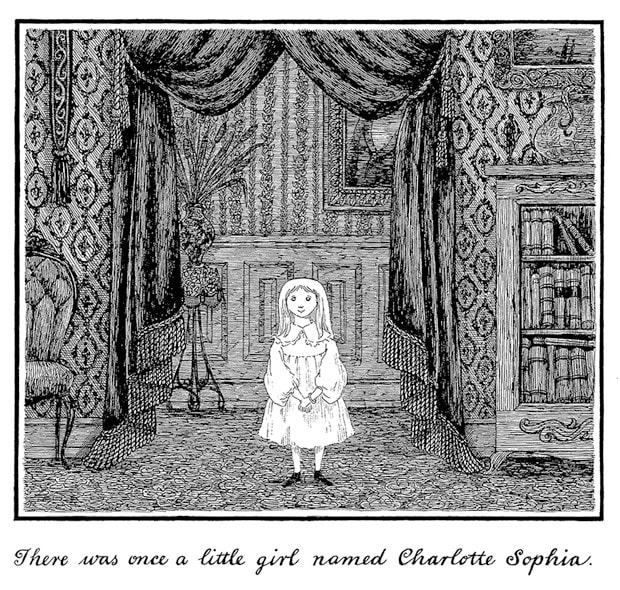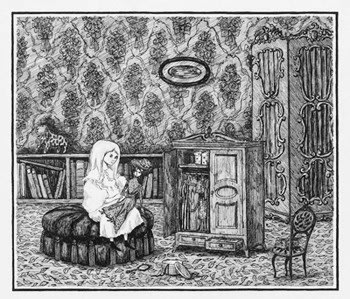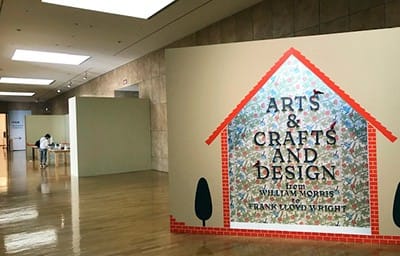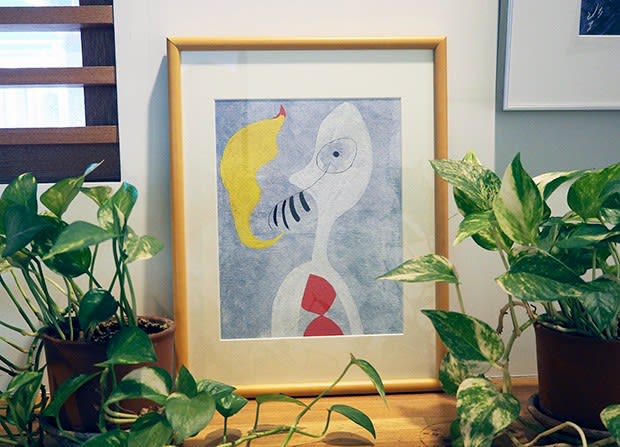映画「ウォンカとチョコレート工場のはじまり」
監督:ポール・キング/原題:Wonka (ウォンカ)/2023年
ロアルド・ダールによる児童小説が原作。チョコレート職人ウィリー・ウォンカが "魔法のチョコレート工場” を作るまでを描くファンタジー・ミュージカル映画。
〜〜〜〜〜〜〜
今回のティモシー・シャラメ演じるウォンカはとてもいい奴に描かれています。前作ティム・バートン監督「チャーリーとチョコレート工場」のジョニー・デップ演じる不気味なウォンカとまるで違います。今回は完全オリジナル、前作にとらわれないまったく新しいウォンカの若い頃の物語です。
そもそも今回はミュージカル映画ですから、全員で歌って踊っているうちにみんな幸せになっていくようにお話はできていますが、人びとを幸せにする ”魔法のチョコレート” を作り出すウォンカ本人が一番楽しそうでした。楽しくてどこか懐かしいミュージカル映画です。
〜〜〜〜〜〜〜
ウォンカの ”魔法のチョコレート” を食べた人たちは、あまりの美味しさに踊りながら空中に浮かんでしまうのです。ハハハ・・・食べてみたい!
この映画を観てからは我が家のチョコレートの消費量が少し増えたような気がします。このブログも不二家の ”チョコまみれ” を食べながら書いてます。

瓶に捕らえられた小人のウンパ・ルンパはウォンカに言います、
「クセになる歌だぞ、頭から離れなくなる・・もう手遅れだ、踊り始めたら止まらない・・♫ウンパ・ルンパ・ルンパティドゥ〜 ♫お利口ならば聞きなさい〜」と突然歌い踊り始めるのでした。
〜〜〜〜〜〜〜
人気キャラクターのウンパ・ルンパも、前作とはまったく別のキャラになっています。なぜこの小人がウォンカをつけ狙い悪さをするのか?・・・その謎が明かされます。ヒュー・グラント演じるウンパ・ルンパがとても良い味を出してます・・・カカオ豆の復習か?ハハハ
(クセになる♫ウンパ・ルンパの歌)