
今日から11月。
鋭角な長い陽射しがリビングに差し込み、テーブルまで届く。
この時期には似つかわしくないような温もりがある。
洗濯ものを干し終え、まだ9時にもなっていないのに、
昨日大量に頂いたケーキを消費しなければと
起きてきたばかりの次男にロンネフェルトの紅茶を淹れてもらい、我が家には珍しくないモーニングケーキ(^_^;)
抹茶ムースの上に、わらび餅、栗の甘煮が渋皮付のと2種類、黒豆、ミニマドレーヌがのった和洋コラボのスイーツ。

本の虫が騒ぎ出して、どうにも止まらない読書欲。
村上春樹のエッセイ、村上ラヂオ2。買ったのは夏だったのに今頃埃を払ってページを開いている。
年齢が近いせいか(と言っても5歳くらい上かな?)同級生と会話をしているような楽しさがある。
小説の村上ワールドとは少し違ったエッセンス、いややっぱり似ているかな?
大橋歩さんの挿絵もほんわか楽しい。
タイトルにあった「むずかしいアボカド」に激しく頷きながら手に取ったのを思い出す。
アボカドの食べごろにいつも失敗してしまうmintは、この中にヒントがあるのかと思ってしまいましたが、
残念ながらそれはありませんでした(笑)
まだまだ読みたい本がたくさん。困ったな~。
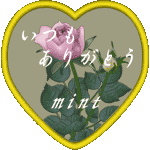
ozさん作
長かった病院通いも、妹の病状が落ち着くと気持ちにも余裕ができ、本をたくさん持ちこむようになりました。
読書タイムは自分へのご褒美と、家にある本を手当たり次第に。
買ったはいいけど積読のままになっていた本、昔々に読んだけどまた読んでみたいなと思っていた本など。

その一つ。上田秋成の『雨月物語』
昔々読んだけど、何年か前青木政次の対訳本が文庫本になっているのを見つけ買っておいたもの。
短編で構成されているので、どこから読み始めていいのがお手軽。
内容的には怪奇物なので病室で読むには相応しくないかもと思いましたが、若い時に読んだ記憶とはまた違った味わいがあって、趣深く読みました。
なかでも巻一の「菊花の約」を読んだときは、時節が重なるのと、北原白秋がこの物語のことを詠んだ歌があるのを思い出し、悲しいまでに純粋な左門と宗右衛門に、心臓あたりが痛くなるような思いがしました。

寂しさに 成秋が書読みさして 庭に出でたり 白菊の花
北原白秋
重陽の節句に帰ってくると約束した宗右衛門のため、粗末な家を掃除して小菊を数本飾り、貧しい財布から酒食の用意をして待っていた左門。
捕らわれの身となっていた宗右衛門は、
『人一日に千里をゆくことをあたわず。魂よく一日に千里をもゆく』という言葉を思い出し
左門との約束を果たすため自刃して霊となり、左門のもとへ辿りつく。
左門はこの後、宗右衛門を裏切った丹治のもとへ行き、「私は信義を重んじここへ来た。あなたは不義のために汚名を残せ」と言って、丹治を抜き打ちに斬り付けた。
おどろおどろしいことの運びとは無縁に微笑むような可憐な小菊。
庭の小菊を手折って飾り、粗末な酒食を用意して待つ左門の純粋と狂気。
そのあと左門はどんなふうに生きたのかと思いを馳せる
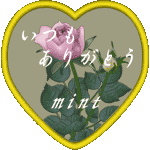
ozさん作

3月12日 鶏そぼろ弁当
寒い!春は何処へ!なんて文句タラタラだったのに、
身体の方は春眠暁を覚えず・・・と、
しっかり春に反応して、うっかり寝坊が多くなりました(^_^;)
時間が無い時のお約束、丼物のお弁当が多発しそうなこの頃です。
早いし安いし、何よりこんなお弁当の方が息子は喜ぶので、
手抜きの後ろめたさも少なくて済みます。
青いお野菜はプチベール、頂き物の鰊の甘露煮もあったので入れてあげました。
(お酒のおつまが減ってしまいました~ )
)
~*~*~*~*~*~
寒さの春に閉じこもる日も多く、何冊か本を読みました。
その中で、米原万里さんのエッセイ「魔女の1ダース」が面白かったのでご紹介。
ロシア語の同時通訳として、ソ連邦解体前から活躍していた米原万里さんの
比較文化論的なエッセイとも言える本書には、異端のいる風景を紹介しながら、
たとえば、イスタンブールの日本人、モスクワのベトナム人、
マニラのスイス人、シベリアのフランス人等々のように、
(因みに東京の福島県人というのも・・・福島県人は東京では異端? )
)
見慣れた風景の中に異文化分子を送り込むことによって
今まで見えなかったものが見えてくるというパラドックス、
正義や常識に冷や水を浴びせようとする13章(=魔女の1ダース)が書かれているのです。
え、1ダースなのに13章?
実は、悪魔と魔女の辞典では、1ダースは13個になるらしいのです。
米原さんは「物事に絶対なんていうことはない」と、おっしゃってます。
物事は全て相対的にあるのであって、常日頃考えている常識や価値というものは
所変われば逆転することもあり得るということです。
著者ご自信が、通訳という異文化コミュニケーションのお仕事を通して経験したことを
歴史、教育、国際政治問題に、お国柄を表す下ネタジョーク等も取り混ぜて
真面目に面白く、知的に際どく軽快に語りながら、見事に常識のどんでん返しを見せてくれました。
米原万里さんて、スゴイ人だなぁ~と、改めて感じました。
本書の中にあるロシアの小噺をひとつ
天寿を全うしたブレジネフ書記長は、当然の成り行きとして地獄に落ちた。
入り口のところで門番が待ち構えていて、注意する。
「ブレジネフさん、地獄に来た以上、必ず罰を受けなくてはいけません。書記長とて逃れる術はありません。ただし、どんな罰を受けるかは選択できる仕組みになっています。自分で選びなさい」
そう言われて、ブレジネフは地獄を一通り見学した。
すると、レーニンは針の山でもがき、スターリンは煮えたぎる窯の中で悶えていた。
ところがなんと向こうの方では、フルシチョフがマリリンモンローと抱き合っているではないか。
ブレジネフは手をたたいて叫んだ。
「これだ。わたしにもフルシチョフ同志と同じ罰を与えてもらいたい」
地獄の職員が言った。
「とんでもない。あれはフルシチョフではなく、マリリンモンローが受けている罰ですよ」
ozさん作

今年の冬は、週末が来ても出不精になっている私たち夫婦。
(年のせいかしら・・・ )
)
朝の温泉&サウナ→ランチ→本屋さんのコースが日課になってしまっています。
土曜日も、食材の買い物帰りにいつもの本屋さんに寄り道して
併設のカフェで一休みしていると、夫の携帯が鳴り、急ぎの用が入った様子。
そんなに時間はかからないので、ちょっと行って来て良いかと言うので
本があればいくらでも待っていられるので、時間は気にしないで行ってらっしゃいと
快く返事をし、笑顔で夫に手を振る良妻の私
バッグの中に眼鏡が入っているのを確かめて、
女性バリスタに、
本を買って来るので席をこのままにして置いてくれるように頼み
本屋のスペースに行こうとしたら、
こちらに向かって小走りに戻って来る夫???
携帯でも忘れたかしらと思っていたら、これを読んで待っていてねと手渡された本
江國香織や小川洋子など私が好きな作家の名前を見つけて
多分好きだろうと思って、買って戻ってきてくれたのです。
八人の女性作家による、八つの短い物語。
本の帯には“とてつもなく甘美で、けっこう怖い・・・”と書いてあります。
8繋がりで、フランソワ・オゾンの映画「8人の女たち」をなんとなく思い出しました。
目次を眺めてから、一番好きな小川洋子さんのページから・・・
一行目からツボにハマリ、コーヒーが冷めるのも気にせず一気読み、
途中で夫が戻ってきましたが、234ページ、8人を読破させていただきました。
大人の女性の深層心理を衝いてくる、帯に書かれていた通りけっこう怖いお話です。
貴方なら誰の招待状から受け取りますか?
~*~*~*~*~*~
今日のお弁当
1月25日
セロリとパスタのケチャップ炒め
椎茸のグリル
野菜ハンバーグ(蓮根・人参入り)
プチトマト ブロッコリー
ハムとチーズのココット
じゃこ入り発芽玄米
ozさん作
焼酎のことではありませんョ(^^ゞ
長いこと私の本棚で埃を被っていた本、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』
奥付には、16刷 2003.7.15と記されているので買ったのは6年前?
実は、『百年の孤独』は学生の頃にも一度買ったことがあるのですが、
未読のまま実家に置き忘れ、その後紛失してしまっていた本でした。
あの時とは装丁も違っていて、99年には全面的な改訳もあったというこの本が
書店の平台に並んでいるのを見たときは、思わず手に取り買ってしまいました。
それなのにあれから6年、またもや本棚の片隅に~・・・(^_^;)
初めて手にした時から数えて三十?年、ようやく物語の扉を開くこととなりました。
ブエンディア一族の百年にわたる壮大な物語は、
摩訶不思議な大人のファンタジー、とでも言ったらいいのでしょうか。
似通った名前の登場人物の多さと、
外国文学特有のセンテンスの長さが少し疲れますが、
ファンタジー好きの私にとっては
一旦足を踏み入れると、その勢いに巻き込まれ、
時間が経つのも忘れて読み進みました。
それほど力強い物語でした、私にとっては。
お蔭でこの数日、ブログとはご無沙汰でした(^^ゞ
思えば、学生時代、何故この本を買ったのか・・・
多分、大学の友人の勧めだったような気がします。
そしてその数年後、マルケスはノーベル文学賞を受賞したのです。
ホセ・アルカディオ・ブエンディアとその一族と、
彼の手によって生まれたマコンドという町が消滅するに至るまでの百年は
一言で言えば、現実にはあり得ない、絵空事のようなお話なのですが、
そこには逆に、人間の欲望とか愛とか滑稽さとか
あらゆる人間模様を凝縮したリアリティーを感じました。
それは、言葉にして説明するのは難しいのだけれど
魂にズンと響く絵画に出合った時のような、とでも言えばいいのでしょうか・・・
そして、その魔術のようなリアリズムは、
村上春樹の1Q84で青豆が眼にする二つの月と、
どうしても重なってしまう私でした。
息子のお弁当
8月4日
エビフライ
かぼちゃのバター焼き
フェットチーネのトマトソース
ミートボール
ウインナー
トウモロコシ
オクラ・プチトマト
ハートのキュウリの浅漬け
久しぶりに遊んで、お子様ランチ風にしました
8月5日
茄子の豆板醤炒め
コロッケ
きんぴら
里芋の味噌煮
竹輪の磯辺揚げ
ozさん作

「1Q84」が発売された日なので、少し前の画像です。
ちょうどこの頃、aromaさんから
「今頃はグラス片手に1Q84じゃないですか(^_-)-☆」のコメントを頂いてドキッ!
グラス片手ではありませんでしたが、まさに手元には“1Q84”でした(笑)
ネットで予約したわけではないのですが、発売日にたまたま本屋さんへ立ち寄った夫が
店先に10冊ほどあった「1Q84」が目に付いたからと、買ってきてくれました。
その数分後には、本は売り切れてしまったようです。
内容を明かさないという新潮社の宣伝が功を奏したのか、
先だってのエルサレム賞受賞の騒ぎの影響なのか・・・
そんなことはどうでもいいのです。
雨でも降ってくれれば読書に没頭できるのに、降りそうで降らないお天気
そちらの方が気になります(笑)
1Q84の物語は
カーラジオから流れるヤナーチェックの「シンフォニエッタ」と共に始まります。
ここからもう春樹ワールドにようこそ、ですね。
淡々とした言葉とは裏腹に、普通じゃない世界にどんどん引きずり込まれます。
春樹ワールドの吸引力は相変わらず凄いゎ~。
まだbook1の途中ですが、彼が地下鉄サリン事件のインタビューを綴った
「アンダーグラウンド」のことを思い出しました。
あの時からこの作品を温めていたのかなと感じながら読んでいます。
せっかく内容を秘密にして出版された作品ですから、私も内容には触れません。
ただ、1984年は次男が生まれる前の年で
主人公の青豆と天吾の生まれ年が、私のそれと同じ1954年。
はっきり言ってどうでもいいことですけど(^_^;)
ミーハーな私。
物語に出てきた“トムコリンズ”が飲みたくなって、それ風に作ってみました(^^ゞ
レシピはオールド・トム・ジン、レモンジュース、シュガーシロップ、ソーダです。
ベースのオールド・トム・ジンが無いので、ボンベイ・サファイアですし
チェリーもありませんが、何となくそれっぽく(笑)
今夜はグラス片手に「1Q84」でした♪
ozさん作

背筋を伸ばし、素敵なプロポーションで
「これからは、プリンセスとお呼び!」と颯爽としている表紙の女性
著者のイガラシ・ヒロコさんは、実は私の知人です。
彼女とは、長男が小学校の5・6年生の時一緒にPTAの役員をさせていただき
聡明で行動力があることは承知していましたが、
久しぶりに見た彼女の姿に、えぇ~っ
その素敵な変身振りに驚きを隠せませんでした。
before and after を目の当たりにしたのです。
プロポーションは創るもの、と言う彼女。
50代半ばでウォーキング教室に通い始め、今では自らが教室を主宰しています。
彼女のプロポーション創りの考え方は、いたってシンプルなもの。
「歪んでしまった身体は正しい位置に戻せばよい」ということ。
そのためにすることが、筋肉を耕す「リフォマ」のメソッドと
プロポーション維持のために大切な「美しい姿勢と歩き方」だそうです。
リフォマ リフォメーション(矯正)+マジック(魔法・手品)からの造語
アンチエイジング美容食
彼女は昔から美的センスがありましたし、明るくて聡明でパワフルでした。
そんな彼女ですが、歩き方にはコンプレックスを持っていたそうです。
確かにちょっと猫背でスタイルもかなりパワフルだったかも・・・
でも、その彼女が今は、
表紙を見てもお分かりのように、とてもアラ還世代には見えませんでしょう。
私より7歳も年上だったなんて~嫉妬してしまいます~(笑)
しかも、50代半ばで始まった「アンチエイジング道」
つい“私だってプリンセスになれるかも ”って気になりません?
”って気になりません?
「どうせオバサンだもん」と居直って、綾小路きみまろさんの笑いの種になるか、
「美しく老いる」決心をして吉永小百合さんを目指すか(←目標大きすぎだって )
)
ブログ以外は三日坊主の私。今度は本気モードになれるかも~
ヒロコ・ウォーキング・アカデミー
http://www.iibai.com/hiroko/ お弁当
お弁当
5月18日
豚ロール(ポロネギ)
ほうれん草のお浸し
明太子入り卵焼き
牛蒡のゴマ味噌煮
マカロニサラダ
プチトマト
5月19日
味付けコロッケ(肉じゃが風)
豚肉・ピーマン・しめじのガーリックマヨネーズ炒め
プチトマト
目玉焼き
夕食は外だった長男、コロッケが残ってしまったので
レンジでチンして入れてみたけど、なんだかマズそ~
5月22日
オムライス
牛ロールすき焼き味(人参・ブロッコリーの芯)
蓮根のきんぴら
ブロッコリー
ポテトサラダ
昨日も外ご飯の長男。ご飯が残ったので炒めてオムライスに。
今週は、やる気なし~のお弁当でした(^_^;)
ozさん作
高校生の頃は、お弁当にお魚は入れないでと言われていたけれど
社会人になった今は、お魚を入れても大丈夫らしいです。
嗜好もだんだん大人に?
4月28日
鯖の竜田揚げ
牛蒡と牛肉の甘辛煮(牛蒡・牛肉・ニンニクの芽・人参)
ピーマン、パプリカ赤と黄、たまねぎのスパイス炒め
かぼちゃのマッシュ
蒲鉾梅肉はさみ
卵焼きを作ったのに、入れる所がなくなってしまいました
![]()
晴耕雨読?+ちょこっと一杯
週末はお天気が悪かったので、久々に本などを開いてみました。
私の大好きな村上春樹の訳で(自称ハルキストです^^;)
レイモンド・チャンドラーの「ロング・グッドバイ」を再読です。
探偵ものですが、フィリップ・マーロウが渋くて、タフで超クール
ハードボイルド小説が特に好きなわけではありませんが、
チャンドラーのサラリとした文章と洗練された会話は何度読んでも面白く大好きです。
例えば
チャンドラーを読んだことがない方でも、きっと聞いたことがあると思うセリフ
「男はタフでなければ生きてはいけない。優しくなければ生きていく資格がない」
ね、聞いたことがあるでしょう
こんな名セリフがちょこちょこ出てきます・
字面だけを追うとキザなようですが、
マーロウという男は、決してキザではありません。
「ロング・グッドバイ」では
自殺したはずのテリー・レノックスが、姿を変えて再びマーロウの前に現れた時
見事な推理を披露したマーロウにレノックスが言うクライマックスでのセリフ
「ギムレットには少し早すぎるね」
という有名なセリフがあります。
デートでバーなんかに行くと、
何人かの男性が必ずチャンドラーの小説を引き合いに出して
ギムレットについての薀蓄を語るに違いありません
さて、何が早すぎるのか、時間?時期?それとも年齢的に?
話せば長いギムレットのことですが、
いわばマーロウとレノックスの友情の杯みたいなギムレット。
このカクテルがいい小道具になって
「ロング・グッドバイ」を上等なハードボイルド小説に仕上げているような気がするのです。
なので、私も「ロング・グッドバイ」をより深く理解する為に
ジンとライムジュースのカクテル「ギムレット」をいただきながら
続きを読むことに・・・
今日もご訪問 ありがとう
ozさん作

イギリスのブッカー賞作家、カズオ・イシグロの小説です。
大分前に買って積読状態だった本ですが、先月思い出して読みました。
カズオ・イシグロを知ったのは、ブッカー賞をもらった「日の名残り」という小説です。
アンソニーホプキンスとエマ・トンプソンが主役で映画化もされ、そのDVDも観ました。
エリザベス女王も大変お気に入りだったとか。
彼の作品をもっと読んでみたいと思い「私を離さないで」を手にしたのですが、
それは、「日の名残り」とは全く違った趣の物語でした。
人はこの世に生を受けたとき、
これからどんな人生を送るのか、それは未知数に溢れているはずです。
ところが、この小説の中の子供たちは、ある目的を持たされてこの世に生を受けました。
主人公キャシーによって淡々と語られる、彼女と彼女の友人たちの過去。
その淡々とした語りの中には、
彼女たちが辿るであろう人生の、見えているようで見えていない
確かなのに不確かな、
それは、青春時代のもやもやとどこか共通するような気もしますが
彼女たちの宿命を通して、
生と死というものを深く考えないわけにはいかなくなる物語がありました。
これ以上書くと、ネタバレしそうなので止めますが
カズオ・イシグロという作家に益々興味を持ちました
PCばかり見ていると本を読む時間が無くなってしまうし
本を読み始めると、PCに向かう時間が無くなってしまう・・・ の私は、秋の夜長をもっと欲しいと思うのでした~
の私は、秋の夜長をもっと欲しいと思うのでした~


~お弁当~
10月8日 
秋刀魚の梅干し煮
牛肉ともやしの炒め物
おからと野菜の炒り煮
牛蒡のきんぴら
卵焼き
もみじ麩・プチトマト
10月9日
ハンバーグ
キャベツとじゃがいものソテー
ピーマンとじゃこの炒め物
カボチャサラダ
ブロッコリー
プチトマト
・
葡萄
今日もご訪問
ozuさん&マリアさん作

我が家の庭で見つけた蝉の抜け殻たち
8月の下旬だったと思いますが、庭の草取りをしていた時、
家のドアや壁に、バチッ、バチッとぶつかりながら飛ぶ蝉を見かけました。
次男によると、それは死期が迫って方向感覚を失った蝉だと言うのです。
ふ~ん、そうなんだ~。
土の中に7年も暮らして地上に出て、たった1~2週間で命が絶えてしまう蝉。
思えば地上に出てきた時には既に死期が迫っている状態なんですね。
蝉の鳴声があんなに一生懸命なのは、
地上にいる短い時間に、恋をして子孫を残さなければならないためなのでしょうか。
暗い土の中の長い年月と、たった一週間の地上の暮らしは、
蝉にとってどんなものなのだろうかと、
草取りをしながら次男とあれこれ話しましたが、
人間には分るはずもありませんね。
そんな蝉に纏わる出来事があった後に、
本屋さんの平台に並べられていた角田光代の「八日目の蝉」が目に入ったものだから、
タイトルに惹かれ何となく買ってしまいました。
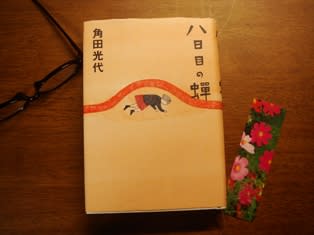
本の帯には、太田光氏も大絶賛!「最後の数ページ、震えが止まらなかった」
とあり、本屋大賞にも選ばれていました。
読んだ後、震えこそは来ませんでしたが、
血の繋がりって何だろう、母性って?
家族って?罪って何?
それらのことが、暫らくは頭の中をぐるぐると回っていました。
愛するということは、与えることも多いけれど奪ってしまうこともまた多いものと、
少なからぬ衝撃を受けた本でした。
次男との蝉の話しがなければ買わなかったかもしれない「八日目の蝉」でしたが、
思わぬ良い本との出会いがありました。 秋の夜長にいかがですか。


昨日はお彼岸のお中日だったので、おはぎを作りました。
いつもは粒餡なのですが、粒餡は歯に挟まってイヤ!と言う母のお言葉。
4対1でも母には敵いません。 今年は晒し餡のおはぎになりました
いつもなら、お鍋一杯に小豆を煮て、余るほど餡を作るのですが、
晒し餡は艶よくできなかったりと自信が無いので、
餡はお菓子屋さんに分けていただいたのですが
お値段が高くてビックリ !
!
当然お味はいいのですが、
ケチケチ餡子のおはぎになってしまいました~
今日もご訪問
ozuさん&マリアさん作














