台風が去り、昨日と今日は爽やかな秋晴れになりました。
閉め切っていた戸を開け放ち、シーツやタオルケットなどの大物を洗い
庭の物干し竿には、シーツが眩しくはためいています(笑)
何時になく頑張りすぎて少々疲れ気味の今日は、程々にダラダラ(^_^;)
午後は、本を持ってエクセルシールカフェでティータイム。
梨木香歩の『家守奇譚』
彼女の本との出会いは、『西の魔女が死んだ』でした。
児童書ですが、「魔女」が出てくると聞いては読まずにいられないmint(笑)
大好きな一冊になり、女の孫ができたら絶対読んでほしいと思った本です。
『家守奇譚』は、明治時代のお話。
非常勤の講師をしながら売れない文章を書いて暮らす学士綿貫征四郎が、
亡くなった親友の実家の守りを頼まれたことから始まる、奇妙な物語。
植物がタイトルになった、28の短編が集まっています。
冒頭はサルスベリ。
床の間の掛け軸を通り、亡くなったはずの親友、高堂が会いに来たり
庭のサルスベリに懸想されたり・・・
都わすれ、ヒツジグサ、ダァリヤ・・・と、章は続き、河童や子鬼が出てきて綿貫を驚かせます。
可笑しいのは、不思議な現象に驚くのは綿貫ばかりで、
隣の奥さんも和尚さんも、出版社の山内でさえも当然の事のように真顔で過ごしている事です。
折々の四季がとても美しく、自然界の和風妖精?たちのすることが面白く古典文学のよう。
夫の実家の古い建物と庭を思い出し、あそこで読んだらどんなにか素敵だったろうなといつも思います。
梨木香歩の不思議世界、あなたもいかが?
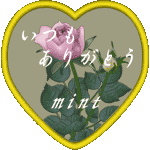
ozさん作

東京土産のメープルマニアのバタークッキーとフィナンシェ。
パッケージがポップで可愛くて、思わず笑っちゃいます。
メープルシロップがジュワ~ッと浸みているフィナンシェが、特に美味しい♪



梅雨がまだ明けないmint地域は、時折強く降ったり小雨になったりと情緒不安定な空模様が続いております。
母が帯状疱疹で痛がっているので、甲斐甲斐しく介護に励んで家に籠りっきりの孝行娘、mintです。
そんな引き籠りのお供は、やっぱり「本」ですね。
一時、『ハリー・ポッター』に凝っていた私に、同じ作家の本が出たからと言って
夫が買って来てくれていたJ.K.ローリングの『カジュアル・ベイカンシー』
半年ほど本棚で眠ったままでした。
イギリスの小さな町の議員だったバリー・フェアブラザーの急死をきっかけに、次々と事件が起きます。
小さな田舎町で、空席になった議席を巡り対立する人間関係が浮き彫りに。
登場人物が多いうえに、細かい描写が読むのに少々難儀ですが、ここは堪え処?
これって、絶対人物相関図を付けて欲しいです、講談社さん(-_-)
ページはなかなか進まないけれど、メープルマニアはどんどん進みます ~
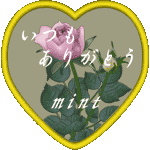
ozさん作

小川洋子の作品はどれも好きで、『猫を抱いて象と泳ぐ』も再読です。
少し前に、BSで見た映画『恋人たちのパレード』の中に出てきた象のロージーを見て
ふと、この本の中の象“インディラ”を思い出したのでした。
象は、あの大きな体の中に静かで優しくて悲しげなものを秘めているような気がして
私にとっては、とても心惹かれる動物なのです。
久しぶりに小川ワールドに浸りたいなと思い、引っ張り出してきました。
ちょこっとあらすじを
物語の主人公は祖父母に育てられる寡黙な少年。
少年の友達は、デパートの屋上に置き去りにされて死んだ象のインディラと、ベッドの脇の壁の中に住む少女のミイラだけだった。
そんな少年が、廃バスの中で暮らすマスターにチェスを教わり、才能を開花していく。
ある日のマスターとの一局で、少年は今まで味わったことのない不思議な感触を覚えた。
猫のポーンを抱いて深い海を泳いでいた。インディラとミイラも一緒だった。
そしてその日、少年が初めてマスターに勝利したのだった。
いつしか少年はリトル・アリョーヒンと呼ばれるようになり、チェスを続けていくことになる・・・
アリョーヒンの棋譜は詩のように美しい・・・
あまり説明をすると、透明で静謐な小川ワールドをかき回して濁らせてしまうようで怖いので
この辺で止めておきます(^_^;)
物語の結末はとても悲しいのですが、何故か心が癒されて温かい気持ちになるのです。
余談ですが、リトル・アリョーヒンにチェスを教えたマスターは、甘いものが大好き。
廃バスの小さなキッチンを巨体で動き回り、ありとあらゆるお菓子を手づくりしていました。
私も、マスターとリトル・アリョーヒンにお相伴して、京都土産の“阿闍梨餅”をパクつきながら
活字に疲れた目を一休み・・・(笑)
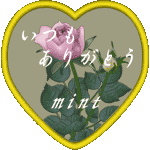
ozさん作

図書館で、熊井明子さんの『夢のかけら』という本を見つけ、借りてきました。
熊井さんの本は、一昨年の冬に『続続・私の部屋のポプリ』というエッセイに出会い、
数十年ぶりに復刻出版されたというその本の、
帯に書かれていた短い文章にとても惹かれて買ったのが初めてでした。
読むたびに幸せになれる素敵な文章にすっかりハマり、
小さな時間を見つけてはランダムにページを開いていたのですが、
数日後に起きた東日本大震災で家の中がごちゃごちゃになり、
どこにどう片づけたのか本の所在が分からなくなってしまいました。
『夢のかけら』は、エッセイではなく5編の短編小説を集めた本なのですが、
最初の短編「薔薇が香るとき」を読み始めてびっくり。
樹里という老女が出てくるのですが、これは間違いなく森茉莉のこと・・・
(本の何処にも森茉莉のこととは書いていませんが)
偶々心ひかれた本の著者が、私の好きな作家をモデルに短編を書いていたことも小さな驚きでした。
「安曇野の女」ヒロインは
、荻原碌山(彫刻家)の作品を、生涯を通して守り続けた作家の姪にあたる女性、妙。
安曇野を訪れることがあれば、碌山美術館を訪ね、
妙を生涯にわたり引きつけていた碌山の彫刻『女』に会ってみたい・・・そう思いました。
「懐剣と香水」では、
ヴェネチアでムッソリーニと会見した女流詩人が、ムッソリーニこそダンテの後裔と胸を高鳴らせ
自作の詩と、母の形見の懐剣を彼に捧げます。
ヨーロッパから帰国し、
戦争が始まった日本で、ペンを剣のように持ち愛国詩や軍歌を書いた女流詩人は、
戦後、そのことを後悔し、批判される中で償うように平和運動、婦人運動に関わっていきます。
女流詩人は、
「ムッソリーニに捧げた懐剣を心にとり戻し、自らを突き刺し、血を浴びながら今日まで生きてきた」
とその頃を振り返ります。
この女流詩人が深尾須磨子であることは、後付の参考文献からわかりますが、
熊井さんのエッセイ『続続・私の部屋のポプリ』の初めにも、彼女の詩が使われていました。
他にも2編の短編が収められていて、五人五様の女性が描かれています。
短編なので、読みやすく、でも心に響く何かを含んでいる、そんな本でした。
写真のケーキは矢吹町の“ハッピーベリー”のもの。
苺がものすごく甘くてジューシーで美味しかった~♥
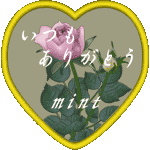
ozさん作
先週、探し物をしていた時に見つけた、中里恒子の『時雨の記』
今は亡き義母が、随分昔に私に貸してくれた本でした。
瑠璃紺の無地のハードカバーで、背に銀箔でタイトルと著者名があるだけのシンプルさ。
凛とした趣に、色焼けやシミによる年代物の風情も加わって味わいがあります(^_^;)
昭和52年が初刷ですから長男と同じ年の本です(笑)
何かの折に義母が貸してくれたのでしょうが、当時の私はほとんど興味が湧かず、
義母には申し訳なかったのですがそのまま積読状態でした。
懐かしくて手に取って眺めていたら、急に読んでみたくなりました。
旧仮名遣いがとても情緒的です。
ストーリーは、ひと言で言えば壬生と多江という熟年男女のプラトニックラブ。
多江は、昔壬生がまだ独身の頃、通夜に行った知人宅で見かけ強く心を引かれたけれど、
彼女が既婚者と知らされ、高嶺の花と諦めてしまった人でした。
それが、何十年か後に、知人の息子の結婚式の席で再会します。
壬生は五十半ばの会社社長で妻子あり、多江も四十を過ぎ、夫を亡くした未亡人。
壬生は強引とも思える押しの強さで、多江の家に通うようになります。
壬生にとって多江は、初花であって、終わりの花だと言います。
いつか一緒に暮らそうと言いながら、
二人が男女の一線を越えることは無いまま、壬生が心臓病で他界します。
ストーリー的にはベタですけど、古典的な文章がとても美しいです。
それに、私が心惹かれたのは、ストーリーよりも中里恒子的な美的感覚とでもいうのでしょうか
風情のある暮らし方、生き方でした。
例えばこんな件
(多江の家で、壬生が)
毛氈の上に出してある茶碗や、香合や、茶入れをひと通り見て、二つ三つ、脇へどけました。
それから壬生は、
「こんなもの、捨ててしまひなさいよ、」
「どうして、」
「あんたが持ってゐるには、ふさわしくない、高いの、安いの、といふことではありませんよ、僕がいやなんだ、」
「あなたのものでもあるまいし、」
「・・・・・そんなことは萬萬ないけれど、もしもだね、あなたの亡いあとに、誰かが、この道具を見るとしよう・・・・・さうすると、あなたの持ってゐるいい品まで、下がる・・・・・」
多江は、どきりとしました。
(中略)
ただ、數だけ揃へてあつたところで、どこに、執心が殘らうか。好きなものを、二つでも三つでも、多江らしいと言はれるものを殘した方が、どんなにか、すっきりするであらう、すぐ、それは、多江の心を波立たせました。
好きなものだけを少し持てばいい・・・そんな暮らし方に憧れます。
中里恒子の小説は初めてでしたが、過去にエッセイを何篇か読んだことがありました。
オムレツに拘る文章を見つけ、食いしん坊な私は直ぐにそれに食いついたのです(笑)
日々の食事のこと、庭の草花のことなど、日々の暮らしの愉しみが美しく書かれていました。
また、別のエッセイでは、
「安物でも気に入って使い続けたものは、味わいのある良いものに変わっていく」
というようなことも書いていたように思います。
中里恒子の作品をもっと読んで、彼女の審美眼にもっと触れてみたいと思いましたが、
出版社品切れなど本屋では手に入りにくく、そのまま過ぎてしまっていました。
私が『時雨の記』を義母から借りたときは、既に古本の風情を漂わせていたので、
義母はこの本が好きで何度も繰り返し読んだのだろうな、と思いました。
多江が壬生のお見舞いに、庭のナデシコをひと束ねにして持っていく件などは
義母が日課にしていた義父と義兄のお墓参りに、庭の草花を摘んで出かけて行く姿と重なりました。
定家が隠栖して和歌の編纂に打ち込んだとされる京都の時雨亭跡が
物語の中で重要な場面になっていたのも、和歌が好きな義母には気に入っていたのかもしれません。
遠ざかる夫の足音忍びつつ ただつつましく生きむとぞ思う
義父が亡くなった後、一人暮らしの中で義母が詠んだ歌・・・
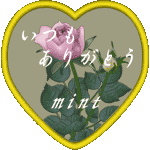
ozさん作
昨日は雨降りの一日だったので、読みかけだった本を開いて雨読の日。
森茉莉のエッセイ『父の帽子』
父鴎外を語る森茉莉は、
少女のように曇りのない眼差になっている、と私は思うのです。
切ないほどの愛情で包まれた茉莉の記憶の中の鴎外は
アルバムに貼られた写真が、映像になって動き出すように詳細に生き生きと語られ
「お茉莉は、綺麗だなぁ」
「よしよし、お茉莉のすることは何でも上等よ。」
まるで、茉莉が鴎外の膝の上に座って父の体温を感じているようです。
16歳で結婚し、19歳で父鴎外を失った茉莉にとって、
父と過ごした日々は色あせるどころか、濃密にその体温までを残したまま
森茉莉の人生に寄り添っていたのかもしれないですね。
16編が収められたエッセイ集ですが、「父の帽子」が作品のタイトルになっているのも
とってもお洒落だし、この本を手に取った理由の一つ。
帽子好きだった自分の父のことがチラッと思い出されたりもするものだから。
そして、森茉莉は家事はまるで駄目な人だったけれど、お料理だけは好きだったようです。
幼いころから親しんだ一流料亭とヨーロッパの味が身に沁み込んでいた森茉莉の
~マリア(森茉莉のこと)は、貧乏なブリア・サヴァランである~と始まる
『貧乏サヴァラン』
巻末には、茉莉のちょっとしたレシピも載っていて、食いしん坊mintにとってはこちらも面白い一冊。
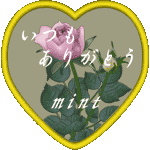
ozさん作
『恋しぐれ』・・・背表紙のタイトルだけ見たなら多分買わなかったと思うのですが
与謝蕪村、丸山応挙、上田秋成など豪華な登場人物と、
五十近い年の差を厭わぬ蕪村と祇園の妓女の恋路の結末は・・・と書かれた本の帯に
ワイドショー的ミーハー心が反応して、買ってしまいました(^_^;)
老いらくの恋・・・と片付けてしまうには、切なくて美しい。
老いが恋わすれんとすればしぐれかな
タイトルは、この句からきているのだろうか・・・
時代小説をほとんど読まないmintなので、葉室麟の本を読むのは初めてです。
初めは晩年の蕪村の評伝のような読み物かと思ったのですが、
どうやら、蕪村とその門弟、友人の句をもとに、葉室麟流の解釈で構築された小説のようです。
表紙のカバー絵は、蕪村の絵の門弟だった月渓(松村呉春)の「白梅図屏風」
白梅にあくる夜ばかりとなりにけり
臨終間際に蕪村が詠んだ辞世の句。
師匠の思いを絵に描きたいと思い続けた月経が、
「白梅図屏風」を仕上げたのは、蕪村が亡くなってから10年後のこと。
蕪村を支え、蕪村亡き後は蕪村の家族も支えていった弟子、月渓。
恋しぐれには、『月渓の恋』という、月渓の心の奥に閉じ込めた慟哭が漏れ聞こえてくるような
せつない短編も入っています。
葉室麟の淡々とした文章が、恋慕の情を抑えながら、抒情詩のような蕪村の俳句に相応しく
穏やかで静かな大人の恋愛を描いている物語だと思いました。
枯渇した侘び寂の俳句とは少し違う、感情豊かな瑞々しい蕪村の俳句を
もっと読んでみたいなと思わせる一冊でした。
読書のお供は、大心堂の雷おこし「古代」
雷おこしって特に好きなわけではありませんでしたが、このおこしは別格。
甘すぎず、落花生の香りと歯ごたえが風味を増して上品な味わいです。
白砂糖と黒砂糖の詰め合わせになっているようです。
オンラインショップもあるようですが、ひたすらお土産を待ちたい気持ち(笑)
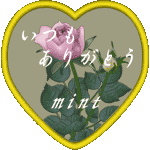
ozさん作

写真は先々週のムスクマロウ。
こんなに綺麗に咲いていたのに、先週の断続的な強い雨に打たれて倒れてしまい
その後の蒸し暑さもあってかヨレヨレになってしまい、思い切って切り戻しました。
みさと64さんによれば、若い葉は茹でたり炒めたりして食べられるそうですが、
花が咲いてしまって、ましてやもう倒れてしまっていますから、
どんなお味なのか試食の機を逃してしまいました。残念。
ブログアップがボチボチなので、撮り溜めた写真も賞味期限が切れてお蔵入り・・・
天気予報で、昨日は最後の晴れの日と脅かされ、母のタオルケットやらシーツを無理矢理剥いでお洗濯。
お部屋もプチ大掃除。
今日は筋肉痛なので、静かにブログでも綴ることにします(^_^;)
先月の個人的な読書週間が、静かにのろのろと続いていて今や読書月間に、いえもっと続くかも・・・
と言うことで、随分前に読んだ本なのですが、ドツボに嵌ってしまったヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』のことを。
実は、この『ダロウェイ夫人』、20代の頃に一度読んでいるのですが、複雑な構成に読破するのが面倒になってしまった本でした。
いつか読み返さなくてはと思いながら、その本はもう手元には無く、誰の訳だったのかも忘れてしまっていました。
前回記事にしたゲーテの『ファウスト』もそうでしたが、若い頃は背伸びをして本を選んでいたせいか、読んでいる本に置き去りにされていた感が拭えませんでした。
『ダロウェイ夫人』を読もうと思ったのは、数年前に、映画『めぐりあう時間たち』を観たのがきっかけでした。
そして、2年前、3年前?だったでしょうか、藤の花が満開の表紙の『ダロウェイ夫人』を書店で見つけて、つい買ってしまいました(笑)
乱雑な引き出しを開けたように、時間も登場人物もランダムになって交差する、
あれほど読みにくいと思ったウルフの文章が、不思議にさらさらと流れ、美しい散文詩のように感じたほど。
以前の古臭く気取った感じがしないと思うのは、丹治愛さんの訳によるところなのか、
私も年を取って古くなったからなのか・・・(笑)
もう、クラリッサ・ダロウェイの年齢をとうに過ぎていますからねぇ^_^;
滴る緑に包まれたロンドンの、6月のある日の晴れやかな早朝、
ミセスダロウェイがその夜開くことになっているパーティーのための花を、
自ら買いに出かけるところから始まり、パーティがお開きになる真夜中までの一日を書いた物語です。
クラリッサが「なんてすてきな朝だろう」と感じた6月のその日は、生命力にあふれ、ロンドンでも最も美しい季節でしたが、
第一次世界大戦が終わったばかりで、まだた死の影が所々に残っている時代でもありました。
清々しい朝は、突然クラリッサを青春時代に過ごしたある夏の日にと意識を運びます。
50歳を過ぎ、自分の中に忍び寄る老いを脅迫のように感じているクラリッサの意識が、過去と行き来します。
そしてその意識は、登場人物の意識へと変わり、物語の中で交差します。
一見バラバラに思える意識が繋がり始めるのを感じると、物語から離れられなくなってしまいます。
ウルフが試みた、登場人物の背後に美しい洞窟を掘ることによって過去を自在に「現在の瞬間」によみがえらせる手法を、「トンネル掘りのプロセス」と詠んだそうです(訳者あとがき)
何となく村上春樹の小説を思い出しました。彼も確かトンネル堀りが好きな作家(笑)
あ~、限がないのでこの辺にしておきます。(^_^;)
何となく風が湿っぽくなってきました。
やはりお天気は崩れるのでしょうか。
こちらも先々週の、アスチルベ。
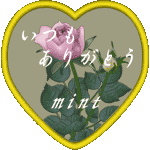
ozさん作

ミニバラが花盛り。
シラン。花姿はすてきなのですが繁殖力が旺盛でちょっと持て余し気味(^_^;)
先週、二日ほど庭の草引きをしたら、アレルギーのお薬を飲んでも鼻水が止まらない・・・
鼻や目の周りがヒリヒリとして、あ~これはヤバいかも(T_T)
スギ花粉はそれほどでもなかったのに、今年はカモガヤの花粉に悩まされています。
カモガヤ草は、英名をオーチャードグラスと言い、なんだかステキな響きの名前ですが、
アレルギーを持つ人にとって症状は強烈そうです。
今年は近所でもやけに目に付きますし、いつもの年より草丈が高いような・・・気のせいでしょうか。
掛かりつけのクリニックで、新しいお薬をプラスしていただきました。
暫くは庭仕事も止めにして引き籠ることに・・・
引き籠り・・・実は結構好きです。積読状態の本もたくさんありますし。
読書には、お供も欠かせない

さて、何の本でしょう?(笑)
戯曲ですね。 見ればわかるって?ごもっともです(^_^;)
初めてゲーテの作品を読んだのは中学生の頃、ジュニア版世界文学全集の『若きウェルテルの悩み』でした。
恋する乙女になりかけの頃でしたから、結構夢中になって読み、誰かウェルテルのような悩みを私にも持ってはくれないかな~と憧れたのを覚えています。
誰かを好きになりたいではなく、誰かが私を好きにならないかなという我儘な憧れです(笑)
ゲーテはなかなかハンサムのようでしたし、他の作品も気になり、家の本棚を探して見つけたのは、
森鴎外訳の「ファウスト」
悪魔が出てきたりと面白そうだったのですが、中学生の私には文章が格調高すぎて途中で面倒に(^_^;)
今、我が家にあの本が見当たらないということは、あれは父の本だったのかしら?
母の荷物はどんながらくた(?)でも持って来たはずだから、引っ越しの時、他の荷物と一緒に処分されちゃったのかな・・・
ゲーテとはそれっきりでした。
それが、学生で一人暮らしをする息子の所へ足繁く通っていた頃、大丸東京の三省堂書店で偶然出会った柴田翔訳の「ファウスト」。
彼の作品は学生時代によく読んだ思い出があったので、柴田訳『ファウスト』を迷わず一部と二部まとめて買いました。
帰りの新幹線ですっかり本読みに没頭した私は、あわや郡山駅を乗り越しそうになり慌てて降りて、なんと本を車中に置き去りに・・・失くしたことに気が付いたのは翌日でした(T_T)
まだ第一部の初めの方、ファウストの書斎にメフィストや霊たちが現れた辺りまでしか読んでいなかったのですが、すぐさま新しいのを買う気にもなれずそのままになってしまいました。
そして数年前、地元デパートの本屋さんが八重洲書店からジュンク堂書店に変わって間もなく、探していたわけではなかったのですが、一部と二部が一冊にまとまっていて3000円というお値ごろな「ファウスト」に出会いました。
知らない方の訳でしたが、ファウストについての本も書かれていて、マルクスの翻訳本も出されているようなので、即買いで我が家の本棚へ収めましたが、暫くはそのまま^_^;
「ファウスト」については名訳と言われる本が他にもあるようですが、注釈が細かく、ページを行ったり来たりしなくても読めるようになっている小西先生の本は、知識のない私が読むにはピッタリでした。
読んだのは昨年の10月。妹が入院していた病院を行ったり来たりしていた時のことでした。
そして今年の春、同じジュンク堂書店で山本容子さんの銅版画が装丁や挿絵に使われている、絵本の様な『ファウスト』を見つけ、思わず買ってしまいました。
ただ今、引っ張り出して読んでいます。
池内紀氏の訳は、かなり現代的な口語調でテンポが良く、ファウストとメフィストとの掛け合いは、まるで漫才のようです。
もちろん読書のお供は欠かしません。
今度の『ファウスト』のお供には、東京土産に頂いたブールミッシュの『シブースト』
なんだか語呂がいいですね~(笑)
一見地味ですが、とっても美味しいお菓子なんですョ。
パイ生地にバターでソテーしたりんご、ゼラチンとメレンゲを合わせたカスタードクリームをのせ
表面を焦した、タルトタタンとクレームブリュレを合体させたようなお菓子。
名高い宮廷菓子職人だったシブーストが書き残したというレシピを
150年ぶりに、ブールミッシュ店主が再現した云々と栞には書いてありました。
大、大、大好きなお菓子なので、冷蔵庫の奥に隠してこっそり独り占めしたいくらい(笑)
この一切れが最後なので、ファウストのように「時よ、止まれ!」と叫びたいです(笑)
あらら、お話が横道に(^_^;)
最初に買った「ファウスト」は訳者に惹かれて買いましたが、
その次はお値段に惹かれて(笑)
3冊目は、装丁に惹かれて(笑)
自分でも、本を買う動機が本当にいい加減だなぁと思うのですが、装丁に惹かれて買うことは多いです。
特に翻訳本に関しては。
だって、原文が読めないんですから、良い訳かどうかなんてわかりませんもの~。
見かけに騙されやすいタイプでしょうか、私(^_^;)
ただ、一冊で済ませてしまうには危険が多いので、翻訳本は2冊以上読むようにしています。
もちろん2冊目はお値段が安い文庫本か、図書館で借りてきて、あるいはその反対も。
今回のように2冊目(正確には3冊目?)も、外側に惹かれるのは例外です^^;
お気に入りの装丁の本と美味しいお菓子・・・至福の時です ♥
そして、懲りずに柴田翔訳が欲しいかも^^;
本読みが始まると、なかなかPCの時間が取れなくて・・・
ご訪問のコメントができずにいるご無礼をどうぞお許しくださいませ~<(_ _)>
そろそろ目がショボショボしてきましたので、読書も程々にしませんと今度は眼科のお世話になりそうです(苦笑)
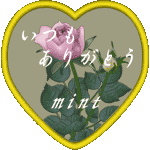
ozさん作

妹の付添いをしていた時、傍に置いて時々ページを開いていた、白洲正子の『私の百人一首』
著者が六十の手習いと称して手がけた小倉百人一首の解釈は、選者の定家を含め百人百様の人間模様を見るようでとても興味深く読みました。
母がかるた好きで、お正月には家族でかるた取りをしていたことから、何となく百人一首は知っていたのですが
子どもなので、一首ずつきちんと読んで鑑賞したりはせず、一字きまりやゴロ合わせで覚えて、少しでも早くたくさん取るという超合理的な方法で覚えた百人一首でした(^_^;)
一字きまりというのは、例えば
「村雨の露もまだひぬ真木の葉に 霧立ちのぼる秋の夕暮」という寂蓮法師の歌がありますが、
「む」で始まる歌は、この寂蓮法師の歌しかありませんから、読み手が「む」と言ったら後の続きは聞きもせず、取り札のはじめに「霧」と書いてあるものを目をギラギラさせて探すわけです。
歌の内容にはお構いなしです(笑)
「す」と言ったら「夢」、「め」と言ったら「雲」などの一字きまりの札は何枚かあって、誰よりも早く取れると誇らしい気持ちになる、スポーツみたいなかるた取りでした。
今思うとなんとも味気ないですよね~(^_^;)
 著者が京都の骨董屋で見つけたというかるたの美しい読み札が
著者が京都の骨董屋で見つけたというかるたの美しい読み札が
一番歌から順に載っていて、眺めているだけでも楽しいです♪
高校1年の時の古文の先生が、バツイチ子持ちのなかなかチャーミングな先生で
「個人的には、お高い紫式部より、ゴシップに事欠かなかった和泉式部の方が好みだった」とか
和歌に解説を加えるとき、
「うっとりするような一首だけど、恥ずかし過ぎる~」などと顔を赤らめて、個人的な感想も入れながら楽しい授業をしてくだったのを覚えています。
その頃から、古典作品を読むのが好きになったような気がします。
 和泉式部の読札
和泉式部の読札
『あらざらむこの世のほかの思ひでに 今ひとたびの逢ふこともがな』
恋多き女と言われた和泉式部は、夫がありながら二人の親王と恋に落ち、親王は二人とも早世しその後再婚もしているという経歴の持ち主ですが、
晩年「私はもうすぐ死んでしまうかもしれない、あの世へ行く思い出に、せめてもう一度あなたにお会いしたいものです。」
と、切々と詠んだこの歌が、最初の夫の道貞へ送った歌と言われています。
であるとすれば、悲しすぎるな~と思ってしまいますね。
白洲正子は、数ある和泉式部の歌の中から定家はなぜこの一首を選んだのか、とか、和泉式部を評した紫式部の文や、和泉式部集、後拾遺集などからも和歌を引いて、和泉式部の人となりに触れ、歌を鑑賞しています。
それは、他の作者においても同様で、歌の訳よりも詠み手の人間関係や置かれた立場などに思いを馳せながら百人一首を紐解き、この本を書いたようです。
たった31文字の和歌から広がる、王朝時代の人々のおおらかな恋愛模様や恨み辛みの情の深さ。
読めば読むほど、新鮮な気持ちで味わうことができます。
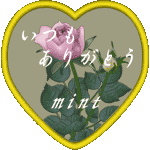
ozさん作














