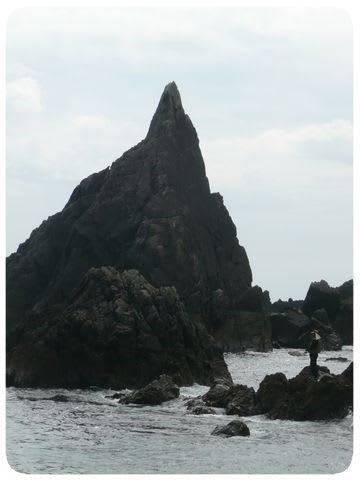以前、明石大橋を紹介した際、明石海峡大橋のあるJR舞子の駅にも降り立ってみようと言っていました。その思いを実現するため、清水の舞台から飛び降りるような気持ちで西明石駅から170円の切符を買って、舞子駅で降りたのでした。
当日は天気は良かったものの、遠くが霞んで見え、大橋の先にある淡路島もくっきりとは見えません。

これが何だか解りますか。お花畑ではありませんよ。蜂の巣に色を塗ったものでもありません。

離れて見ると、全体は丸いのです。
この写真で右上の高架は明石海峡大橋で、左の建物は『橋の科学館』です。

これは大橋を吊っているワイヤーですね。何本あるのか判りませんが、六角に束ねたワイヤーをまた丸く束ねたのではありませんね。見てくれのいいように後でペンキを塗ったのでしょう。

『橋の科学館』は有料なので入館はしませんでした。だからあのワイヤーは何本束ねてあるのかとか、大橋の詳しいことは判りません。

舞子駅から大橋の袂一帯へ行く途中の歩道橋からの明石海峡大橋の眺めです。
この写真では人が写っていませんが、観光客や修学旅行の学生と思われる人で賑わっていたのですよ。

この辺りの案内図、きれいですが何が書いてあるのか判りませんね。

前述の歩道橋の上から西方面を眺めたもの、明石市が写っているものと思います。

当日は天気は良かったものの、遠くが霞んで見え、大橋の先にある淡路島もくっきりとは見えません。

これが何だか解りますか。お花畑ではありませんよ。蜂の巣に色を塗ったものでもありません。

離れて見ると、全体は丸いのです。
この写真で右上の高架は明石海峡大橋で、左の建物は『橋の科学館』です。

これは大橋を吊っているワイヤーですね。何本あるのか判りませんが、六角に束ねたワイヤーをまた丸く束ねたのではありませんね。見てくれのいいように後でペンキを塗ったのでしょう。

『橋の科学館』は有料なので入館はしませんでした。だからあのワイヤーは何本束ねてあるのかとか、大橋の詳しいことは判りません。

舞子駅から大橋の袂一帯へ行く途中の歩道橋からの明石海峡大橋の眺めです。
この写真では人が写っていませんが、観光客や修学旅行の学生と思われる人で賑わっていたのですよ。

この辺りの案内図、きれいですが何が書いてあるのか判りませんね。

前述の歩道橋の上から西方面を眺めたもの、明石市が写っているものと思います。