私の勤務先は明治10年10月に当時の国立銀行条例に
に則ってできた国立銀行の生き残りです。
単独で存続する銀行で国内最古のものは新潟県の第四銀行。うちが2番目だそうです。
そんな象徴的な建物が勤務先のセンター界隈にあります。

このお家です。1階は連子格子(れんじごうし)の商家風の造りです。
2階の窓は鉄格子をはめ、壁を漆喰で固めた堅牢な造りです。

そして2階の庇の下に隣との防火用でしょうか、
「袖壁(そでかべ)」なるものが付いています。
袖壁はよく宿場町などで見かけます。
一見「うだつ」のようにも見えますが、
「うだつ」は屋根の上にあって、防火壁の上に瓦が載せてあります。
そして1階と2階の間にあるものを「袖うだつ」というそうですが、
瓦が載っているのが違いだそうです(うだつの研究より)。
このお家がなんで象徴的な建物かというと、使ってある瓦にヒントがあります。

鬼瓦に「銀」の字。
これこそ、我が銀行のカールトンなどに使われていた「マル銀」マークなのです。

反対側の屋根にも「マル銀」マークがありますね。
勤務先の歴史的建造物というと旧徹明支店とか明知支店とかありますけれど
ここも歴史的建造物のひとつではないでしょうか?
「いい建物だね~」と思われた方はクリックしてくださいね~♪
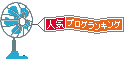
人気ブログランキングへ
↑
日々更新の励みになりますので、クリックをお願いいたします。
に則ってできた国立銀行の生き残りです。
単独で存続する銀行で国内最古のものは新潟県の第四銀行。うちが2番目だそうです。
そんな象徴的な建物が勤務先のセンター界隈にあります。

このお家です。1階は連子格子(れんじごうし)の商家風の造りです。
2階の窓は鉄格子をはめ、壁を漆喰で固めた堅牢な造りです。

そして2階の庇の下に隣との防火用でしょうか、
「袖壁(そでかべ)」なるものが付いています。
袖壁はよく宿場町などで見かけます。
一見「うだつ」のようにも見えますが、
「うだつ」は屋根の上にあって、防火壁の上に瓦が載せてあります。
そして1階と2階の間にあるものを「袖うだつ」というそうですが、
瓦が載っているのが違いだそうです(うだつの研究より)。
このお家がなんで象徴的な建物かというと、使ってある瓦にヒントがあります。

鬼瓦に「銀」の字。
これこそ、我が銀行のカールトンなどに使われていた「マル銀」マークなのです。

反対側の屋根にも「マル銀」マークがありますね。
勤務先の歴史的建造物というと旧徹明支店とか明知支店とかありますけれど
ここも歴史的建造物のひとつではないでしょうか?
「いい建物だね~」と思われた方はクリックしてくださいね~♪
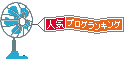
人気ブログランキングへ
↑
日々更新の励みになりますので、クリックをお願いいたします。













