旅行記を中断して、秋田の話題です。
昨年11月の記事の通り、秋田駅東口直結の「秋田拠点センター“アルヴェ”(ALVE、アルベ)」の14階にあった飲食店が閉店し、改装工事が行われていた。
年が明けても、飲食店があった部分は閉じられており、やけに長期間の工事だったが、それがやっと終わったとの話を聞いたので、行ってみた。
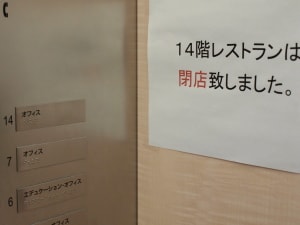 エレベーター内
エレベーター内
レストラン閉店の貼り紙が大きくなっているが、「14」のボタンの横には「オフィス」とある?!
 14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる
14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる
右に目を転じると…


飲食店入口だった部分にガラスのドアがある。そして、
 無情な警告
無情な警告
「これから先は大塚製薬グループに御用がある方以外の入室はご遠慮ください」
飲食店跡地はオフィスとなり、そこに入居しているのは大塚製薬・大塚製薬工場・アース製薬という、大塚グループの企業のようだ。
「大塚製薬工場」というのは初めて聞いたが、ここに工場があるわけではなく、そういう会社名で、医薬品からオロナインやオロナミンCまで、様々な製品の開発・製造・販売を行っている(販売は別会社がしている製品もある)企業らしい。
ネットで調べると、ここには各社の「秋田出張所」が置かれており、以前は3社とも泉北二丁目(グランマートの向かい、コメリのそば)に秋田出張所があったので、揃って駅前へ移転してきたようだ。
このご時世に秋田駅前に進出してきて、1フロアを占有するとは、なかなかやりますな。ちなみに大塚の創業地・現在の拠点は、旅行記で紹介中の徳島。
 14階のフロアガイド
14階のフロアガイド
青い部分が各社のオフィスなので、ガラスドアの向こうも東側には窓際に廊下があるようだ(薄いグレーの部分)。下の赤い四角で囲った部分しか一般人は立ち入れないわけだが、ちょっと見にくいが、その名称が「エレベーターホール」になっている。ん?
 改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略)
改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略)
この図では、「展望ロビー」となっている。
場所自体はまったく変化していないのに、以前は「展望ロビー」だった部分が、飲食店閉鎖・オフィス化後は「エレベーターホール」に名前だけ変わったわけだ。
次に、
 各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア)
各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア)
14階には「オフィス(エレベーターホールは展望可)」とある。
なんとなく「オフィスだけど景色を見たけりゃ見ていいよ」と恩着せがましい気がしてしまう。今まで通り「展望ロビー」じゃいけないの?
これらの言い回しによって「あそこはあくまでもエレベーターホール」「展望したければ見ていいよ」すなわち、「積極的には展望しに来てほしくない」と言っているようにとれてしまうのは僕だけだろうか?
たしかにオフィスの前をいろんな人がうろうろしていては迷惑なのかもしれないけれど。
アルヴェは、官民共同で建てられ、秋田駅前の拠点として、いろんな人が交流できて賑わいのある施設を目指していたはず。
だからこそ、展望スペース(かなり貧弱だが)があったのだろうし、お金を払って飲食店に入れば、誰でも14階からの各方位の景色を楽しめたのだろう。
そんな場所を、大塚製薬の関係者という、ごく限られた人だけしか景色を眺められない空間に変えてしまったというのは、いかがなものか。
この部分はおそらく民間所有で、公的資金は投入されていないのかもしれないし、ビル運営会社にしてみれば、いつ潰れて出て行くか分からない飲食店よりも、大手企業が店子さんになって家賃を納めてくれた方が安心で確実なのも分かる。
でも、ここは上記の通り、秋田駅周辺の賑わい創りを目的に建てられたビル。単なるオフィスビルや雑居ビルじゃないんだ。そこに製薬会社の事務所が入っても、新たな賑わいにはならないだろうし、駅前を訪れるほとんどの一般人(市民や旅行客)には何のメリットもない。
うまく言えないが、本件には秋田市民としてはがっかりしてしまったし、日赤病院跡地にできるという建物もこのようになるのではと、とても心配になってきた。
東側しか見えず、かつ「エレベーターホール」という名に成り下がってしまった場所だが、僕がいた2・3分の間に、若い女性2人組と年配のご夫婦が来て景色を眺めていった。秋田に帰省している人だろうか、旅行客だろうか。
やっぱり景色を見たいという需要はあるんだ。オフィスとして閉じてしまった空間を少しでも開放することはできなかったのだろうか。
 ガラスは先日の黄砂で汚れていた
ガラスは先日の黄砂で汚れていた
単なる「エレベーターホール」となってしまった以上、このガラスがきれいになって“展望”できる日は来るのだろうか。
【4月27日追記】この記事アップ後、久しぶりに14階に行ったところ、ガラスはきれいに拭かれて黄砂の汚れは取れていたことを、いちおう付記しておきます。
昨年11月の記事の通り、秋田駅東口直結の「秋田拠点センター“アルヴェ”(ALVE、アルベ)」の14階にあった飲食店が閉店し、改装工事が行われていた。
年が明けても、飲食店があった部分は閉じられており、やけに長期間の工事だったが、それがやっと終わったとの話を聞いたので、行ってみた。
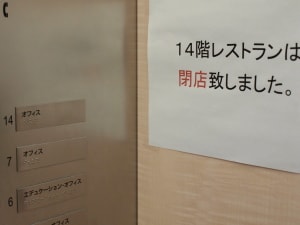 エレベーター内
エレベーター内レストラン閉店の貼り紙が大きくなっているが、「14」のボタンの横には「オフィス」とある?!
 14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる
14階へ到着。従来通り正面に太平山が見渡せる右に目を転じると…


飲食店入口だった部分にガラスのドアがある。そして、
 無情な警告
無情な警告「これから先は大塚製薬グループに御用がある方以外の入室はご遠慮ください」
飲食店跡地はオフィスとなり、そこに入居しているのは大塚製薬・大塚製薬工場・アース製薬という、大塚グループの企業のようだ。
「大塚製薬工場」というのは初めて聞いたが、ここに工場があるわけではなく、そういう会社名で、医薬品からオロナインやオロナミンCまで、様々な製品の開発・製造・販売を行っている(販売は別会社がしている製品もある)企業らしい。
ネットで調べると、ここには各社の「秋田出張所」が置かれており、以前は3社とも泉北二丁目(グランマートの向かい、コメリのそば)に秋田出張所があったので、揃って駅前へ移転してきたようだ。
このご時世に秋田駅前に進出してきて、1フロアを占有するとは、なかなかやりますな。ちなみに大塚の創業地・現在の拠点は、旅行記で紹介中の徳島。
 14階のフロアガイド
14階のフロアガイド青い部分が各社のオフィスなので、ガラスドアの向こうも東側には窓際に廊下があるようだ(薄いグレーの部分)。下の赤い四角で囲った部分しか一般人は立ち入れないわけだが、ちょっと見にくいが、その名称が「エレベーターホール」になっている。ん?
 改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略)
改装工事中の同じ図(工事部分は隠されていたので省略)この図では、「展望ロビー」となっている。
場所自体はまったく変化していないのに、以前は「展望ロビー」だった部分が、飲食店閉鎖・オフィス化後は「エレベーターホール」に名前だけ変わったわけだ。
次に、
 各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア)
各階にあるご案内(抜けている階はビジネスホテルの占有フロア)14階には「オフィス(エレベーターホールは展望可)」とある。
なんとなく「オフィスだけど景色を見たけりゃ見ていいよ」と恩着せがましい気がしてしまう。今まで通り「展望ロビー」じゃいけないの?
これらの言い回しによって「あそこはあくまでもエレベーターホール」「展望したければ見ていいよ」すなわち、「積極的には展望しに来てほしくない」と言っているようにとれてしまうのは僕だけだろうか?
たしかにオフィスの前をいろんな人がうろうろしていては迷惑なのかもしれないけれど。
アルヴェは、官民共同で建てられ、秋田駅前の拠点として、いろんな人が交流できて賑わいのある施設を目指していたはず。
だからこそ、展望スペース(かなり貧弱だが)があったのだろうし、お金を払って飲食店に入れば、誰でも14階からの各方位の景色を楽しめたのだろう。
そんな場所を、大塚製薬の関係者という、ごく限られた人だけしか景色を眺められない空間に変えてしまったというのは、いかがなものか。
この部分はおそらく民間所有で、公的資金は投入されていないのかもしれないし、ビル運営会社にしてみれば、いつ潰れて出て行くか分からない飲食店よりも、大手企業が店子さんになって家賃を納めてくれた方が安心で確実なのも分かる。
でも、ここは上記の通り、秋田駅周辺の賑わい創りを目的に建てられたビル。単なるオフィスビルや雑居ビルじゃないんだ。そこに製薬会社の事務所が入っても、新たな賑わいにはならないだろうし、駅前を訪れるほとんどの一般人(市民や旅行客)には何のメリットもない。
うまく言えないが、本件には秋田市民としてはがっかりしてしまったし、日赤病院跡地にできるという建物もこのようになるのではと、とても心配になってきた。
東側しか見えず、かつ「エレベーターホール」という名に成り下がってしまった場所だが、僕がいた2・3分の間に、若い女性2人組と年配のご夫婦が来て景色を眺めていった。秋田に帰省している人だろうか、旅行客だろうか。
やっぱり景色を見たいという需要はあるんだ。オフィスとして閉じてしまった空間を少しでも開放することはできなかったのだろうか。
 ガラスは先日の黄砂で汚れていた
ガラスは先日の黄砂で汚れていた単なる「エレベーターホール」となってしまった以上、このガラスがきれいになって“展望”できる日は来るのだろうか。
【4月27日追記】この記事アップ後、久しぶりに14階に行ったところ、ガラスはきれいに拭かれて黄砂の汚れは取れていたことを、いちおう付記しておきます。










 “徳バス”こと徳島バス
“徳バス”こと徳島バス 浜でワカメの水揚げをしていた
浜でワカメの水揚げをしていた

 橋を挟んで反対側には土産物屋が集まる
橋を挟んで反対側には土産物屋が集まる 千畳敷からの眺め
千畳敷からの眺め 大鳴門橋の真下へ
大鳴門橋の真下へ 大鳴門橋遊歩道・徳島県立「渦の道」に入場
大鳴門橋遊歩道・徳島県立「渦の道」に入場 始めはこんな通路。途中にベンチがあった
始めはこんな通路。途中にベンチがあった おおっ! 下に渦潮が!!
おおっ! 下に渦潮が!! 床に窓があり、その真下に渦潮が!!
床に窓があり、その真下に渦潮が!! 展望室。下を観潮船が通った
展望室。下を観潮船が通った 橋の真下、橋脚付近
橋の真下、橋脚付近

 船は果敢に渦に入っていく
船は果敢に渦に入っていく 鳴門公園のバス乗り場には、バスが2台待機してた
鳴門公園のバス乗り場には、バスが2台待機してた 市営バス正面の鳴門市の市章。渦潮だ
市営バス正面の鳴門市の市章。渦潮だ


