| 二度殺せるなら Kill and Tell |
||
|---|---|---|
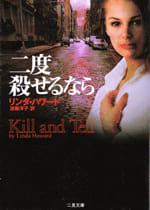 |
読了日 | 2018/09/20 |
| 著 者 | リンダ・ハワード Linda Howard |
|
| 訳 者 | 加藤洋子 | |
| 出版社 | 二見書房 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 356 | |
| 発行日 | 1999/02/25 | |
| ISBN | 4-576-99004-7 | |
 の物事に対するスランプ状態から抜け出すためには、どうも読書しかないようだ。パソコンの故障を直すためには、しばらくメールの配達の仕事を頑張るのだが、パソコンとインターネットで、その仕事の効率化を図ろうとしていた矢先の故障だったから、当分パソコンなしの落ち着いた生活もいいかな、そんな気分でいたのに、読書に対する意欲が少しずつ高まりつつある今、大分サボってしまったブログの隙間を埋めようとしても、肝心のインターネット環境が整わないから、困ったものだ。
の物事に対するスランプ状態から抜け出すためには、どうも読書しかないようだ。パソコンの故障を直すためには、しばらくメールの配達の仕事を頑張るのだが、パソコンとインターネットで、その仕事の効率化を図ろうとしていた矢先の故障だったから、当分パソコンなしの落ち着いた生活もいいかな、そんな気分でいたのに、読書に対する意欲が少しずつ高まりつつある今、大分サボってしまったブログの隙間を埋めようとしても、肝心のインターネット環境が整わないから、困ったものだ。
今年の11月2日、79歳の誕生日までに1900冊には程遠くなってしまって、いまさら急いでも到底無理なことはわかっているが、それでも何とか目標の数値に近づけようとしている。
というのは、本書を読んだ昨年9月の事だ。いまさらという感じだが、80歳2000冊という目標から、遠く離れてしまった遅れを、いくらかでも取り戻そうと、毎日読書に励んでいるが、僕の読書は励むものではなく、純粋に楽しむものだから、そうはいってもそれほどスピードが増すわけではない。
今のところはわずかに昨年読み終わっている本について、記録をブログにアップロードしているだけで、早くそれを済ませて、今進行中の本の記録に移りたい。

図書館を利用することで、古書を買うことからは半年ばかりの間、遠ざかっていたが、何もいろいろ自分を窮屈な状態に落とし込まなくてもいいじゃないかと、都合のいい、言い訳を心の中でしている。
まあ、とにかく読書だけでも細々と続ける意欲がよみがえったことだけでも、いいんじゃないの?僕の中ではいろいろと思いが交錯している。 息子がお世話になっている福祉施設の、保護者・家族の会のために会報作りをしていたのが、パソコンの故障のために、何回か休まなくてはならなくなったことも、僕のスランプ状態を引き起こした要因の一つで、それでも何も考えずにその日その日を漫然と過ごすのもいいか、などという気もあったりして・・・・。
唯一の慰めは、3月半ばから始めたメール便配達という仕事が、思いのほか面白くて、月水金に配達物が届けられることだけを、楽しみにしている状態が続いている。
今読み返すと、この時期は本人は意識してないのかもしれないが、かなり落ち込んでいたことがわかる。何にしても今、読書への意欲も普段の生活も以前の姿に帰りつつあることに満足している。

 およそ東西3㎞、南北2㎞の広さの団地内とはいえ、全域の地理や住宅配置図を記憶することは難しいから、配達時にはその都度作る配達先名簿と、動態地図をもって仕事にあたる。
およそ東西3㎞、南北2㎞の広さの団地内とはいえ、全域の地理や住宅配置図を記憶することは難しいから、配達時にはその都度作る配達先名簿と、動態地図をもって仕事にあたる。
だがそれでも時には迷うこともあって、だからこそその奥深さにも面白さを感じるのかもしれない。
僕はだらだらと無意味な生活に陥ることを防ぐため、起床や食事の時刻などを、できるだけ規則正しくしている。朝は6時から6時30分の間に起きて、洗顔歯磨きから朝食までを7時30分までに済ます。
12時から13時の間に昼食、夕食は6時から軽くとって7時までに歯磨きをする。とまあ、以上が僕の一日の日程だ。なぜそのようなことを心掛けているかといえば、やはり健康面への気遣いだ。歳を取るにしたがって、若いころのように無理がきかなくなっているから、無理をせずにできることといえば、時間を決めてできるのがそのくらいのものだろう。
長生きをしようとは思わないが、健康を維持することには少しの気遣いを心掛けようと、思っている。
今日は雲が多く、日差しが少し少ない分、ストーブの出番が多くなるのが、ちょっと気がかりだ。
にほんブログ村 |













 年10月から、ガードナー氏のぺりイ・メイスン・シリーズの長編全作を読み切ったほどの情熱はないものの、またぞろ、この作者の著作を読み続けてみようか?などとも思えるようになった。
年10月から、ガードナー氏のぺりイ・メイスン・シリーズの長編全作を読み切ったほどの情熱はないものの、またぞろ、この作者の著作を読み続けてみようか?などとも思えるようになった。 が国でも多くの女性作家が活躍しており、特に新人作家の登竜門ともいうべき、ミステリー賞の受賞者を受賞して、活躍する女性作家の多いことが、僕にはミステリーやサスペンス小説が、女性作家の専門になりつつあるような気さえしている。
が国でも多くの女性作家が活躍しており、特に新人作家の登竜門ともいうべき、ミステリー賞の受賞者を受賞して、活躍する女性作家の多いことが、僕にはミステリーやサスペンス小説が、女性作家の専門になりつつあるような気さえしている。
 却期限の10月4日、「櫻子さんの足下には死体が埋まっている ジュリエットの告白」を返しに、木更津市立図書館に行って、本書を借りてきた。「櫻子さん・・・」はもっと前に読み終わっていたので、早く返しに行こうと思いながら、ズルズルと期限いっぱいまで手元に置いてしまった。
却期限の10月4日、「櫻子さんの足下には死体が埋まっている ジュリエットの告白」を返しに、木更津市立図書館に行って、本書を借りてきた。「櫻子さん・・・」はもっと前に読み終わっていたので、早く返しに行こうと思いながら、ズルズルと期限いっぱいまで手元に置いてしまった。 生は儚く短い。この世を去るときは、多分あれもこれも読みたかったと、思うに違いないが、できる限りそうした思いを少なくしておきたいと思う。
生は儚く短い。この世を去るときは、多分あれもこれも読みたかったと、思うに違いないが、できる限りそうした思いを少なくしておきたいと思う。
 日から過去の記事を少しずつ修正している。と言っても記事の内容ではなく、記事の頭に設定してあるドロップキャップや、記事と記事の間にある飾り罫が、表示不可となっているのを表示するための修正だ。
日から過去の記事を少しずつ修正している。と言っても記事の内容ではなく、記事の頭に設定してあるドロップキャップや、記事と記事の間にある飾り罫が、表示不可となっているのを表示するための修正だ。
 隆三氏と中原理恵氏の主演によるドラマは、いかにも斎藤澪氏の作品だと思わせる、田舎の港町で起きた船員の殺害事件を追う話で、静かなそして少し暗い雰囲気で進む展開が、1989年制作の古さもあってか、観ていて物憂い感じを抱かせたものの、まあまあみられる出来だった。
隆三氏と中原理恵氏の主演によるドラマは、いかにも斎藤澪氏の作品だと思わせる、田舎の港町で起きた船員の殺害事件を追う話で、静かなそして少し暗い雰囲気で進む展開が、1989年制作の古さもあってか、観ていて物憂い感じを抱かせたものの、まあまあみられる出来だった。
 月10日に行われた薄光会の保護者・家族の会、役員会で、使ったパワーポイントによるプレゼンテーションに、音声による説明を加えるため、ここ一日二日パワーポイントをいじくりまわした。 前にも書いたが、以前薄光会法人の監事を務めていたころは、プレゼンの作成も毎年行っていたから、割合慣れていたはずなのだが、しばらく離れていたことや加齢による物忘れも重なって、簡単なプレゼンにも結構手間がかかる。
月10日に行われた薄光会の保護者・家族の会、役員会で、使ったパワーポイントによるプレゼンテーションに、音声による説明を加えるため、ここ一日二日パワーポイントをいじくりまわした。 前にも書いたが、以前薄光会法人の監事を務めていたころは、プレゼンの作成も毎年行っていたから、割合慣れていたはずなのだが、しばらく離れていたことや加齢による物忘れも重なって、簡単なプレゼンにも結構手間がかかる。 者・柚月裕子氏の最新刊を木更津市立図書館で借りてきた。いつもは早く予約したつもりでも二番手か三番手だが、今回は本の状態から僕が一番手だったことがわかる。新しい本は比較的きれいな状態で読めるのだが、たまに煙草の灰が挟まっていたり、コーヒーのようなシミが有ったりと、本を大事に扱わない輩もいて、不愉快な思いをさせられることもあるから、できるだけ早く読みたいというのは、時間的なことばかりでなく、きれいな本を読みたいという気持ちがあるからだ。
者・柚月裕子氏の最新刊を木更津市立図書館で借りてきた。いつもは早く予約したつもりでも二番手か三番手だが、今回は本の状態から僕が一番手だったことがわかる。新しい本は比較的きれいな状態で読めるのだが、たまに煙草の灰が挟まっていたり、コーヒーのようなシミが有ったりと、本を大事に扱わない輩もいて、不愉快な思いをさせられることもあるから、できるだけ早く読みたいというのは、時間的なことばかりでなく、きれいな本を読みたいという気持ちがあるからだ。
 書店で安く買い求めたものでISBNの表記がなく、Amazonで新装版の番号を調べて書いた。
書店で安く買い求めたものでISBNの表記がなく、Amazonで新装版の番号を調べて書いた。 者の代表作としては「幻の女」があげられるが、僕は本書に収められているような短編にも、後の作家に大きな影響を与えている作品が多くあるような気がする。
者の代表作としては「幻の女」があげられるが、僕は本書に収められているような短編にも、後の作家に大きな影響を与えている作品が多くあるような気がする。
 杉健司氏の著作で未読の旧作は、まだ結構数多くあるから、新作にはまったく目を向けていなかった。それというのも、まだ古書店で本を購っていた頃に、古書店の棚を見ると時代小説が多くて、近頃は時代小説に転向したのか、とも思っていたからだ。
杉健司氏の著作で未読の旧作は、まだ結構数多くあるから、新作にはまったく目を向けていなかった。それというのも、まだ古書店で本を購っていた頃に、古書店の棚を見ると時代小説が多くて、近頃は時代小説に転向したのか、とも思っていたからだ。 書のストーリーは、選挙そのものを描いたものではないが、タイトルに表れているように、主人公北見史郎にとって、生涯の宿敵と言える検事・若宮祐二との関わり合いが、結局のところ大きなテーマとなっている。
書のストーリーは、選挙そのものを描いたものではないが、タイトルに表れているように、主人公北見史郎にとって、生涯の宿敵と言える検事・若宮祐二との関わり合いが、結局のところ大きなテーマとなっている。
 月10日に社会福祉法人薄光会の保護者・家族の会役員会が富津市の、太陽のしずくで行われた。
月10日に社会福祉法人薄光会の保護者・家族の会役員会が富津市の、太陽のしずくで行われた。 書は前回の「過ぎ去りし王国の城」と一緒に借りてきたもので、パニック映画を思わせるようなシーンも続く、サスペンスストーリーだ。
書は前回の「過ぎ去りし王国の城」と一緒に借りてきたもので、パニック映画を思わせるようなシーンも続く、サスペンスストーリーだ。
 の数学2を読み終わるのに少し時間がかかって、8月23日の返却期限を一日過ぎてしまって、24日に返しに行ったとき、本書があったので借りてきた。知念実希人氏の著作は、どこでも人気があって、比較的新しいものは貸し出し中が多い。
の数学2を読み終わるのに少し時間がかかって、8月23日の返却期限を一日過ぎてしまって、24日に返しに行ったとき、本書があったので借りてきた。知念実希人氏の著作は、どこでも人気があって、比較的新しいものは貸し出し中が多い。 がアッチコッチ飛んでいくな。サラリーマン現役の頃は「君はいろんなことをやるが、一つことに集中したまえ」などと、よく会社のトップから言われたものだが、それはいまだに治ってなくて、集中してやらなけれなならない時に限って、まったく関わりのない下らない用事を自分で作っては、肝心の用事をほったらかしにする癖が抜けないのだ。
がアッチコッチ飛んでいくな。サラリーマン現役の頃は「君はいろんなことをやるが、一つことに集中したまえ」などと、よく会社のトップから言われたものだが、それはいまだに治ってなくて、集中してやらなけれなならない時に限って、まったく関わりのない下らない用事を自分で作っては、肝心の用事をほったらかしにする癖が抜けないのだ。
 変わらずの健筆ぶりを示す著者の最新刊だ。本書の予約は僕が一番乗りだったらしい。思ったより早く読めることになってうれしい。こうした売れっ子作家は、数多くの雑誌・新聞等に連載を抱えているから、思わぬ時期にまとめて単行本が刊行されることが有る。近頃は連載も雑誌・新聞に限らず、各出版社が刊行する文庫版大の冊子にも、作品が載っていることが有り、長編・短編・エッセイ等ジャンルを超えて掲載されている。
変わらずの健筆ぶりを示す著者の最新刊だ。本書の予約は僕が一番乗りだったらしい。思ったより早く読めることになってうれしい。こうした売れっ子作家は、数多くの雑誌・新聞等に連載を抱えているから、思わぬ時期にまとめて単行本が刊行されることが有る。近頃は連載も雑誌・新聞に限らず、各出版社が刊行する文庫版大の冊子にも、作品が載っていることが有り、長編・短編・エッセイ等ジャンルを超えて掲載されている。 イトルにあるネメシスはミステリーの題材によく使われており、復讐の女神と解釈していたら、似たようなものだが義憤の女神らしい。服役中の重大事件の容疑者の家族が殺されるという、事件の現場に残された血文字「ネメシス」。そして、再び同様の事件が発生して、現場にはまたしてもネメシスの血文字が残された。
イトルにあるネメシスはミステリーの題材によく使われており、復讐の女神と解釈していたら、似たようなものだが義憤の女神らしい。服役中の重大事件の容疑者の家族が殺されるという、事件の現場に残された血文字「ネメシス」。そして、再び同様の事件が発生して、現場にはまたしてもネメシスの血文字が残された。
 日か前にブログのテンプレートを変更して、トップページのタイトル部分のバックグラウンドカラーを変えた。たったこれだけのことをするのに、gooブログのスタッフに質問するため、チャットで交信したりと余分な手間をかけた。さらに、昔ぷららのぶろぐで採用していたスタイル―と言ってもどうということの無いもので、右端に自作のシャーロック・ホームズのイラストを配しただけだ―に戻そうと思い、近頃とんとご無沙汰している、HTMLやCSSによるサイトの加工を試みようと、以前の資料を見た。
日か前にブログのテンプレートを変更して、トップページのタイトル部分のバックグラウンドカラーを変えた。たったこれだけのことをするのに、gooブログのスタッフに質問するため、チャットで交信したりと余分な手間をかけた。さらに、昔ぷららのぶろぐで採用していたスタイル―と言ってもどうということの無いもので、右端に自作のシャーロック・ホームズのイラストを配しただけだ―に戻そうと思い、近頃とんとご無沙汰している、HTMLやCSSによるサイトの加工を試みようと、以前の資料を見た。
 うした作品が読者に親近感を与えると同時に怖さを感じさせて、物語に引き込むのだろう。
うした作品が読者に親近感を与えると同時に怖さを感じさせて、物語に引き込むのだろう。
 民健康保険の赤字という実情を考えれば、出来るだけ病院に通うことは避けなければ、とは思うがいろいろとそちこちに不都合な現象が起こって、歳は取りたくないものだ。と言ったところで、ここ1週間以上になるが、右目がかゆくて少し粘り気のある涙が出て鬱陶しいから、眼科に行ってきた。
民健康保険の赤字という実情を考えれば、出来るだけ病院に通うことは避けなければ、とは思うがいろいろとそちこちに不都合な現象が起こって、歳は取りたくないものだ。と言ったところで、ここ1週間以上になるが、右目がかゆくて少し粘り気のある涙が出て鬱陶しいから、眼科に行ってきた。 いプロローグで、このストーリーの主人公・黒谷七波が逮捕されるというショッキングなシーンが描かれて、驚かされる。「エッ!どうなってるんだ。」という思いは、第1章から始まるのが、そのプロローグに至る黒谷七波の回想というか告白ということで、納得するのだが・・・・。
いプロローグで、このストーリーの主人公・黒谷七波が逮捕されるというショッキングなシーンが描かれて、驚かされる。「エッ!どうなってるんだ。」という思いは、第1章から始まるのが、そのプロローグに至る黒谷七波の回想というか告白ということで、納得するのだが・・・・。
 地で桜の開花がちらほらと聞かれるようになったが、関東地方は東京が一番乗りだとは驚きだ。暑さ寒さも彼岸までというように、ようやく春の兆しが見えてきた。そんな中、大相撲は新横綱の稀勢の里が、順調に白星を重ねて10連勝と、ファンの熱狂的な声援を集めている。それこそ日本中の相撲ファンが待ち望んでいた日本人力士の横綱だから、ファンの声援は半端ではない。
地で桜の開花がちらほらと聞かれるようになったが、関東地方は東京が一番乗りだとは驚きだ。暑さ寒さも彼岸までというように、ようやく春の兆しが見えてきた。そんな中、大相撲は新横綱の稀勢の里が、順調に白星を重ねて10連勝と、ファンの熱狂的な声援を集めている。それこそ日本中の相撲ファンが待ち望んでいた日本人力士の横綱だから、ファンの声援は半端ではない。 玉氏のような昭和の著名人が次々と世を去り、だんだん昭和の時代も遠ざかり、寂しい思いを抱くのは僕だけではないだろう。しかし、そうしたことは自然の摂理であり、いずれは僕もその仲間入りをするのだ。
玉氏のような昭和の著名人が次々と世を去り、だんだん昭和の時代も遠ざかり、寂しい思いを抱くのは僕だけではないだろう。しかし、そうしたことは自然の摂理であり、いずれは僕もその仲間入りをするのだ。
 が小雨を伴って戻ってきた、そんな感じの寒い一日だった。とても「春雨じゃ、濡れて行こう」などと言えるものではない。花粉症の人にはありがたい雨かも知れないが、こんな日は炬燵に入って、と昔は言ったが我が家には炬燵がない。
が小雨を伴って戻ってきた、そんな感じの寒い一日だった。とても「春雨じゃ、濡れて行こう」などと言えるものではない。花粉症の人にはありがたい雨かも知れないが、こんな日は炬燵に入って、と昔は言ったが我が家には炬燵がない。 月17日に木更津市立図書館からのメールで、「予約資料の用意が出来ました」ということで、翌18日に借り出してきた。この本の予約は1月中旬だと記憶していたから、割と早かったなという気がしている。
月17日に木更津市立図書館からのメールで、「予約資料の用意が出来ました」ということで、翌18日に借り出してきた。この本の予約は1月中旬だと記憶していたから、割と早かったなという気がしている。
 風が吹き荒れている。テレビでは朝の気象情報で、春2番などと言っていたが、先達て春一番が吹いていよいよ春本番だと思っていたら、また寒さが戻ったりとあわただしい気象が巡る。
風が吹き荒れている。テレビでは朝の気象情報で、春2番などと言っていたが、先達て春一番が吹いていよいよ春本番だと思っていたら、また寒さが戻ったりとあわただしい気象が巡る。 のミステリーがすごい!大賞という宝島社が主宰する、大賞を「さよならドビュッシー」で受賞した中山七里氏の作品にほれ込み、最初に読んだのはその受賞作でなく、スピンオフともいえる「要介護探偵の事件簿」だったが、そのあとすぐに受賞作も読んで、見事に著者の罠にはまってしまったのだ。
のミステリーがすごい!大賞という宝島社が主宰する、大賞を「さよならドビュッシー」で受賞した中山七里氏の作品にほれ込み、最初に読んだのはその受賞作でなく、スピンオフともいえる「要介護探偵の事件簿」だったが、そのあとすぐに受賞作も読んで、見事に著者の罠にはまってしまったのだ。