死刑判決
REVERSIBLE ERRORS |
 |
| 読了日 |
2012/04/18 |
| 著 者 |
スコット・トゥロー
Scott Turow |
| 訳 者 |
佐藤耕士 |
| 出版社 |
講談社 |
| 形 態 |
文庫 |
| ページ数 |
382/404 |
| 発行日 |
2004/10/15 |
| ISBN |
4-06-274866-5
4+06-274867-3 |
上の著者名をクリックすると、今まで読んだ著者の作品一覧へ移動します。
 に、いつだったかは忘れたが、AXNミステリー(CSチャンネル)で、本書を原作としたドラマが放送されて、録画してDVDにした後、見たような気もするがもしかしたら錯覚かもしれない。まったく物忘れが激しく情けない話だ。
に、いつだったかは忘れたが、AXNミステリー(CSチャンネル)で、本書を原作としたドラマが放送されて、録画してDVDにした後、見たような気もするがもしかしたら錯覚かもしれない。まったく物忘れが激しく情けない話だ。
以前はDVDにすると、タイトルや1場面の写真やイラストなどを、ダイレクトにプリントして、ケース用のラベルも作って整理していたのだが、いつの間にか面倒になって、録りっぱなし、作りっぱなしが増えて、整理がつかなくなっている。若いころに、「そのうちやります」とか、「今度やります」などと言い訳を言うと、「今度とお化けにゃ、会ったことがねえよ!」と怒られたことを思い出す。(人から叱られたり、怒られたりしたことはよく覚えているものだ)
サイトの解説などを見ると面白そうなドラマだったので、いつか原作を読んでみようと思っていたら、市内のBOOKOFFで105円の棚に上下巻が揃っていたので買ってきた。
BOOKOFFでは、105円の棚に読みたい本があると、上巻だけ、あるいは下巻だけということが多く、上下巻揃っていることは珍しい。(と思っていたが、最近ではそうでもないのかな?)
聞いたことのある著者名だと思い、略歴を見たら、ハリソン・フォード氏の主演で映画にもなった「推定無罪」の作者だった。いずれ(このいずれも、今度と同じだ、あてにはならないが)「推定無罪」も読んでみよう。
さて、好人物の店主が経営するレストランで、店主と女性客一人を含む3人が射殺され、女性客は凌辱されるという事件があり、容疑者としてロミー・ギャンドルフという、黒人男性が逮捕された。そして、33日後に死刑執行が決まっているロミーの、弁護人に連邦控訴裁判所からアーサー・レイヴンが指名されたのだ。
タイトルからも想像すれば、今までいくつか読んできた作品と同様に、冤罪救済のストーリーではないかと思いながら読み進める。ところが上巻の三分の二くらいまで進むと、青天の霹靂といった具合に話は妙な方向に向きを変える。
まあそうだろうな、この手の名作は数多くあるから、単純な冤罪救済の話ならドラマ化もされないだろうなと、納得しながら下巻へと進む。先にあげた「推定無罪」はまだ読んでないし、映画も見ていないから、この作者がどんな物語を書くのかは本書で初めて知るのだが、「簡単には終わらせないぞ!」と言っているような感じを持つ。二転三転するのだ。
 書のテーマは、つまり主題は死刑囚を冤罪から救おうとすることだ。がしかし、それを阻止しようとする検察と警察側の思惑、何とかひっくり返そうとする弁護側との戦いがあり、それぞれの個人手的な、全く個人的な事情が絡んでくるからややこしくなる。
書のテーマは、つまり主題は死刑囚を冤罪から救おうとすることだ。がしかし、それを阻止しようとする検察と警察側の思惑、何とかひっくり返そうとする弁護側との戦いがあり、それぞれの個人手的な、全く個人的な事情が絡んでくるからややこしくなる。
法曹界の習わしはわが国と違って、司法取引や、免責特権が微妙に裁判を左右することになって、そこいらあたりもサスペンスを誘発するのだが、その辺が本書では冗長といえるほどに描写される。時としてそれは、肝心の死刑囚そっちのけの話に、なりかねないほどの様相を示すことさえあるのだ。
だが、終盤になってそれらも、物語全体にとっては欠かすことのできないことだったのだとわかるのだが・・・・。
アメリカでは州によって法律が異なることから、控訴が最終的に連邦控訴審に持ち込まれるということも、ここでは重要な要素となっていることがわかる。
話は変わる。
3月の末にCRテレコムという会社から電話があった。最近「光回線の接続料金が安くなります」などという電話がよく掛かってきて面倒なので、そういう電話はすぐに切ることにしていたが、そんな話とは別らしくて、よく聞いてみたら、電波によるネット接続ということだった。つまりE-Mobileのことだ。
僕は8年ほど前からNTT東日本のBフレッツを利用している。当時はまだ、パソコン教室講師のアルバイトをしていたから、いくらかの収入があって、パソコン環境を最優先していたもので、木更津市にも光回線が設置されるという説明を聞いて、すぐに契約した。
しかし、収入の道が年金だけとなると、光回線利用料の毎月の負担が重くなってきた。そこで、昨年ライトファミリーという契約に切り替えたのだが、ちょっと油断をしていると、利用料が跳ね上がって以前と変わりない利用料となってしまう。もう速さをそれほど必要としなくなっているから、ダイヤルアップ接続に切り替えようと思っていたところだったので、E-Mobileの話は魅力的に聞こえた。早速E-Mobileのサイトを見て、どんなものかを確認した。

ポケットWi-Fiなるものを持って外に出れば、いたるところでネット接続ができるということに、大いに利用価値があることを認めた。従来は無線LANサービスのあるマクドナルドや、JRの駅構内など、決まったところでしかネット接続ができなかったことを思うと、画期的なことだと思った。
CRテレコムはいわば斡旋会社で、携帯電話の販売会社と同じようなものだから、加入者を募って手数料収入を得ているのだろう。それならどこと契約しても同じようなものだから、最初に情報をくれたCRテレコムと契約することにした。
1週間足らずで、ポケットWi-Fiである「GLO1P」という端末が届いた。早速無線LAN内臓のノートパソコンで、ネットへ接続してみた。光回線とはそれほど見劣りすることなく、接続できる。写真の赤丸で囲んだのがポケットWi-Fiである。となりは大きさを比較するためにおいた携帯電話、ノートパソコンの画面は無線LANで接続しているこのブログの画面である。
デスクトップの方は無線LANを内蔵していないので、CRテレコムの方から、端末を使用できるように、アクセスポイント機器(つまり無線LANの子機だ)を後程くれるということだ。長いことお世話になった光回線を解約するためにNTTに連絡して、光電話から通常の電話回線に切り替える工事を4月13日に行った。工事といっても前の通常の電話回線は残っていたから、接続を変えるだけの簡単なことだった。何よりもE-Mobileのメリットは、ルーターや終端装置がなくなって、配線が要らなくなったということだ。
今、こうしたパソコン周りの環境を思うと、僕がパソコンに携わるようになった40年以上前とは比べようのないほどだ。以前NHKのEテレ(教育テレビ)で放送していた「ITホワイトボックス」を見ていて、IT(Information Technology=情報技術)の発達はどこまで行くのだろうと、思いながらも僕はどのような形で、その恩恵に浴すことができるのだろうかという疑問も感じていた。
だが、こうしてささやかながらも、その波は僕のところにも押し寄せてきていることを実感する。
ところで、E-Mobileにするもう一つのメリットに、ネット接続のためのプロバイダー契約が不要ということがある。そこで、僕はひとつ困ることがあった。このブログのことだ。これは「Plala」というプロバイダーのサービスだから、プロバイダー契約がなくなるとブログの継続もできなくなるという不安があったのだ。
「Plala」にネット接続がE-Mobileになったという連絡をしたら、やはりプロバイダー契約も解除されるのだという。しかし、メールや、ブログ、ホームページ等のサービスは有料で継続可能ということだ。しかも利用料はプロバイダー契約がなくなるので今までより安くなるという。
そんなこんなで、無事このブログが継続できるようになって、一安心だが、実際この後いつまで継続できるのか。それは、僕自身の問題だ。できるだけ長く続けられるよう、身体―じゃなく頭―に気を付けて?(どうやって?帽子でもかぶるか)過ごさなければ。
ネット接続が変わったというだけの話が長くなった。

 ストセラー作品が即僕にとっての面白い作品とは限らないのだが、(僕は評判につられるということはめったにないのだが、それでも気になって読んだものの、さほどでなくがっかり、ということが幾度かあった)、それでも探せばいろいろ出てくるので驚く。
ストセラー作品が即僕にとっての面白い作品とは限らないのだが、(僕は評判につられるということはめったにないのだが、それでも気になって読んだものの、さほどでなくがっかり、ということが幾度かあった)、それでも探せばいろいろ出てくるので驚く。

 年の歳月が過ぎ、クローイはC.J.タウンゼントと改名、マイアミでの司法試験に合格して、マイアミ・デード郡地方検察局の検事補となって活躍、その名をとどろかせてはいたが・・・・。
年の歳月が過ぎ、クローイはC.J.タウンゼントと改名、マイアミでの司法試験に合格して、マイアミ・デード郡地方検察局の検事補となって活躍、その名をとどろかせてはいたが・・・・。









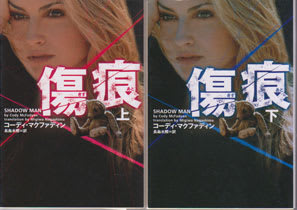
 を読もうかと思っていたら、興味を引く情報が思わぬところから入ってきた。
を読もうかと思っていたら、興味を引く情報が思わぬところから入ってきた。 かの言い方を借りれば、本書はコテコテのサイコサスペンスだ。FBIロサンゼルス支局国立暴力犯罪分析センター(NCAVC)の主任、スモーキー・バレットは半年前に追い詰めた殺人犯に、夫と愛娘を殺され、自身もレイプされた上に、ナイフで傷つけられるという過去を持っており、休職中の現在はFBI専属の精神科医のセラピーに通っていた。
かの言い方を借りれば、本書はコテコテのサイコサスペンスだ。FBIロサンゼルス支局国立暴力犯罪分析センター(NCAVC)の主任、スモーキー・バレットは半年前に追い詰めた殺人犯に、夫と愛娘を殺され、自身もレイプされた上に、ナイフで傷つけられるという過去を持っており、休職中の現在はFBI専属の精神科医のセラピーに通っていた。
 の本を買ったのは、ずっと前に読んだアダム・ファウアー著
の本を買ったのは、ずっと前に読んだアダム・ファウアー著 の母親の自殺が後に物語の謎の部分に、大いにかかわってくるのだが・・・・。
の母親の自殺が後に物語の謎の部分に、大いにかかわってくるのだが・・・・。

 川が上司の捜査1課長・宮田から受け取った継続捜査事件は、2年前に中野駅前の居酒屋で発生した強盗殺人事件だった。殺された二人は接点がなく、一人は宮城県の獣医師・高磨、もう一人は暴力団員で産廃業を営む西野という男だった。
川が上司の捜査1課長・宮田から受け取った継続捜査事件は、2年前に中野駅前の居酒屋で発生した強盗殺人事件だった。殺された二人は接点がなく、一人は宮城県の獣医師・高磨、もう一人は暴力団員で産廃業を営む西野という男だった。
 リーズで何冊か出ているのをBOOKOFFなどで見て、ずっと前から気になっており、処女作だという本書を買ったものの、読まずに積ん読が長く続いた。
リーズで何冊か出ているのをBOOKOFFなどで見て、ずっと前から気になっており、処女作だという本書を買ったものの、読まずに積ん読が長く続いた。 て、そうした状況の中、ジョーディは独自の調査を開始するのだが、とても30歳とは思えないような言動が、読んでいて納得できない箇所が多く、それは僕の身勝手な見方によるものかもしれないが。
て、そうした状況の中、ジョーディは独自の調査を開始するのだが、とても30歳とは思えないような言動が、読んでいて納得できない箇所が多く、それは僕の身勝手な見方によるものかもしれないが。
 々回に読んだ東山彰良氏の「ミスター。グッド・ドクターをさがして」で、本書のタイトルを連想したことから、どんな内容かと興味がわいて、一度読んでおこうかと思ったのだ。
々回に読んだ東山彰良氏の「ミスター。グッド・ドクターをさがして」で、本書のタイトルを連想したことから、どんな内容かと興味がわいて、一度読んでおこうかと思ったのだ。 のデータでわかるように、この作品を翻訳したのは小泉喜美子氏だ。小泉氏の作品はほんの少ししか読んでないから偉そうなことは言えないが、作中の人物造形が、小泉氏が描く女性に一脈相通ずるところがあったのではないか、などという思いを持った。
のデータでわかるように、この作品を翻訳したのは小泉喜美子氏だ。小泉氏の作品はほんの少ししか読んでないから偉そうなことは言えないが、作中の人物造形が、小泉氏が描く女性に一脈相通ずるところがあったのではないか、などという思いを持った。
 すみ市のブックセンターあずまで珍しい講談社文庫の斎藤作品を見かけて買ってきた。 いや、珍しいと思うのは僕だけかもしれないが、なんとなく著者の作品はすべて角川書店から刊行されていると思っていたからだ。
すみ市のブックセンターあずまで珍しい講談社文庫の斎藤作品を見かけて買ってきた。 いや、珍しいと思うのは僕だけかもしれないが、なんとなく著者の作品はすべて角川書店から刊行されていると思っていたからだ。 件を追う中年の雑誌編集長の熱心さと、相反するだらしのなさには、読んでいて時には嫌悪感さえ抱くのだが、よく考えてみれば、同じ年頃だった自分を振り返れば、 似たようなものだったかなと、苦い思いもわく。
件を追う中年の雑誌編集長の熱心さと、相反するだらしのなさには、読んでいて時には嫌悪感さえ抱くのだが、よく考えてみれば、同じ年頃だった自分を振り返れば、 似たようなものだったかなと、苦い思いもわく。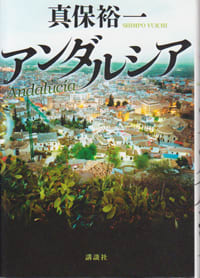
 交官・黒田康作シリーズの第3弾。このシリーズは映画化、ドラマ化どちらもされており、面白いのは映画やドラマと小説とが、部分的に異なっているところだ。
交官・黒田康作シリーズの第3弾。このシリーズは映画化、ドラマ化どちらもされており、面白いのは映画やドラマと小説とが、部分的に異なっているところだ。 れはさておき、そういう設定だから仕方がないが、本編でも外交官・黒田康作は自ら窮地に立ち入ってしまうストーリー展開だ。
れはさておき、そういう設定だから仕方がないが、本編でも外交官・黒田康作は自ら窮地に立ち入ってしまうストーリー展開だ。


 訳ものは何年振りかと思って記録をたどったら、昨年(2011年)の7月にP・コーンウェル女史の検視官シリーズ「核心」を読んでいたので、9か月ぶりくらいか。
訳ものは何年振りかと思って記録をたどったら、昨年(2011年)の7月にP・コーンウェル女史の検視官シリーズ「核心」を読んでいたので、9か月ぶりくらいか。 々と進むストーリーが次第に不気味な不安感を募らせて行く中、僕は唐突に先年亡くなった児玉清氏を思い浮かべた。俳優の児玉氏は読書人としても知られ、NHKBSの番組、「週刊ブックレビュー」の司会も長年続けておられた。あるとき児玉氏はインタビューに答えて、サスペンス小説が好きだと言っていたことを思い出して、本書も読んだろうかというような連想をしたのである。
々と進むストーリーが次第に不気味な不安感を募らせて行く中、僕は唐突に先年亡くなった児玉清氏を思い浮かべた。俳優の児玉氏は読書人としても知られ、NHKBSの番組、「週刊ブックレビュー」の司会も長年続けておられた。あるとき児玉氏はインタビューに答えて、サスペンス小説が好きだと言っていたことを思い出して、本書も読んだろうかというような連想をしたのである。
 の好みのストーリーを描く作者には、時として寡作の人が多いような気がするが、否、そうではなかった。逆に僕は、書店の棚にたくさんの著作が並んでいる作家はなんとなく敬遠する傾向があるのだった。単なる僕の偏見にすぎない。
の好みのストーリーを描く作者には、時として寡作の人が多いような気がするが、否、そうではなかった。逆に僕は、書店の棚にたくさんの著作が並んでいる作家はなんとなく敬遠する傾向があるのだった。単なる僕の偏見にすぎない。 婚式を目前に相手の桜井を交通事故で失った、Jポップ界のスーパースターだったユニット「アダージョ」の小田切加憐。失意の末音楽界から身を引いた後、知り合いの勧めでサラリーマンの後藤と結婚、パチンコ店に通うようになる。もちろん一生遊んで暮らせるほどの蓄えがあるから、パチンコは純粋な遊びだが、そんな世界で知り合った女がホームから転落して轢死するという事件が起こった。
婚式を目前に相手の桜井を交通事故で失った、Jポップ界のスーパースターだったユニット「アダージョ」の小田切加憐。失意の末音楽界から身を引いた後、知り合いの勧めでサラリーマンの後藤と結婚、パチンコ店に通うようになる。もちろん一生遊んで暮らせるほどの蓄えがあるから、パチンコは純粋な遊びだが、そんな世界で知り合った女がホームから転落して轢死するという事件が起こった。
 ステリー作家でも僕の知らない人はたくさんいて、本書の著者中町信(あきら)氏も初めての作家だ。この文庫は2004年の発刊だが、作品そのものは1971年に江戸川乱歩賞への応募用に書かれたものだという。本書が東京創元社の推理文庫に収まったのは、結構前から知ってはいたものの、内容については全く知らず、さして興味もなかった。
ステリー作家でも僕の知らない人はたくさんいて、本書の著者中町信(あきら)氏も初めての作家だ。この文庫は2004年の発刊だが、作品そのものは1971年に江戸川乱歩賞への応募用に書かれたものだという。本書が東京創元社の推理文庫に収まったのは、結構前から知ってはいたものの、内容については全く知らず、さして興味もなかった。
 ラーサスペンス大賞を受賞した作品だということから、さしたる興味を持てなかったが、金曜夜8時からBS11(イレブン)で放送されている「ベストセラーBook TV」の中で、週間文庫ランキングに何度となく表れるから、次第に気になってきて、ポイントで交換したギフト券の残りがあったので、ついに買ってしまった。
ラーサスペンス大賞を受賞した作品だということから、さしたる興味を持てなかったが、金曜夜8時からBS11(イレブン)で放送されている「ベストセラーBook TV」の中で、週間文庫ランキングに何度となく表れるから、次第に気になってきて、ポイントで交換したギフト券の残りがあったので、ついに買ってしまった。
 良三郎氏の「ミステリーの泣きどころ」という評論集を読んで、今まで気にしなかった本のいくつかに興味を惹かれて、読んだ中に著者の作品もあった。
良三郎氏の「ミステリーの泣きどころ」という評論集を読んで、今まで気にしなかった本のいくつかに興味を惹かれて、読んだ中に著者の作品もあった。
 台は北海道、旭川市郊外の辻口総合病院と院長の辻口啓造宅周辺。辻口病院の眼科医師、村井はかねてから美しく若い辻口院長夫人、夏枝に思慕を抱いていた。村井が辻口宅を訪れて夏枝に思いを告げようとしていた時、三歳になる夏枝の娘・ルリ子が行方不明となる。後にルリ子は近くの河原で絞殺死体となって発見された。 啓造はルリ子が殺された時に、「夏枝は村井と何をしていたんだ?」という疑惑にさいなまれるが、それを夏枝に問いただすことが出来なかった。
台は北海道、旭川市郊外の辻口総合病院と院長の辻口啓造宅周辺。辻口病院の眼科医師、村井はかねてから美しく若い辻口院長夫人、夏枝に思慕を抱いていた。村井が辻口宅を訪れて夏枝に思いを告げようとしていた時、三歳になる夏枝の娘・ルリ子が行方不明となる。後にルリ子は近くの河原で絞殺死体となって発見された。 啓造はルリ子が殺された時に、「夏枝は村井と何をしていたんだ?」という疑惑にさいなまれるが、それを夏枝に問いただすことが出来なかった。