| 絵の中の殺人 | ||
|---|---|---|
 |
読 了 日 | 2013/02/08 |
| 著 者 | 奥田哲也 | |
| 出 版 社 | 講談社 | |
| 形 態 | 文庫 | |
| ページ数 | 332 | |
| 発 行 日 | 1996/11/15 | |
| I S B N | 4-06-263026-5 | |
 となく目についたのは、やはりタイトルからか?どんな内容だろうと思って読む気になった。初めての作家ということもあり、興味がわいたのだ。
となく目についたのは、やはりタイトルからか?どんな内容だろうと思って読む気になった。初めての作家ということもあり、興味がわいたのだ。
そんなことがつい最近になって2度目か3度目となる。本当は読みたいと思っている本は他にたくさんあるのに、それらを置いてこうした初めての作家の本を読むというのは、新しい作家を開拓?することがすなわち面白く読める本を探すということに繋がらないかと、かすかな望みを持つからだ。
好みの作家の本が少なくとも十数冊は手元にありながら、こうして新しい本を探すのは、よくばり以外の何物でもない。そうした自覚はあるのだが、欲望を抑えることは難しいものだ。(ヤダネー)

こうしたブログの記事は普通読み終わってから書くものだが、僕の場合、このような前置きは読み始める前から書くこともある。今書いているこの記事も未だ読み始めて間もなく書き始めた。これから先この本が僕の好みに合うか、面白く読めるのか、などと期待と少しの不安が入り混じったような気分で、書き始めるのだ。といっても僕の場合は、大学ノートに記した本の基本的なデータや、簡単なメモをもとにWordで書く。もともと、Wordでブログの体裁を考えてデザインし、それを基にブログのテンプレートをカスタマイズしたものが現在のブログとなっている。
アップロードするときは、HTMLであらかじめ作っておいたいくつかのテンプレートに文章をはめ込んで、そっくりぷららのシンプルエディタモードにペーストする。ぷららというNTTのプロバイダーが提供するブログサービスは、時々実行速度が遅くなったりするトラブルがあるものの、同じNTTのOCNなどと比べると、初心者から上級者までの幅広いブロガーのについての要求を満たすものだと思っている。僕が本格的にHTML言語を学習できたのもこのブログサービスのおかげだ。
しかし、振り返ってみると僕の話は肝心の本の話よりも横道の方が大分が多い。 実生活ではどっちかといえば無口の方に入ると思うが、ブログでは無口というわけにはいかないから、自然と無駄話が多くなるのか。
2007年4月から読書記録をブログで公開するようになって、もうじき丸6年となる。その間、いくらかでもブログの見栄えを良くしようと、老人の手習いが始まり、プロバイダーが提供するお仕着せのテンプレートに飽き足らず、いろいろと先人の知恵を借りながら、カスタマイズにも手を染めたが、まだまだブログについてもやりたいことは沢山あって、よくは限りない。だいぶ余分な話が長くなってしまった。

 書は、1軍のポジションを維持することが難しく、現役を引退したプロ野球選手を主人公としたストーリー。 彼、天矢輝彦は野球選手を退いた後、故郷の北海道に帰り、絵里村美術学院の事務員という全くの畑違いの場所に職を求めた。ところが彼の新入社員歓迎会の夜、事件は起きた。
書は、1軍のポジションを維持することが難しく、現役を引退したプロ野球選手を主人公としたストーリー。 彼、天矢輝彦は野球選手を退いた後、故郷の北海道に帰り、絵里村美術学院の事務員という全くの畑違いの場所に職を求めた。ところが彼の新入社員歓迎会の夜、事件は起きた。
彼の上司がアトリエで殺害されるという事件だった。この学院では1年前には理事長が殺害されるという事件が起こっており、未解決のままだった。今度の事件は前の事件と関係があるのか?
そんな中での新入社員の天矢輝彦の事件解明への挑戦が始まるのだが、どうも僕はこの主人公が元プロ野球の選手だったことが、何か事件解明への手がかりになるのかと思っていたが、そういう気配は全くなく進んでいく。同じ事務職員の仲間への警察の疑惑を払拭しようと、働きかける天矢の原動力もよくわからなく、一応本格推理の形をとっているものの、キャラクターの言動や背景の描写とストーリー展開がかみ合っていないようなちぐはぐな感じを受けたのだが・・・・。単に僕の受容力の不足か?
捜査を担当する県警から応援としてやってきた警部と、所轄の刑事との関係も説明不足で、中途半端な形で終わってしまったような感じだ。読みやすくスムーズに読めたのに、あれはどうなったのだろう?というような小さな疑問をいくつか残しているような思いを持たせる作品だ。期待していたのにちょっと残念。
にほんブログ村 |











 に読んだ「傷痕」や、「報復」のヴィレッジ・ブックスが同じ作品を出しており、「報復」の後ろの方に広告が載っており、目を引いたのがついこの前のことだった。
に読んだ「傷痕」や、「報復」のヴィレッジ・ブックスが同じ作品を出しており、「報復」の後ろの方に広告が載っており、目を引いたのがついこの前のことだった。
 タートで請け負ったターゲットは、政権政党の重要人物だったが、後にその娘を愛するようになるという展開が、どのように収束するのかという興味も、ストーリーを飽かせずに読み進ませる。
タートで請け負ったターゲットは、政権政党の重要人物だったが、後にその娘を愛するようになるという展開が、どのように収束するのかという興味も、ストーリーを飽かせずに読み進ませる。
 つか読もうと思いながらなかなか手につかなかった1冊だ。ポール・ニューマン氏の主演で映画化されて、そちらの方はテレビでも何度か放映されたので、その都度見ているが、その割には内容をおぼろげにしか覚えていないのはどうしたことか。
つか読もうと思いながらなかなか手につかなかった1冊だ。ポール・ニューマン氏の主演で映画化されて、そちらの方はテレビでも何度か放映されたので、その都度見ているが、その割には内容をおぼろげにしか覚えていないのはどうしたことか。 うも映画やドラマの話になると止まらなくなってしまう。
うも映画やドラマの話になると止まらなくなってしまう。
 回で次に読む本を「報復」(ジリアン・ホフマン著)にすると書いたが、強烈なサイコサスペンスでスタミナを消耗した感じなので、カバー裏に記されたあらすじを見て、同様のサイコサスペンスだということなので、予定を変更して、一度他のジャンルの本を読むことにした。
回で次に読む本を「報復」(ジリアン・ホフマン著)にすると書いたが、強烈なサイコサスペンスでスタミナを消耗した感じなので、カバー裏に記されたあらすじを見て、同様のサイコサスペンスだということなので、予定を変更して、一度他のジャンルの本を読むことにした。 おざっぱに言ってしまえば、ビジネスエイジェントとなっている主人公の、ルイス・ケインが、旧知の弁護士から依頼された、事業家をブルターニュからリヒテンシュタインへと護送する話だ。
おざっぱに言ってしまえば、ビジネスエイジェントとなっている主人公の、ルイス・ケインが、旧知の弁護士から依頼された、事業家をブルターニュからリヒテンシュタインへと護送する話だ。
 なり前にハンフリー・ボガード氏の映画を見ているのだが、どんな内容だったのか全く覚えていない。一つだけ記憶にあるのは、タイトルの「マルタの鷹」とは置物だったということだけだ。
なり前にハンフリー・ボガード氏の映画を見ているのだが、どんな内容だったのか全く覚えていない。一つだけ記憶にあるのは、タイトルの「マルタの鷹」とは置物だったということだけだ。 映画のボガード氏とはちょっとかけ離れた様相を示しているが、冒険活劇風の様相を呈すところもあって、映画になっているという先入観があるせいか、映像を意識して書かれたような気もする。
映画のボガード氏とはちょっとかけ離れた様相を示しているが、冒険活劇風の様相を呈すところもあって、映画になっているという先入観があるせいか、映像を意識して書かれたような気もする。 はそれほど昔の探偵小説に詳しくはないので、それまでになかった文体や筋運びに、ハメット氏の本作がハードボイルドというジャンルを確立したことや、新しいミステリーの潮流を作ったことに偽を唱えるつもりは毛頭ない。現在の多くのハードボイルドの、どちらかと言えば速い展開を示す作品と比べて(比べることにあまり意味があるとは思えないが)、多少退屈なところがあるとはいえ、乱歩氏ほどの悪い印象はない。
はそれほど昔の探偵小説に詳しくはないので、それまでになかった文体や筋運びに、ハメット氏の本作がハードボイルドというジャンルを確立したことや、新しいミステリーの潮流を作ったことに偽を唱えるつもりは毛頭ない。現在の多くのハードボイルドの、どちらかと言えば速い展開を示す作品と比べて(比べることにあまり意味があるとは思えないが)、多少退屈なところがあるとはいえ、乱歩氏ほどの悪い印象はない。
 めて本書を読んだのは1998年10月だから、もう14年になるのか!
めて本書を読んだのは1998年10月だから、もう14年になるのか! ログのタイトル(隅の老人のミステリー読書雑感=グリーンのバック)の下に、グレーの帯(ナビゲーションバー)がある。
ログのタイトル(隅の老人のミステリー読書雑感=グリーンのバック)の下に、グレーの帯(ナビゲーションバー)がある。
 月6日に袖ケ浦市立図書館で借りてきた。前に読んだ東京バンドワゴンの第6作「オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ」の巻末の広告ページに載っていた本だ。
月6日に袖ケ浦市立図書館で借りてきた。前に読んだ東京バンドワゴンの第6作「オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ」の巻末の広告ページに載っていた本だ。
 の著者の本も、今のところこれで最後のようだ。
の著者の本も、今のところこれで最後のようだ。
 ちろんストーリーの成り立ちは全く違い、この「赤い闇」の方は、かつて藤田まこと氏らの主演で人気を呼んだ時代劇「必殺シリーズ」のようなシチュエーションで、殺しを請け負うというか、依頼人を探す役目を負う人物がいるのである。
ちろんストーリーの成り立ちは全く違い、この「赤い闇」の方は、かつて藤田まこと氏らの主演で人気を呼んだ時代劇「必殺シリーズ」のようなシチュエーションで、殺しを請け負うというか、依頼人を探す役目を負う人物がいるのである。

 幸な結果を迎えた短い結婚生活を終えて、響子は新たな人生を求めて勤務先の香港支社への転勤に応じた。そこで、人気俳優のジェームスと知り合って、つかず離れずの関係をもつようになる。
幸な結果を迎えた短い結婚生活を終えて、響子は新たな人生を求めて勤務先の香港支社への転勤に応じた。そこで、人気俳優のジェームスと知り合って、つかず離れずの関係をもつようになる。

 の善悪を考慮のほかにすれば、これほどのスーパー・ヒーローとも呼ぶべき主人公を創造したことについては、やはり作者の力量に脱帽だ。
の善悪を考慮のほかにすれば、これほどのスーパー・ヒーローとも呼ぶべき主人公を創造したことについては、やはり作者の力量に脱帽だ。
 後に読んだ著者の作品は、2000年11月の「クリニック」だから、10年も前のことになる。
後に読んだ著者の作品は、2000年11月の「クリニック」だから、10年も前のことになる。


 て、本書は戦後10年という長い期間、シベリアに抑留されていた外池洋祐という青年が主人公だ。ということだけで、かなり古い物語だということがわかるだろう。
て、本書は戦後10年という長い期間、シベリアに抑留されていた外池洋祐という青年が主人公だ。ということだけで、かなり古い物語だということがわかるだろう。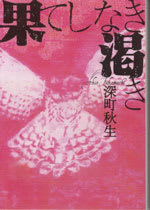




 ころで、本書は1981年に発表された作品で、江口寿史氏の表紙イラストが主人公の雰囲 気をよく捕らえているように(ちょっとスマート過ぎるような気もするが・・・)タフな女性探偵の活躍 が多くの女性読者に支持されたのも無理は無い。今でこそこのような女性を女性作家が描いた作品は、ミ ステリーに限らずわが国でも当たり前のように多く見られるようになった。歓迎すべきことだ。
ころで、本書は1981年に発表された作品で、江口寿史氏の表紙イラストが主人公の雰囲 気をよく捕らえているように(ちょっとスマート過ぎるような気もするが・・・)タフな女性探偵の活躍 が多くの女性読者に支持されたのも無理は無い。今でこそこのような女性を女性作家が描いた作品は、ミ ステリーに限らずわが国でも当たり前のように多く見られるようになった。歓迎すべきことだ。