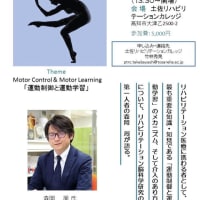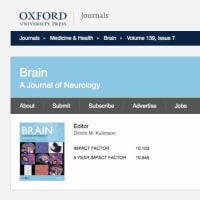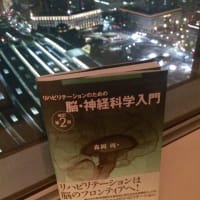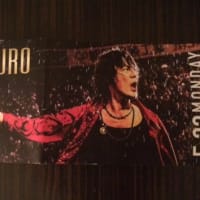専門教育の世界に来て,もう15年以上になります.この間,相当の数の学生に対して,教員という立場で教えてきましたが,いまだに教育とは難しいと思っています.一時期,教育に無関心な時期もありましたが,今はむしろ,その難しさを自己の経験として鮮明に刻んでいっています.
結論としては,あくまでも学校教育とは,フレームを教えるということと,経験を伝えるということしかできないということです.すなわち,どう生きるか,どのように社会に向き合うか,どのように人生をつくっていくか,どのようなビジョンをもっていくか,そして美しく生きるためには?という究極の目標である,美そのものをどう創るかまでは,なかなか教えられないといくことです.
すなわち,リハビリテーションの現場に置き換えてみると,対象者にどのように関わっていくか.どのような治療を選択し,その場で変えていくか,そして,身体を触りながら,何を感じ取っているのか,どのようにコミュニケーションを構築しているのか,などは自分自身で紡いでいくしかないのではないかと思います.もちろん,そのフレームを教えることはできるし,自分が生きてきた経験から,何を選択するかなんかは伝えることができます.
けれど,上記のまさに臨床そのものをおしえることはできないのです.ここに人生のクオリアがあり,事象を現場で現在進行形に,すなわち,1秒前と今自体はすでに現象が異なっている.すなわち,脳内現象は変わっている.そこについて教えることは,現場で自分自身が感じ取るしかないのです.すなわち,そこに感性が必要なのです.エビデンスとは究極にある表現ですが,神経現象から考えて,この感性そのものがエビデンスなんです.感性を持って生きるというもっとも人間らしいものを失ってしまうと,自らが機械になり,患者を機械にあてはめ,自分のなかのある機械脳にあてはまらない現象に出会ってしまえば,それを不良品と解釈して,葬ってしまうのです.そうして葬られた患者さんはいかに多いか・・・
しかしながら,感性ばかりを頼りにしてもなりません.感性があっても,知識・技術がなければ絵にかいた餅です.セラピスト,いや人間は表現者です.セラピストの技術も感性に裏打ちされていますが,感性の前には,やはりフレームの理解が必要です.すなわち,クラシックギターの音色に感性がひかれるが,その感性だけ持っていても,優れた演奏者にはなれません.何よりもクラシックに関する知識,ギターに関する知識,そして演奏法の理解,そして,弦を操作する技術,こうしたものがベースにないと,感性は絵にかいた餅になります.
私たち人間にはその両面があります.おそらくすぐれた表現者(スポーツや芸術)には,その両面の感受性,そして複雑性,そして細分性が存在しているのでしょう.それを単に右脳と左脳という形にわけたくありませんが,両半球のニューロンがシンフォニーを奏でるように,同期化スパイクするのでしょう.しかし,その神経現象の再現は,コヒーレンスは,次の機会に全く同じようになるのでしょうか.脳の神経現象にはまだまだ解明の余地があります.
話がそれてきましたが,臨床力を操作する感性について,そしてどのような人生をつくりビジョンを持っていくかの姿勢は,自分自身でつくっていくしかないのです.一方,そのフレームになる知識・技術はある程度は教育することが可能ですが,その知識・技術は応用科学であればあるほど実は不確実なことばかり,その不確実性を楽しむという姿勢を教えることが,今の専門教育には必要なのではないでしょうか.その教育が決定的に不足しているように思えます.思考と記憶は表裏一体ながら,対極にある認知機能と考えることができます.
記憶の授業を減らしてでも,不確実性を思考する授業を構成することが大学の教育なのでないでしょうか.そこに専門教育と大学教育のジレンマが存在してしまいます.特に日本ではそれを感じてしまうのです.
結論としては,あくまでも学校教育とは,フレームを教えるということと,経験を伝えるということしかできないということです.すなわち,どう生きるか,どのように社会に向き合うか,どのように人生をつくっていくか,どのようなビジョンをもっていくか,そして美しく生きるためには?という究極の目標である,美そのものをどう創るかまでは,なかなか教えられないといくことです.
すなわち,リハビリテーションの現場に置き換えてみると,対象者にどのように関わっていくか.どのような治療を選択し,その場で変えていくか,そして,身体を触りながら,何を感じ取っているのか,どのようにコミュニケーションを構築しているのか,などは自分自身で紡いでいくしかないのではないかと思います.もちろん,そのフレームを教えることはできるし,自分が生きてきた経験から,何を選択するかなんかは伝えることができます.
けれど,上記のまさに臨床そのものをおしえることはできないのです.ここに人生のクオリアがあり,事象を現場で現在進行形に,すなわち,1秒前と今自体はすでに現象が異なっている.すなわち,脳内現象は変わっている.そこについて教えることは,現場で自分自身が感じ取るしかないのです.すなわち,そこに感性が必要なのです.エビデンスとは究極にある表現ですが,神経現象から考えて,この感性そのものがエビデンスなんです.感性を持って生きるというもっとも人間らしいものを失ってしまうと,自らが機械になり,患者を機械にあてはめ,自分のなかのある機械脳にあてはまらない現象に出会ってしまえば,それを不良品と解釈して,葬ってしまうのです.そうして葬られた患者さんはいかに多いか・・・
しかしながら,感性ばかりを頼りにしてもなりません.感性があっても,知識・技術がなければ絵にかいた餅です.セラピスト,いや人間は表現者です.セラピストの技術も感性に裏打ちされていますが,感性の前には,やはりフレームの理解が必要です.すなわち,クラシックギターの音色に感性がひかれるが,その感性だけ持っていても,優れた演奏者にはなれません.何よりもクラシックに関する知識,ギターに関する知識,そして演奏法の理解,そして,弦を操作する技術,こうしたものがベースにないと,感性は絵にかいた餅になります.
私たち人間にはその両面があります.おそらくすぐれた表現者(スポーツや芸術)には,その両面の感受性,そして複雑性,そして細分性が存在しているのでしょう.それを単に右脳と左脳という形にわけたくありませんが,両半球のニューロンがシンフォニーを奏でるように,同期化スパイクするのでしょう.しかし,その神経現象の再現は,コヒーレンスは,次の機会に全く同じようになるのでしょうか.脳の神経現象にはまだまだ解明の余地があります.
話がそれてきましたが,臨床力を操作する感性について,そしてどのような人生をつくりビジョンを持っていくかの姿勢は,自分自身でつくっていくしかないのです.一方,そのフレームになる知識・技術はある程度は教育することが可能ですが,その知識・技術は応用科学であればあるほど実は不確実なことばかり,その不確実性を楽しむという姿勢を教えることが,今の専門教育には必要なのではないでしょうか.その教育が決定的に不足しているように思えます.思考と記憶は表裏一体ながら,対極にある認知機能と考えることができます.
記憶の授業を減らしてでも,不確実性を思考する授業を構成することが大学の教育なのでないでしょうか.そこに専門教育と大学教育のジレンマが存在してしまいます.特に日本ではそれを感じてしまうのです.