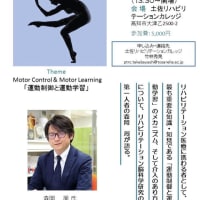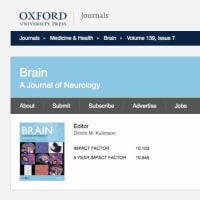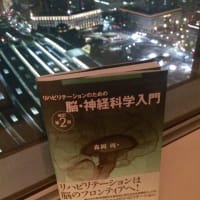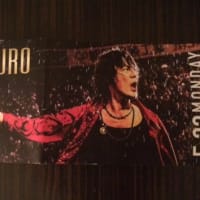英国にはgap yearというものが存在します。これは大学進学を一年間延ばし、その間に海外でボランティアとして働いたり、世界旅行をしたり、地元企業でインターンしたりと、やりたいことを見つめ、創造するというものです。高校卒業者3割ほどが利用しているように、定着しているか、していないかは判断に任せます。これをそっくりそのまま日本に導入しようと考えていた時期もありますが、現状の高校までの教育体制からすると根づかないと思います。
日本人の体質は根気強く、勤勉で、そして日本語の文脈が繊細であるから裏を読むことが得意です。そのため、模倣しそれを改良するのが得意なのです。自らが先頭をきることは極めて苦手なのですが、リーダーシップのもと、勤勉にかつ、模倣し続けることが得意です。サッカーにも表れており、ストライカーはいつになっても不在ですが、パス回し、個人の認識能力、技術能力は相当に高いものと思えます。昨日、BSでサッカーに関する番組をしていましたが、日本サッカーの父、クラマーはその点に気付いたそうです。だから基本練習を集中的に行ったようです。ちなみに、その時のメンバーであった監督の長沼さん、コーチの岡野さん、そしてその後の監督の森さんらのサインがなぜか私の家にありました。私は小中高とサッカーをしていて、ちょうど高知に日本代表のチームドクターがいて、その関係でサインをもらったのを今でも記憶が蘇ります。
さて、gap yearに戻りますが、日本は新幹線が5分おきに出発するような国ですので、やはり、何もない期間を持つということは、現状からすると合わない気がします。もっとゆっくりという精神が根付かないと難しいでしょう。その前にまずは導入すべきは、休む時は休むということです。GWまっただ中ですが、民族大移動のように「せかされて」動くのではなく、余裕を持ち、何もしないバカンスを楽しむ、そして「バカンスのために」仕事をするといった自らの余暇を得るために、仕事をするというこころを身につけることが、楽に生きていくためには必要なのかもしれません。「会社」のためとか、「学生」のためとか、はたまた「理学療法」のためとか、と思うのではなく、「自分」のため、「家族」のため、と思えるかが、バカンスやgap yearを成功させるための必需品だと思います。「自分」を犠牲にして「学生」のためとか思うから、「自分」がなくなっていくのだとも思うのです。大義名分は棚上げし、自分を満足させるために生きるということを身につけることが必要ではにでしょうか。
この自分は「自分勝手」という意味でもありません。最低限の責任は守るべきです。しかし、その責任は、実は思いあがりの面もあります。よく聞くフレーズで「辞めたら迷惑をかける」というのもその一つです。私は自分がいなくなっても、自分がやらなくても、誰かがそれをやる、代わりはいつもいると思っています。なぜなら、社会というのはシステムで動いているからです。これはある意味無責任な部分も含んでいますが、他人を信頼しているからこそ機能するものです。すべてを抱え込み背負い込んでしまう日本人性質が自分にもありますが、1年近く欧州で生活した経験から、このようなもう一つの私も持っています。昨日の龍馬伝では、まさに典型的な日本人が武市半平太、そして、欧米人が坂本龍馬のような気がしました。武市は真面目で勤勉で、その最期は腹を切ります。長州の者たちから土佐に帰ることは危険だから、脱藩して京に留まれという忠告も自らの責任という視点から土佐に戻ります。そしてとらえられ切腹を命じられます。くしくも後藤象二郎の復活劇になりますが、自分を殺し藩のためお国のためと思い、最期は使い捨ての状態になり、責任をとって自害するというものです。なんだか日本の少し前の会社のスタイルに似ていませんか。一方、坂本はベンチャーみたいなもので、自由奔放にやり、本人は楽しいのですが、まわりは翻弄され、最終的には「目の上のたんこぶ」となって暗殺され、追いやられてしまいます。これも最近よく聞く話です。日本人の気質がこの両方によく表れていると思います。
さてさて、先日、T大学文学部教員は数年間働くと、1年間フリーということを聞きました。このフリーの期間は何をしてもよい(出勤しないでもよし、授業もなし;してもよい)というものです。外国に行くのもよし、充電期間にするのもよし、その時にしかできない調査や研究をするのもよし、と創造性の源といってもよい時間です。しかしながら、今の日本人に1年間フリーにさせるといっても、何をしてよいのかわからない、となるかもしれません。すなわち、もとめられるのは「欲求」なのかもしれません。「あれもこれもしたい」「ここに行ってみたい」「誰にあいたい」などの欲求をいくつも持ち続ける姿勢・社会・教育というのが決定的に不足しているのかもしれません。よいものを評価せず、わるいものを批判するという根深い思想がそれを邪魔しているように思うのです。過去(他人)を批判しながら(たとえば江戸幕府)、新しいものを学ぶ(つくる)というより(新政権)も、自らがそれを学びたい、知りたい、したいというものを優先に考えるように日本人がなれば、gap yearやバカンスが定着するかもしれません。
留学中に欧州のセラピストはきっちり3週間休んでいました。365日体制になった病院。病院の収益のため、量や集中的効果のエビデンスから、患者さんのためと言っていますが、それにより「こなし」作業となり、治療技術の追求の時間、学ぶための時間、そして何よりも「創造性」が奪われてしまうのなら、最終的には「患者さん」のためにはならないのかもしれません。
日本人の体質は根気強く、勤勉で、そして日本語の文脈が繊細であるから裏を読むことが得意です。そのため、模倣しそれを改良するのが得意なのです。自らが先頭をきることは極めて苦手なのですが、リーダーシップのもと、勤勉にかつ、模倣し続けることが得意です。サッカーにも表れており、ストライカーはいつになっても不在ですが、パス回し、個人の認識能力、技術能力は相当に高いものと思えます。昨日、BSでサッカーに関する番組をしていましたが、日本サッカーの父、クラマーはその点に気付いたそうです。だから基本練習を集中的に行ったようです。ちなみに、その時のメンバーであった監督の長沼さん、コーチの岡野さん、そしてその後の監督の森さんらのサインがなぜか私の家にありました。私は小中高とサッカーをしていて、ちょうど高知に日本代表のチームドクターがいて、その関係でサインをもらったのを今でも記憶が蘇ります。
さて、gap yearに戻りますが、日本は新幹線が5分おきに出発するような国ですので、やはり、何もない期間を持つということは、現状からすると合わない気がします。もっとゆっくりという精神が根付かないと難しいでしょう。その前にまずは導入すべきは、休む時は休むということです。GWまっただ中ですが、民族大移動のように「せかされて」動くのではなく、余裕を持ち、何もしないバカンスを楽しむ、そして「バカンスのために」仕事をするといった自らの余暇を得るために、仕事をするというこころを身につけることが、楽に生きていくためには必要なのかもしれません。「会社」のためとか、「学生」のためとか、はたまた「理学療法」のためとか、と思うのではなく、「自分」のため、「家族」のため、と思えるかが、バカンスやgap yearを成功させるための必需品だと思います。「自分」を犠牲にして「学生」のためとか思うから、「自分」がなくなっていくのだとも思うのです。大義名分は棚上げし、自分を満足させるために生きるということを身につけることが必要ではにでしょうか。
この自分は「自分勝手」という意味でもありません。最低限の責任は守るべきです。しかし、その責任は、実は思いあがりの面もあります。よく聞くフレーズで「辞めたら迷惑をかける」というのもその一つです。私は自分がいなくなっても、自分がやらなくても、誰かがそれをやる、代わりはいつもいると思っています。なぜなら、社会というのはシステムで動いているからです。これはある意味無責任な部分も含んでいますが、他人を信頼しているからこそ機能するものです。すべてを抱え込み背負い込んでしまう日本人性質が自分にもありますが、1年近く欧州で生活した経験から、このようなもう一つの私も持っています。昨日の龍馬伝では、まさに典型的な日本人が武市半平太、そして、欧米人が坂本龍馬のような気がしました。武市は真面目で勤勉で、その最期は腹を切ります。長州の者たちから土佐に帰ることは危険だから、脱藩して京に留まれという忠告も自らの責任という視点から土佐に戻ります。そしてとらえられ切腹を命じられます。くしくも後藤象二郎の復活劇になりますが、自分を殺し藩のためお国のためと思い、最期は使い捨ての状態になり、責任をとって自害するというものです。なんだか日本の少し前の会社のスタイルに似ていませんか。一方、坂本はベンチャーみたいなもので、自由奔放にやり、本人は楽しいのですが、まわりは翻弄され、最終的には「目の上のたんこぶ」となって暗殺され、追いやられてしまいます。これも最近よく聞く話です。日本人の気質がこの両方によく表れていると思います。
さてさて、先日、T大学文学部教員は数年間働くと、1年間フリーということを聞きました。このフリーの期間は何をしてもよい(出勤しないでもよし、授業もなし;してもよい)というものです。外国に行くのもよし、充電期間にするのもよし、その時にしかできない調査や研究をするのもよし、と創造性の源といってもよい時間です。しかしながら、今の日本人に1年間フリーにさせるといっても、何をしてよいのかわからない、となるかもしれません。すなわち、もとめられるのは「欲求」なのかもしれません。「あれもこれもしたい」「ここに行ってみたい」「誰にあいたい」などの欲求をいくつも持ち続ける姿勢・社会・教育というのが決定的に不足しているのかもしれません。よいものを評価せず、わるいものを批判するという根深い思想がそれを邪魔しているように思うのです。過去(他人)を批判しながら(たとえば江戸幕府)、新しいものを学ぶ(つくる)というより(新政権)も、自らがそれを学びたい、知りたい、したいというものを優先に考えるように日本人がなれば、gap yearやバカンスが定着するかもしれません。
留学中に欧州のセラピストはきっちり3週間休んでいました。365日体制になった病院。病院の収益のため、量や集中的効果のエビデンスから、患者さんのためと言っていますが、それにより「こなし」作業となり、治療技術の追求の時間、学ぶための時間、そして何よりも「創造性」が奪われてしまうのなら、最終的には「患者さん」のためにはならないのかもしれません。