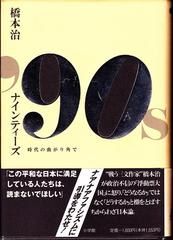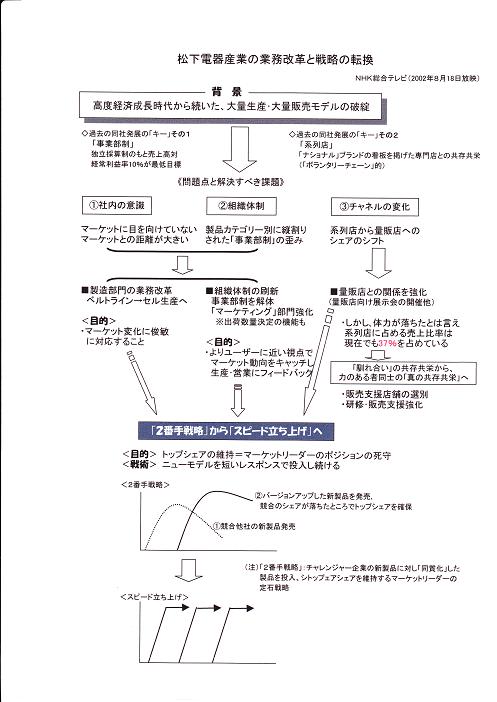数ヶ月前、日本の誇るべきカルチャーのひとつ「機動戦士ガンダム」の海外での評価が、他の代表的作品ほど高くはない(売上げも同様)というある記事を読んだ。
その記事はあまり真剣に読まなかったので(大したことが書いてなかったからか?)、内容は忘れたが、この分野に詳しい友人の説によれば、代理店さんを含めたプロモーションの方法に問題があったとのことだった。
詳細については、彼も語るわけにはいかず、私も推測するしかなかったが、仮説としての説得力はあると思った。
ここでも書かない。
プロモーションの方法論の話ではなく、コンテンツの中身と核心についての話をしよう。
最近、見つけたのが新清士氏の書かれた「日本人の神話へと変わってきた『機動戦士ガンダム』だ。
文化マーケティング視点では、ロジカルで説得力はあると考える。
新清士氏のこの記事には、拙著「コンテンツを求める私たちの『欲望』」(PDF版23ページ、「小さな世間」の説明)でも援用させて頂いた土井健郎の「『甘え』の構造」をで述べられている日本社会(人)のハイコンテキスト性から、「機動戦士ガンダム」がいかに“日本人向き”のコンテンツであるかが述べられている。
日本社会(人)のハイコンテキスト性が国際社会でネガティブに働く事例としては、戦前の中国大陸や朝鮮半島での日本の行為、「良かれ」と思ってしたことが、ま逆に現地の人達から激しい反感を買ってしまった悲劇についてコメントされている。
一見、顔とかにていても日本人と中国人、朝鮮人の思考回路は違う、ということを理解していなかったばかりか、大いなる誤解をしていた事例だ。
(以下黒字部分が引用箇所)
ところが、その論理で世界に広げると困ったことも起きた。明治維新を中国で行わなければならないという善意の気持ちで、中国に渡っていった「大陸浪人」と言われた人たちにも、中国のナショナリズムの台頭により排斥されていく。満州を謀略によって作り上げた石原完爾の「五族共和」という理想も、軍部の現実には機能しなかった。元首相の鳩山由紀夫氏の09年の「東アジア共同体構想」にしても、「こちらが誠意を見せれば、気持ちを斟酌してくれる」という「甘え」があった。
重要なのは、そうした意識が、日本人には無自覚に出てくるところだ。これが政治的な活動だけではない。個人レベルで日常的に自動的に出てくる。それになかなか気づける機会は、少なくとも日本にいると多くない。
こちらの記事、「『機動戦士ガンダム』から見える日本人の甘えの構造」でも触れられている。
(以下黒字部分が引用箇所)
ただし、ガンダムは日本以外の地域では基本的に人気がない。その理由は、戦争を扱いながら、極めて日本人的な想像の範囲でしか、戦争が行われていないからだろう。戦争は、ほとんどが軍閥による地域紛争で、戦国時代を彷彿とさせる。
1932年に満州国を設立したときの「五族共和」という建国理念は、日本人・漢人・朝鮮人・満州人・蒙古人が共に進む国民国家であるとするものだったが、日本人のロジックに他の民族も共感してくれるという甘さがどこかにあったのだろう。満州国建国の謀略を進めた石原完爾には、民族間が素朴に理解し合えるという感覚があった。しかし、それは現実には機能しない。ガンダムの主人公は、撃ち殺されるのが、本来の戦争状態だ。
今から30年以上前から、この問題の核心を指摘していたのが、フロイド研究者の岸田秀である。
岸田秀の「唯幻論」を、誰にでもわかるよう平易に解説した『ものぐさ精神分析』はお薦めだ。
90年代以降、「日本! 日本!」と声高に叫ぶような人達は一度、眼を通しておいたほうがいいと思うよ。

(この書棚の下の奥にあるよ・・・今は文庫があるからいいね)
もちろん、「ガンダム」が日本以外のローコンテキスト社会では概ね不評ということではない。
あくまで、日本発のコンテンツにおける相対的評価での話だろう。
拙著「コンテンツを求める私たちの『欲望』」(PDF版186ページ)でも
サヘル・ローズは母国イランで、「ガンダム」を見て「戦争で肉親を失った子供達が、闘争心という面でシンパシーを感じた」とコメントしている。
イランでも「ガンダム」は人気があったのだ。
ただし、サヘル・ローズの指摘は「闘争心」がポイント。
我々日本人が感動するような新清士氏が挙げたポイントとは別だ。
そのあたりのことは、日本の既成文壇からの評価は低いものの、海外で受け入れられる普遍性、つまり日本社会(人)に限定されることのない「物語性」によって、多くの国々で翻訳され愛読されている村上春樹の作品群との相違点ではないだろうか。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数8,500突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

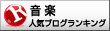 音楽 ブログランキングへ
音楽 ブログランキングへ
 マーケティング・経営 ブログランキングへ
マーケティング・経営 ブログランキングへ
その記事はあまり真剣に読まなかったので(大したことが書いてなかったからか?)、内容は忘れたが、この分野に詳しい友人の説によれば、代理店さんを含めたプロモーションの方法に問題があったとのことだった。
詳細については、彼も語るわけにはいかず、私も推測するしかなかったが、仮説としての説得力はあると思った。
ここでも書かない。
プロモーションの方法論の話ではなく、コンテンツの中身と核心についての話をしよう。
最近、見つけたのが新清士氏の書かれた「日本人の神話へと変わってきた『機動戦士ガンダム』だ。
文化マーケティング視点では、ロジカルで説得力はあると考える。
新清士氏のこの記事には、拙著「コンテンツを求める私たちの『欲望』」(PDF版23ページ、「小さな世間」の説明)でも援用させて頂いた土井健郎の「『甘え』の構造」をで述べられている日本社会(人)のハイコンテキスト性から、「機動戦士ガンダム」がいかに“日本人向き”のコンテンツであるかが述べられている。
日本社会(人)のハイコンテキスト性が国際社会でネガティブに働く事例としては、戦前の中国大陸や朝鮮半島での日本の行為、「良かれ」と思ってしたことが、ま逆に現地の人達から激しい反感を買ってしまった悲劇についてコメントされている。
一見、顔とかにていても日本人と中国人、朝鮮人の思考回路は違う、ということを理解していなかったばかりか、大いなる誤解をしていた事例だ。
(以下黒字部分が引用箇所)
ところが、その論理で世界に広げると困ったことも起きた。明治維新を中国で行わなければならないという善意の気持ちで、中国に渡っていった「大陸浪人」と言われた人たちにも、中国のナショナリズムの台頭により排斥されていく。満州を謀略によって作り上げた石原完爾の「五族共和」という理想も、軍部の現実には機能しなかった。元首相の鳩山由紀夫氏の09年の「東アジア共同体構想」にしても、「こちらが誠意を見せれば、気持ちを斟酌してくれる」という「甘え」があった。
重要なのは、そうした意識が、日本人には無自覚に出てくるところだ。これが政治的な活動だけではない。個人レベルで日常的に自動的に出てくる。それになかなか気づける機会は、少なくとも日本にいると多くない。
こちらの記事、「『機動戦士ガンダム』から見える日本人の甘えの構造」でも触れられている。
(以下黒字部分が引用箇所)
ただし、ガンダムは日本以外の地域では基本的に人気がない。その理由は、戦争を扱いながら、極めて日本人的な想像の範囲でしか、戦争が行われていないからだろう。戦争は、ほとんどが軍閥による地域紛争で、戦国時代を彷彿とさせる。
1932年に満州国を設立したときの「五族共和」という建国理念は、日本人・漢人・朝鮮人・満州人・蒙古人が共に進む国民国家であるとするものだったが、日本人のロジックに他の民族も共感してくれるという甘さがどこかにあったのだろう。満州国建国の謀略を進めた石原完爾には、民族間が素朴に理解し合えるという感覚があった。しかし、それは現実には機能しない。ガンダムの主人公は、撃ち殺されるのが、本来の戦争状態だ。
今から30年以上前から、この問題の核心を指摘していたのが、フロイド研究者の岸田秀である。
岸田秀の「唯幻論」を、誰にでもわかるよう平易に解説した『ものぐさ精神分析』はお薦めだ。
90年代以降、「日本! 日本!」と声高に叫ぶような人達は一度、眼を通しておいたほうがいいと思うよ。

(この書棚の下の奥にあるよ・・・今は文庫があるからいいね)
もちろん、「ガンダム」が日本以外のローコンテキスト社会では概ね不評ということではない。
あくまで、日本発のコンテンツにおける相対的評価での話だろう。
拙著「コンテンツを求める私たちの『欲望』」(PDF版186ページ)でも
サヘル・ローズは母国イランで、「ガンダム」を見て「戦争で肉親を失った子供達が、闘争心という面でシンパシーを感じた」とコメントしている。
イランでも「ガンダム」は人気があったのだ。
ただし、サヘル・ローズの指摘は「闘争心」がポイント。
我々日本人が感動するような新清士氏が挙げたポイントとは別だ。
そのあたりのことは、日本の既成文壇からの評価は低いものの、海外で受け入れられる普遍性、つまり日本社会(人)に限定されることのない「物語性」によって、多くの国々で翻訳され愛読されている村上春樹の作品群との相違点ではないだろうか。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数8,500突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
▼パートナー企業様
*詳細につきましては担当者とご説明に参ります。
【ソーシャルリスニング】につきましては、
GMOリサーチ株式会社 「GMOグローバル・ソーシャル・リサーチ」
http://www.gmo-research.jp/service/gsr.html#tabContents01
【激変するメディアライフ! 感性と消費の新常識】
アスキー総合研究所「MCS2012」
http://research.ascii.jp/consumer/contentsconsumer/
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。