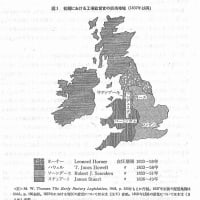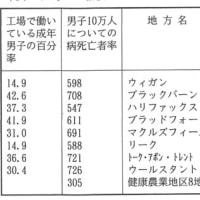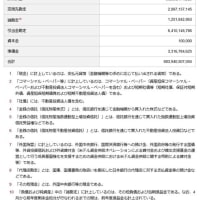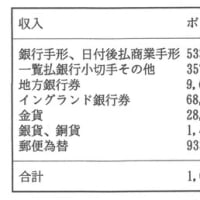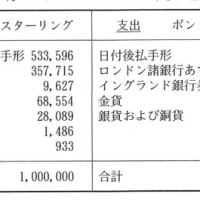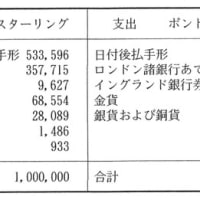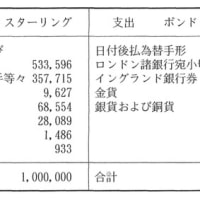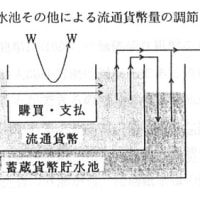『資本論』学習資料No.37(通算第87回) (5)
◎原注118
【原注118】〈108 (イ)この法律に関連してジョン・ウェードが次のように言っているのは正しい。(ロ)「1496年の法律からは、食物は手工業者の所得の3分の1、農業労働者の所得の2分の1に相当するものと認められたということがわかる。そして、このことは、労働者の独立の程度が今日の大部分の状態よりも高かったということを示すものであって、今日では農業でも工業でも労働者の食物は彼らの賃金にたいしてずっと高い割合をなしているのである。」(ジョン・ウェード『中間階級および労働者階級の歴/史』、24、25、577ページ。)(ハ)この差異は、食料と衣料との価格の割合が現在と当時とでは違っていることによるものだ、というような見解は、ビショップ・フリートウッドの『物価年表』、初版、ロンドン、1707年、第2版、ロンドン、1745年、をほんのちょっとのぞいて見ただけでも反駁できるものである。〉 (全集第23a巻357-358頁)
(イ)(ロ) この法律に関連してジョン・ウェードが次のように言っているのは正しいです。「1496年の法律からは、食物は手工業者の所得の3分の1、農業労働者の所得の2分の1に相当するものと認められたということがわかる。そして、このことは、労働者の独立の程度が今日の大部分の状態よりも高かったということを示すものであって、今日では農業でも工業でも労働者の食物は彼らの賃金にたいしてずっと高い割合をなしているのである。」(ジョン・ウェード『中間階級および労働者階級の歴史』、24、25、577ページ。)
これは〈しかし、食事時間は朝食の1時間と昼食の1時間半と4時のパンの半時間とであり、現行の工場法によるそれのちょうど2倍だった(118)。〉という本文に付けられた原注です。因みにここでマルクスが〈この法律に関連して〉と述べているのは、1496年の法律のことを指しています。
ここでウェードが述べていることは、いわゆるエンゲル係数というもののようで、収入のうちに食料費がどれだけ占めているかというものです。それを見ると、15世紀末には、手工業者は3分の1、労働者は2分の1だということで、これは比較的低い数値を表しています。ウェードがこの著書を出したのが1835年ですが、その当時では、農業でも工業でも労働者の食物は賃金に対してずっと高い割合を示していたということです。
ジョン・ウェード『中間階級および労働者階級の歴史』についてはすでに「第3節 搾取の法的制限のないイギリスの産業諸部門」のなかで注64として引用されていました。そのときもマルクスはウェードに対して一定の評価をして引用していましたが、今回はウェードの主張を正しいものとして引用しています。以前も、『61-63草稿』におけるマルクスのウェードへの評価を紹介しましたが、もう一度、『資本論辞典』の説明の概要とともに紹介しておきましょう。
〈(ウェイドは、彼の著書の抽象的な経済学的部分では、少しばかりの、当時としては独創的なものを示している、--たとえば経済恐慌、等々。これにたいして、歴史的部分はその全体が、イギリスの経済学者たちのあいだで流行っている恥知らずな剽窃の適切な一例である。つまり彼は、サー・F・モートン・イーデンの『貧民の状態、または、ノルマン征服期から現在までのイギリス労働者階級の歴史』、全3巻、ロンドン、1797年、からほとんど逐語的に引き写しているのである。)〉 (草稿集④150頁)
〈ウェイドJohn Wade (1786-1875) イギリスの文筆業者.……主著としては.《British History.chronologically arranged》(1839)や《History of the Middle and Working Class.Also an Appendix of Prices》(1833)などがあげられる.マルクスは,この後者の著書をしばしば引用し,これを評して,その歴史的都分はイーデンの《The State of the Poor:or,An History of the Labouring Classes.in England.etc.》(1797)からの剽窃におわっているときめつけている.しかし,この彼の理論的な部分は.一種の経済原論をなしており.当時としては独創的なものをいくらかふくんでおり,たとえば商業恐慌にかんする叙述などにはそれがあらわれている.と評している.また彼の労働者階級の運命やこの階級の経済的利害についての叙述にも,かなりするどい洞察がみられるという.たとえば,労働者階級の全所得のうちで,食料に支出される部分の割合は. 18世紀末では手工業者で3分の1. 農業労働者で2分の1であるが. 19世紀中葉の資本主義社会では,その割合がきわめて高いとし,ここから労働者たちの経済的独立性は時代とともに失われてきているという帰結をひきだしている点や,また,資本蓄積の条件にかんして,資本が労働者を雇用する経済的限界を正しく指摘しながら,‘雇主の利益が平均利潤以下に低下するほど労働賃銀の率が高くなれば,彼は労働者を使用するのをやめるか,または,労働者が労働賃銀の引下げを承認するという条件で彼らを使用する'とのべている点などが,これである.〉 (『資本論辞典』475頁)
(ハ) この差異は、食料と衣料との価格の割合が現在と当時とでは違っていることによるものだ、というような見解は、ビショップ・フリートウッドの『物価年表』、初版、ロンドン、1707年、第2版、ロンドン、1745年、をほんのちょっとのぞいて見ただけでも反駁できるものです。
これはその前のウェードの主張は、300年以上も前と今日とでの食料と衣料との価格の割合の違いを見ていない、という批判に対して、ビショップ・フリートウッドの『物価年表』を見ればそれは間違いだということが分かるというものです。
『物価年表』の詳しい内容は分かりませんが、食料と衣料との価格の割合はそれほど変わっているわけではないということなのでしょう。
文献索引では〈ビショップ・フリートウッド〉ではなく、〈フリートウッド,ウィリアム〉となっています。初版とフランス語版は〈フリートウッド司教〉となっています。つまり〈ビショップ〉というのは「司教」(あるいは主教)という意味で、キリスト教の高級聖職者のことのようです。人名索引には〈イギリスの教会監督.イギリスにおける物価の歴史について書いた〉(全集第23b巻81頁)とあります。また年表の正式名称は文献索引によりますと、〈『物価年表,または,過去600年のイギリスの貨幣,穀物その他の商品の価格の調査』,ロンドン,1707年〉(全集第23b巻31頁)というものです。
◎原注119
【原注119】〈119 W・ペティ『アイルランドの政治的解剖、1672年』、1691年版、10ページ。〔岩波文庫版、松川訳『租税貢納論』、179ページ。〕〉 (全集第23a巻358頁)
これは本文で引用されているペティからの引用文の典拠を示すものです。
ペティについては、以前、「第4章 貨幣の資本への転化」の原注45に関連して、『剰余価値学説史』から次のような一文を紹介したことがありましたので、それを再掲しておきます。
〈『アイルランドの政治的解剖』および『賢者には一言をもって足る』1672年(出版、ロンドン、1691年)。
……
「平均的に見た一人の成年男子の、日々の労働ではなく日々の食料が、価値の一般的尺度であり、そしてこれは、純銀の価値と同じく規則的で恒常的であるように思われる……それゆえ私は、一戸のアイルランド人の小屋の価値を、建造者がそれの建築に費やした日々の食料の数によって評価した。」(65ぺージ。〔同前、松川訳、135ページ。〕)
このあとのほうの文章はまったく重農主義的である。
「なかには他の人たちよりも多く食べる人々もいるだろうということは、重要なことではない。なぜなら、われわれが日々の食料と言っているのは、あらゆる種類と大きさをもった〔100人の人が〕生活し、労働し、子孫をふやすために食べる食料の100分の1を考えているのだからである。」(64ページ。〔同前、松川訳、134ページ。〕)
しかし、ペティがここでアイァランドの統計のうちに求めているものは、価値の一般的〔common〕尺度ではなく、貨幣が価値の尺度であるという意味における価値の尺度である。〉 (全集第26巻Ⅰ456-457頁)
また『資本論辞典』の説明の概要も紹介しておきましょう。(解説は大変長く、マルクスの文献の版と頁数を示すものは煩雑になりますので省略しました)。
〈ペティ Sir Wil1iam Petty (1633-1687)近世経済学の建設者にしてその父,もっとも天才的・独創的な経済学研究者であると同時に,いわば統計学の発明者。/まずしい毛織物工業者の第3子として南西イングランドに生まる。……/ベティは,労働は富の父であり、土地はその母だといい,また資本(Stock)とは過去の労働の成果だといっているが,ここで彼が問題にしている労働は.交換価値の源泉をなす抽象的・人間的労働ではなくて,土地とならんで素材的富の一源泉をなすところの具体的労働,つまり使用価値をつくりだすかぎりでの労働である。そして彼はこの現実的労働をただちにその社会的総姿態において,分業としてとらえたのであるが,彼が商品の「自然価格」を規定するばあい,それは事実上,この商品の生産に必要なる労働時間によって公的に規定されるところの(交換)価値にほかならないのである。しかし,同時に彼は,交換価値を,それが諸商品の交換過程で現象するがままに,貨幣と解いし,そして貨幣そのものは,これを実存する商品すなわち金銀と解した。彼は,一方では重金主義のあらゆる幻想をくつがえしつつも,他方ではこの幻想にとらわれ,金銀を獲得する特殊の種類の現実的労働を,交換価値を生む労働だと説明したのである。/彼の価値規定においては. a) 同等な労働時問によって規定される価値の大いさと. b)社会的労働の形態としての価値,したがって真実の価値姿態としての貨幣と,c) 交換価値の源泉としての労働と,使用価値の源泉としての労働(このばあい労働は,自然質料すなわち土地を前提とする)との混同,の三者が雑然と混乱している。彼が貨幣の諸機能を一応正当に把握しつつも,他方ではそれを金銀と解し,不滅の普通的富と考えたり,また価値の尺度として土地・労働の両者を考え,この両者のあいだに‘等価均等の関係'をうちたてようとしたりしたのも(このぱあい,事実上,土地そのものの価値を労働に分解することだけが問題になっているのだが),この混乱にもとづくのである。/ところで,以上の価値裁定に依存するベティの刺余価値の規定はどうかといえば.彼は剰余価値の本性を予感してはいたけれども彼が見るところでは,剰余がとる形態は'土地の賃料'(地代〕と‘貨幣の賃料'(利子)の二つだけであった。そして彼にとっては,のちに重農主義者にとってそうであるのと同じように,地代こそが'剰余価値'の本来の形態であって,彼は地代を剰余価値一般の正常的形態と考えるのであるから,利潤の方はまだぼんやりと労賃と熔けあっているか,またはたかだか,この剰余価値のうち資本家によって土地所有者から強奪される一部分として現象するのである。すなわち.彼は地代(剰余)を生産者が'必要労働時間'をこえておこなう超過労働として説明するばかりでなく,生産者自身の'剰余労働'のうち,彼の労賃および彼自身の資本の填補をこえる超過分として説明する,つまり地代は,'農業的剰余価値'全体の表現として,土地からではな<.労働からひきだされ,しかも労働のうち労働者の生計に必要なものをこえる剰余として説明されているのである。(以下、まだ続きますが長すぎるので省略します。)〉 (547-548頁)
◎原注120
【原注120】〈120 (イ)『機械工業奨励の必要に関する一論』、ロンドン、1690年、13べージ。(ロ)イギリスの歴史をウイッグ党とブルジョアとの利益に合うように偽造したマコーリは、次のように弁じたてる。(ハ)「子供を早くから労働につかせる慣習は……17世紀には、産業の当時の状態からはほとんど信じられないほどに広まっていた。羊毛工業の中心地ノリッジでは、6歳の子供が労働能力のあるものとして扱われた。なかには特別に温情的と見られた人もあった当時のいろいろな著述家たちは、この都市だけでも少年少女が創造する富は彼ら自身の生活費よりも1年間に12,000ポンドも多いという事実を、『大喜び』で述べている。われわれは、過去の歴史を詳しく研究すればするほど、われわれの時代を新たな社会的害悪に満ちたものと考える人々の見解をしりぞけるべき理由をますます多く見いだすのである。……新たなものは、この害悪を発見する知性と、それを直す人間性とである。」(『イギリス史』、第1巻、417ページ。) (ニ)マコーリは、さらに進んで、17世紀には「特別に温情的な」商業の友〔amls du commerce〕が、オランダのある救貧院で4歳の子供が働かされたことを「大喜び」で語っていると、いうことや、また、この「実践に移された徳性」〔“vertu mise en pratique"〕の実例は、アダム・スミスの時代に至るまでマコーリ流の人道主義者たちのあらゆる著書のなかで模範としてあげられているということを伝えることもできたであろう。(ホ)手工業とは違って、マニュファクチェアが現われるようになると、児童搾取の痕跡がはっきりしてくるが、この搾取は以前から或る程度まで農民のあいだに存在していたのであり、農夫に負わされるくびきが重ければ重いほどますますそれがひどくなるということは、ほんとうである。(ヘ)資本の傾向は紛れもないが、事実そのものはまだ双頭児の出現のようにまばらである。(ト)それだからこそ、このような事実は、特に注意に値し驚嘆に値するものとして、先の見える「商業の友」によって同時代の人のためにも後の世のためにも「大喜び」で書き留められ、またそれにならうことを勧められたのである。(チ)このスコットランド生まれのへつらいもので口じょうずな同じマコーリは言う、「今日聞こえるのはただ退歩だけで、見えるのはただ進歩だけだ」と。/(リ)なんという目、ことにまたなんという耳だろう!〉 (全集第23a巻358-359頁)
(イ) 『機械工業奨励の必要に関する一論』、ロンドン、1690年、13べージ。
これは本文の最後で引用されているものの典拠を示すものでしょう。すなわち〈「われわれの少年は、このイギリスでは、彼らが徒弟になるまではまったくなんの仕事もしない。そして、それからも、できあがった手工業者になるためには、もちろん長い時間--7年--を必要とする。」これに反して、ドイツはほめられる。なぜならば、そこでは子供たちは揺りかごのなかから少なくとも「わずかばかりの仕事は仕込まれる(120)」からである。〉という一文の前半の引用と後半の引用は『機械工業奨励の必要に関する一論』からのものだということです。文献目録を見ても、この著書の作者など詳しい説明はありませんでした。
(ロ)(ハ) イギリスの歴史をウイッグ党とブルジョアとの利益に合うように偽造したマコーリは、次のように弁じたてる。「子供を早くから労働につかせる慣習は……17世紀には、産業の当時の状態からはほとんど信じられないほどに広まっていた。羊毛工業の中心地ノリッジでは、6歳の子供が労働能力のあるものとして扱われた。なかには特別に温情的と見られた人もあった当時のいろいろな著述家たちは、この都市だけでも少年少女が創造する富は彼ら自身の生活費よりも1年間に12,000ポンドも多いという事実を、『大喜び』で述べている。われわれは、過去の歴史を詳しく研究すればするほど、われわれの時代を新たな社会的害悪に満ちたものと考える人々の見解をしりぞけるべき理由をますます多く見いだすのである。……新たなものは、この害悪を発見する知性と、それを直す人間性とである。」(『イギリス史』、第1巻、417ページ。)
マコーリについて、マルクスは〈歴史の偽善者〉(草稿集⑨654頁)と述べていますが、彼はウィッグ党員で議員でしたが、ブルジョアの利益にあうように歴史を偽造したというとです。彼は17世紀にはすでに児童労働が信じられないほど広まっていたと言いますが、これなどは嘘っぱちだとマルクスは述べているわけです。
(ニ) マコーリは、さらに進んで、17世紀には「特別に温情的な」商業の友〔amls du commerce〕が、オランダのある救貧院で4歳の子供が働かされたことを「大喜び」で語っていると、いうことや、また、この「実践に移された徳性」〔“vertu mise en pratique"〕の実例は、アダム・スミスの時代に至るまでマコーリ流の人道主義者たちのあらゆる著書のなかで模範としてあげられているということを伝えることもできたでしょう。
こうした偽善者たちには事欠かないわけですから、マコーリはいくらでも児童労働の例を持ち出すことは可能だっただろう、とマルクスは述べているわけです。
(ホ)(ヘ)(ト) 手工業とは違って、マニュファクチェアが現われるようになると、児童搾取の痕跡がはっきりしてきますが、この搾取は以前から或る程度まで農民のあいだに存在していたものであり、農夫に負わされるくびきが重ければ重いほどますますそれがひどくなるということは、ほんとうです。資本の傾向は紛れもないものですが、事実そのものはまだ双頭児の出現のようにまばらなのです。それだからこそ、このような事実は、特に注意に値し驚嘆に値するものとして、先の見える「商業の友」によって同時代の人のためにも後の世のためにも「大喜び」で書き留められ、またそれにならうことを勧められたのです。
児童労働そのものは確かに古くは農民のあいだで存在し、農夫に負わされるくびきが重ければ重いほどますますそれがひどくなるというのは本当だと思います。しかし資本主義的生産が発展していない段階で児童労働が一般的であったかにいうのは歴史の偽造なのです。資本の本性としては例え児童であろうと搾取の対象にして剰余労働を貪ろうとする傾向はありますが、しかし歴史的事実としては、資本主義的生産の発展以前は、児童労働そのものはまだ双頭児の出現のようにまれなことなのです。だからこそそのよう事実があれば、「商業の友」はそれを書き立てて勧めたということです。マルクスは『61-63草稿』でもマコーリの同じ一文を引用して論じていますが、そこでは次のように述べています。
〈{マコーリが、現存するものの弁護者である--ただ過去にたいしてだけは監察官(ケンソル)カトーであり、現在への追従(ツイショウ)屋である--ウィッグ党員としてふるまうことができるために、経済上の事実をどんなにひどく歪めているかは、とりわけ次の箇所から〔明らかになる〕。--「児童をあまりにも早く労働に就かせる慣習--すなわち、われわれの時代には、自分自身を保護できない人々の正統の保護者たる国家が、賢明かつ慈悲ぶかくも禁止してしまったような慣習--は、17世紀には、当時の工業組織〔manufacturring system〕の規模に比べればほとんど信じられないほど、広く行きわたっていた。羊毛工業の中心地ノリッヂでは、ほんの6歳の子供が労働に就く能力があるものと考えられた。当時のいろいろの著述家たちは--そしてそのなかにはきわめて情けぷかいと見なされていた人もあった--、この都市一つだけでも幼い少年少女が創造する富は彼ら自身の生存に必要であるものよりも1年間に12,000ポンド・スターリングも多いという事実を、大喜びで述ベている。過去の歴史をたんねんに調べれば調べるほど、われわれの時代を新しい社会的害悪に満ちているものと考え/る人々に同じない理由を、われわれはますます多く見いだすのである。真実は、害悪はほとんど例外なしに昔のことである、ということである。新たなものは、これらの害悪を見きわめる知性とそれをただす人間性である」〈マコーリ『イギリス史』、第1巻、ロンドン、1854年、417ページ)。この箇所が証明しているのはまさに正反対のこと、すなわち、当時は児童労働はまだ例外的な現象だったのであり、だからこそ経済学者たちはこの現象に、とくに称揚すべきものとして大喜びで言及したのだ、ということである。現代のどの著述家が、いたいけな年の児童が工場で使用されていることを、なにかとくにめだったこととして言いたてるであろうか。チャイルドやカルペパなどのような著述家を良識をもって読む人であれば、だれでも同じ結論に達するのである。}〉 (草稿集④352-353頁)
(チ)(リ) このスコットランド生まれのへつらいもので口じょうずな同じマコーリは言う、「今日聞こえるのはただ退歩だけで、見えるのはただ進歩だけだ」と。なんという目、ことにまたなんという耳でしょう!
このマルクスの引用しているマコーリの一文は他の文献の引用のなかにも出てきませんでしたが、ここでマコーリが〈今日聞こえるのはただ退歩だけ〉と述べているのは、恐らく児童労働を制限する工場法のことを指しているのだと思えます。ブルジョアにとっては児童労働の制限は退歩に見えるからです。それを際立たせるために、マコーリは17世紀の昔はもっと児童労働が多かったかに歴史を偽造したわけです。そして〈見えるのはただ進歩だけだ〉というのも、いま一つハッキリしませんが、〈過去の歴史をたんねんに調べれば調べるほど、われわれの時代を新しい社会的害悪に満ちているものと考える人々に同じない理由を、われわれはますます多く見いだすのである。真実は、害悪はほとんど例外なしに昔のことである、ということである。新たなものは、これらの害悪を見きわめる知性とそれをただす人間性である〉(草稿集④)と述べていることと関連しているのかも知れません。つまりマコーリは害悪は例外なしに昔のことで、われわれの新しい時代は社会的害悪に満ちているなどいう考えには同意しないというのですから、今の社会は進歩しているのだということなのでしょう。
しかしこうした歴史の偽造と現実をみない恥知らずな追従屋に対して、マルクスは〈なんという目、ことにまたなんという耳だろう!〉と感嘆符を付けて批判しているわけです。
最後にマコーリについて『資本論辞典』から解説の概要を紹介しておきます。
〈マコーリ Thomas Babington Macaulay,First Baron Macaulay (1800-1859)イギリスの政治家・歴史学者.……政治活動のかたわら書きはじめられた主著《History of England from the Accession of James Ⅱ》(1846-1861)は,その出版の当初から空前の売行を示し,マコーリの文名を不動のものとした. ……マルクスも『資本論』でイングランド銀行にたいして'すべての金匠や質屋が憤怒の叫ぴを挙げた'というマコーリの有名な一句を引用している。またたとえば,産業革命時代の幼児労働や苛酷な労働条件にふれても,これをその暗黒面としてとらえるよりは,むしろこれにそれ以後の知織とヒューマニティの増大とを対比させ,現状を是認する。マルクスは『資本論』で,マコーリは'イギリスの歴史をウィッグズとブルジョアジーの利益となるようにすりかえた'といい,また'計画的な歴史の偽造者'であると, 批判している。〉 (557-558頁)
◎第9パラグラフ(18世紀の大部分をつうじて、大工業の時代に至るまでは、まだイギリスの資本は労働力の週価値を支払うことによって労働者のまる1週間をわがものにすることには成功していなかった。)
【9】〈(イ)18世紀の大部分をつうじて、大工業の時代に至るまでは、まだイギリスの資本は労働力の週価値を支払うことによって労働者のまる1週間をわがものにすることには成功していなかった。(ロ)といっても、農業労働者は例外であるが。(ハ)労働者たちが4日分の賃金でまる1週間暮らすことができたという事情は、彼らには、残りの2日間も資本家のために労働するということの十分な理由だとは思われなかった。(ニ)イギリスの経済学者たちの一方のものは資本に奉仕してこのわがままを激しく非難し、他方のものは労働者を擁護した。(ホ)たとえば、当時その商業辞典が今日マカロックやマクグレガーの同種の著述が博しているのと同じ好評を博したポスルスウェートと、前に引用した『産業および商業に関する一論』の著者との論戦を聞いてみよう(121)。〉 (全集第23a巻359頁)
(イ)(ロ) 18世紀の大部分をつうじて、大工業の時代に至るまでは、まだイギリスの資本は労働力の週価値を支払うことによって労働者のまる1週間をわがものにすることには成功していませんでした。といっても、農業労働者は例外ですが。
18世紀の大部分を通じて、つまり大工業、すなわち資本主義的生産がまだ本格的に一人立ちして歩きだす以前においては、イギリスの資本は労働力を週価値で買ったとしても、労働者を1週間まるまる我がものにすることはできなかったということです。ただ農業労働者は例外だということです。
イギリスの農業労働者については「第23章 資本主義的蓄積の一般的法則」の第5節の 「例証」のなかの「e 大ブリテンの農業プロレタリアート」に詳しく展開されています。マルクスはその書き出しで〈資本主義的生産・蓄積の敵対的な性格が野蛮に現われているという点では、イギリス農業(牧畜を含む)の進歩とイギリス農業労働者の退歩とにまさるものはない。〉(全集第23b巻878頁)と述べて、農村の労働者の過酷な状態が暴露されています。
(ハ) 労働者たちが4日分の賃金でまる1週間暮らすことができたという事情は、彼らには、残りの2日間も資本家のために労働するということの十分な理由だとは思われなかったからです。
というのは、当時は労働者たちはが4日分の賃金でまる1週間暮らすことができたからです。そうなりますと残りの2日間も資本家にために働く必要を彼らは感じなかったという単純な理由からです。
(ニ)(ホ) イギリスの経済学者たちの一方のものは資本に奉仕してこのわがままを激しく非難し、他方のものは労働者を擁護しました。たとえば、当時その商業辞典が今日マカロックやマクグレガーの同種の著述が博しているのと同じ好評を博したポスルスウェートと、前に引用した『産業および商業に関する一論』の著者との論戦を聞いてみましょう。
そしてこうした事情について、イギリスの経済学者の間で論争が生じたということです。
一方のものは資本の肩を持って、労働者のわがままを激しく批判し、他方のものは労働者を擁護したというのです。
そこでこの両陣営の意見を聞いてみることにしましょう。一方の、資本の肩を持つ御仁は以前にも引用した『産業および商業に関する一論』という匿名の著書(しかし実際にはカミンガムが匿名で書いたものです)、他方は、商業辞典の著者ポスルスェートです。
この論争者の二人については、すぐ続くパラグラフで取り上げられます。ここでは〈当時その商業辞典が今日マカロックやマクグレガーの同種の著述が博しているのと同じ好評を博したポスルスウェート〉という一文に出てくるマカロックとマクレガーについてどういう人物かを見ておくことにします。
マカロックについては何度か説明したことがありました。それを再現しておくことにします。まず『剰余価値学説史』における言及です。
〈〔マカロックは、〕リカードの経済学を俗流化した男であり、同時にその解体の最も悲惨な象徴である。彼は、リカードだけでなくジェームズ・ミルをも俗流化した男である。
そのほか、あらゆる点で俗流経済学者であり、現存するものの弁護論者であった。喜劇に終わっているが彼の唯一の心配は、利潤の低下傾向であった。労働者の状態には彼はまったく満足しているし、一般に、労働者階級に重くのしかかっているブルジョア的経済のすべての矛盾に満足しきっている。〉 (全集第26巻Ⅲ219-220頁)
〈マカロックは、徹頭徹尾リカードの経済学で商売をしようとした男であって、これがまた彼にはみごとに成功したのである。〉 (同224頁)
全体としてはマルクスはマカロックを俗流経済学者として厳しい言葉で論難しています。
『資本論辞典』からも説明の概要を紹介しておきます。
〈マカロックJohn Ramsay M'Culloch(1789-1864) イギリスの経済学者.……/マルクスは『資本論』でも,十数箇所でマカロッタに言及しているが,包括的に彼の著書をとり上げて批判しているのは『剰余価値学説史』においてである.……/要するにマカロックは.リカードウの理論の発展と擁護を自称しながら,結果においてはその価値規定を根抵から破棄することになった.リカードウ派経済学を俗流化すると同時に解体させた,もっともあわれむべき像であり,またリカードウのみでなくジェイムズ・ミルをも俗流化した人物だといっている.……〉 (555-556頁)
次はマクグレガーについてですが、この人物については詳しいものはありません。全集版の人名索引から紹介しておくだけにします。
〈マクグレガー・ジョン MacGregor,John(1797-1857)イギリスの統計学者,自由貿易論者,国会議員,ブリティシュ・ロイアル・バンクの創立者で理事のひとり(1849-1856年).〉 (全集第23b巻35頁)
((6)に続く。)