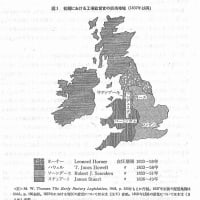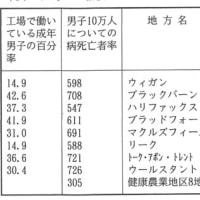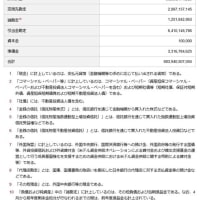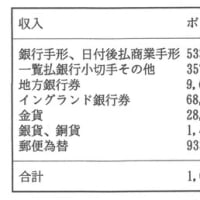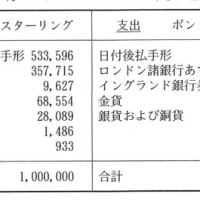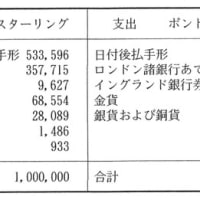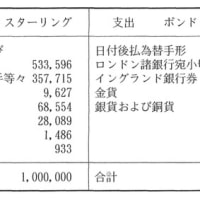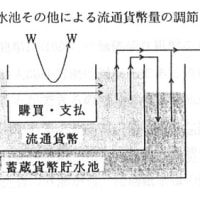『資本論』学習資料No.41(通算第91回)(2)
◎第6パラグラフ(従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされうる)
【6】〈(イ)それゆえ、一定量の剰余価値の生産では、一方の要因の減少は他方の要因の増加によって埋め合わされることができる。(ロ)可変資本が減らされて、同時に同じ割合で剰余価値率が高くされれば、生産される剰余価値の量は不変のままである。(ハ)前に仮定したように、資本家は毎日100人の労働者を搾取するためには100ターレルを前貸しし/なければならないものとし、剰余価値率は50%だとすれば、この100ターレルの可変資本は、50ターレルの、言い換えれば 100×3労働時間 の剰余価値を生む。(ニ)剰余価値率が2倍に高められれば、すなわち労働日が6時間から9時間にではなく6時間から12時間に延長されれば、50ターレルに半減された可変資本がやはり50ターレルの、言い換えれば 50×6労働時間 の剰余価値を生む。(ホ)だから、可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされうるのである。(ヘ)したがって、ある限界のなかでは、資本によってしぼり出されうる労働の供給は労働者の供給に依存しないものになる(202)。(ト)反対に、剰余価値率の減少は、それに比例して可変資本の大きさまたは従業労働者数が増大するならば、生産される剰余価値の量を変えないのである。〉(全集第23a巻400-401頁)
(イ)(ロ) ということは、一定量の剰余価値の生産においては、一方の要因の減少は他方の要因の増加によって埋め合わされることができるということになります。可変資本が減らされても、同時に同じ割合で剰余価値率が高くされれば、生産される剰余価値の量は不変のままだからです。
第一の法則というのは
生産される剰余価値量(M)=前貸しされる可変資本の量(V)×剰余価値率(m/v)
というものでした。ということはVを減らしても(雇用する労働者数を減らしても)、m/v(剰余価値率=搾取率)をそれと同じ割合で高めれば、生産される剰余価値量(M)は変わらないということになります。つまり一定の剰余価値の生産においは、一方の要因の減少は、他方の要因の増大によって補うことができるということです。
(ハ)(ニ)(ホ) 前に仮定しましたように、資本家は毎日100人の労働者を搾取するためには100ターレルを前貸ししなければならないものとし、剰余価値率は50%だとしますと、この100ターレルの可変資本は、50ターレルの、言い換えれば 100×3労働時間=300時間が対象化された剰余価値を生みます。ここで労働日が延長されて剰余価値率が2倍に高められますと、つまり労働日が6時間の必要労働に3時間の剰余労働を足した9時間から、6時間の必要労働に6時間の剰余労働を足した12時間に延長されますと、今、例え労働者が50人に減らされて、可変資本が100ターレルから50ターレルに半減したとしましても、やはり先と同じように50ターレルの、言い換えれば 50×6労働時間=300時間の剰余労働が対象化された剰余価値を生みます。だから、可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされうるのです。
前に仮定した数値を入れて考えますと、資本家は100人の労働者を雇用するためには100ターレルを前貸ししなければなりません。いま搾取率を50%としますと、100ターレルの可変資本は50ターレルの剰余価値を生みだします。これは1人の労働者の必要労働時間が6時間ですから、50%の搾取率では剰余労働時間は3時間です。ですから50ターレルの剰余価値というのは、3時間の剰余労働時間×100人=300労働時間が対象化されたものになります。
ここで労働時間が延長されて剰余価値率が2倍に高められたとします。つまり労働時間が9時間(必要労働6時間+剰余労働3時間)から12時間(必要労働6時間+剰余労働6時間)に延長されたとします。すると剰余労働時間が3時間から6時間に2倍になります。つまり剰余価値率が2倍になったということです。
しかしその代わりに雇用される労働者数は半分に減らされて100人から50人になったとしますと、可変資本は100ターレルから50ターレルになります。しかし生産される剰余価値量そのものは、剰余労働時間が2倍になっていますから、50×6労働時間=300時間の剰余労働の対象化されたものになり、その前と変わりません。
第一の法則にあてはめますと 生産される剰余価値量=前貸しされる可変資本の量(100ターレルの1/2)×2倍の剰余価値率 となりますから、生産される剰余価値量は変わらないわけです。
つまり可変資本が減少しても(雇用される労働者数が減らされても)、それに比例する労働力の搾取度が引き上げられれば(労働日が延長されれば)、生産される剰余価値量は変わらないということです。つまり労働者数の減少は搾取率の引き上げて埋め合わせることができるということです。
(ヘ)(ト) だから、ある限界のなかでは、資本によってしぼり出されうる労働の供給は労働者の供給に依存しないものになります。反対に、剰余価値率の減少は、それに比例して可変資本の大きさ、あるいは従業労働者数が増大するのでしたら、生産される剰余価値の量を変えないことになります。
ということは、ある限界のなかでのことですが、資本によって絞り取られる労働量は労働者数には依存しないということです。反対に、剰余価値率の減少は、つまり労働時間の短縮は、それに比例して可変資本の大きさを増やせば、つまり雇用される労働者数が増やされるなら、生産される剰余価値量は変わらないということにもなります。
◎原注202
【原注202】〈202 (イ)この基本法則を俗流経済学の諸君は知っていないように見える。(ロ)彼ら、さかさにされたアルキメデスたちは、需要供給による労働の市場価格の規定のうちに、世界を一変させるためのではなく、世界を静止させるための支点を見つけたと思っているのである。〉(全集第23a巻401頁)
(イ)(ロ) この基本法則を俗流経済学の諸君は知っていないように見えます。彼らは、つまりさかさにされたアルキメデスたちは、需要供給による労働の市場価格の規定のうちに、世界を一変させるためのではなく、世界を静止させるための支点を見つけたと思っているのです。
これは〈だから、可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされうるのである。したがって、ある限界のなかでは、資本によってしぼり出されうる労働の供給は労働者の供給に依存しないものになる(202)。〉という本文に付けられた原注です。
俗流経済学についてマルクスは『61-63草稿』で次のように特徴づけています。
〈労働の価値または労働時間の価格というこの表現では、価値概念は完全に消し去られているだけでなく、それと直接に/矛盾するものに転倒されている。……とはいえ、それは、生産過程の必然的な結果として生ずる表現なのである、つまり労働能力の価値の必然的な現象形態なのである。その不合理な表現は、すでに労賃という言葉自体のなかにある。そこでは労働の賃金イコール労働の価格イコール労働の価値なのである。しかし、労働者の意識のなかでも資本家の意識のなかでも同じように生きているこの没概念的な形態は、実生活において直接的に現われる形態なのであるから、それゆえこの形態こそ、俗流経済学が固執するところの形態なのである。彼らは、他のすべての諸科学から区別される経済学の独自性は次の点にあるというのである。すなわち他の諸科学が、日常の諸現象の背後にかくれている、そして日常の外観(たとえば、地球をめぐる太陽の運動のような)とたいていは矛盾する形態にある本質を暴露しようとするのにたいして、経済学の場合には、日常の諸現象を同じく日常的な諸表象のうちへたんに翻訳することをもって科学の真の事業だと言明してはばからない、と。〉(草稿集⑨350-351頁)
つまり俗流経済学はブルジョア社会の表面に転倒して現れている諸現象をただそのままに叙述するだけなのですが、彼らは需要供給によって労働の市場価格が高くなるとブルジョア社会そのものが停止すると警告するわけです。
ここで〈さかさにされたアルキメデスたち〉というのは、内在的な諸法則が転倒して現象しているものをそのままに叙述することを自らの経済学としている俗流経済学を揶揄しているわけです。アルキメデスは梃子の支点を見いだせば、世界を一変させうると主張したのですが、逆立ちした俗流経済学者たちはその反対に世界を制止させるための支点を労働の価格に見いだしたということです。
エンゲルスは「『資本論』第3部への補遺」のなかで次のように述べています。
〈彼はついにあのアルキメデスの挺子の支点を見つけたのだ。この支点からやれば彼のような一寸法師でもマルクスの堅固な巨大な建築を空中に持ち上げて粉砕することができるというのである。〉(全集第25b巻1136頁)
なお 新日本新書版では〈彼ら、さかさにされたアルキメデスたちは、需要供給による労働の市場価格の規定のうちに、世界を一変させるためのではなく、世界を静止させるための支点を見つけたと思っているのである〉のところに次のような訳者注が付いています。
〈アルキメデスの言とされる「我に立つべき場所を与えよ。さすれば地球を動かさん」にちなむ。数学の先人の書を解説したアレクサンドリアのパップス『著作集』、第8巻、11の10。とくに最後の「さすれば……」の句は、ギリシアの哲学者シンプリキウスによれば「さすれば地球をその地軸から持ち上げん」であるとされ、(『アリストテレス 形而上学注釈』、第4巻続、ディールス編、1110ページ)、マルクスはこの語法をここでそのまま用いている。俗流経済学のあべこべへの皮肉。〉(531頁)
◎第7パラグラフ(第二の法則;平均的な労働日の絶対的な限度は、本来いつでも24時間より短いのであって、可変資本を剰余価値率の引き上げでもって補填することの絶対的な限度、または、搾取される労働者の数を労働力の搾取度の引き上げでもって補填することの絶対的な限度、を成している)
【7】〈(イ)とはいえ、労働者の数または可変資本の大きさを剰余価値率の引き上げまたは労働日の延長によって補うということには、飛び越えることのできない限界がある。(ロ)労働力の価値がどれだけであろうと、したがって、労働者の維持に必要な労働時間が2時間であろうと10時間であろうと、1人の労働者が毎日生産することのできる総価値は、つねに、24労働時間の対象化である価値よりも小さいのであり、もし対象化された24労働時間の貨幣表現が12シリングまたは4ターレルならば、この金額よりも小さいのである。(ハ)われわれのさきの仮定によれば、労働力そのものを再生産するためには、または労働力の買い入れに前貸しされた資本価値を補填するためには、毎日6労働時間が必要であるが、この仮定のもとでは、100%の剰余価値率すなわち12時間労働日で500人の労働者を使用する500ターレルの可変資本は、毎日500ターレルの、または 6×500労働時間 の剰余価値を生産する。/(ニ)200%の剰余価値率すなわち18時間労働日で毎日100人の労働者を使用する100ターレルの資本は、たった200ターレルの、または 12×100 労働時間の剰余価値量を生産するだけである。(ホ)そして、この資本の総価値生産物、すなわち、前貸可変資本の等価・プラス・剰余価値は、けっして毎日400ターレルまたは 24×100 労働時間という額に達することはできない。(ヘ)本来つねに24時間よりも短い平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしているのである。(ト)このわかりきった第二の法則は、後に展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする資本の傾向、すなわちできるだけ大きな剰余価値量を生産しようとする資本のもう一つの傾向とは矛盾した傾向から生ずる多くの現象を説明するために、重要なのである。(チ)逆に、使用される労働力の量または可変資本の量がふえても、そのふえ方が剰余価値率の低下に比例していなければ、生産される剰余価値の量は減少する。〉(全集第23a巻401-402頁)
このパラグラフは、フランス語版では三つのパラグラフに分けられ、全体に書き換えられています。一応、だいたい対応するフランス語版を最初に紹介しておくことにします。
(イ)(ロ) といいましても、労働者の数または可変資本の大きさを剰余価値率の引き上げか、または労働日の延長によって補うということには、飛び越えることのできない限界があります。なぜなら、労働力の価値がどれだけであっても、だから、労働者の維持に必要な労働時間が2時間であっても10時間であっても、1人の労働者が毎日生産することのできる総価値は、つねに、24労働時間の対象化である価値よりも小さいからです。もし対象化された24労働時間の貨幣表現が12シリングかまたは4ターレルでしたら、この金額よりも小さいからです。
まずフランス語版です。
〈しかし、この種の相殺は一つの乗り越えがたい限界に出会う。24時間という自然日は平均労働日よりも必ず長い。だから、平均的な労働者が1時間に1/6エキュの価値を生産しても、平均労働日はけっして4エキュの日価値をもたらすことができない。4エキュの価値を生産するためには、平均労働日は24時間を必要とするからである。剰余価値については、その限界はなおいっそう狭い。〉(江夏・上杉訳315頁)
前パラグラフで述べましたように、〈一定量の剰余価値の生産では、……可変資本の減額は、それに比例する労働力の搾取度の引き上げによって、または従業労働者数の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わされうる〉と言いましても、それには絶対的な限界があります。
というのも、労働力の価値、つまり必要労働時間がどれだけでありましても、労働日の延長には1日24時間という飛び越えることのできない限界があるからです。1人の労働者が対象化できるのは1日24時間よりも小さいのです。もし対象化された24労働時間の貨幣表現が12シリング=4ターレルでしたら、この金額よりも小さいわけです。
(ハ)(ニ)(ホ) 例えば、私たちのさきの仮定によりますと、労働力そのものを再生産するためには、または労働力の買い入れに前貸しされた資本価値を補填するためには、毎日6労働時間が必要ですが、この仮定のもとでは、100%の剰余価値率すなわち12時間労働日で500人の労働者を使用する500ターレルの可変資本は、毎日500ターレルの、または 500×6労働時間 の剰余価値を生産します。いま、買い入れる労働者を5分の1の100人にして、その代わりに労働時間を延長して、200%の剰余価値率したとします。しかし18時間労働日で毎日100人の労働者を使用する100ターレルの資本は、たった200ターレルの、または 100×12労働時間 の剰余価値量を生産するだけです。そればかりか剰余価値だけではなくて、この資本の総価値生産物、すなわち、前貸可変資本の等価・プラス・剰余価値を見ても、けっして毎日400ターレルまたは 100×24労働時間 という額に達することはできないのです。
フランス語版です。
〈もし日々の賃金を補填するために必要な労働日部分が6時間に達するならば、自然日のうち残るのは18時間だけであって、生物学の法剥は、この18時間のうちの一部を労働力の休息のために要/求する。労働日を18時間という最高限度に延長して、この休息の最低限度として6時間を想定すれば、剰余労働は12時間にしかならず、したがって、2エキュの価値しか生産しないであろう。
500人の労働者を100%の剰余価値率で、すなわち6時間が剰余労働に属する12時間の労働をもって、使用する500エキュの可変資本は、日々500エキュあるいは 6×500労働時間 の剰余価値を生産する。日々100人の労働者を200%の剰余価値率で、すなわち18時間の労働日をもって、使用する100エキュの可変資本は、200エキュあるいは 12×100労働時間 の剰余価値しか生産しない。その生産物は総価値で、1日平均400エキュの額あるいは 24×100労働時間 にけっして達することができない。〉(江夏・上杉訳315-316頁)
これまでの仮定にもとづいて考えてみますと、労働力を再生産するためには、あるいは労働力の買い入れに前貸しされた資本価値を補填するためには、労働者は毎日6労働時間を対象化させなければなりません。
いま、剰余価値率を100%、すなわち1日の労働時間を12時間としますと、500人の労働者を使用する500ターレルの可変資本は、毎日500ターレルの剰余価値を、すなわち500×6労働時間 の対象化された剰余価値を生産します。
いま、雇用する労働者数を減らして100人にします。しかしその代わりに搾取率を2倍に、つまり労働時間を12時間から18時間に延長したとします。しかしその場合の生産される剰余価値は 100×12労働時間 、つまり100×2ターレル=200ターレルの剰余価値を生産できるだけです。
それだけではなく、剰余価値だけではなくて、この資本の総価値生産物、つまり前貸可変資本の価値+剰余価値を見ましても、100ターレル+200ターレル=300ターレルでしかありません。だから毎日400ターレルまたは100×24労働時間 という額には達することはできないのです。
(ヘ) 本来つねに24時間よりも短い平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしているのです。
フランス語版です。
〈したがって、可変資本の減少が剰余価値率の引き上げによって、または結局同じことになるが、使用される労働者の数の削減が搾取度の上昇によって、相殺できるのは、労働日の、したがって、労働日に含まれる剰余労働の、生理的な限界内にかぎられる。〉(江夏・上杉訳316頁)
だから本来24時間より短い労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値率の引き上げによっては補うことのできない絶対的な限界なのです。あるいは言い換えますと、搾取される労働者数の減少を、労働力の搾取度の引き上げ(すなわち労働時間の延長)によって補うことの絶対的な限界をなしているのです。
(ト) このわかりきった第二の法則は、後に展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする資本の傾向と、できるだけ大きな剰余価値量を生産しようとする資本のもう一つの傾向とは矛盾したものであり、そこから生ずる多くの現象を説明するために、重要なのです。
フランス語版です。
〈全く明白なこの法則は、複雑な現象の理解にとって重要である。われわれはすでに、資本が最大限可能な剰余価値を生産しようと努力することを知っているし、後には、資本がこれと同時に、事業の規模に比較してその可変部分あるいはそれが搾取する労働者の数を最低限に削減しようと努めることを見るであろう。これらの傾向は、剰余価値量を規定する諸因数中のある一因数の減少がもはや他の因数の増大によって相殺されえなくなるやいなや、あい矛盾したものになる。〉(同上)
これは第二の法則です。この法則は、後に展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数を、あるいは労働力に転換する可変資本の量をできるだけ縮小しようとする資本の傾向(いわゆる省力化です)は、他方でできるだけ大きな剰余価値を生産しようとする資本のもう一つの傾向と矛盾し、そこから生じるさまざまな現象を説明するために重要なのです。
新日本新書版では〈後に展開される資本の傾向〉の部分には次のような訳者注が付いています。
〈本書、第23章、第2節「蓄積とそれにともなう集積との進行中における可変資本部分の相対的減少」参照〉(532頁)
この訳者注が参照指示しているところは長いですが、その一部分を抜粋しておきましょう。
〈資本主義体制の一般的基礎がひとたび与えられれば、蓄積の進行中には、社会的労働の生産性の発展が蓄積の最/も強力な槓杆となる点が必ず現われる。……労働の社会的生産度は、一人の労働者が与えられた時間に労働力の同じ緊張度で生産物に転化させる生産手段の相対的な量的規模に表わされる。彼が機能するために用いる生産手段の量は、彼の労働の生産性の増大につれて増大する。……だから、労働の生産性の増加は、その労働量によって動かされる生産手段量に比べての労働量の減少に、または労働過程の客体的諸要因に比べてのその主体的要因の大きさの減少に、現われるのである。〉(全集第23b巻811-812頁)
もちろん、この参照指示は適切とは思いますが、ただマルクスがここで〈後に展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする資本の傾向、すなわちできるだけ大きな剰余価値量を生産しようとする資本のもう一つの傾向とは矛盾した傾向から生ずる多くの現象〉という場合には、第3部で資本の有機的構成の高度化には資本の本質的な矛盾が存在すると述べていることに関連しているように思えます。生産力を高めるために、資本は大規模な工場や機械設備などに投資し、可変成分に比較して不変成分を圧倒的に増大させる傾向がありますが、しかしそれは資本にとっては剰余価値、すなわち彼らの直接の目的である利潤の増大をはかるためであるのに、その剰余価値の生み出す唯一の源泉である労働力を可能なかぎり減らそうとするわけです。だからこれはある意味では根本的な矛盾なのです。できるだけ大きな剰余価値を得ようとしながら、その剰余価値の唯一の源泉を減らすのですから。これが利潤率の傾向的低下をもたらし、資本主義的生産様式の本質的な矛盾として、周期的な恐慌として爆発してくるわけです。こうしたものを説明するのものの基礎がここで与えられているのだということではないでしょうか。
(チ) 逆に、使用される労働力の量または可変資本の量が増えたとしましても、その増え方が剰余価値率の低下に比例していないと、生産される剰余価値の量は減少します。
フランス語版にはこれに相当するものはありません。
それとは逆のケース。つまり使用される労働力の量または可変資本の量が増えたとしましても、その増え方が剰余価値率の低下の割合、すなわち労働日の短縮の方が比例せず大きすぎると、生産される剰余価値の量は減ります。
◎第8パラグラフ(第三の法則;剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例する)
【8】〈(イ)第三の法則は、生産される剰余価値の量が剰余価値率と前貸可変資本量という二つの要因によって規定されているということから生ずる。(ロ)剰余価値率または労働力の搾取度が与えられており、また労働力の価値または必要労働時間の長さが与えられていれば、可変資本が大きいほど生産される価値と剰余価値との量も大きいということは、自明である。(ハ)労働日の限界が与えられており、その必要成分の限界も与えられているならば、1人の資本家が生産する価値と剰余価値との量は、明らかに、ただ彼が動かす労働量だけによって定まる。(ニ)ところが、この労働量は、与えられた仮定のもとでは、彼が搾取する労働力量または労働者数によって定まるのであり、この数はまた彼が前貸しする可変資本の大きさによって規定されている。(ホ)つまり、剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例するのである。(ヘ)ところで、人の知るように、資本家は自分の資本を二つの部分に分ける。(ト)一方の部分を彼は生産手段に投ずる。(チ)これは彼の資本の/不変部分である。(リ)他方の部分を彼は生きている労働力に転換する。(ヌ)この部分は彼の可変資本をなしている。(ル)同じ生産様式の基礎の上でも、生産部門が違えば、不変成分と可変成分とへの資本の分割は違うことがある。(ヲ)同じ生産部門のなかでも、この割合は、生産過程の技術的基礎や社会的結合が変わるにつれて変わる。(ワ)しかし、ある与えられた資本がどのように不変成分と可変成分とに分かれようとも、すなわち前者にたいする後者の比が 1:2 であろうと、1:10 であろうと、1:× であろうと、いま定立された法則はそれによっては動かされない。(カ)なぜならば、さきの分析によれば、不変資本の価値は、生産物価値のうちに再現はするが、新たに形成される価値生産物のなかにははいらないからである。(ヨ)1000人の紡績工を使用するためには、もちろん、100人を使うためよりも多くの原料や紡錘などが必要である。(タ)しかし、これらの追加される生産手段の価値は、上がることも下がることも不変のままのことも、大きいことも小さいこともあるであろうが、それがどうであろうとも、これらの生産手段を動かす労働力の価値増殖過程にはなんの影響も及ぼさないのである。(レ)だから、ここで確認された法則は次のような形をとることになる。(ソ)いろいろな資本によって生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていて労働力の搾取度が等しい場合には、これらの資本の可変成分の大きさに、すなわち生きている労働力に転換される成分の大きさに、正比例する。〉(全集第23a巻402-403頁)
このパラグラフもフランス語版では二つのパラグラフに分けられ、全面的に書き換えられています。だから今回も最初にだいたいに該当するフランス語版をまず紹介することにします。なおフランス語版には「第一の法則」「第二の法則」「第三の法則」という表現は使われていません。
(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ) 第三の法則は、生産される剰余価値の量が剰余価値率と前貸可変資本量という二つの要因によって規定されているということから生じます。剰余価値率または労働力の搾取度が与えられており、また労働力の価値または必要労働時間の長さが与えられていますと、可変資本が大きいほど生産される価値と剰余価値との量も大きいということは明らかです。労働日の限界が与えられており、その必要成分の限界も与えられているのでしたら、1人の資本家が生産する価値と剰余価値との量は、明らかに、ただ彼が動かす労働量だけによって定まります。ところが、この労働量は、与えられた仮定のもとでは、彼が搾取する労働力量または労働者数によって定まるのであって、この数はまた彼が前貸しする可変資本の大きさによって規定されているのです。だから、剰余価値率が与えられていて労働力の価値が与えられていますと、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例するのです。
まずフランス語版です。
〈価値とは実現された労働にほかならないから、資本家の生産させる価値量がもっぱら彼の動かす労働量に依存することは、自明である。彼は同数の労働者を用いて、労働者の労働日がより長くまたはより短く延長されるのに応じて、労働量をより多くまたはより少なく動かすことができる。ところが、労働力の価値と剰余価値率とが与えられていれば、換言すれば、労働日の限界と、労働日の必要労働と剰余労働への分割とが与えられていれば、資本家の実現する剰余価値を含んでいる価値の総量は、もっぱら、彼が働かせる労働者の数によって規定され、労働者の数そのものは、彼が前/貸しする可変資本の量に依存している。
そのばあい、生産される剰余価値の量は前貸しされる可変資本の量に正比例する。〉(江夏・上杉訳316-317頁)
第三の法則は、第一の法則、すなわち生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の量に剰余価値率を掛けたものに等しいということから直接導き出されます。つまり生産される剰余価値の量は剰余価値率と前貸可変資本量という二つの要因によって規定されているということから生じます。つまり第一の法則から剰余価値率または労働力の搾取度が与えられていて、労働力の価値または必要労働時間の長さが与えられていますと、可変資本の量は、ただ資本が使用する労働力の量(資本家が雇用する労働者数)によって与えられることになります。だから可変資本の量が大きければ大きいほど、つまり使用される労働者数が多ければ多いほど、生産される剰余価値の量もまた大きいという関係が出てきます。だから、剰余価値率が与えられていて、労働力の価値も与えられていますと、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさ(雇用される労働者数)に正比例するという第三の法則が導き出されるのです。
(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ) ところで、周知のように、資本家は自分の資本を二つの部分に分けます。一方の部分を彼は生産手段に投じます。これは彼の資本の不変部分です。他方の部分を彼は生きている労働力に転換します。この部分は彼の可変資本をなしています。同じ生産様式の基礎の上でも、生産部門が違えば、不変成分と可変成分とへの資本の分割は違うことがあります。また同じ生産部門のなかでも、この割合は、生産過程の技術的基礎や社会的結合が変わるにつれて変わります。
フランス語版です。
〈ところで、産業部門がちがえば、総資本が可変資本と不変資本とに分割される割合は非常にちがう。同種の事業では、この分割は技術的条件と労働の社会的結合とに応じて変化する。〉(江夏・上杉訳317頁)
ところで「第6章 不変資本と可変資本」で明らかになりましたように、資本の前貸資本は、二つの部分に分けられます。一つは生産手段(原料や機械等)の購入のために、もう一つは労働力の購入のために。生産手段は価値を生産物に移転しますがそれ自体は増殖しません。だからそれを不変資本と名付けました。価値を増殖するのは労働力に転換したもののみでした。だからそれを可変資本と名付けたのでした。
この前貸資本が分かれる二つの部分は、生産部門が違えば、その割合、構成は当然違ってきます。また同じ生産部門でも、生産過程の技術的基礎や労働の社会的結合が変わるに連れて変わってきます。
(ワ)(カ)(ヨ)(タ) しかし、ある与えられた資本がどのように不変成分と可変成分とに分かれていたとしても、すなわち前者にたいする後者の比が 1:2 であったとしても、1:10 であったとしても、あるいは 1:× であっても、いま定立された法則はそれによっては動かされません。というのは、これまでの分析によりますと、不変資本の価値は、生産物価値のうちに再現はしますが、新たに形成される価値生産物のなかにははいらないからです。もちろん、1000人の紡績工を使用するためには、100人を使うためよりもより多くの原料や紡錘などが必要です。しかし、これらの追加される生産手段の価値は、上がることも下がることも不変のままのことも、大きいことも小さいこともあるでしょうが、それがどうであろうと、これらの生産手段を動かす労働力の価値増殖過程にはなんの影響も及ぼさないのです。
フランス語版です。
〈ところが、周知のように、不変資本の価値は、生産物のうちに再現するのに対し、生産手段に付加される価値は、可変資本、すなわち前貸資本のうち労働力に変わる部分からのみ生ずる。ある与えられた資本が不変部分と可変都分とにどのように分解しても、前者と後者の比が 2:1,10:1, 等々であっても、すなわち、使用される労働力の価値に比べた生産手段の価値が増大しても減少しても不変のままであっても、それが大きくても小さくても、どうでもよいのであって、それは生産される価値量にはやはり少しも影響を及ぼさない。〉(同上)
しかしある与えられた資本の構成がどのようであっても、すなわちその可変成分と不変成分がどのような組み合わせになっていようとも、いま定立された法則、すなわち剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例するという法則には何の影響もありません。というのは第6章の分析で明らかになりましたように、不変資本の価値は、具体的な有用労働によって移転され、生産物の価値のうちに再現はしますが、あらたに形成される価値生産物のなかには入らないからです。
もちろん、1000人の紡績工を使用するためには、100人を使用する場合より、より多くの原料や紡錘、つまり生産手段(不変資本)が必要です。だから前貸しされる資本量も増大しなければなりませんが、しかし不変資本部分がどれだけ増大しようと、確かにそれらは生産物の価値量を大きくしますが、しかし価値生産物の大きさそのものには何の変化も無いのです。つまりそれらは労働力の価値増殖過程にはまったく何の影響も及ぼさないからです。
(レ)(ソ) ですから、ここで確認された法則は次のような形をとることになります。すなわち、いろいろな資本によって生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていて労働力の搾取度が等しい場合には、これらの資本の可変成分の大きさに、すなわち生きている労働力に転換される成分の大きさに、正比例するということです。
フランス語版です。
〈このばあい、前貸資本が不変部分と可変部分とに分割される割合がどうありうるにしても、上述の法則を種々の産業部門に適用すれば、次の法則に到達する。平均労働力の価値とその平均搾取度が、種々の産業で同等であると仮定すれば、生産される剰余価値の量は、使用される資本の可変部分の大きさに正比例する、すなわち、労働力に変えられる資本都分に正比例するのである。〉(同上)
ということから、第三の法則は、次のような形をとることになります。すなわち、いろいろな産業部門で生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値と労働力の搾取度が同じものとして与えられていますと、可変成分の大きさ(雇用される労働者数)に正比例するということです。
言い換えますと、同じ前貸資本量であっても、その不変資本部分と可変資本部分との構成が異なれば、生産される剰余価値の量も違ってくるということです。
ここで確認のために、もう一度、三つの法則を並べて書いておきましょう。
・第一の法則:生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の量に剰余価値率を掛けたものに等しい。
・第二の法則;平均的な労働日の絶対的な限度は、本来いつでも24時間より短いのであって、可変資本を剰余価値率の引き上げでもって補填することの絶対的な限度、または、搾取される労働者の数を労働力の搾取度の引き上げでもって補填することの絶対的な限度、を成している
・第三の法則;剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の大きさに正比例する。
((3)に続く。)