第48回「『資本論』を読む会」の報告(その2)
◎第10パラグラフ
【10】〈(イ)商品交換がそのもっぱら局地的な束縛を打破し、したがって商品価値が人間労働一般の物質化にまで拡大していくのと同じ割合で、貨幣形態は、一般的等価という社会的機能に生まれながらにして適している商品に、すなわち貴金属に、移っていく。〉
(イ)商品交換がますます盛んになり、局的な束縛を打ち破って拡大していくにつれて、商品の価値はますます人間労働一般が物質化したものとしての性格を強めていきます。そしてそれと同じ割合で、貨幣形態も、ますます一般的等価という社会的機能に適した商品に、すなわち貴金属に移っていきます。
『経済学批判』には、〈一商品の交換価値は、その等価物の系列が長ければ長いほど、つまりその商品にとって交換の範囲が大きければ大きいほど、それだけますます高度に交換価値としてあらわされる。だから交換取引の漸次的拡大、交換の増大、交換取引にはいってくる商品の多様化は、商品を交換価値として発展させ〉(全集13巻34頁)ると指摘されています。そして商品の価値がますます人間労働一般の物質化にまで拡大すると同時に、貨幣もまた貴金属に移っていくと指摘されています。貴金属が一般的等価という社会的機能に〈生まれながらにして適している〉という事情は、次のパラグラフで説明されています。
◎第11パラグラフ
【11】〈(イ)ところで、「金銀は生まれながらにして貨幣ではないが、貨幣は生まれながらにして金銀である(42)」ということは、金銀の自然諸属性が貨幣の諸機能に適していることを示している(43)。(ロ)しかし、われわれは、これまでのところでは、貨幣の一つの機能しか知らない。(ハ)すなわち、商品価値の現象形態として、または商品の価値の大きさが社会的に表現される材料として、役立つという機能だけである。(ニ)価値の適切な現象形態、または抽象的な、したがって同等な、人間労働の物質化となりうるのは、どの一片をとってみてもみな同じ均等な質をもっている物質だけである。(ホ)他面、価値の大きさの区別は純粋に量的なものであるから、貨幣商品は純粋に量的な区別ができるもの、したがって任意に分割ができてその諸部分がふたたび合成できるものでなければならない。(ヘ)ところが、金銀は生まれながらにしてこの属性をそなえている。〉
(イ)ところで、「金銀は生まれながらにして貨幣ではないが、貨幣は生まれながらにして金銀である」ということは、金銀の自然諸属性が貨幣の諸機能に適していることを示しています。
ここで学習会では、〈「金銀は生まれながらにして貨幣ではないが、貨幣は生まれながらにして金銀である(42)」〉ということが〈金銀の自然諸属性が貨幣の諸機能に適していることを示している〉と言われているのですが、いま一つよく分からないという意見が出されました。どうして最初の文言が後の理由になるのかがいま一つ納得が行かないというのです。そこでこの一文が出てくる『経済学批判』をみてみることにしましょう。マルクスは、「4 貴金属」において、〈なぜほかの諸商品ではなく金銀が貨幣の材料として役だつかという問題〉(全集13巻130頁)について論じています。その内容を箇条書き的に紹介してみましょう。
①まず〈一般的労働時間そのものはただ量的な区別を許すだけであるから、その独特な化身として通用すべき対象物は、純粋に量的な区別をあらわすことができるものでなければならず、したがって質の同一性、一様性が前提とされる〉が〈金銀は、単一体としていつでもそれ自体同等であり、したがってそれらの等しい量は等しい大きさの価値をあらわす〉。(同)
②〈一般的等価物として役だつべき商品にとっての、純粋に量的な区別をあらわすという機能から直接に生じるいまひとつの条件は、それが任意の諸部分に細分することができ、また諸部分をふたたび合成することができるということであり、したがって計算貨幣が感覚のうえでもあらわされるということである。金銀はこれらの属性を非常によくそなえている。〉(同上131頁)
③〈流通手段としては、金銀は他の諸商品にくらべて次のような長所をもっている。すなわち、その比重が大きく、相対的に大きな重量を小さな容積であらわすことができるし、それにおうじてその経済的比重も大きく、相対的に大きな労働時間、すなわち大きな交換価値を小さな容量のうちにふくむことができる、ということである。これによって、運搬の容易さ、一人の手から他の人の手への、一国から他国への移転の容易さ、急速に出没する能力――要するに、流通過程の永久機関〔perpetuum mobile〕として役だつべき商品の必須条件〔sine qua non〕である物質的可動性が保証されている。〉(同)
④〈貴金属の高い価値比重、耐久性、相対的に破壊しにくいこと、空気に触れて酸化しないこと、金の場合にはとくに王水以外の酸に溶解しない性質、これらすべての自然的属性が貴金属を貨幣蓄蔵の自然的材料にする。〉(同)
⑤〈金属一般が直接的生産過程の内部でもつ大きな意義は、生産用具としての金属の機能と関連している。ところが金銀は、それらが稀少であることを度外視しても、鉄はもちろんのこと、銅(古代人の用いた合金状態の)とくらべてさえきわめて軟らかいので、生産用具として利用することができず、したがって金属一般の使用価値の基礎をなす諸属性を大幅に奪われている。金銀は直接的生産過程の内部ではこのように役にたたないのであるが、これと同様に、生活手段として、消費の対象として現われる場合にも、なければなくてもすむものである。だから金銀は、直接的な生産と消費との過程をそこなわずに、どんなに任意の量ででも社会的流通過程にはいることができるのである。〉(同上131-2頁)
⑥〈他方で金銀は、消極的な意味で余分な、すなわちなくてもすむ対象物であるばかりでなく、金銀の美的な諸属性は、それを華美、着飾り、盛装、日曜日にふさわしい諸欲望の天然の材料に、つまり贅沢と富の積極的形態にするのである。それらは、いわば地下界から掘り出されたまじり気のない光として現われる。というのは、銀はすべての光線をそれらの光線の本来の配合のままに反射し、金は最も強い色彩である赤だけを反射するからである。だが色彩感覚は美的感覚一般のうちで最もとっつきやすい形態である。〉(同上132頁)
⑦〈最後に、金銀が鋳貨の形態から地金形態へ、地金形態から奢侈品の形態へ、そしてまた逆の方向へ転化されうるということ、いちどあたえられた一定の使用形態に縛られないという他の諸商品にまさった長所、これらが金銀を、たえず一つの形態規定性から他の形態規定性に転化しなければならない貨幣の自然的材料にするのである。〉(同)
このようにマルクスは金銀が貨幣としての社会的機能を果たす上で、優れている属性を上げたあと、次のように述べています。
〈自然は銀行家や為替相場を生みださないのと同じように、貨幣を生みださない。しかしブルジョア的生産は、富を一個の物の形態をとった物神として結晶させざるをえないから、金銀は富のそれ相応な化身である。金銀は生まれながらに貨幣ではないが、貨幣は生まれながらに金銀である。一方では、銀または金の貨幣結晶は流通過程の産物であるばかりではなく、実際上その唯一の停留する産物である。他方では、金銀はできあがった自然生産物であって、それらは第二のものであるとともに、そのまま第一のものであり、なんらの形態的相違によっても区別されない。社会的過程の一般的生産物、または生産物としての社会的過程そのものが、一つの特殊な自然生産物であり、大地の奥ふかいところに隠れていて、そこから掘り出すことのできる金属なのである。〉(全集13巻132頁、下線は引用者)
このマルクスの説明を見ると、〈金銀は生まれながらに貨幣ではない〉というのは、〈自然は銀行家や為替相場を生みださないのと同じように、貨幣を生みださない〉という意味だと分かります。そして同じように〈貨幣は生まれながらに金銀である〉というのは、貨幣というのは、人間の社会的関係が物の形態をとったものであり、ブルジョア的生産では、こうした物象的関係は不可避に生まれくること、だから物象的関係である貨幣は、生まれながらにして金銀という物的なものに癒着して登場するのだというわけです。そして金銀が貨幣という社会的機能を果たす上で物性的に優れていることは、すでに縷々述べてきたということだと思います。
(ロ)(ハ)
しかし私たちは、これまでのところでは、貨幣の一つの機能しか知りません。つまり、商品の価値の現象形態として、あるいは商品の価値の大きさを社会的に表す材料として、役立つという機能だけです。
〈金銀の自然諸属性が貨幣の諸機能に適している〉と言っても、私たちがまだ貨幣の機能として知っているのは、価値の現象形態であり、価値の大きさをその物的素材によって表すという機能だけだとマルクスは指摘しています。これは後に第3章「貨幣または商品流通」に出てくる説明にもとづけば、「価値尺度の機能」と言えます。その意味では、(イ)の解説のなかで紹介した『経済学批判』の一連の説明は貨幣のそれ以外の諸機能(流通手段としての機能等)も含んだものだったと言えます。
(ニ)価値の適切な現象形態、すなわち抽象的な、したがって同等な、人間労働の物質化となりうるためには、どの一片をとってみてもみな同じ均等な質をもっている物質でなければなりません。
この属性は、先に紹介した『批判』で指摘されていたものとしては、①に該当しますが、『批判』では、必ずしも質と量とが明確に区別されて論じられていないことが分かります。
(ホ)また価値の大きさの区別は純粋に量的なものでしかありませんから、貨幣商品は、純粋に量的に区別ができるもの、だから任意に分割できて、その分割された諸部分から再び合成できるものでなければなりません。
これは『批判』の説明では①と②に該当します。
(ヘ)ところが、金銀は生まれながらにして、こうした諸属性をそなえています。
全集版や新日本新書版では〈この属性をそなえている〉となっていますが、これでは〈この属性〉が指しているのは、直前の〈任意に分割ができてその諸部分がふたたび合成できる〉というものだけと誤解されかねません。やはりここは(ニ)と(ホ)で述べられている二つの属性を指しているわけですから、やはり「こうした諸属性」と訳すべきでしょう。因みに長谷部訳では「こうした諸属性」となっています。
◎注42と43
第11パラグラフには二つの注がついていますが、それらも本文を紹介し、簡単な解説を加えておきます。
【注42】〈(42) カール・マルクス『経済学批判』、135ページ〔『全集』、第13巻、132ページ〕。「これらの金属は・・・・生まれながらにして、貨幣である」(ガリアーニ『貨幣について』、所収、クストーディ編、前出叢書、近代篇、第三巻、一三七ページ)。〉
この注によれば、先に見た『経済学批判』に出てくる〈金銀は生まれながらに貨幣ではないが、貨幣は生まれながらに金銀である〉という一文は、ガリアーニの『貨幣について』の中の主張に対置されたものだということが分かります。ただ『批判』では、ガリアーニの『貨幣について』からの引用は幾つかありますが、上記の一文の引用はありませんでした。マルクスはガリアーニついて、〈多かれ少なかれ適切な着想で商品の正しい分析にふれている一連のイタリアの経済学者たち〉(全集13巻42頁)の一人とみていたようです。
【注43】〈(43) これについての詳細は、前出の私の著作の中の「貴金属」の節を見よ。〉
この注で触れている〈「貴金属」の節〉の内容については、すでに本文の(イ)の解説のなかで詳しく紹介した通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【付属資料】
●第9パラグラフ
《初版本文》
〈直接的な生産物交換にあっては、どの商品も、その所持者にとっては直接的な交換手段であり、その非所持者にとっては等価物である。といっても、それが非所持者にとって使用価値であるというかぎりにおいてのことでしかないが。だから、この交換品は、それ自身の使用価値または交換者の個人的必要から独立した価値形態を、まだなんら獲得していない。こういった形態の必然性は、交換過程にはいってくる諸商品が数を増し多様になるにつれて、発展する。課題は、その解決手段と同時に生まれる。商品所持者たちに彼ら自身の物品を他のいろいろの物品と交換させ、したがって比較させる交易は、いろいろな商品所持者たちのいろいろな商品が、これらの商品の交易の内部で、一つの同じ第三の商品種類と交換されたり価値として比較されたりしなければ、けっして行なわれない。このような第三の商品は、それがいろいろな他商品にたいする等価物になることによって、たとい狭い限界内であろうとも、一般的なあるいは社会的な等価形態を直接に獲得する。この一般的な等価形態は、それを産み出した一時的な社会的接触とともに、生成し消滅する。かわるがわるしかも一時的に、それはあれこれの商品に帰属する。ところが、商品交換の発展につれて、それは排他的に、特殊な商品種類に固着する、すなわち、貨幣形態に結晶する。それがどんな商品種類に付着したままになるかは、最初は偶然的である。とはいえ、一般には二つの事情がことを決定する。貨幣形態は、事実上域内諸生産物の交換価値の自然発生的な現象形態である最も重要な外来の交換品に、付着するか、または、域内の譲渡可能な財産の主要な要素を成している使用対象に、たとえば家畜のようなものに、付着する。遊牧民族が最初に貨幣形態を表示するが、そうなるのは、彼らの全財産が可動的な形態、したがって直接的に譲渡可能な形態にあるからであり、また、彼らの生活様式が、彼らを絶えず他の共同体と接触させ、したがって、彼らに生産物交換を促すからなのである。人聞はしばしば、人間そのものを奴隷の形で原始的な貨幣素材にしたが、土地については、そうしたことはけっしてなかった。土地を貨幣素材にするような考えは、すでにできあがった市民社会においてのみ生ずることができた。このような考えは一七世紀の最後の三分の一期に始まり、このような考えの一国的な規模での実施は、一世紀後に、フランス人たちのブルジョア革命において、初めて試みられたのである。〉(75-6頁)
《フランス語版》
〈直接的な生産物交換では、各々の商品は、それを所有する人にとっては直接的な交換手段であるが、それを所有しない人にとっては、それが彼にとって使用価値であるばあいにかぎって等価物になる。したがって、交換物品はまだ、それ自身の使用価値あるいは交換者たちの個別的必要から独立した価値形態を、全然獲得していない。この形態の必然性は、しだいに交換のうちに入りこむ商品の数と多様性とが増すのにつれて発展するのであって、課題はその解決手段と同時に生まれる。さまざまな商品が価値として、そのさまざまな持ち主によって同一の第三の商品種類と交換され、比較されなければ、これら商品の所有者たちはけっして自分の物品を他のさまざまな物品と交換し、比較することがない。このような第三の商品は、他のさまざまな商品にたいして等価物になることによって、狭い限界内ではあるが、一般的あるいは社会的な等価形態を直接に獲得する。この一般的等価形態は、これを産んだ一時的な社会的接触とともに発生し消滅するのであって、迅速にしかもかわるがわる、あるときはある商品に、あるときは別の商品に付着する。交換がある程度の発達に到達してしまうやいなや、この一般的等価形態はもっぱら特殊な商品種類に付着する、すなわち、貨幣形態に結晶する。それがどんな商品種類に固定されたままになるかは、最初は偶然によってきまる。しかし、一般には二つの決定的な事情による、と言ってよい。貨幣形態は、域内生産物の交換価値を実際上最初に示すような最も重要な輸入物品に付着するか、あるいは、たとえば家畜のごとき、その域内の譲渡可能な富の主要素をなすような物体あるいはむしろ有用物に、付着する。遊牧民が最初に貨幣形態を発展させる。というのは、彼らの財貨と財産のどれもが、動産形態、したがって、直接に譲渡可能な形態にあるからである。さらに、彼らの生活様式は、彼らを外部の社会と絶えず接触させ、まさにそのために、彼らを生産物交換に駆り立てる。人間はしばしば、人間自身を奴隷の形で自分の原始的な貨幣材料にした。土地については、こうしたことは一度もなかった。そのような思いつきは、すでに発達したブルジョア社会ではじめて生まれることができた。そのような思いつきは一七世紀の最後の三分の一期に始まっており、その実現はそれからやっと一世紀後、フランスの一七八九年革命において、全国的に大規模に試みられたのである。〉(65-6頁)
●第10パラグラフ
《初版本文》
〈商品交換がそれの単なる地方的な枠を突破し、したがって、商品価値が人間労働一般の具象物にまで広がってゆくのと同じ割合で、貨幣形態が、一般的な等価物という社会的機能に生来適している諸商品の上に、貴金属の上に、移ってゆくのである。〉(76頁)
《フランス語版》
〈交換が純粋に地方的な絆を断ち、その結果、商品の価値がますます人間労働一般を代表するようになるにつれて、貨幣形態は、一般的等価物の社会的機能を果たすに適した性質をもつ商品、すなわち貴金属に、移行する。〉(66頁)
●第11パラグラフ
《初版本文》
〈ところで、「金銀は生来貨幣でなくとも、貨幣は生来金銀である(37)」ということは、金銀の自然的な諸属性が貨幣の諸機能に適合していることを、示している(38)。ところが、われわれはこれまで、貨幣の一つの機能しか知らない。その機能は、商品価値の現象形態として、あるいは、諸商品の価値量がそのなかで社会的に表現されるところの素材として、役立っているという機能である。価値の適当な現象形態、あるいは、抽象的でありしたがって同等である人間労働の具象物は、ある物質--この物質のすべての見本が同じ一様な質をもっている--でしかありえない。他方、価値量の差異は、純粋に量的であって、凝固した労働時間のいろいろな量を表現しているから、貨幣商品は、純粋に量的な区別が可能なもの、つまり、随意に分割可能でありまたそれの諸部分から再び合成可能なもの、でなければならない。ところが、金銀は生来これらの属性をもっている。〉(76-7頁)
《フランス語版》
〈さて、「銀と金は生来貨幣ではないが、そういっても貨幣は生来銀と金である」ということは、これら金属の自然属性と貨幣の機能とのあいだに存在する一致と類似とを、示している(7)。だが、われわれがこれまでに知っている貨幣の機能は、一つの機能--商品価値の表示形態として役立つ、すなわち、商品の価値量を社会的に表現するための材料として役立つ、という一つの機能--だけである。ところで、価値を表示するのに適切な形態でありうる、すなわち、抽象的な、したがってまた同等な人間労働の具体的な形象として役立ちうる材料は、たった一つしかない。それは、どの一片も同じ画一的な質を有する材料である。他方、価値は量だけが異なるのであるから、貨幣商品は、純粋に量的な差を示しうるものでなければならない。貨幣商品は、任意に分割可能なものであり、その諸部分の総和で再構成されうるものでなければならない。金と銀が生来これらの属性のすべてをもっていることは、誰でも知っている。〉(66-7頁)
●注42と43
《初版本文》
〈(37)カール・マルクス、前掲書〔『経済学批判』〕、135ページ。「貴金属は……生来貨幣である。(ガリアーニ『貨幣について』、所収、クストディの叢書、近世篇、第三巻、72ページ。)〉(77頁)
〈(38) これについてさらに詳しいことは、私の前記著書の「貴金属」という節を参照せよ。〉(77頁)
《フランス語版》
〈(6) カール・マルクス『経済学批判』、135ぺージ。「貴金属は生来貨幣である」(ガリアーニ『貨幣について』、クストディの叢書に所収、近世の部、第三巻、137べージ)。〉(67頁)
〈(7) この問題についてさらに詳細なことは、すでに引用した私の著書の「貴金属」の章を見よ。〉(67頁)










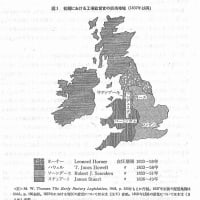
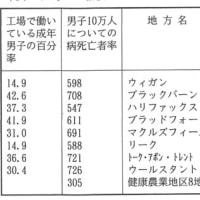
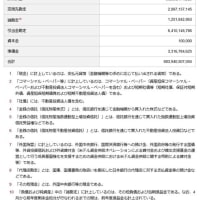

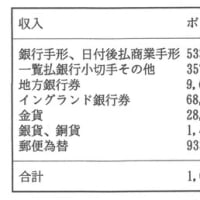
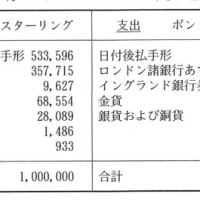
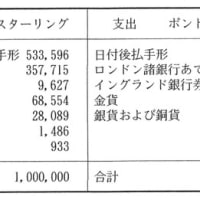
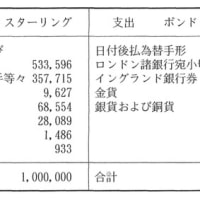
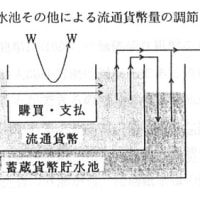







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます