第43回「『資本論』を読む会」の報告(その1)
◎関電、全原発停止
関西電力は21日未明、福井県にある高浜原子力発電所3号機(出力87万キロワット)の原子炉を停止しました。これで関電の11基あるすべての原発が停止したことになります。当面の電力需給は安定していますが、関電は夏の需要ピーク時には大変なことになるなどと「危機的状況」を強調し、「電力の需給安定には、原子力の再稼働が不可欠」(八木社長)などと述べています。
ところがおかしなことに、関電は、大阪府や大阪市の電力需給の詳しいデータの公開要請にはガンとして答えようとしていません。節電への協力を呼びかけながら、それが必要である裏付けとなるデータの公開を拒み続けているのです。これは一体、どうしたことでしょうか。
それは恐らくデータを公開すれば、これまで原発に反対する人たちが主張してきた、原発がなくても日本には電力需要を十分にまかなうだけ発電設備はある、という主張を裏付けてしまうからではないかと思われます。
というのも、私の知人は関電で長く働き、今はすでに定年退職していますが、彼のいうには、これまでは、原発の稼働率を上げるために、関電管内の火力発電所の多くは停止ししてきたというのです。だから停止した火力発電所を再稼働すれば、十分電力の需要に応じることが出来るだけの余力を今の関電は持っていると言います。例えば多奈川第二火力発電所は定格出力は120万キロワットです。これがすべて停止したままなのです。あるいは海南火力発電所(同210万キロワット)もその一部は停止したままです。
もちろん、停止している火力発電所を再稼働すれば、それだけ燃料代がかかるかも知れません。しかし、老朽化して危険極まりない原発を再稼働して、放射能の恐怖にさらされるより、よっぼとましというものではないでしょうか。
関電にとっては、原発は“ドル箱”であり、稼ぎ頭なので、何としても原発を動かしたいとの思いがあるのは分かるのですが……。
◎ロビンソンの問題を再び議論
さて、今回の学習会はやや違った趣のもとに始まりました。というのはNさんが、彼は第41回の報告で紹介しましたように、第12パラグラフに関連して、ロビンソンが飼っていたのはヤギなのに、どうしてマルクスはラマにしたのか、と問題提起をされた方ですが、今度は、同じ第12パラグラフに関連する資料として、大塚久雄著『社会科学における人間』(岩波新書)からロビンソンに言及しているところ(96-110頁)をコピーして資料として持ってきてくれたからです。だから学習会は、まずこの資料に一通り目を通すことから始めました。そしてその中身について、若干の議論を行ったわけです。その詳しい内容を紹介することは、やはりこの報告のなかでは主題を外してしまうので、出来ませんが、大塚氏のこの著書は、コピーされた部分を読むだけでも、細かく見て行くと色々と問題が多いものでした。だからここでは、主要な点に限って、その問題点を指摘しておきたいと思います。
●わざわざマルクスの取り上げている問題を、近代経済学(ブルジョア経済学)の「資源配分」という用語に置き換える
さて、この大塚氏の著書は、1976年のNHK人間大学における講義を新書に再編したもののようですが、同氏は、マルクスがロビンソン物語で問題にしているのは次のようなことだと述べています。
〈このマルクスの指摘する基本的な諸事実は、実は、われわれが現在使い慣れている語で言いかえますと、物的ならびに人的資源の配分、簡単に資源配分とよばれているものですね。〉〈経済の本質が資源配分である〉〈およそ経済現象なるものはつねに「資源配分」の問題だ〉云々。
確かにマルクスがロビンソン物語を取り上げているのは、これまでの報告でも指摘してきたように、あらゆる社会的生産諸形態に共通する物質的な生産を人間と自然というもっとも抽象的な契機に還元して考察するためでした。しかしそれを〈物的ならびに人的資源の配分、簡単に資源配分とよばれているもの〉だと捉えるのは、決して正しくありません。そもそもマルクスは商品の物神的性格の秘密を暴露しているのです。その内容を紹介するに際して、物神崇拝に取り込まれたカテゴリーである〈物的ならびに人的資源の配分〉などという用語を使うこと自体、おかしなことです。ましてや、それがマルクスの主張していることだ、などと説明することは途方もないことではないでしょうか。おまけに大塚氏は〈「資源配分論」はいわれる近代経済学の方のレパートリーのなかに含まれている〉などとも述べており、そのことを先刻承知の上で使っているのですから、何をか況んやです。
〈人的資源〉という用語を調べてみますと、次のような説明があります。
〈資源ということばは……主として人間の利用できる天然資源 natural resources を指すようである。しかし,一方〈人的資源〉なることばも使われ,この場合は人間がみずからを客観的に見て,なんらかの目的の達成には人間も必要な資源と考えているのであろう。〉〈資本とは投資によってその価値を増大させることのできる財貨であるが,この考え方を投資対象としての人間に適用したものが〈人的資本〉の概念である。すなわち,人間の経済的価値を投資によって高めることができるという考え方である。〉(平凡社世界大百科事典)
しかしマルクスはこうした考え方こそ〈資本主義的な考え方の狂気の沙汰〉だと、次のように述べているのです。
〈国債という資本ではマイナスが資本として現われる――ちょうど利子生み資本一般がすべての狂った形態の母であってたとえば債務が銀行業者の観念では商品として現われることができるように――のであるが、このような資本に対比して次には労働力を見てみよう。労賃はここでは利子だと考えられ、したがって、労働力は、この利子を生む資本だと考えられる。たとえば一年間の労賃が五〇ポンドで利子率が五%だとすれば、一年間の労働力は一〇〇〇ポンドという資本に等しいとみなされる。資本家的な考え方の狂気の沙汰はここでその頂点に達する。〉(全集25b596頁)
マルクスはあらゆる社会的生産諸形態に共通して存在している〈本来の物質的生産の領域〉(『資本論』第3部・全集25巻b1051頁)について、次のように述べています。
〈未開人は、自分の欲望を充たすために、自分の生活を維持し再生産するために、自然と格闘しなければならないが、同じように文明人もそうしなければならないのであり、しかもどんな社会形態のなかでも、考えられるかぎりのどんな生産様式のもとでも、そうしなければならないのである。彼の発達につれて、この自然必然性の国は拡大される。というのは、欲望が拡大されるからである。しかしまた同時に、この欲望を充たす生産力も拡大される。自由はこの領域のなかではただ次のことにありうるだけである。すなわち、社会化された人間、結合された生産者たちが、盲目的な力によって支配されるように自分たちと自然との物質代謝によって支配されることをやめて、この物質代謝を合理的に規制し自分たちの共同的統制のもとに置くということ、つまり、力の最小の消費によって、自分たちの人間性に最もふさわしく最も適合した条件のもとでこの物質代謝を行なうということである。しかし、これはやはりまだ必然性の国である。〉(同1051頁)
このように、ここでもマルクスはロビンソン物語と同じように、社会を一人の人間に置き換えて、未開人や文明人という形で、それを直接自然に対峙させて、「彼の発達」を問題にしています。大塚氏が指摘していることは、その限りでは、こうしたあらゆる社会形態からも独立した物質的生産の領域そのものなのですが、しかし、大塚氏は、それを、マルクスが「商品の物神的性格とその秘密」を暴露しているパラグラフの説明として、敢えてわざわざブルジョア経済学の「資源配分」という用語に置き換えて論じているのです。これはまさに氏のブルジョア的本性を暴露するだけではなく、悪しき意図をも示すものではないでしょうか。
●「人間類型」から社会を説明する観念的な俗説をマルクスに被せる
また大塚氏はマックス・ウェーバーの「人間類型論」に引き付けて、マルクスを読んでいます。ロビンソンクルーソーを「第一の人間類型」とし、「中産的生産層の典型」として捉えているわけです。そしてマルクスにも同じようなとらえ方があるのではないか、というのが、どうやら大塚氏の問題意識のようです。次のように述べています。
〈少なくとも、経済学の範囲内で論じている限り、マルクスもまた「ロビンソン的人間類型」を認識のモデルとして前提していた、と。あるいは、マルクスは、「ロビンソン的人間類型」がおよそ経済学における理論形成の前提となっている、と考えていた、と。私はそう言ってさしつかえないのではない、と思います。〉
しかし、これはとんでもない話ではないでしょうか。『資本論』のどこを読めばそうした理解が可能なのか、さっぱり分かりませんが、こんな観念的な歴史観をマルクスになすりつけることは許されるものではありません。大塚氏は最後には〈厳密な意味では、マルクスの学問には、人間論は立派にあっても、人間類型論はなかった、ということになるかと思います〉などとも述べていますが、とうていマルクスの理論を語る資格などないといわざるを得ないと思います。
また大塚氏は、『資本論』の前に書かれた遺稿として『資本制的生産に先行する諸形態』も紹介して、それについて次のようにも述べています。
〈そこでは、……『資本論』の段階では慣用することになるような、そしてわれわれにはなじみの、生産諸力が発達すれば生産関係としての共同体は解体する、というような言い方はしていません。〉
しかし、これも真っ赤なウソであることは明らかです。次の一文を見てください。
〈労働する諸主体相互間の、また彼らの自然にたいする、一定の諸関係は、彼らの生産諸力の一定の発展段階に対応するのであって、彼らの共同体組織もこれにもとづく所有も、結局のところ、この発展段階に帰着するのである。ある点までは再生産〔が行われる〕。それから解体に転変する。〉(『資本論草稿集』2、149頁)
そもそも『先行する諸形態』というのは、一般に『経済学批判要綱』と言われている1857-58年の草稿の一部なのです。マルクスはこの『要綱』での研究とそこで明確になった経済学批判のプランにもとづいて、その第一分冊として『経済学批判』を1859年に刊行し、その「序言」で、〈私の研究にとって導きの糸として役だった一般的結論〉として定式化したものが、あの有名な「唯物史観の定式」と言われるものなのです。つまりマルクス自身が、『批判』のもとになった『要綱』における研究を、「序言」で定式化したような観点を導きとして行ったのだと、自ら述べていることになるのです。だからその一部である『先行する諸形態』にそうした観点が貫かれていることは当然といえばあまりにも当然なのです。
大塚氏が『先行する諸形態』が書かれた、こうした経緯を知った上であのようなことを述べているのでしたら、でたらめな人間であるといわざるを得ないし、知らずに書いているなら、学者として“失格”であると言わなければなりません。
いずれにせよ、大塚氏のこの著書は、残念ながら、われわれの『資本論』の理解を助けて、深めるものというより、間違った理解へと、われわれを導き迷わす類のものといわざるを得ないでしょう。
(テキストの学習の報告は、「その2」を参照してください。)











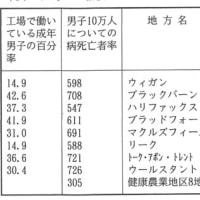
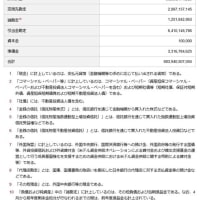

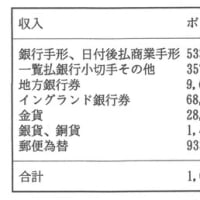
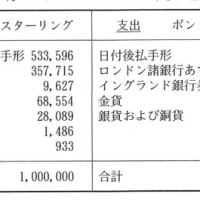
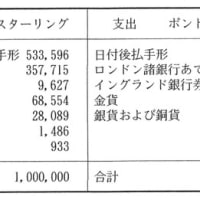
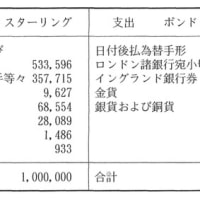
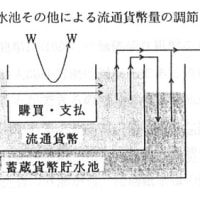






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます