第45回「『資本論』を読む会」の報告(その1)
◎桜も終わり……
あっというまに桜は終わり、今はツヅジが満開です。
第45回「『資本論』を読む会」が開催された4月15日には、会場の堺市立南図書館の3階の窓からは、散り急ぐ桜がまだ僅かに残っていました。
しかし5月のゴールデンウィークも終わりました。つまり報告はずいぶんと遅れてしまったわけです。せっかくの連休はどうしたのか? 言い訳はしません。遊ぶのに忙しく、また雑用もあって、無駄に過ごしてしまった次第です。面目無い。
というわけで、とにかく遅ればせながら、第45回の報告を行わなければなりません。今回から、ようやく第2章に入りました。今回は三つのパラグラフを進んだだけでしたが、この章もなかなか難しく、それも報告が遅れた一因ともいえます。しかし、とにかく、テキストを徹底的に読み込んで、その解読を試みることにしましょう。
◎第1章と較べた第2章の課題
まず第2章にとりかかるにあたって、やはり第2章の課題について、論じる必要があります。つまり第2章では、何が問題になるのか、また何が新しく考察の対象にならなければならないのか、ということです。以前にも一度紹介したことがありますが、もう一度、第2章の課題を確認するために、初版のいわゆる「移行規定」と『経済学批判』の「交換過程」の分析が始まる冒頭部分とを、紹介しておきましょう。
〈商品は、使用価値と交換価値との、したがって二つの対立物の、直接的な統一である。だから、商品は直接的な矛盾である。この矛盾は、商品が、これまでのように、分析的に、あるときは使用価値の観点のもとで、あるときは交換価値の観点のもとで、観察されるのではなくて、一つの全体として、現実に、他の諸商品に関係させられるやいなや、発展せざるをえなくなる。諸商品の相互の現実の関係は、諸商品の交換過程なのである。〉(初版、江夏訳69頁)
〈いままで商品は、二重の観点で、使用価値として、また交換価値として、いつでも一面的に考察された。けれども商品は、商品としては直接に使用価値と交換価値との統一である。同時にそれは、他の諸商品にたいする関係でだけ商品である。諸商品相互の現実的関係は、それらの交換過程である。それは互いに独立した個人がはいりこむ社会的過程であるが、しかし彼らは、商品所有者としてだけこれにはいりこむ。彼らのお互いどうしのための相互的定在は、彼らの諸商品の定在であり、こうして彼らは、実際上は交換過程の意識的な担い手としてだけ現われるのである。〉(『批判』全集13巻、26頁)
これらの文章を検討すると、第1章に対する第2章の特徴、あるいはそこでの課題、つまり、そこでは何が解明されなければならないかが明らかになります。
(1)まず第1章では商品は、二重の観点で観察され、ある時は使用価値の観点のもとに、他の時は、交換価値の観点のもとに、分析されたのですが、しかし第2章では、商品はひつの全体として、すなわち使用価値と交換価値との直接的な統一物として考察されるということです。つまり第1章では、その限りでは商品は抽象的に取り上げられたのですが、第2章では、商品はより具体的なものとして取り上げられることが分かります。だから諸商品の相互の現実の関係、つまり諸商品の交換過程が考察の対象になるというわけです。
(2)そしてそうすると、商品はそうした使用価値と交換価値との直接的な統一物としては、直接的な矛盾だとも指摘されています。第1章では商品の二要因である使用価値と交換価値(価値)とは、互いに対立するものとして考察されました。これに対して、第2章では、そうした対立物の直接的な統一として商品は考察されるために、諸商品は直接的な矛盾だというのです。矛盾ということは、諸商品が、使用価値として存在する場合、あるいは交換価値として存在する場合、それらは互いに前提し合いながらも、同時に排斥し合う関係にもあるということです。第2章では、現実の諸商品の相互の関係が、こうした直接的な矛盾として分析されることが指摘されています。そしてその矛盾が現実に解決されていく過程こそが、すなわち貨幣の発生過程でもあるというわけです。だから第2章は現実の諸商品の交換過程において、如何にして商品は貨幣へと転化するのかを解明するものでもあるといえるでしょう。
(3)そしてまた商品の現実の関係である交換過程においては、互いに独立した諸個人、すなわち商品所有者が入り込む社会的過程でもあると指摘されています。つまり商品は第1章に比べてより具体的に考察されるわけですが、それは使用価値と交換価値との直接的な統一物として考察されるだけではなく、第1章では捨象されていた、それらの諸商品の所有者が新たに考察の対象に入ってくるということです。
とりあえず、こうしたことを確認して、テキストの解読に取りかかることにします。いつものように、テキストの各文節ごとに(イ)、(ロ)、(ハ)、……の記号を打ち、それぞれについて解読していくことにします。
◎第1パラグラフ
【1】〈(イ)諸商品は、自分で市場におもむくこともできず、自分で自分たちを交換することもできない。(ロ)したがってわれわれは、商品の保護者、すなわち商品所有者たちを探さなければならない。(ハ)商品は物であり、したがって人間に対して無抵抗である。(ニ)もしも商品が言うことを聞かなければ、人間は暴力を用いることができる。(ホ)言いかえれば、商品を持っていくことができる(37)。(ヘ)これらの物を商品としてたがいに関係させるためには、商品の保護者たちは、自分たちの意志をこれらの物に宿す諸人格としてたがいに関係しあわなければならない。(ト)それゆえ、一方は他方の同意のもとにのみ、すなわちどちらも両者に共通な一つの意志行為を媒介としてのみ、自分の商品を譲渡することによって他人の商品を自分のものにする。(チ)だから、彼らはたがいに相手を私的所有者として認めあわなければならない。(リ)契約をその形式とするこの法的関係は、法律的に発展していてもいなくても経済的関係がそこに反映する意志関係である。(ヌ)この法的関係または意志関係の内容は、経済的関係そのものによって与えられている(38)。(ル)諸人格は、ここではただ、たがいに商品の代表者としてのみ、したがってまた商品所有者としてのみ、存在する。(ヲ)われわれは、展開が進むにつれて、諸人格の経済的扮装はただ経済的諸関係の人格化にほかならず、諸人格はこの経済的諸関係の担い手としてたがいに相対するということを、総じて見いだすであろう。〉
(イ)(ロ)
諸商品は、物であり、自分で市場に行くわけでもなく、自分で自分たちを交換することも出来るわけではありません。だからわれわれは、商品を市場に持って行く人、つまり商品の所有者を問題にする必要があるわけです。
第1章では諸商品の交換は前提されていました。つまり現実に交換されている諸商品の、商品そのものに注目し、それらの交換関係だけを純粋に取り出し、分析したのです。だから第1章では、あたかも諸商品は主体に互いに関係し合うものとして取り扱われ、だから商品所有者は捨象されて登場しませんでした。しかし第2章からは、第1章では捨象されていた、商品の所有者が登場します。第2章では、使用価値と交換価値の統一物としての商品が主体となります。そうしたものとして、他の諸商品との現実の関係、すなわち交換過程が問題になるわけです。そして現実の交換過程では、現実の商品の運動が問題になるわけですが、その運動を商品の意を体して担うのが、商品の保護者である商品所有者というわけです。つまり商品を市場に持って行き、その交換を行う商品の保護者であり監督者である、商品所有者が登場しなければならないというわけです。
(ハ)(ニ)(ホ)
商品は単なる物ですから、人間に対して無抵抗です。もちろん、商品が言うことを聞かないとなれば、人間は暴力を用いてでも、それを市場に持っていくことが出来るわけです。
ここには〈もしも商品が言うことを聞かなければ、人間は暴力を用いることができる〉という一文があります。学習会では、ここでマルクスは何を言いたいのか、ということが問題になりました。これは、注37で〈当時のフランスの一詩人は、ランディ〔パリ近郊の町〕の市場に見られた商品のうちに、服地、靴、なめし革、農具、皮革類などと共に、「“みだらな遊び女 femmes folles de leur corps ”」をあげている〉と指摘されているように、マルクスは、商品の一つとして娼婦を想定して、このように述べているのではないかということになりました。つまり例え商品に意志があって、市場に出て行くことを拒んでも、しかし商品としては例え娼婦や奴隷のように意志を持った人間であっても、彼ら(彼女ら)は単なる「物」として扱われ、無理やり暴力を持ってでも、市場に引っ張りだされて売りに出されるというわけです。
(ヘ)これらの物を商品としてたがいに関係させるためには、商品の保護者たちは、自分の意志をこれらの商品に宿す諸人格として互いに関係し合わなければなりません。
ここで学習会では、「諸人格(Person)」という用語が出てきますが(全集版では単に「人」と訳されています)、これは(ハ)や(ニ)に出てくる「人間(Mensch)」とどのように区別されるのか、ということが問題になりました。第1版序文には、次のような一文があります。
〈起こるかもしれない誤解を避けるために一言しておこう。私は決して、資本家や土地所有者の姿態をバラ色には描いていない。そしてここで諸人格(Person)が問題になるのは、ただ彼らが経済的諸カテゴリーの人格化(Personifikation)であり、特定の階級諸関係や階級利害の担い手である限りにおいてである。経済的社会構成体の発展を一つの自然史的過程ととらえる私の立場は、他のどの立場にもまして、個々人に社会的諸関係の責任を負わせることはできない。個人は主観的には諸関係をどんなに超越しようとも、社会的には依然として諸関係の被造物なのである。〉(10-11頁。頁数は全集版ですが、訳文は新書判から。全集版では「諸人格」ではなく、単なる「人」と訳されています。)
つまり「人格」というのは、経済的な関係を反映し、それを代表している人間のことを意味しているのにたいして、「人間」というのは、この場合は「物」に対峙するものとして述べられていることが分かります。
(ト)それゆえに、一方は他方の同意のもとにのみ、つまり両者に共通な一つの意志行為にもとづいて、彼らは自分の商品を譲渡する代わりに、他人の商品を自分のものにします。
(チ)だから、彼らは互いに相手を私的所有者として認め合わなければなりません。
ここには〈私的所有者〉という言葉が出てきます。「私的所有」とはそもそもどのように理解したら良いのでしょうか。マルクスは『剰余価値学説史』において〈「社会」そのものが--人間は「社会」のなかで生活するのであって、独立独歩の個人として生活するのではないということが--所有の根源なのであり、この所有に立脚する法律と不可避的な奴隷制度との根源なのである〉(26巻Ⅰ431頁)と述べています。そして『資本論』第1部「第24章 いわゆる本源的蓄積」「第7節 資本主義的蓄積の歴史的傾向」の最初のところで、次のように述べています。
〈社会的・集団的所有の対立物としての私的所有は、労働手段と労働の外的諸条件とが私人に属する場合にのみ存立する。しかし、この私人が労働者であるか非労働者であるかに応じて、私的所有もまた異なる性格をもつ。一見したところ私的所有が示している無限にさまざまな色あいは、ただこの両極端のあいだにあるいろいろな中間状態を反映しているにすぎない。〉(『資本論』23巻b-993頁)
つまり私的所有とは「私人」の所有ということです。人間の「社会」が人間自身の関係として、すなわち彼らの相互の意識的で自覚的な関係として存在するのではなく、彼らから疎外されたものとして、第三者(個人あるいは共同体)によって代表され、支配されるものとして存在するようになることによって、人間が「公人」と「私人」とに分裂する結果、私的所有は社会的・集団的所有の対立物として生まれてくるということです。だから私的所有は社会が諸階級に分裂し、対立する、階級社会の発生と同時に生まれるものでもあるわけです。
(リ)契約をその形式とするこの法的関係は、法律的に発展していても、いなくても経済的関係がそこに反映している意志関係です。
ここで〈契約をその形式とするこの法的関係〉とありますが、〈この〉というのはその前に述べていること、すなわち〈これらの物を商品としてたがいに関係させるためには、商品の保護者たちは、自分たちの意志をこれらの物に宿す諸人格としてたがいに関係しあわなければならない。それゆえ、一方は他方の同意のもとにのみ、すなわちどちらも両者に共通な一つの意志行為を媒介としてのみ、自分の商品を譲渡することによって他人の商品を自分のものにする。だから、彼らはたがいに相手を私的所有者として認めあわなければならない〉という全体を指していると思います。つまり〈一方は他方の同意のもとにのみ、すなわちどちらも両者に共通な一つの意志行為を媒介としてのみ、自分の商品を譲渡することによって他人の商品を自分のものにする〉ということを商品所有者は互いに「契約」という形式で法的関係として結び合うということです。これは民法のような法律として明文化されていようが、いまいが、商品所有者の間では、互いに結び合わなければならない関係だということです。あるいはそれが契約書という文書になっていようが、口頭によるものであっても、やはり「契約」なわけです。
因みに民法第555条は「売買」について、〈売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる〉とし、売買契約が成立する要件としては次のように定めているのだそうです。
〈契約は法律行為であるから、総則の意思表示の規定が適用される。すなわち、効果が発生するには以下の要件を満たす必要がある。
1.成立要件
1.申込みと承諾(521条~528条)
2.売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
3.売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する。〉(以上、ウィキペディアから)
(ヌ)この法的関係、あるいは意志関係の内容は、経済的関係そのものによって与えられています。
(ル)諸人格は、ここでは、ただ互いに商品の代表者としてのみ、だから商品所有者としてのみ存在しています。
(ヲ)われわれは、展開が進むにしたがって、諸人格の経済的扮装はただ経済的諸関係の人格化にほかならず、諸人格はこの経済的関係の担い手として互いに相対することを、総じて見いだすでしょう。
つまり「資本家」=「資本の人格化」というのは、こうしたことを意味しています。例えば次のように説明されています。
〈単純な商品流通--購買のための販売--は、流通の外にある究極目的、すなわち使用価値の取得、欲求の充足、のための手段として役立つ。これに反して、資本としての貨幣の流通は自己目的である。というのは、価値の増殖は、このたえず更新される運動の内部にのみ存在するからである。したがって、資本の運動には際限がない。……この運動の意識的な担い手として、貨幣所有者は資本家になる。彼の人格、またはむしろ彼のポケットは、貨幣の出発点であり帰着点である。あの流通〔G-W-G〕の客観的内容--価値の増殖--は彼の主観的目的である。そして、ただ抽象的富をますます多く取得することが彼の操作の唯一の推進的動機である限り、彼は資本家として、または人格化された--意志と意識とを与えられた--資本として、機能するのである。〉(『資本論』23a198-200頁)
〈資本家としては彼はただ人格化された資本でしかない。彼の魂は資本の魂である。〉(同23a302頁)
◎注37と注38
なおこのパラグラフには注37と注38が付いています。それらも紹介して起きましょう。
【注37】〈(37) その敬けんさで聞こえた一二世紀にも、これらの商品のうちに、しばしば、はなはだか弱いものが出現する。たとえば、当時のフランスの一詩人は、ランディ〔パリ近郊の町〕の市場に見られた商品のうちに、服地、靴、なめし革、農具、皮革類などと共に、「“みだらな遊び女 femmes folles de leur corps ”」をあげている。〉
これは特に説明は不要でしょう。ここで〈当時のフランスの一詩人〉というのは、ギヨーの風刺詩『ランディ物語』を指しているのだそうです。
【注38】〈(38) プルードンは、まず正義、“永遠の正義 justice eternelle ”という彼の理想を商品生産に照応する法的諸関係からくみ取る。ついでに言っておけば、このことによって、商品生産の形態は正義と同じように永遠であるというすべての素町人にとってはなはだ好ましい証明が与えられるというわけである。彼は、今度は反対に、現実の商品生産とこれに照応する現実の法をこの理想に従って改造しようとする。もしも物質代謝の現実的諸法則を研究してこれらの法則に基づいて一定の課題を解決するのではなく、「“自然状態 naturalite ”」や「“親和力 affinite ”」という「永遠の理念」によって物質代謝を改造しようとする化学者がいたとしたら、この化学者を何と考えたらよいであろうか? 「高利」は「“永遠の正義”」や「“永遠の公正 equite eternelle ”」や「“永遠の相互扶助 mutualite eternelle ”」やその他の「“永遠の真理 verites eternelles ”」と矛盾すると言う時、人が「高利」なるものについて知るところは、教父たちが高利は「“永遠の恩寵 grace eternelle ”」、「“永遠の信仰 foi eternelle ”」、「“神の永遠の意志 volonte eternelle de dieu ”」と矛盾すると言う時に彼らが高利について知っていたものよりも、はたしてより多いであろうか?〉
この注は〈この法的関係または意志関係の内容は、経済的関係そのものによって与えられている(38)。〉という一文に付けられています。つまり法的関係や意志関係の内容というのは、経済的諸関係を反映したものに過ぎないということを理解しない一例としてプルードンの主張が紹介されているわけです。こうしたプルードンの観念的な主張の特徴をより分かりやすく説明したものとして、マルクスのアンネコフへの手紙(1846年12月28日ブリュッセル)があります。そこから少し紹介しておきましょう。
〈歴史の現実の運動を追跡することができないで、プルードン氏は幻覚をつくりだしている。それは弁証法的幻覚である、と言いはっている。彼は17、18、19世紀のことを述べる必要を感じていない。というのは、彼の歴史は霧ふかい想像の国でおこっており、時間と場所をはるかに超越しているからである。一言でいえば、それはへーゲルふうの古いがらくたであり歴史ではない。それは一世俗的な歴史──人間の歴史──ではなく、聖なる歴史、すなわち観念の歴史である。彼の見方によると、人間というものは、観念または永遠の理性がそれを利用して展開するための道具であるにすぎない。プルードン氏のいう進化は、絶対的観念の神秘的な胎内でおこなわれるような進化だと考えられている。この神秘的な言語からヴェールをはぐとしたら、それはプルードン氏が彼の頭のなかで経済的範疇がならんでいる順序をわれわれにしめしているということである。〉(全集第4巻564-5頁、但し訳文は文庫本から、以下同じ)
〈このようにプルードン氏は、主として歴史の知識が欠けているために、人間がその生産諸力を発展させるとともに、つまり生活するとともに、相互のあいだの一定の関係を発展させること、この関係の仕方がこれら生産諸力の変化と増大につれて変化することを、見なかった。彼は、経済的範疇がこれらの現実の関係の抽象にすきないこと、これらの関係が存するかぎりでこれらの範疇が真理であるにすぎないことを、見なかった。こうして、彼は、これらの経済的範疇を永遠の法則とみとめ、生産諸力のある一定の発展にだけあてはまる法則である歴史的法則とみとめないブルジョア経済学者の誤謬におちいった。そこで、政治的=経済的範疇を、現実の、暫時的な、歴史的な、社会関係から抽象されたものとして観察するかわりに、プルードン氏は、神秘的に転倒したために、現実の諸関係をこれらの抽象の具象化だとみとめている。これらの抽象そのものは、天地開闢以来、神のふところでまどろんでいた公式なのである。〉(同上567-8頁)
〈プルードン氏は、その物質的生産様式に応じて社会関係をつくりあげる人間が、観念や範疇をも、すなわちこれらの社会関係の観念的・抽象的表現をも、つくりだすということは、なおさら理解しなかった。したがって、範疇は、自分が表現する関係とまさに同じように、永遠のものではない。範疇は歴史的・暫時的な産物である。プルードン氏にとっては、これとは正反対に、抽象、範疇が第一原理である。彼の意見にしたがうと、歴史をつくるのはそれであって、人間ではない。抽象、範疇それ自体、つまり人間およびその物質的行動と切りはなしてとりあげられた範疇は、もちろん不死、不変、不動である。それは、純粋理性の一つの有である。それは、抽象それ自体は抽象的である、というだけのことである。すばらしい同語反復!
このように範疇の形でみられた経済関係は、プルードン氏にとっては、起源も進歩もない永遠の公式である。
別の言いかたをしてみよう。プルードン氏は、ブルジョア的生活が彼にとって永遠の真理であると直接に主張しているわけではない。彼は、ブルジョア的関係を思想の形で表現する範疇を神化することによって、間接にそう言っている。〉(同上570頁)
◎第2パラグラフ
【2】〈(イ)商品所有者を特に商品から区別するものは、商品にとっては他のどの商品体もただ自分の価値の現象形態としての意味しかもたないという事情である。(ロ)だから、生まれながらの水平派であり犬儒学派である商品は、他のどの商品とも、たとえそれがマリトルネスよりまずい容姿をしていても、魂だけでなく体までも取り替えようとたえず待ちかまえている。(ハ)商品所有者は、こうした、商品には欠けている、商品体の具体性に対する感覚を、彼自身の五感およびそれ以上の感覚でもって補う。(ニ)彼の商品は彼にとっては何らの直接的使用価値をも持たない。(ホ)さもなければ、彼はそれを市場に持っていきはしなかっただろう。(ヘ)それがもっているのは他人にとっての使用価値である。(ト)彼にとってそれは、直接的には、ただ交換価値の担い手であり、したがって交換手段であるという使用価値をもっているだけである(39)。(チ)だからこそ、この商品を彼は自分を満足させる使用価値をもつ商品と引きかえに譲渡しようとするのである。(リ)すべての商品は、その所有者にとっては非使用価値であり、その非所有者にとっては使用価値である。(ヌ)したがって、これらの商品は、全面的に持ち手を交換しなければならない。(ル)そして、この持ち手の交換が諸商品の交換なのであって、またそれらの交換が諸商品を価値としてたがいに関係させ、諸商品を価値として実現する。(ヲ)したがって、諸商品は、みずからを使用価値として実現しうるまえに、価値として実現しなければならない。〉
(イ)商品の所有者を商品そのものと区別するものは、商品にとっては他のどの商品体(使用価値)もただ自分の価値の現象形態としての意味しかもたないということです。
第1パラグラフで、第1章では商品そのものが分析の対象であったのに対して、第2章では、さらに商品の所有者が分析の対象として加わることが指摘されましたが、では、商品そのものを分析の対象にするのと、より具体的に商品所有者をも分析の対象として加えることで何が問題になるのかが次に問われているわけです。そして、まず、第1章の場合は、商品にとって、他の商品の使用価値は、ただ自分の価値の現象形態、つまり自分の価値を相対的に表す材料という意味しか持たなかったと指摘されています。
(ロ)だから、生まれながらの水平派であり犬儒学派である商品は、他のどの商品とも、例えそれがマリトルネスよりまずい容姿をしていても、魂だけでなく体までも取り替えようとたえず待ち構えています。
水平派というのは、新日本出版の新書版の注によれば、〈17世紀イギリスのピューリタン革命期にリルバーンたちに指導されて活躍した左翼民主主義的平等主義者たち〉のことであり、犬儒学派というのは〈ディオゲネスたち古代ギリシアの一学派で、禁欲的自然主義者。礼儀、慣習を無視した〉との説明があります。またマリトルネスというのは、セルパンテスの『ドン・キホーテ』に出てくる醜い女中のことだそうです。つまりどちらも相手の風采は気にせずに、誰彼とも無く相手にするということでしょうか。つまり第1章では商品リンネルは商品上着と交換すると前提されていましたが、もちろん、リンネルと交換されるのは、上着に限らず、コーヒーでも鉄でも金でも何でも良かったわけです。とにかく商品であれば任意のものを想定して、われわれは考察することが出来たのでした。
(ハ)商品所有者は、こうした商品には欠けている、商品の使用価値に対する具体的な感覚を、彼の五感、あるいはそれ以上の感覚で補うことになります。
ところが、商品所有者が分析の対象に加わってくる第2章では、商品所有者の欲望が問題になります。つまり交換の対象になる商品の使用価値は、何でもよいというわけでは無くなるわけです。そうしたことが第2章では、新たに問題になってくるということが分かるわけです。ここで〈彼自身の五感およびそれ以上の感覚〉とありますが、〈五感〉は、視覚・嗅覚・味覚・聴覚・触覚ですが、〈それ以上の感覚〉というのは、内面的な欲望にもとづく感覚ということでしょうか。
(ニ)(ホ)(ヘ)
彼にとって自分の商品は直接的な使用価値ではありません。つまりそれは彼の欲望の対象ではないのです。なぜなら、もしそれが彼の欲望の対象であれば、彼はそれを市場に持って行く代わりに、自分の欲望を満たすために消費してしまうでしょう。だから、それは商品にはなりえません。だからそれが彼の商品であるということは、それは彼にとっては直接的な使用価値ではないとういことです。彼の欲望の対象は、彼が交換しようとする他人の持っている商品であり、だから彼の商品の使用価値も、それが商品である限りは、他人にとっての使用価値で無ければならないわけです。
すでに第1章「商品」の第1節「商品の二つの要因--使用価値と価値(価値の実体、価値の大きさ)」において、次のように説明されていました。
〈自分の生産物によって自分自身の欲求を満たす人は、たしかに使用価値を作りだすが、商品を作りだしはしない。商品を生産するためには、彼は、使用価値を生産するだけでなく、他人のための使用価値を、社会的使用価値を、生産しなければならない。{しかも、ただ単に他人のためというだけではない。中世の農民は、封建領主のために年貢の穀物を生産し、僧侶のために十分の一税の穀物を生産した。しかし、年貢穀物も十分の一税穀物も、それらが他人のために生産されたということによっては、商品にはならなかった。商品になるためには、生産物は、それが使用価値として役立つ他人の手に、交換を通して移譲されなければならない(エンゲルスの追加)。}〉(全集版55-6頁)
ただ、ここでは商品所有者の欲望と商品の使用価値との関係が問題になっています。商品所有者にとって彼の商品は何らの直接的な使用価値を持ちません。それは彼の生産物のうち、彼の欲望を満たしたあとに残った余剰物のようなものでなければならないわけです。だからそれは他人にとっての使用価値、つまり社会的使用価値を持たねばならないのです。社会的使用価値を持つということは、その商品に支出された労働が、社会的な分業の環をなしているということです。
(ト)(チ)
彼にとって、それは直接的には、ただ交換価値の担い手であり、したがって交換手段であるという使用価値を持っているだけです。だからこそ、この商品を自分の欲望を満足させる使用価値をもつ商品と引き換えに譲渡しようとするわけです。
(リ)(ヌ)(ル)
すべての商品は、その所有者にとっては非使用価値であり、その非所有者にとって使用価値です。だからこそ、これらの商品は、その持ちを手を全面的に交換しなければならないのです。そしてこの持ち手の交換が、すなわち諸商品の交換なのであって、またこれらの交換が諸商品を価値として互いに関係させ、諸商品を価値として実現するのです。
(ヲ)したがって、諸商品は、みずからを使用価値として実現しうる前に、価値として実現しなければなりません。
ここでは〈価値として実現する〉、〈使用価値として実現〉という用語が出てきます。ここで〈価値として実現する〉とは、「価値の実現」とは同じではありません。商品の価値の実現とは、貨幣の存在を前提した上で、商品を貨幣に転換すること、つまり商品の販売のことです。だから商品を〈価値として実現する〉とは、商品が他の諸商品と質的に同じものとして関係するということです。つまりそれが抽象的人間労働の対象化されたものとして妥当するということではないかと思います。また〈使用価値として実現する〉とは、「使用価値の実現」とは違います。「使用価値の実現」とは商品が交換過程から出て、消費過程に入り、その使用価値が消費されることです。しかし〈使用価値として実現する〉というのは、交換過程内の問題であり、だから商品に支出された具体的な有用労働が、社会的な分業の環をなしていることが示されることにほかなりません。つまりそれが社会的使用価値であることが実証されることです。
さて全体としてのこのパラグラフを理解するのに役立つと思える『経済学批判』の一文を紹介しておきましょう。
〈商品は、使用価値、小麦、リンネル、ダイヤモンド、機械等々であるが、しかし商品としては、同時にまた使用価値でない。もしそれがその所有者にとって使用価値であるならば、すなわち直接に彼自身の欲望を満足させるための手段であるならば、それは商品ではないであろう。彼にとっては、それはむしろ非使用価値であり、すなわち、交換価値のたんなる素材的な担い手、またはたんなる交換手段である。交換価値の能動的な担い手として、使用価値は交換手段となる。その所有者にとっては、商品は交換価値としてだけ使用価値なのである〔*〕。だから、使用価値としては、それはこれから生成しなければならないのである。しかもまずもって他の人々にとっての使用価値としてである。商品はそれ自身の所有者にとっての使用価値ではないのであるから、他の商品の所有者にとっての使用価値である。そうでないとすれば、彼の労働は無用な労働であったし、したがってその成果は商品ではなかったわけである。他方では、商品は所有者自身にとっての使用価値にならなければならない。なぜならば、彼の生活手段は、この商品以外に、他人の諸商品の使用価値として存在しているからである。使用価値として生成するためには、商品は自分が充足の対象であるような特殊の欲望に出会わなければならない。だから諸商品の使用価値は、商品が全面的に位置を転換し、それが交換手段である人の手から、それを使用対象とする人の手に移ることによって、使用価値として生成するのである。諸商品のこのような全面的外化〔*〕によってはじめて、それにふくまれている労働は有用労働になる。使用価値としての諸商品相互のこのような過程的関係においては、諸商品はなんら新しい経済的形態規定性をうけない。それどころか、商品を商品として特徴づけた形態規定性が消え去る。たとえばパンは、パン屋の手から消費者の手に移っても、パンとしてのその定在を変えない。反対に、それがパン屋の手中では一つの経済的関係の担い手であり、一つの感覚的でしかも超感覚的なものであったのに、消費者がはじめて、使用価値としての、こうした一定の食料品としてのパンに関係するのである。だから、諸商品が使用価値としてのその生成中にはいりこむ唯一の形態転換は、それがその所有者にとって非使用価値、その非所有者にとって使用価値であった、その形態的定在の揚棄である。諸商品の使用価値としての生成は、その全面的外化、それが交換過程へはいることを予想しているが、しかし交換のための商品の定在は、交換価値としてのその定在である。したがって、使用価値として自己を実現するには、商品は交換価値として自己を実現しなければならない。
〔*〕 アリストテレス (本章の冒頭に引用した個所を参照)が交換価値を把握したのは、この規定性においてである。
〔*〕 「外化」の原語はEntäuβerung。あるものが自分自身をある状態から自分にとって外的な状態に移すことであり、またあるものを自分の手から外部の者の手へ移すといった意味である。 前者の意味では、Entfremdung「疎外」ということばと同義と解してよく、同じ現象を「外化」は過程として把握し、「疎外」は結果の側からみたものといえよう。ここでは諸商品が全面的な位置転換によってそれぞれそれを使用対象とする人の手に移ることをさしている。日常用語では「譲渡」、「移譲」の意味に用いられる。 本書で「外化」とある場合も、以上の意味がふくまれている。〉(全集13巻27-8頁)
(以下は、「その2」に続く。)











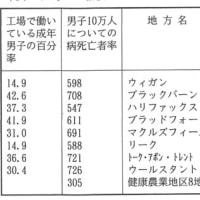
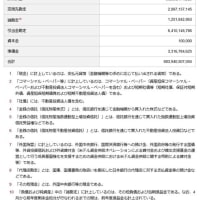

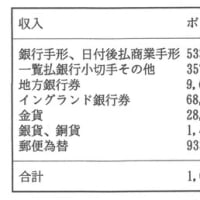
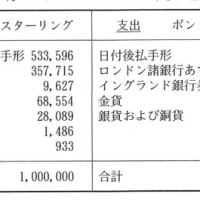
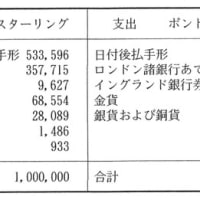
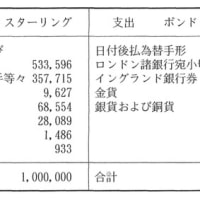
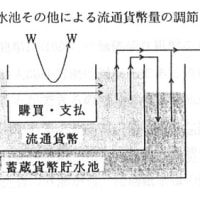






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます