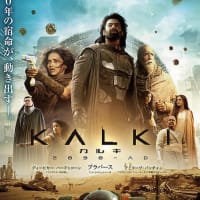‘Because I could not stop for Death-’
Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –
The Carriage held but just Ourselves –
And Immortality.
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility –
We passed the School, where Children strove
At Recess – in the Ring –
We passed the Fields of Gazing Grain –
We passed the Setting Sun –
Or rather – He passed us –
The Dews drew quivering and chill –
For only Gossamer, my Gown –
My Tippet – only Tulle –
We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground –
The Roof was scarcely visible –
The Cornice – in the Ground –
Since then – ‘tis Centuries – and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses’ Heads
Were toward Eternity –
私は死のために止まれなかったので―
私は死のために止まれなかったので―
死が親切にも私のために止まってくれた―
馬車に乗っていたのはただ私たちだけ―
実はさらに永遠(immortality)も。
私たち(私と死)はゆっくり進んだ―死は急ぐことを知らなかった
そして私は放棄していた
私の仕事もまた私の余暇も
死の礼節に応えるために―。
私たち(私と死)は学校を通り過ぎた、そこでは子供たちが遊んだ
休み時間―輪になって―
私たちは、凝視する穀物の畑を通り過ぎた―
私たちは、夕日を通り過ぎた―
というよりむしろ―夕日が私たちを通り過ぎた―
露が、震えと寒さを引き寄せた―
というのも私のガウンはただの蜘蛛の糸織り―
私のショールは―ただの薄絹―だから
私たち(私と死)は止まった。
地面の盛り上がったような家の前に―
屋根はほとんど見えない―
軒蛇腹(ノキジャバラ)は―土の中―
その時から―数世紀がたつ―しかしそれは
あの1日より短く感じる。
馬が、永遠(eternity)に向かっているのだと
私が初めて思ったあの1日よりも―
《感想1》
詩は、数世紀前の死者の立場で書かれている。
「死が親切にも私のために止まってくれた」。死が、私を選んだ。私が、死を選ぶわけでない。
つまり「私は死のために止まれな」い。私に、死か不死かの選択権はない。死が私を選び取った。
人生の馬車に、私と死が乗った。
だが実は、永遠(immortality)も馬車に乗った。永遠に不滅の真理。“人間は死すべきものだ”という真理。
《感想2》
「私たち(私と死)はゆっくり進んだ」。墓に行きつくまで時間があった。
死は急がない。だから私の人生があった。
そして私は知っていた。「私の仕事もまた私の余暇も」消え去るものであり、私のものにならないこと。それらを、あらかじめ私は「放棄していた」。
“死が、私の生をしばらくの間、許す”、つまり“死が急がない”ことが、死が私に示す「礼節」。その「礼節」に応えるため、私は、私の生が消え去ることを受け入れた。
《感想3》
私たち(私と死)の馬車は、私の人生を、ゆっくり進んだ。学校に通う少年期、実る穀物の壮年期、夕日の老年期。
壮年期の実る穀物は、私の生の対象化であり、それらを生み出した私を指し示す、つまり凝視し続ける。
《感想4》
時間とは何か?
時間は、過ぎていくと言われる。私たち(私と死)の馬車が、夕日を過ぎていく。だから、「私たちは、夕日を通り過ぎた」と言う。
だが、時間の中の対象(Ex. 夕日)は、“常にここにある今の私”を、通り過ぎて、過去へと去っていく。だから「夕日が私たちを通り過ぎた」とも言える!
人生の秋が来て、死の予感が到来する。「露が、震えと寒さを引き寄せた」。
私の生を守った「ガウン」も「ショール」も、私と死の共在、つまり死の不可避性の前に、無力だった。それらは、「ただの蜘蛛の糸織り」、「ただの薄絹」だった。
《感想5》
私たち(私と死)は、ついに、墓に到着した。
《感想6》
馬車には、私たち(私と死)だけでなく、永遠の真理(eternity )も乗っていた。
存在(世界)が、“私の生が消え去ること”(死の不可避性)の形式をとるしかないという永遠の真理!
この世の数世紀も、この真理の永遠性には、及ばない、つまり、ついに覆すことが出来ない。
Because I could not stop for Death –
He kindly stopped for me –
The Carriage held but just Ourselves –
And Immortality.
We slowly drove – He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility –
We passed the School, where Children strove
At Recess – in the Ring –
We passed the Fields of Gazing Grain –
We passed the Setting Sun –
Or rather – He passed us –
The Dews drew quivering and chill –
For only Gossamer, my Gown –
My Tippet – only Tulle –
We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground –
The Roof was scarcely visible –
The Cornice – in the Ground –
Since then – ‘tis Centuries – and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses’ Heads
Were toward Eternity –
私は死のために止まれなかったので―
私は死のために止まれなかったので―
死が親切にも私のために止まってくれた―
馬車に乗っていたのはただ私たちだけ―
実はさらに永遠(immortality)も。
私たち(私と死)はゆっくり進んだ―死は急ぐことを知らなかった
そして私は放棄していた
私の仕事もまた私の余暇も
死の礼節に応えるために―。
私たち(私と死)は学校を通り過ぎた、そこでは子供たちが遊んだ
休み時間―輪になって―
私たちは、凝視する穀物の畑を通り過ぎた―
私たちは、夕日を通り過ぎた―
というよりむしろ―夕日が私たちを通り過ぎた―
露が、震えと寒さを引き寄せた―
というのも私のガウンはただの蜘蛛の糸織り―
私のショールは―ただの薄絹―だから
私たち(私と死)は止まった。
地面の盛り上がったような家の前に―
屋根はほとんど見えない―
軒蛇腹(ノキジャバラ)は―土の中―
その時から―数世紀がたつ―しかしそれは
あの1日より短く感じる。
馬が、永遠(eternity)に向かっているのだと
私が初めて思ったあの1日よりも―
《感想1》
詩は、数世紀前の死者の立場で書かれている。
「死が親切にも私のために止まってくれた」。死が、私を選んだ。私が、死を選ぶわけでない。
つまり「私は死のために止まれな」い。私に、死か不死かの選択権はない。死が私を選び取った。
人生の馬車に、私と死が乗った。
だが実は、永遠(immortality)も馬車に乗った。永遠に不滅の真理。“人間は死すべきものだ”という真理。
《感想2》
「私たち(私と死)はゆっくり進んだ」。墓に行きつくまで時間があった。
死は急がない。だから私の人生があった。
そして私は知っていた。「私の仕事もまた私の余暇も」消え去るものであり、私のものにならないこと。それらを、あらかじめ私は「放棄していた」。
“死が、私の生をしばらくの間、許す”、つまり“死が急がない”ことが、死が私に示す「礼節」。その「礼節」に応えるため、私は、私の生が消え去ることを受け入れた。
《感想3》
私たち(私と死)の馬車は、私の人生を、ゆっくり進んだ。学校に通う少年期、実る穀物の壮年期、夕日の老年期。
壮年期の実る穀物は、私の生の対象化であり、それらを生み出した私を指し示す、つまり凝視し続ける。
《感想4》
時間とは何か?
時間は、過ぎていくと言われる。私たち(私と死)の馬車が、夕日を過ぎていく。だから、「私たちは、夕日を通り過ぎた」と言う。
だが、時間の中の対象(Ex. 夕日)は、“常にここにある今の私”を、通り過ぎて、過去へと去っていく。だから「夕日が私たちを通り過ぎた」とも言える!
人生の秋が来て、死の予感が到来する。「露が、震えと寒さを引き寄せた」。
私の生を守った「ガウン」も「ショール」も、私と死の共在、つまり死の不可避性の前に、無力だった。それらは、「ただの蜘蛛の糸織り」、「ただの薄絹」だった。
《感想5》
私たち(私と死)は、ついに、墓に到着した。
《感想6》
馬車には、私たち(私と死)だけでなく、永遠の真理(eternity )も乗っていた。
存在(世界)が、“私の生が消え去ること”(死の不可避性)の形式をとるしかないという永遠の真理!
この世の数世紀も、この真理の永遠性には、及ばない、つまり、ついに覆すことが出来ない。