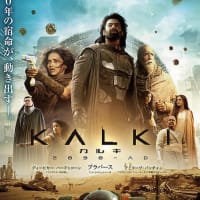※斎藤美奈子(1956生)『日本の同時代小説』(2018年、62歳)岩波新書
(58)「異化される太平洋戦争」:古処(コドコロ)誠二『UNKNOWN』(2000)、『ルール』(2002)、『七月七日』(2004)!
J 2000年代の「戦争小説」のタイプは、すでに述べたように①「戦時下の国」を描いた小説(195頁以下)、②「9・11やイラク戦争」を直接的、間接的に描いた小説(198頁以下)、そしてこれから述べる③過去の戦争に取材した小説だ。(201頁)
J-2 古処(コドコロ)誠二(1970-)『UNKNOWN』(2000、30歳)は自身の自衛隊の体験を描いた小説だ。(201頁)(※「アンノウン」は識別不明機。)
《書評1》舞台は静岡の自衛隊対空レーダー基地。隊長の部屋で盗聴器が見つかる。中央から派遣された朝香ニ尉と補佐の野上三曹は内偵捜査を始める。ただしミステリというより、自衛隊と民間の観点の相違や自衛隊員の葛藤など、色々考えさせられる場面が多い。良作。
《書評2》「自衛隊が本来の活躍をすることがあってはならない。日々の努力の成果を発揮してはならない。それが平和というものであり、武力を持っている組織は国民から白い目で見られている間が幸せなのだ」という言葉が印象に残った。自衛隊は創設以来このジレンマに、もがき続けている。国防の最前線で任務についている自衛隊員の複雑な心中が垣間見える。
J-3 古処(コドコロ)誠二(1970-)『ルール』(2002、32歳)は、戦争末期のルソン島を舞台に、臨時編成の小隊の指揮を命じられた中尉が、絶望的な飢餓と戦いながら架空の任務をこなす物語だ。(大岡昇平『野火』と重なる題材。)(201頁)
《書評1》補給もなく、道中の蛆や蛭を食べながら生きながらえるルソン島の戦況を描く。統率もなく、肉を得るための殺し合いまで発生する。極限状態を描く小説。凄惨な描写が多い。『野火』を連想させるが、ミステリー仕立てであることと、アメリカ人捕虜の目線が入っていることで新しさがある。
《書評2》食料は敵から強奪する、現地調達するという無茶な戦略の無惨さ。死を目前にしても、身体が欲する食欲は意識や概念を凌駕する。中隊は、上層部のいいように使われ殆ど犬死となってしまった。
《書評3》フィリピンは米軍、ゲリラ、敗残兵、飢餓、病気など日本兵には敵だらけ。自分は、特攻隊が出てくる小説が一番辛いと思っていたが違った。「特攻隊」の話は一種のカタルシスを感じるが、「フィリピンの日本兵」は悲惨だった。
J-4 古処(コドコロ)誠二(1970-)『七月七日』(2004、34歳)は、1944/6/18 から7/7のサイパンを舞台に、米軍捕虜収容所の日系二世の語学兵と、捕虜となった日本軍将兵との対話を通して、国家に忠誠を誓った兵士の複雑な内面を描く。(大岡昇平『俘虜記』と重なる題材。)(201頁)
《書評1》太平洋戦争でのサイパン島の戦闘を、アメリカ兵で日系二世のショーティの目を通して描く。 戦争は、敵も味方も、勝者も敗者も、等しく地獄を見ると教えてくれる、素晴らしい作品だった。
《書評2》移民の子が、たまたま世界情勢により元の祖国と闘わなければならなくなった、その大いなる矛盾を描いた作品と思った。
《書評3》日系二世米語学兵がみたサイパン戦。日本兵や民間人との接触を通じて、当時の日本人のメンタリティが語られる。捕虜となると家族が辱めを受け、日本軍が奪還すると八つ裂きにされる。従って捕虜となるよりは手榴弾で自爆を選ぶ。他方で、米国の部隊の中で差別される日系二世兵士。非常に重い題材を客観的に描き、一気に読ませる筆力にただただ感服。素晴らしい。
《書評4》氏の長編の中では屈指の作品だと思う。前のこと言っても仕方ないけど、直木賞あげたかった。
(58)-2 20世紀の戦争の歴史(1940年代以降)を軍用犬の目を通して語った怪作:古川日出男『ベルカ、吠えないのか?』(2005)!
J-5 古川日出男(フルカワヒデオ)(1966-)『ベルカ、吠えないのか?』(2005、39歳)は、20世紀の戦争の歴史(1940年代以降)を軍用犬の目を通して語った怪作だ。(201頁)
J-5-2 1943年7月、日本軍が撤退した後のキスカ島に4頭(雄3頭・雌1頭)の軍用犬が残された。この4頭を始祖とし混血と交配を繰り返して何千頭にも増えた犬たちが、その後の戦争の時代(冷戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガン戦争、ソ連崩壊)を軍用犬としてどう生きたかを、叙事詩のように語る。(201-202頁)
《書評1》言わば「犬が主役のハードボイルド小説」。脚韻を踏んでラップを聞くようなリズム感のいい短めの文体が心地よい。ベルカは1960年ソ連の人工衛星の二匹のライカ犬の雄の名前。1943年旧日本軍がキスカ島に置き去りにした4匹の犬が米大陸に渡り次々と子孫を産んで、20世紀後半の世界各地の戦争に軍用犬として参戦していく。
《書評2》イヌは生きる。ただイヌとして生きるために。自らの数奇な運命、また現実への悲嘆も絶望もない。そして、吠える。人間のエゴに向かって。世の不条理に向かって。「うぉん」は、「20世紀という戦争の世紀、何かに何者かに踊らされ、騙されてきた」と感じる語り手(作者)の怒りの叫びか。
《書評3》とっても凄いものを読んだ! こういう読後感は、平山夢明(ユメアキ)(1961-)『ダイナー』(2009、48歳)(※激しい拷問の末、殺人者の会員制食堂『ダイナー』でウエイトレスとして働くことになった女性の物語)以来かも。 1943年、日本軍のキスカ島撤退で置き去りにされた4頭の軍用犬。 このイヌたちの系譜をたどりながら描かれる二十世紀の戦争。 「大義やメンツ、欲望、損得勘定で動く」人間と違い、「信頼を裏切らず本能で行動する」イヌたちの迷いのなさが美しい。
(58)-3 荻原浩『僕たちの戦争』(2004):2001年19歳のフリーターと1944年霞ヶ浦航空隊の飛行術練習生がタイムスリップし入れ替わる!
J-6 荻原浩(オギワラヒロシ)(1956-)『僕たちの戦争』(2004、48歳)は現代と太平洋戦争をつなぐ青春小説だ。2001年3月、サーフィンの最中だった19歳のフリーター尾島健太(オジマケンタ)と、1944年9月、霞ヶ浦航空隊の飛行術練習生・石庭吾一(イシバゴイチ)が、入れ替わってしまう。(202頁)
J-6-2 2001年3月にタイムスリップした石庭吾一は、(米同時多発テロで)摩天楼に飛行機が突入する映像を見て、「特攻隊の活躍がはじまった」と思い込む。(202頁)
J-6-3 他方、戦中・1944年9月にタイムスリップした尾島健太は、海の特攻=人間魚雷(回天)に回される。(202頁)
J-6-4 よくあるタイムスリップものとはいえ、戦争体験ごっこではすまない当事者性が随所ににじみ出る。(202頁)
《書評1》現代のフリーター健太と、終戦間近の軍人吾一。それぞれタイムスリップして入れ替わるが、二人は見た目そっくりなので、周囲の人は気付かない。自分が置かれた現状を認め、元の世界に戻る術を探す二人の視点で交互に描かれる長編。健太の成長と戦争の悲惨さを描く感動作。
《書評2》戦争系の作品では『永遠の0』より好きな作品だ。だらしなくて、ちゃらんぽらんと思ってた主人公・健太が大切なものに気づいて、それを守ろうとする姿には心がうたれた。
《書評3》吾一は戸惑いながらも現代で楽しさを知り恋も知る。それに比べ戦時下に来た健太は可哀想すぎる。恋人ミナミと会えず大好きなコーラも唐揚げもない。先輩から訓練という名の容赦ない暴力を受け、特攻隊として死と隣り合わせで過ごすなんて、辛すぎる!でも健太はたくましい青年に成長してゆく。
《書評4》読み続けていくうちにこれは「回天」の話だと思うと胸打たれる。理不尽な犬死は虚しすぎる。最後2人が元の時代に戻れたか、曖昧なまま終わるが、吾一はもう過去の人であり健太に戻ってきてほしい。美味いもの食べて暖かいベッドで眠ってほしい。
(58)-4 奥泉光『神器――軍艦「橿原」殺人事件』(2009):戦争自体を哄笑しているような作品!
J-7 奥泉光(ヒカル)(1956-)『神器――軍艦「橿原」(カシハラ)殺人事件』(2009、53歳)は、往年の伝奇小説のような作品。戦艦「橿原」(カシハラ)の乗組員・石目が艦内で起こった殺人事件の探偵ごっこから、幾重にもからまりあった「橿原」の謎解きに熱中する。物語は現実とも妄想ともつかず展開。どんな任務を負っているかも不明な戦艦「橿原」。戦艦「矢魔斗」、戦艦「無左志」も登場するこの小説は、戦争自体を哄笑しているようだ。(202-203頁)
《書評1》上下巻1000ページ以上の大作は私にとって高い壁だった。ミステリー要素だけでなく、怪奇幻想、SF、耽美等様々なジャンルにとどまらず、人称も一から三へと変化させ、戯曲形式も混ぜながらの総合小説の様相だ。
《書評2》推理小説ではない。軍人と鼠と死人が入り混じり、軍艦「橿原」は謎の場所を目指す。そのあいだ艦上では切腹が行われ、男色行為が横行し、密告や拷問など、大混乱。鼠たちの会話や登場人物たちが滑稽で可笑しい。「作者が何を伝えたかったのか」は、わからなかった。
《書評3》奇妙と異常が加速し、狂気は「橿原」を覆って最高潮に達する。「さあ何が起こるのか」と読んでいくと猥雑で醜悪な性の儀式が執り行われ気持悪くなった。こんな事のために乗組員は踊らされ自死していったのか。だが、こうした思考は「神風特攻」や「一億玉砕」を美談と捉えたがることと繋がっている。戦争なんて実際は「気狂いの愚者による命令と叫び」でしかないのだ。
(58)-5 百田尚樹(ヒャクタナオキ)『永遠の0(ゼロ)』(2006):特攻の「美しい死」が、東日本大震災の「無意味な死」「大量死」への「癒し」となった!
J-8 この時期の戦争小説でもっとも多くの人に読まれたのは百田尚樹(ヒャクタナオキ)(1956-)『永遠の0(ゼロ)』(2006、50歳)だ。26歳の「ぼく」佐伯健太が亡き祖父・宮部久蔵の戦中の足跡をたどる。宮部は空母「赤城」の戦闘機パイロットとして真珠湾攻撃にも参加した撃墜王だったが、敗戦の数日前に特攻隊として出撃し戦死した。(203頁)
J-8-2 『永遠の0』は2009年に文庫化され、2012年以降、爆発的にヒットする。(2013年には文庫だけで300万部超のベストセラーとなる。)(203-204頁)
《書評1》こんなに心を動かされた小説は初めてだった。 私は、この本を読むまでは戦争など悲しい悲惨なことから目を背けていたが、この本を読んで「伝えていかなければならない」、「忘れてはいけない」と強く思った。 このような本に出会えてよかった。
《書評2》礼儀正しく高潔なパイロット、宮部久蔵の愛の(影響力の)物語。実は私は戦争モノは避けていた。目の当たりにするのがこわかったからだ。戦争や特攻隊について、「知っている」「心情を理解できる」「想像できる」気になっていた。しかし読んでみたら、もっともっと複雑だった。今、出会えて、読めてよかった。
《書評3》八時間も飛べる、最初は百戦錬磨、最後は十死零生の零戦闘機、皮肉である。「特攻隊に志願するか否か・・・・」うわべは自由意志のようにみえるが、同調圧力下では「命令ではない命令」⇒「上は責任は取らない」ということ。コロナ禍の自粛要請(自粛のお願い)と似た構図か。
J-8-3 数ある戦争小説の中で『永遠の0』だけが、なぜ飛びぬけて売れたのか。(203頁)
J-8-3-2 ここで思い出すべきは、「無意味な死」「大量死」の後には、「意味ある死」「小さな死」「美しい死」の物語が求められることだ。これは「失楽園の法則」と呼んでもよい。(斎藤美奈子氏。)①『失楽園』(1997)(心中という「意味ある死」)が阪神淡路大震災(1995.1月)・地下鉄サリン事件(1995.3月)の後に、「癒し」としてヒットした。(203頁)②『世界の中心で、愛を叫ぶ』(2001)(白血病の恋人の「小さな死」)は、実は2003年イラク戦争の後に爆発的に売れた。そして③『永遠の0』(2006)(特攻という「美しい死」)は、2011年の東日本大震災後、2012年以降、爆発的にヒットした。(203-204頁)
J-8-3-3 百田尚樹『永遠の0(ゼロ)』は、特攻の「美しい死」の物語だ。宮部は撃墜王で英雄であり、また愛する人のために死んだ宮部は戦後価値観に合致し、東日本大震災後の読者の心を癒した。(204頁)
J-8-4 『永遠の0(ゼロ)』は「特攻の美化」でもある。(204頁)
J-8-5 百田尚樹(1956-)『海賊とよばれた男』(2012、56歳)も大ヒットする。これは出光(イデミツ)興産の創業者・出光佐三(サゾウ)をモデルにした実業家の成功譚だ。(204頁)
《書評》戦前から戦後にかけ、国・消費者のため生涯を賭け石油産業を切り開いてきた主人公の姿は圧巻。読者の心を掴む文章はさすが放送作家の作品だ。 他方で「社員は皆家族」「タイムカードもなく休日返上で働く」「国・天皇の為に」という言葉が頻出しており、グローバル化が進む今の世の中でどこまで通用する哲学かは疑問だ。 巷では「右傾エンタメ」等と言われているようだが、戦中・戦後を舞台とした作品として一歩引いて読めば、一人の人の伝記として大変面白い内容だった。
J-8-6 特攻隊員と石油王。人々は「強い男」を求めたのかもしれない。(204頁)
(58)-6 2000年代の小説のトレンドは第1に「殺人」(or「テロ」)であり、第2に「戦争」だった!21世紀、「テロとの戦い」というロジックは、「いつどこが戦場になってもおかしくない」ことを意味する!
J-9 2000年代の小説のトレンドは第1に「殺人」(or「テロ」)であり、第2に「戦争」だった。(195頁)
J-9-2 2001年9月11日米国同時多発テロ、いわゆる「9・11」が世界を一変させた。米国(ジョージ・ブッシュ大統領)は10月にアフガニスタン戦争を開始する。さらに2003年3月には国連の合意がないままイラク戦争を開始した。(174頁)
J-9-3 「9・11」は、私たちの意識を明らかに変えた。21世紀、「テロとの戦い」というロジックは、「いつどこが戦場になってもおかしくない」ことを意味する。20世紀には、それはなかった感覚だった。(204頁)
(58)「異化される太平洋戦争」:古処(コドコロ)誠二『UNKNOWN』(2000)、『ルール』(2002)、『七月七日』(2004)!
J 2000年代の「戦争小説」のタイプは、すでに述べたように①「戦時下の国」を描いた小説(195頁以下)、②「9・11やイラク戦争」を直接的、間接的に描いた小説(198頁以下)、そしてこれから述べる③過去の戦争に取材した小説だ。(201頁)
J-2 古処(コドコロ)誠二(1970-)『UNKNOWN』(2000、30歳)は自身の自衛隊の体験を描いた小説だ。(201頁)(※「アンノウン」は識別不明機。)
《書評1》舞台は静岡の自衛隊対空レーダー基地。隊長の部屋で盗聴器が見つかる。中央から派遣された朝香ニ尉と補佐の野上三曹は内偵捜査を始める。ただしミステリというより、自衛隊と民間の観点の相違や自衛隊員の葛藤など、色々考えさせられる場面が多い。良作。
《書評2》「自衛隊が本来の活躍をすることがあってはならない。日々の努力の成果を発揮してはならない。それが平和というものであり、武力を持っている組織は国民から白い目で見られている間が幸せなのだ」という言葉が印象に残った。自衛隊は創設以来このジレンマに、もがき続けている。国防の最前線で任務についている自衛隊員の複雑な心中が垣間見える。
J-3 古処(コドコロ)誠二(1970-)『ルール』(2002、32歳)は、戦争末期のルソン島を舞台に、臨時編成の小隊の指揮を命じられた中尉が、絶望的な飢餓と戦いながら架空の任務をこなす物語だ。(大岡昇平『野火』と重なる題材。)(201頁)
《書評1》補給もなく、道中の蛆や蛭を食べながら生きながらえるルソン島の戦況を描く。統率もなく、肉を得るための殺し合いまで発生する。極限状態を描く小説。凄惨な描写が多い。『野火』を連想させるが、ミステリー仕立てであることと、アメリカ人捕虜の目線が入っていることで新しさがある。
《書評2》食料は敵から強奪する、現地調達するという無茶な戦略の無惨さ。死を目前にしても、身体が欲する食欲は意識や概念を凌駕する。中隊は、上層部のいいように使われ殆ど犬死となってしまった。
《書評3》フィリピンは米軍、ゲリラ、敗残兵、飢餓、病気など日本兵には敵だらけ。自分は、特攻隊が出てくる小説が一番辛いと思っていたが違った。「特攻隊」の話は一種のカタルシスを感じるが、「フィリピンの日本兵」は悲惨だった。
J-4 古処(コドコロ)誠二(1970-)『七月七日』(2004、34歳)は、1944/6/18 から7/7のサイパンを舞台に、米軍捕虜収容所の日系二世の語学兵と、捕虜となった日本軍将兵との対話を通して、国家に忠誠を誓った兵士の複雑な内面を描く。(大岡昇平『俘虜記』と重なる題材。)(201頁)
《書評1》太平洋戦争でのサイパン島の戦闘を、アメリカ兵で日系二世のショーティの目を通して描く。 戦争は、敵も味方も、勝者も敗者も、等しく地獄を見ると教えてくれる、素晴らしい作品だった。
《書評2》移民の子が、たまたま世界情勢により元の祖国と闘わなければならなくなった、その大いなる矛盾を描いた作品と思った。
《書評3》日系二世米語学兵がみたサイパン戦。日本兵や民間人との接触を通じて、当時の日本人のメンタリティが語られる。捕虜となると家族が辱めを受け、日本軍が奪還すると八つ裂きにされる。従って捕虜となるよりは手榴弾で自爆を選ぶ。他方で、米国の部隊の中で差別される日系二世兵士。非常に重い題材を客観的に描き、一気に読ませる筆力にただただ感服。素晴らしい。
《書評4》氏の長編の中では屈指の作品だと思う。前のこと言っても仕方ないけど、直木賞あげたかった。
(58)-2 20世紀の戦争の歴史(1940年代以降)を軍用犬の目を通して語った怪作:古川日出男『ベルカ、吠えないのか?』(2005)!
J-5 古川日出男(フルカワヒデオ)(1966-)『ベルカ、吠えないのか?』(2005、39歳)は、20世紀の戦争の歴史(1940年代以降)を軍用犬の目を通して語った怪作だ。(201頁)
J-5-2 1943年7月、日本軍が撤退した後のキスカ島に4頭(雄3頭・雌1頭)の軍用犬が残された。この4頭を始祖とし混血と交配を繰り返して何千頭にも増えた犬たちが、その後の戦争の時代(冷戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガン戦争、ソ連崩壊)を軍用犬としてどう生きたかを、叙事詩のように語る。(201-202頁)
《書評1》言わば「犬が主役のハードボイルド小説」。脚韻を踏んでラップを聞くようなリズム感のいい短めの文体が心地よい。ベルカは1960年ソ連の人工衛星の二匹のライカ犬の雄の名前。1943年旧日本軍がキスカ島に置き去りにした4匹の犬が米大陸に渡り次々と子孫を産んで、20世紀後半の世界各地の戦争に軍用犬として参戦していく。
《書評2》イヌは生きる。ただイヌとして生きるために。自らの数奇な運命、また現実への悲嘆も絶望もない。そして、吠える。人間のエゴに向かって。世の不条理に向かって。「うぉん」は、「20世紀という戦争の世紀、何かに何者かに踊らされ、騙されてきた」と感じる語り手(作者)の怒りの叫びか。
《書評3》とっても凄いものを読んだ! こういう読後感は、平山夢明(ユメアキ)(1961-)『ダイナー』(2009、48歳)(※激しい拷問の末、殺人者の会員制食堂『ダイナー』でウエイトレスとして働くことになった女性の物語)以来かも。 1943年、日本軍のキスカ島撤退で置き去りにされた4頭の軍用犬。 このイヌたちの系譜をたどりながら描かれる二十世紀の戦争。 「大義やメンツ、欲望、損得勘定で動く」人間と違い、「信頼を裏切らず本能で行動する」イヌたちの迷いのなさが美しい。
(58)-3 荻原浩『僕たちの戦争』(2004):2001年19歳のフリーターと1944年霞ヶ浦航空隊の飛行術練習生がタイムスリップし入れ替わる!
J-6 荻原浩(オギワラヒロシ)(1956-)『僕たちの戦争』(2004、48歳)は現代と太平洋戦争をつなぐ青春小説だ。2001年3月、サーフィンの最中だった19歳のフリーター尾島健太(オジマケンタ)と、1944年9月、霞ヶ浦航空隊の飛行術練習生・石庭吾一(イシバゴイチ)が、入れ替わってしまう。(202頁)
J-6-2 2001年3月にタイムスリップした石庭吾一は、(米同時多発テロで)摩天楼に飛行機が突入する映像を見て、「特攻隊の活躍がはじまった」と思い込む。(202頁)
J-6-3 他方、戦中・1944年9月にタイムスリップした尾島健太は、海の特攻=人間魚雷(回天)に回される。(202頁)
J-6-4 よくあるタイムスリップものとはいえ、戦争体験ごっこではすまない当事者性が随所ににじみ出る。(202頁)
《書評1》現代のフリーター健太と、終戦間近の軍人吾一。それぞれタイムスリップして入れ替わるが、二人は見た目そっくりなので、周囲の人は気付かない。自分が置かれた現状を認め、元の世界に戻る術を探す二人の視点で交互に描かれる長編。健太の成長と戦争の悲惨さを描く感動作。
《書評2》戦争系の作品では『永遠の0』より好きな作品だ。だらしなくて、ちゃらんぽらんと思ってた主人公・健太が大切なものに気づいて、それを守ろうとする姿には心がうたれた。
《書評3》吾一は戸惑いながらも現代で楽しさを知り恋も知る。それに比べ戦時下に来た健太は可哀想すぎる。恋人ミナミと会えず大好きなコーラも唐揚げもない。先輩から訓練という名の容赦ない暴力を受け、特攻隊として死と隣り合わせで過ごすなんて、辛すぎる!でも健太はたくましい青年に成長してゆく。
《書評4》読み続けていくうちにこれは「回天」の話だと思うと胸打たれる。理不尽な犬死は虚しすぎる。最後2人が元の時代に戻れたか、曖昧なまま終わるが、吾一はもう過去の人であり健太に戻ってきてほしい。美味いもの食べて暖かいベッドで眠ってほしい。
(58)-4 奥泉光『神器――軍艦「橿原」殺人事件』(2009):戦争自体を哄笑しているような作品!
J-7 奥泉光(ヒカル)(1956-)『神器――軍艦「橿原」(カシハラ)殺人事件』(2009、53歳)は、往年の伝奇小説のような作品。戦艦「橿原」(カシハラ)の乗組員・石目が艦内で起こった殺人事件の探偵ごっこから、幾重にもからまりあった「橿原」の謎解きに熱中する。物語は現実とも妄想ともつかず展開。どんな任務を負っているかも不明な戦艦「橿原」。戦艦「矢魔斗」、戦艦「無左志」も登場するこの小説は、戦争自体を哄笑しているようだ。(202-203頁)
《書評1》上下巻1000ページ以上の大作は私にとって高い壁だった。ミステリー要素だけでなく、怪奇幻想、SF、耽美等様々なジャンルにとどまらず、人称も一から三へと変化させ、戯曲形式も混ぜながらの総合小説の様相だ。
《書評2》推理小説ではない。軍人と鼠と死人が入り混じり、軍艦「橿原」は謎の場所を目指す。そのあいだ艦上では切腹が行われ、男色行為が横行し、密告や拷問など、大混乱。鼠たちの会話や登場人物たちが滑稽で可笑しい。「作者が何を伝えたかったのか」は、わからなかった。
《書評3》奇妙と異常が加速し、狂気は「橿原」を覆って最高潮に達する。「さあ何が起こるのか」と読んでいくと猥雑で醜悪な性の儀式が執り行われ気持悪くなった。こんな事のために乗組員は踊らされ自死していったのか。だが、こうした思考は「神風特攻」や「一億玉砕」を美談と捉えたがることと繋がっている。戦争なんて実際は「気狂いの愚者による命令と叫び」でしかないのだ。
(58)-5 百田尚樹(ヒャクタナオキ)『永遠の0(ゼロ)』(2006):特攻の「美しい死」が、東日本大震災の「無意味な死」「大量死」への「癒し」となった!
J-8 この時期の戦争小説でもっとも多くの人に読まれたのは百田尚樹(ヒャクタナオキ)(1956-)『永遠の0(ゼロ)』(2006、50歳)だ。26歳の「ぼく」佐伯健太が亡き祖父・宮部久蔵の戦中の足跡をたどる。宮部は空母「赤城」の戦闘機パイロットとして真珠湾攻撃にも参加した撃墜王だったが、敗戦の数日前に特攻隊として出撃し戦死した。(203頁)
J-8-2 『永遠の0』は2009年に文庫化され、2012年以降、爆発的にヒットする。(2013年には文庫だけで300万部超のベストセラーとなる。)(203-204頁)
《書評1》こんなに心を動かされた小説は初めてだった。 私は、この本を読むまでは戦争など悲しい悲惨なことから目を背けていたが、この本を読んで「伝えていかなければならない」、「忘れてはいけない」と強く思った。 このような本に出会えてよかった。
《書評2》礼儀正しく高潔なパイロット、宮部久蔵の愛の(影響力の)物語。実は私は戦争モノは避けていた。目の当たりにするのがこわかったからだ。戦争や特攻隊について、「知っている」「心情を理解できる」「想像できる」気になっていた。しかし読んでみたら、もっともっと複雑だった。今、出会えて、読めてよかった。
《書評3》八時間も飛べる、最初は百戦錬磨、最後は十死零生の零戦闘機、皮肉である。「特攻隊に志願するか否か・・・・」うわべは自由意志のようにみえるが、同調圧力下では「命令ではない命令」⇒「上は責任は取らない」ということ。コロナ禍の自粛要請(自粛のお願い)と似た構図か。
J-8-3 数ある戦争小説の中で『永遠の0』だけが、なぜ飛びぬけて売れたのか。(203頁)
J-8-3-2 ここで思い出すべきは、「無意味な死」「大量死」の後には、「意味ある死」「小さな死」「美しい死」の物語が求められることだ。これは「失楽園の法則」と呼んでもよい。(斎藤美奈子氏。)①『失楽園』(1997)(心中という「意味ある死」)が阪神淡路大震災(1995.1月)・地下鉄サリン事件(1995.3月)の後に、「癒し」としてヒットした。(203頁)②『世界の中心で、愛を叫ぶ』(2001)(白血病の恋人の「小さな死」)は、実は2003年イラク戦争の後に爆発的に売れた。そして③『永遠の0』(2006)(特攻という「美しい死」)は、2011年の東日本大震災後、2012年以降、爆発的にヒットした。(203-204頁)
J-8-3-3 百田尚樹『永遠の0(ゼロ)』は、特攻の「美しい死」の物語だ。宮部は撃墜王で英雄であり、また愛する人のために死んだ宮部は戦後価値観に合致し、東日本大震災後の読者の心を癒した。(204頁)
J-8-4 『永遠の0(ゼロ)』は「特攻の美化」でもある。(204頁)
J-8-5 百田尚樹(1956-)『海賊とよばれた男』(2012、56歳)も大ヒットする。これは出光(イデミツ)興産の創業者・出光佐三(サゾウ)をモデルにした実業家の成功譚だ。(204頁)
《書評》戦前から戦後にかけ、国・消費者のため生涯を賭け石油産業を切り開いてきた主人公の姿は圧巻。読者の心を掴む文章はさすが放送作家の作品だ。 他方で「社員は皆家族」「タイムカードもなく休日返上で働く」「国・天皇の為に」という言葉が頻出しており、グローバル化が進む今の世の中でどこまで通用する哲学かは疑問だ。 巷では「右傾エンタメ」等と言われているようだが、戦中・戦後を舞台とした作品として一歩引いて読めば、一人の人の伝記として大変面白い内容だった。
J-8-6 特攻隊員と石油王。人々は「強い男」を求めたのかもしれない。(204頁)
(58)-6 2000年代の小説のトレンドは第1に「殺人」(or「テロ」)であり、第2に「戦争」だった!21世紀、「テロとの戦い」というロジックは、「いつどこが戦場になってもおかしくない」ことを意味する!
J-9 2000年代の小説のトレンドは第1に「殺人」(or「テロ」)であり、第2に「戦争」だった。(195頁)
J-9-2 2001年9月11日米国同時多発テロ、いわゆる「9・11」が世界を一変させた。米国(ジョージ・ブッシュ大統領)は10月にアフガニスタン戦争を開始する。さらに2003年3月には国連の合意がないままイラク戦争を開始した。(174頁)
J-9-3 「9・11」は、私たちの意識を明らかに変えた。21世紀、「テロとの戦い」というロジックは、「いつどこが戦場になってもおかしくない」ことを意味する。20世紀には、それはなかった感覚だった。(204頁)