木下是雄さん(4) 理解されない木下さん 国語教育と英語教育の架け橋
次の文は、木下是雄著『リポートの組み立て方』(1990)、28ページに引用される、
若干問題のある文の例です。どこが問題なのか分かりますか。
大磯は、冬、東京より暖いと信じられているが、私は、夜は東京より気温が下がるのではないかと思う。夜間、大磯のほうが低温になることにふしぎはない。暖房その他の熱源が少ないし、第一、東京にくらべてはるかに空気が澄んでいて、夜は地面から虚空(こくう)に向かってどんどん熱が逃げて行くからである。
おかしいと思わない人も多いのではないかと思います。木下さんの例文の選び方はとても用心深く、ここぞ、という問題を指摘できるような文を選んでいます。
「夜間、大磯のほうが低温になることに不思議はない。」という部分です。その前の文からの流れを考えてください。「気温が下がる」ことは著者の意見です。大磯のほうが低温になるのは事実ではないので、「大磯のほうが低温になるとしてもふしぎはない。」とすべきです。「~になることに不思議はない」の表現は、通常、読者を、事実を前提して述べているのだと思わせる表現なので、トリッキーだと言えます。
こういう点を読者はじっくり読みこなしているかというと、必ずしもそうは言えないのではないかと思います。その結果、毎年、『理科系の作文技術』と『リポートの組み立て方』は版を重ねながら、日本人の言語能力が上がったと思えないのです。英語教育でも、ときおりディベート・ブームになったり、プレゼン・ブームになったりしますが、しばらくするとしぼんでしまいます。また、木下さんは、パソコンの黎明期に、これから普及する「テクニカル・ライティング」を念頭に国語教育に打ち込んだのですが、その後のパソコンのマニュアル、いや、マニュアルどころか、パソコン内の表示の分かりにくさは、木下さんの危惧したとおりになったと言えます。学習院でも木下さんのグループが作った教科書はあまり使われていないという噂も聞こえてきます。木下さんは、「将来、さすが学習院出は違う、文章力がすばらしい」、と言われたいと夢を語っていましたが、少なくとも、その夢がかなったとは言いがたいようです。
では、木下さんが見込み違いのことをしたか、というと、そうではなく、むしろ、その逆です。国語教育が深刻な問題を抱えているという木下さんの直感はまさにそのとおりだったのです。しかし、その問題を克服するのは木下さん一人の手にはあまりました。『理科系の作文技術』が発行されてから、井上ひさしや、丸谷才一といった文学者の熱烈な支持がありましたし、学習院では「同志」を集めて教科書の編纂も行いました。しかし、木下さん以外の方は、意思の疎通ということで切実に悩むということが少なかったのではないかと推察しています。
木下是雄さんには、以下のような「原体験」があります。
1976年に、2年間アメリカで月の化学の研究をしていた同僚が帰国して、お子さんたちがヒューストンの小学校で使っていた国語の教科書を見せてくれた。硬い表紙で分厚い21cm×24cm版の、きれいな色刷りの本だ。5年生用のを手にした私は、たまたま開いたページに
ジョージ・ワシントンは米国の最も偉大な大統領であった。
ジョージ・ワシントンは米国の初代の大統領であった。
という二つの文ば並び、その下に
どちらの文が事実の記述か、もう一つの文に述べてあるのはどんな意見か、事実と意見はどう違うか
と尋ねてあるのを見て、衝撃を受けた。
(『リポートの組み立て方』 文庫p.26)
木下さんは、「衝撃」を受けたのです。この衝撃を共有できるかどうかが、この書が理解できるどうかの、試金石だと思います。もちろん、各自の属している分野は違うものの、この記述を読んで、あ、そうだ、と腑に落ちる人、または、そのときは何気なく読みすごしていても、しばらくして、木下さんの述べていることはこのことか!、と納得する経験がない人は、評判でこの本を読んでも、決して身につくことはないでしょう。
では、その「衝撃」とは何か。この箇所は「事実と意見の峻別」がテーマですが、その根底には、人と意思の疎通を図ることがいかに困難であるか、という問題があります。そして、理解しよう、伝えようと常に努力していない限り人間は孤独だということです。それをごまかして伝わったように、分かったように思い込むことのいかがわしさに、我々は鈍感になってはいないか、という問いかけが木下さんのその後の国語教育の原動力だったと思います。これはすぐれて倫理的な営みと言えます。
なにしろ、最初の本の書名が、『理科系の作文技術』です。「作文技術」という表現には皮肉が込められていると、あとで木下さんは述べていますが、今でもこの本が売れる理由は、「~すればなんとかができる」のような十分条件を与えてくれると本だと人々が思い込むからでないでしょうか。そういう人は、ぼんやり読んでも、この記事の冒頭の例文が何故おかしいか、立ち止まって考えることはないと思います。てっとり早く教えてくれ、という人たちは、なんとなく読んで、説教くさいなという印象と伴に書棚のすみにほったらかしにするということになるでしょう。木下さんはこうした読者への皮肉を意識したのでしょう。読者のうち10%の人でも本当に分かって欲しいという気持ちだったのかもしれません。
事実と意見の章の終わり近くに、このように書いています。
事実の記述と意見とのちがいを詳述してきたが、事実と意見とを異質のものとして感じ分ける感覚を子供の時から心の奥底に培っておくことが何より大切である。この感覚が抜けている人は、科学、あるいはひろく言って学問の道に進むことはむずかしい。また、この感覚のにぶい人はたやすくデマにまどわされる。 p.42
このような部分を読めば、たんなる「技術書」ではないことは明らかです。厳しく、かつ明朗な姿勢を読者に伝えようとしています。このブログの、木下是雄・シリーズの最初に取り上げたY新聞の記者は、この本のような「技術」だけでは、論文盗用問題は解決できないという趣旨のことを述べていましたが、この記者もぼんやりとしていたのでしょう。
先日、小学6年生に、一生ものですよ、と言って、『リポートの組み立て方』を買い与えました。与えただけではだめです。どのように問題意識を育てるかは、私の役割です。











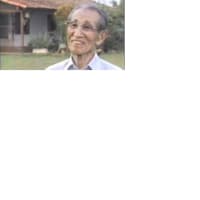
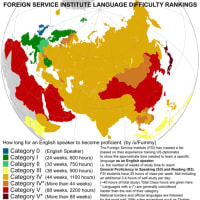




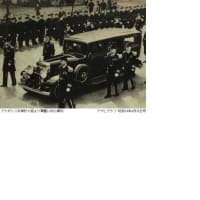
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます