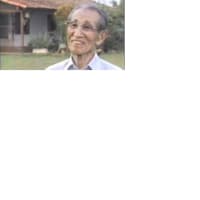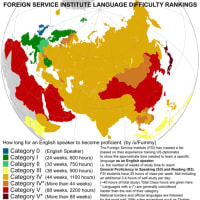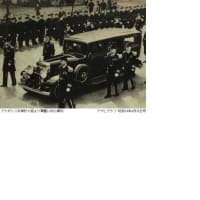福沢諭吉の愉快な英語修行 2 人間技と思えぬ写本の日々。しかし、の巻

一回目は、競争心溢れる適塾の様子を福沢さん自身に語っていただきました。ところで、今日の教育における競争とどう違うのでしょう。
競争というと、現代では「ゆとり」と対比して語られることが多いです。競争には、実力向上というメリットと同時に、競争の為の競争が非人間的だというマイナス面がある、一方、「ゆとり」は、生徒の人間性を育てるが、怠惰を呼ぶ。ざっとこういうメリット、デメリットを対立項として、同じようなことが繰り返し論じられています。しかし、「競争」ということの意味を十分吟味した上でのことでしょうか。前回の適塾における競争は、現代私たちが論じる競争と少し意味合いが違うようです。
競争が何をもたらすか、この適塾の描写は、現代、目標としている「平均点の向上」だけでは説明できないものがあるということを示唆しています。「正味の実力を養うと云うのが事実に行われて居た」、これは何を意味するでしょう。学力の現実を見失っていないということです。たんに他より優れるということではない、という点に注意を止める必要があります。現代の競争支持論者で、そのことを指摘するのを聞いたことがありません。この視点が失われたら、些末な点数争いを指摘するゆとり派のぶの方が高くなってしまいませんか。
 二点目として、この競争は一回限りのものではなく、始終、切磋琢磨するので、やり直しがきくということです。現代風に言えばフィードバックが仕組まれているということができるでしょう。この点も現代の競争対ゆとり論争に欠けがちな点です。試験結果が次回の試験へのインセンティヴになっているかどうか、まったく論じられることはありません。
二点目として、この競争は一回限りのものではなく、始終、切磋琢磨するので、やり直しがきくということです。現代風に言えばフィードバックが仕組まれているということができるでしょう。この点も現代の競争対ゆとり論争に欠けがちな点です。試験結果が次回の試験へのインセンティヴになっているかどうか、まったく論じられることはありません。
三点目としては、以上の、⓵現実を見つめる、⓶フィードバックになる、という二つの点を踏まえてのことですが、学生の学習意欲を高めているという点です。よく「やるき」なるものがよく口の端に上りますが、「やるき」がどこから生じるという議論も絶えて聞きません。
これだけ見ても、福沢の描写による適塾のあり方が現代の私たちに反省を迫るということが分かるというものです。ただ、最期に問題点も指摘したいと思います。適塾の場合、知識欲が高い集団だということが前提になっているということです。現代の教育論の場合、「全国一律」が暗黙の前提です。その違いを踏まえることを忘れるわけにはいきません。「なんとかに学ぼう」というよく言われる常套句をそのまま受け入れるわけにはいかないのです。
さて、適塾の勉学から英語学習へはまだ距離があります。今回、もう一つ適塾の特徴について触れましょう。これだけは現代では必要がなくなったことに疑いはありません。「写本」です。時折たのまれる写本は塾生にとっての収入源にもなりましたが、新知識を身に着けるためのまたとない機会でもありました。ある日、緒方先生が黒田の殿様から拝借してきたというオランダ語の書物を福沢に見せます。このあと、少々長いですが、福沢さんにじかに語っていただきましょう。
 (-----) なかんずくエレキトルの事が如何にもつまびらかに書いてあるように見える。私などが大阪で電気の事を知ったと云うのは、ただわずかに和蘭の学校読本の中にチラホラ論じてあるより以上は知らなかった。ところがこの新舶来の物理書は英国の大家フ
(-----) なかんずくエレキトルの事が如何にもつまびらかに書いてあるように見える。私などが大阪で電気の事を知ったと云うのは、ただわずかに和蘭の学校読本の中にチラホラ論じてあるより以上は知らなかった。ところがこの新舶来の物理書は英国の大家フ ラデーの電気説を土台にして、電池の構造法などがちゃんと出来て居るから、新奇とも何ともただ驚くばかりで、一見ただちに魂を奪われた。それから私は先生に向むかって、「これは誠に珍らしい原書でございますが、いつまでここに拝借して居ることが出来ましょうかと云うと、「左様(さよう)さ。何いずれ黒田侯は二晩とやら大阪に泊ると云う。御出立(しゅったつ)になるまでは、あちらに入用もあるまい。「左様でございますか、一寸と塾の者にも見せとう御在ますと云て、塾へ持って来て、「どうだ、この原書はと云ったら、塾中の書生は雲霞(うんか)のごとく集って一冊の本を見て居るから、私は二、三の先輩と相談して、何でもこの本を写して取ろうと云うことに一決して、「この原書をただ見たって何にも役に立たぬ。見ることはやめにして、サア写すのだ。しかし千頁もある大部の書を皆写すことはとても出来できられないから、末段のエレキトルの処だけ写そう。
ラデーの電気説を土台にして、電池の構造法などがちゃんと出来て居るから、新奇とも何ともただ驚くばかりで、一見ただちに魂を奪われた。それから私は先生に向むかって、「これは誠に珍らしい原書でございますが、いつまでここに拝借して居ることが出来ましょうかと云うと、「左様(さよう)さ。何いずれ黒田侯は二晩とやら大阪に泊ると云う。御出立(しゅったつ)になるまでは、あちらに入用もあるまい。「左様でございますか、一寸と塾の者にも見せとう御在ますと云て、塾へ持って来て、「どうだ、この原書はと云ったら、塾中の書生は雲霞(うんか)のごとく集って一冊の本を見て居るから、私は二、三の先輩と相談して、何でもこの本を写して取ろうと云うことに一決して、「この原書をただ見たって何にも役に立たぬ。見ることはやめにして、サア写すのだ。しかし千頁もある大部の書を皆写すことはとても出来できられないから、末段のエレキトルの処だけ写そう。
 一同みんな筆紙墨の用意して総がかりだと云た所でここに一つ困る事には、大切な黒田様の蔵書をこわすことが出来ない。毀(こわ)して手分わけて遣れば、三十人も五十人も居るからまたたく間に出来てしまうが、それは出来ない。けれども緒方の書生は原書の写本に慣れて妙(みょう)を得て居るから、一人ひとりが原書を読むと一人はこれを耳に聞いて写すことが出末る。ソコデ一人は読む、一人は写すとして、写す者が少し疲れて筆が鈍って来るとすぐにほかの者が交代して、その疲れた者は朝でも昼でもすぐに寝るとこういう仕組しくみにして、昼夜の別なく、飯を喰う間まもタバコを喫む間まも休まず、ちょいともひまなしに、およそ二夜三日(にやさんにち)のあいだに、エレキトルの処は申すに及ばず、図も写して読合わせまで出来てしまって、紙数は凡そ百五、六十枚もあったと思う。ソコデ出来ることならほかの処も写したいといったが時日が許さない。マア/\是これだけでも写したのは有難いというばかりで、先生の話に、黒田侯はこの一冊を八十両で買取られたと聞て、貧書生等はただ驚くのみ。もとより自分に買うと云う野心も起りはしない。いよいよ今夕、侯の御出立と定まり、私共はその原書を撫でくり廻まわし誠に親に暇乞いをするように別れを惜しんで還えしたことがございました。それからのちは塾中にエレキトルの説が全く面目を新たにして、当時の日本国中最上の点に達して居たと申して憚りません。岩波文庫p.90
一同みんな筆紙墨の用意して総がかりだと云た所でここに一つ困る事には、大切な黒田様の蔵書をこわすことが出来ない。毀(こわ)して手分わけて遣れば、三十人も五十人も居るからまたたく間に出来てしまうが、それは出来ない。けれども緒方の書生は原書の写本に慣れて妙(みょう)を得て居るから、一人ひとりが原書を読むと一人はこれを耳に聞いて写すことが出末る。ソコデ一人は読む、一人は写すとして、写す者が少し疲れて筆が鈍って来るとすぐにほかの者が交代して、その疲れた者は朝でも昼でもすぐに寝るとこういう仕組しくみにして、昼夜の別なく、飯を喰う間まもタバコを喫む間まも休まず、ちょいともひまなしに、およそ二夜三日(にやさんにち)のあいだに、エレキトルの処は申すに及ばず、図も写して読合わせまで出来てしまって、紙数は凡そ百五、六十枚もあったと思う。ソコデ出来ることならほかの処も写したいといったが時日が許さない。マア/\是これだけでも写したのは有難いというばかりで、先生の話に、黒田侯はこの一冊を八十両で買取られたと聞て、貧書生等はただ驚くのみ。もとより自分に買うと云う野心も起りはしない。いよいよ今夕、侯の御出立と定まり、私共はその原書を撫でくり廻まわし誠に親に暇乞いをするように別れを惜しんで還えしたことがございました。それからのちは塾中にエレキトルの説が全く面目を新たにして、当時の日本国中最上の点に達して居たと申して憚りません。岩波文庫p.90
現代では不要のことと申しましたが、ここにも今忘れられている大事なことが述べられていると思いませんか。試験と写本という二つの側面から適塾における「まじめ」な様子を垣間見ました。いよいよ次回は、何か問題が起きそうです。