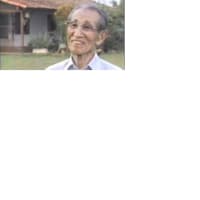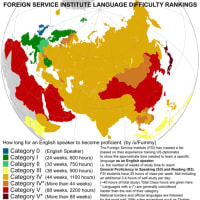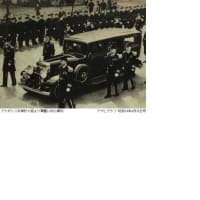対象から切り離した英語力って存在するの?。
「英語力」というものが、「握力」とか、「計算能力」のように単独の能力として存在するのか。そんな当たり前のことをなぜ問うのかと言われるでしょう。今回、問題にしたいのは大学入試の外部委託に関することです。切り離し、外部委託するということは、単独の英語力というものが存在することが前提です。もしそうでなかったら外部委託自体が疑わしいことになります。
でも、決まりかかっていることをなぜ改めて問うのかという声が聞こえますが、しかし、何か大切なことを忘れてはいませんか。言語は何かを対象として初めて存在するということです。何かを表わすために言語が使われるので、その「何か」、つまり言語の外のものに依存しているのが本質です。もしその「何か」と切り離せる言語能力があるとすれば、単独切り離しも多いに可能性があります。自動車や電子機器のようなものを作る大企業はそのような切り離しでスリム化を図り巨大化してまいりました。携帯自体は本体は本社がデザインするとしても、中のチップス、さらには半導体の高性能化を図る希少金属は他国の他企業との取引で手に入れます。その方が官僚主義に陥りやすい一体化よりずっと効率があがると信じられています。しかし、その会社の製品独自の特徴を生みさす技術はブラックボックスとして決して外注に出しません。果たして、英語能力は外注可能か、ブラックボックスなのか。
もし英語力が「切り離せる」ものなら社員教育用の検定試験でも、大学入試に用いることも可能でしょう。そこで、その「何か」をまず検討する必要があります。ところが、すでにして、この段階で人々はもう考えることをやめているように見えるのです。それほど、英語力という単独能力が存在することが当たり前に見なされているのですね。いや、もっとほんとうのことを言えば、大学入試などは、何か難しいもの、苦労して超える関門、バンジージャンプのような一種の成人儀礼のようなものだと思われているようで、中身などどうでもいいのでしょう。ただ「難しければよい」と。
こういう、世間の思い込みがもたらす障壁をよっこらしょと超えて、その「何か」を検討すれば、まず、以下の理由が浮上します。
大学での学業に耐える資格があるかどうか。それは英語で書かれた各学問分野 - dischipines - の著書を読む力があるかどうかが、問われます。理系、文系など細分化される学問分野を理解するために前提される「教養」と言われる文献を限られた時間に正確に読む力を持っているかどうか、これが大学入試の「英語力」の「何か」が何かというという問いへの一つの答えです。こうした前提に立つと、試験で読ませる文章の質、語彙、表現法にも一定の条件がありことが分かります。明快な論理、伝統と現代社会を理解する前提となる語彙、効果的なレトリックなど、これからの学習の発展の基礎になることが効果的に試験で問うことが目標となるでしょう。何より生徒の学習意欲を高めるものでなければなりません。なんでも英語であればよいというものではないです。通常の高校段階の英語と大学入試の英語の際立った違いはまさにここにあるのです。
そう考えると、アウトソーシングをする場合、そういう「何か」を外注先が備えているかどうかが問われなければならないのですが、それは十分検討されているかどうか。たんに世間で有名な試験だから、手を挙げてくれさえすれば採用しますよ、というのではないですか。簡単な社内文書の高速な読解を中心的な内容とするTOEICが初回のアウトソーシングから撤退した背景には、自社の問題が大学入試にふさわしくないのではという議論があったからではないかということも考えられます。一方、TOEFLについては、リーディングの内容が高校と大学を結ぶことを意識して巧妙に作られているので、その「何か」についてはかなり備えていると言えます。このようにアウトソーシング先すべてを頭ごなしに否定するわけにはいきません。(が、ほとんどの論者はTOEICやTOEFLの問題を実際に見て論じているのかどうかはなはだ疑問です。)
今回、言語、または言語能力が対象に依存するということに注目していただくことが第一の目的だったので、長くなる具体的な例文など使いませんでした。また、口頭や文章での表現能力をどう考えるかも不問でした。上記の、大学入試にふさしい英文の条件にも不備な点があることも触れていません(註)。昔と今の大学は違うとか、全国一律の議論は無意味だという意見も考えなければなりません。回を改めて、大学へ入る準備をしている学生はどう英語を学習すべきか、また、入った直後の英語教育はどうあるべきかにつながるエッセイを書きたいと思います。
註:リーディングの問題のみを中心に学習すると、音声との乖離、母国語の文法に影響されやすい点などの限界が生じます。たとえば、冠詞や複数形への感覚は養えない。また、英語特有の時制、助動詞の学習を無視するという欠陥があります。さらに深いことを言いましょう。リーディングだけだと、英語が、自分とは異なる他者の言語だということへの尊敬心、畏怖が生まれにくいという傾向を生み出しかねません。この件、再論します。