「エンジョイ イングリッシュ」に対する疑問
前回、次回は「他者の意識の薄さ」が、日本人が語学ベタである基本的原因であることに触れる予定であると書きましたが、それは次回に回し、それと同じように基本的で、重要なことを先にします。同じように抽象的ではありますが、少し外国語学習をしたことがある方のなかには、同じように感じる方がおられるかもしれません。
「レッツ エンジョイ イングリッシュ」とは英語教材の帯などによくみかける文字です。だれも、とくに意味がある表現だとは思わず、また、とくに変な表現だとも感じずに見過ごしているでしょう。この表現はおかしいということを指摘したのは、NHKの小学生向け英語番組『プレキソ』の最初の監修者である小泉清裕さんという方でした。
言語は、何であれ言語の外側にあるものを理解し、伝えるためにあるものだから、言語で何かを理解し、伝え、嬉しかったり、悲しかったりすることはあっても、言葉自体を愉しむ、ということは変ではないかとういう趣旨でした。
小泉さん編集の<旧>プレキソは、この考えに貫かれており、毎回テーマは、一見、語学の学習のテーマとはかけ離れているものが選ばれます。例えば色。たんに赤はred、青はblueというところに留まらず。アメリカのブルージーンズの工場で、「青」がどのように生まれるか、日本の伝統的な工房で「藍」色はどう染められるかを追っていきます。その過程で、たんに青=blueというだけで終わらない、言葉の裏に潜んでいるさまざまなことに興味を向けるのがねらいです。そのため、初心者レベルの英語以上の表現も学習者は耳にすることになりますが、対象に興味を持つことで、今は分からない英語も分かるようにしたいという気持ちが生まれることを監修者は期待しているのでしょう。必要最小限の英語表現だけで構成されるふつうの初級講座とこの点が違います。もしかして、1年だけで<旧>プレキソが終わってしまったのは、「分かり易い英語だけにしてほしい」という視聴者の声に負けてしまったのだったとしたら残念なことです。
語学学習が、言語の外側にあるもの、それは科学でも美的なものでも、政治でも、なんでもいいのですが、それらに導かれていないと、だんだんおかしなことになってしまいます。ただひたすら「語学のための語学」を勉強していると、無意識にそのむなしさが分かってきますから、「人よりTOEICなどの点数を上げよう」という競争心(程度問題です)の方が勝ってしまって、950点をとったとたんに、英語の勉強をしなくなってしまう、ということにもなりかねません。「英会話」というのも盲点です。相手に伝える、相手を理解するという言語の目的を忘れて、「英会話を楽しむ」、つまり「エンジョイ・イングリッシュ」が目的になってしまっている風景はよく見られます。外人講師もそのへんの事情は分かっていますから、おかしな馴れ合いのような空気が流れがちです。馴れ合い、つまり、お互い判った気になるのは、言語学習の趣旨とは逆の方向を向いた態度です。
そうならないようにするために、語学の先生や教材、カリキュラムの作成者が、<旧>プレキソ監修者のように、つねに、学習者の関心を「外」に向けるようにしくんでおくべきです。少なくとも、点数競争や、「英会話」をしていることの自己満足に陥らないように気をつけておかなければなりません。客観的な点数評価は社会が必要とするものなので、そのことだけに注意がいってしまいがちです。が、それだけに、点数に学習者が捉われないような工夫を講じるのは、緊喫の課題ではないとしても、いつまでの放置しておいてよい問題ではないと思います。
さて、習う側はどうすればよいか。登山中の人が、自分の位置や進むべき方向が分からないように、習っている人は、なかなか方法が分からないものです。何度も試行錯誤を重ねるしかないのかもしれません。「愉しみながら力がつけばいいではないか」くらいにしか考えていない人もいるでしょう。しかし、そのうちに詐欺まがいの教材販売にひっかかってたくさんお金を使ってしまう例はたくさん見てきました(できないのは習う側の問題だ、と言えばいいので、詐欺罪にはならないのですね)。そこで、教える側のアドヴァイスがやはり必要だと思います。近日中にアップロウドするコラム、『40年前の英語学習』でその問題に再び触れましょう。











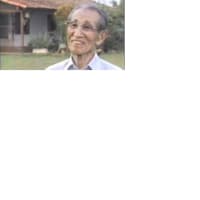
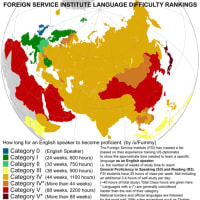




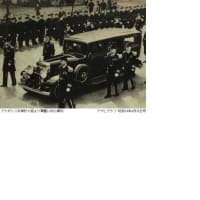
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます