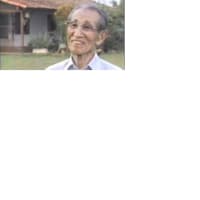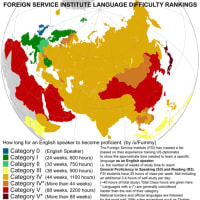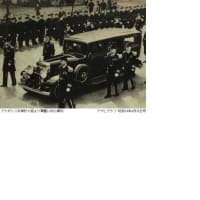アカデミズム、健在なり。木村汎さんの「受賞の言葉」から
木村さんは去る2019年11月14日にお亡くなりになりました。Rest In Peace
去る12月に、ロシア政治研究家の木村汎さんが産経新聞の『正論大賞』を受賞されて、「喜びの言葉」を産経新聞に寄せられていました。受賞の言葉というと、「過分のお褒めの言葉をいただいて」とか、「身が引き締まる思いで」などの決まりきった表現を連ねるのがふつうですが、木村さんの受賞の言葉には、そのような常套句は一切ありません。かといって、専門分野のロシア政治に関することもまったく述べられていません。そこには、専門分野を横断する学問の基本的技量、つまり、言葉を探求する人の述懐があったのです。
以下のサイトからはまもなく削除されてしまうので、要所、要所をコメント付でご紹介します。
http://www.sankei.com/column/news/161201/clm1612010006-n1.html
“正論”同人になるまでの私は、専ら一部の研究者相手に学術論文を書いていた。ところが、「産経新聞」の読者向けとなると、基本は変わらないとはいえ、その表現法に若干の工夫を凝らす必要があることを悟った。
学者、とりわけ「文系」に区分される学者は、世間では言葉のプロと見なされているのでしょうが、思いのほか、言葉への関心は薄いものです。なぜなら、同じ専門の人たちの間で、内輪の言葉を使っていればよいからです。「基本は変わらないとはいえ」という小さい部分に注目したいです。木村さんはたぶん専門家どうしの論文でも、言葉への関心は篤いのでしょう。ところが、新聞紙上に書くとなると、書き方が異なるという点を強烈に意識します。
活字が氾濫する中で己の文章に注目し、且(か)つ最後まで読み通していただくのは、至難の業である。例えばタイトル、そして小見出しの付け方が大きく作用する。「最近のロシアを巡る国際情勢」といった漠然かつ悠長な題の付け方では、多忙な現代人は洟(はな)もひっかけてくれない。
新聞に書くことの難しさと楽しさは、こんなふうに語られます。
文章の書き出しも、同様に重要。私は、司馬遼太郎氏の所謂(いわゆる)「自転車漕ぎ操法」を念頭におくことにした。書き出しは短く、だが滑らかに始める。次は、やや長い文章へと加速してゆく。もとより、いったん食いついた読者を途中で手放すのは、愚の骨頂。こう教えた米国のミリオンセラー作家スティーブン・キング、故ヒチコック監督による、次から次への「巻き込み手法」も参考になる。
自らに制限を課すという課題を楽しげに追求します。
現在、“正論”コラムは2千字という厳しい字数制限を敷いている。この字数では、学術論文とは異なり、先行研究や己の仮説を嫋嫋(じょうじょう)と説明する余裕などあるはずはない。
ここで、ハタと気がつきます。自己の自由にならない客体と格闘するというのは、学問そのものではないかと。専門に深入りすると、ややもすると「嫋嫋」たつ耽溺に気がつかないこともあります。木村さんは学問に対する基本的姿勢がしっかりしている人だな、と、言葉について述べているこの小論で分かりました。
上の引用に続いて、日々の心構えに触れます。
そうすれば、忽(たちま)ち読者諸賢兄姉から「結局、お前は何が言いたいのだ?」とのお叱りを頂戴すること必定。そのために、専門論文ですら漫然と書きはじめる怠惰な私が、“正論”用には手許(てもと)のメモ用紙に3つばかりの要点を記してから原稿用紙に向かう習慣をいつしか身につけることになった。
拓殖大学の前学長の渡辺利夫さんは、お祝いの言葉で、「『青年の生気』立ちのぼる碩学の文章」と、木村さんの文章を評しています。私は新聞紙上での木村さんの評論しか読んだことがありませんが、「青年の」という言葉に頷きます。たんに「気持ちが若い」という意味ではなく、言葉を正確に相手に伝えるという姿勢があるということです。権威に持たれて、分からない方が悪いという姿勢で、どこにでも書いてあるようなことを言う老大家とういものが多いものです。
言葉に対する厳しい態度は、どうも日本の大学ではだいぶ薄れているように思います。かつての旧帝大などから引き継がれたと思われる、この姿勢も、大学紛争の時代を経て、それを維持するだけの精神の余裕がなくなったからでしょうか。木下是雄さんの『理科系の作文技術』、『リポートの組み立て方』の二著は、この伝統が消えかかったころに、なんとか食い止めようという気持ちで書かれたものだと思います。大学側の書店では4月にはこの二つの書が平積みされます。が、じっさいこれらの書を読んで真髄を理解する人が多いかとういと、懐疑的にならざるを得ません。
そんなことを考えているときに、木村さんの文を読み、なるほど、日本も捨てたものではないなと思いました。言葉に対する厳しい態度、これは、アカデミズムと呼ぶべきでしょう。その言葉の元来の意味で。
■