今、料理メニューを中国語に翻訳する仕事をしている。
どんな分野でもそうなのだが「名前」を翻訳するにはかなり神経を使う。
定訳があるのか、なければどのように表記すべきかなど、ある一定のルールを
つくらなければ「何が何やら」わからなくなってしまう。
たとえば、私の大好物の「竹輪の磯部揚げ」を中国語にするとしたら、
(エキサイト翻訳では「竹圈的矶部油炸」。絶対ウソだよ!)
1)まず定訳をさがす。中華料理であれば話は簡単だが、もしなければ、
2)具体的な意味を考える。
例えば、「竹輪」これを中国語にすると「竹圈」となり、これでは「竹を食う」
ことになってしまう。これじゃパンダである。ちなみに「揚げる」は「炸」である。
とりあえず意味的には「魚のすり身を竹につけて焼いた輪状のもの」である。
しかも、「魚のすり身を竹につけて焼いた輪状のもの」を今度はあろうことか
青のりと小麦粉をまぶして、再び揚げるのだ。
3)それを踏まえた上で、「名詞化」する。
まさにオーマイガー!!である。
まあ、実際は私が翻訳するわけではなく、中国人のネイティブが翻訳するわけで、
そういう意味では、実に優秀な翻訳者で助かっている。
私は日本語のニュアンスを翻訳者に伝え、翻訳者があげてきたものが日本語の
意味を逸脱していないかをチェックする。不明な点があれば電話やメール等で
ニュアンスをつめてゆく、という実に緻密な作業だ。
以前、翻訳者に依頼した時に、「縁日のたこ焼き」という飲み屋のメニューで、
「縁日」の意味を翻訳者がとらえきれていないと思ったので、問いただしたら、
いわゆる「因縁の日のたこ焼き」という意味合いで訳していたことが判明した。
納品する前に気がついたからよかったものの、少し胆を冷やしたことがある。
因縁の日のたこ焼きとはなんぞや?
父を殺された因縁の日に仇討を胸に誓いながら食うたこ焼きはさぞしょっぱかろう。
それにしても、こういう作業はクリエイティブとは言えないまでも大変に面白いものだ。
ある言語を別の言語に置き換えることは、最後は「表現力」の勝負だと思うが、
原文を活かす誠実さとのバランスが重要で、うまい翻訳者はそれが絶妙なわけである。
まさに「原文に即しながら、しかもすーっと頭に入ってくる」。そういう翻訳。
話は全然ちがうが面白いといえば、
「アナゴ」のことを中国語では「星鰻」というのね。
たしかに、形はウナギとよく似ているのでWikiで調べてみたら、
ウナギ=ウナギ目ウナギ属
アナゴ=ウナギ目アナゴ科
なのだそうで、同じ種類っぽい。
それではなぜ「星」なのか?
ああいうニョロニョロのくせに、「星」とはあまりにロマンチック
ではないか…。
アナゴは夜行性なので「星」がついたのだと思ってウナギを調べると
やっぱり「夜行性」とある。
ちなみに、食用のアナゴは「アナゴ亜目ウミヘビ科」だそうだ。でもウミヘビとはまた
ちがう種類らしい。もう、種類が多すぎてわけがわからん。
あーもう、何が何だか…!?
まあ、今度中国人に聞いてみよう。
私の出身は北陸だが、実は「アナゴ」は上京するまで、食べたことも
見たこともなかった。

アナゴといえば、サザエさんの「アナゴさん」かと思っていた(笑)。
初めて食べた時、ウナギとは似て非なるものだとわかった。
やはりウナギは淡水魚だからか、と納得しかけたが、よく調べるとウナギは両方OKらしい。
生体は謎に包まれているらしいが、稚魚の時は深海にいるらしい。
アナゴのお寿司は有名だが、ウナギのお寿司というのもある(少なくとも私の地元では)。
しかしウナギの天ぷらは見たことがない。ただ蒲焼は両方あるぞ。
カレイとヒラメが顔の向きだけでなく、料理法が異なっていることと同じことか。
翻訳同様、料理も奥がふかいなー。

写真は観賞魚として人気がある「チンアナゴ」。
かわいいなー。
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト
どんな分野でもそうなのだが「名前」を翻訳するにはかなり神経を使う。
定訳があるのか、なければどのように表記すべきかなど、ある一定のルールを
つくらなければ「何が何やら」わからなくなってしまう。
たとえば、私の大好物の「竹輪の磯部揚げ」を中国語にするとしたら、
(エキサイト翻訳では「竹圈的矶部油炸」。絶対ウソだよ!)
1)まず定訳をさがす。中華料理であれば話は簡単だが、もしなければ、
2)具体的な意味を考える。
例えば、「竹輪」これを中国語にすると「竹圈」となり、これでは「竹を食う」
ことになってしまう。これじゃパンダである。ちなみに「揚げる」は「炸」である。
とりあえず意味的には「魚のすり身を竹につけて焼いた輪状のもの」である。
しかも、「魚のすり身を竹につけて焼いた輪状のもの」を今度はあろうことか
青のりと小麦粉をまぶして、再び揚げるのだ。
3)それを踏まえた上で、「名詞化」する。
まさにオーマイガー!!である。
まあ、実際は私が翻訳するわけではなく、中国人のネイティブが翻訳するわけで、
そういう意味では、実に優秀な翻訳者で助かっている。
私は日本語のニュアンスを翻訳者に伝え、翻訳者があげてきたものが日本語の
意味を逸脱していないかをチェックする。不明な点があれば電話やメール等で
ニュアンスをつめてゆく、という実に緻密な作業だ。
以前、翻訳者に依頼した時に、「縁日のたこ焼き」という飲み屋のメニューで、
「縁日」の意味を翻訳者がとらえきれていないと思ったので、問いただしたら、
いわゆる「因縁の日のたこ焼き」という意味合いで訳していたことが判明した。
納品する前に気がついたからよかったものの、少し胆を冷やしたことがある。
因縁の日のたこ焼きとはなんぞや?
父を殺された因縁の日に仇討を胸に誓いながら食うたこ焼きはさぞしょっぱかろう。
それにしても、こういう作業はクリエイティブとは言えないまでも大変に面白いものだ。
ある言語を別の言語に置き換えることは、最後は「表現力」の勝負だと思うが、
原文を活かす誠実さとのバランスが重要で、うまい翻訳者はそれが絶妙なわけである。
まさに「原文に即しながら、しかもすーっと頭に入ってくる」。そういう翻訳。
話は全然ちがうが面白いといえば、
「アナゴ」のことを中国語では「星鰻」というのね。
たしかに、形はウナギとよく似ているのでWikiで調べてみたら、
ウナギ=ウナギ目ウナギ属
アナゴ=ウナギ目アナゴ科
なのだそうで、同じ種類っぽい。
それではなぜ「星」なのか?
ああいうニョロニョロのくせに、「星」とはあまりにロマンチック
ではないか…。
アナゴは夜行性なので「星」がついたのだと思ってウナギを調べると
やっぱり「夜行性」とある。
ちなみに、食用のアナゴは「アナゴ亜目ウミヘビ科」だそうだ。でもウミヘビとはまた
ちがう種類らしい。もう、種類が多すぎてわけがわからん。
あーもう、何が何だか…!?
まあ、今度中国人に聞いてみよう。
私の出身は北陸だが、実は「アナゴ」は上京するまで、食べたことも
見たこともなかった。

アナゴといえば、サザエさんの「アナゴさん」かと思っていた(笑)。
初めて食べた時、ウナギとは似て非なるものだとわかった。
やはりウナギは淡水魚だからか、と納得しかけたが、よく調べるとウナギは両方OKらしい。
生体は謎に包まれているらしいが、稚魚の時は深海にいるらしい。
アナゴのお寿司は有名だが、ウナギのお寿司というのもある(少なくとも私の地元では)。
しかしウナギの天ぷらは見たことがない。ただ蒲焼は両方あるぞ。
カレイとヒラメが顔の向きだけでなく、料理法が異なっていることと同じことか。
翻訳同様、料理も奥がふかいなー。

写真は観賞魚として人気がある「チンアナゴ」。
かわいいなー。
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト












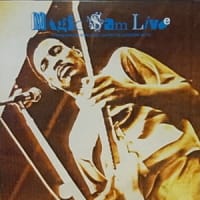
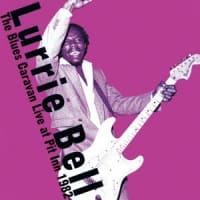




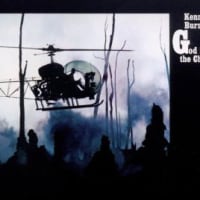
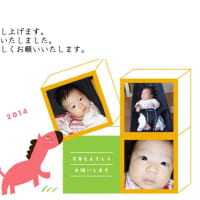
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます