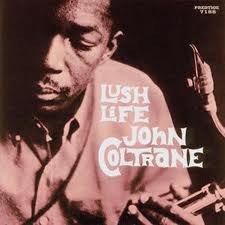このブログの読者の方で「EFT」という言葉を耳にされた方は
おそらくいないと思う。
EFTとは、Emotional Freedom Techniqueのことで、
ロジャー・キャラハン博士によって考案されたTFT、
Thought Field Therapy(思考場療法)をより簡素化した方法である。
キャラハン氏が水恐怖症で水をさわることすらできない女性の眼の下のツボを
刺激したところ、恐怖症はおさまり、なんとプールで遊びだしたという
劇的な経験をもとに研究をかさね、創られたものだ。
TFTがキャラハン氏のように精神科医の専門家が行うものであるのに
対して、キャラハン氏のもとで学んだゲアリー・クレイグ(Gary Craig)
が、より簡単に行える方法を研究し、1996年に開発したものだ。
いずれも、ツボをタッピングすることで、体のエネルギー(磁場のようなもの)
を整えて、メンタルな要素を癒し、改善してゆくものだが、TFTは診断によって
タッピングの方法が異なるなど複雑な体系をもっていたのに対し、
EFTは診断しなくとも、誰もが簡単に行える。それによってEFTは世界中に
普及していったのだといえる。
こうした肉体と精神の相関性に着目している点が気功などと似ている気もするし
大変興味深いのだが、私は専門家ではないし、詳しい話はできない。
私が興味をもったのは、「精神というとらえどころないものを特定し、
改善してゆくプロセスの本質的なところ」である。
何度もいうが、私は専門家ではないし、たぶんに独断的、個人的印象を
述べているにすぎないので、ここらで語り口をかえよう(笑)。
ぶっちゃけていえば(いきなりくだけすぎじゃい!)それは、
「心の解放」
だと思う。そう考えると世に出まわる様々な「癒し系の本」のプロセスと
符合する(あくまで私の印象だよん。)
だから「本質的なところ」と書いた。
人は様々なレベルで「判断」する。
正しいとか間違っているとか、
こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない(同じことやろ!)
なんかムカつくとか、あれが好きだ、これが嫌いだ、
どうも苦手だ…、とか。
そうした概念が心のタガとなり、自分をしめつけ、自分を観念の牢獄に
とじこめ、時には良心の呵責をうみだす。
それらをひとつひとつ取り払っていく。決して自分の心の奥底にしまい
込んでしまうのではなく、受け入れ、リリースするのだ。

『すべての望みを引き寄せる法則―夢を叶えるタッピング』(ブレンダ)
この本は、上記のEFTの技法と願望実現(引き寄せ)をミックスした本だ。
非常に欲張りな本ではあるがこれらのミックスは私にはうなづける。
願望は固執すればするほど叶わない、というのが私の持論だからである。
願望への固執はいうなれば精神的(感情的)な病気のようなものだ。
上記の本では、
ネガティブからポジティブへのリマインダー・フレーズというのが用いられる
のだが、そのネガポジ変換プロセスのキーワードが「ネガな自分(感情)を受け入れる」
だと思う。
これまた、ぶっちゃけトークで、「いいじゃん」ってこと。
あいつがゆるせない(いいじゃん)
あいつがゆるせないという自分がゆるせない(いいじゃん)
あいつがゆるせないという自分がゆるせないという自分がゆるせない(……笑)
まあ、様々な技法があっておもしろい。
というわけで今日は最近のマイ・ブーム(「いいじゃんゲーム」)について
書いてみた。
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト
おそらくいないと思う。
EFTとは、Emotional Freedom Techniqueのことで、
ロジャー・キャラハン博士によって考案されたTFT、
Thought Field Therapy(思考場療法)をより簡素化した方法である。
キャラハン氏が水恐怖症で水をさわることすらできない女性の眼の下のツボを
刺激したところ、恐怖症はおさまり、なんとプールで遊びだしたという
劇的な経験をもとに研究をかさね、創られたものだ。
TFTがキャラハン氏のように精神科医の専門家が行うものであるのに
対して、キャラハン氏のもとで学んだゲアリー・クレイグ(Gary Craig)
が、より簡単に行える方法を研究し、1996年に開発したものだ。
いずれも、ツボをタッピングすることで、体のエネルギー(磁場のようなもの)
を整えて、メンタルな要素を癒し、改善してゆくものだが、TFTは診断によって
タッピングの方法が異なるなど複雑な体系をもっていたのに対し、
EFTは診断しなくとも、誰もが簡単に行える。それによってEFTは世界中に
普及していったのだといえる。
こうした肉体と精神の相関性に着目している点が気功などと似ている気もするし
大変興味深いのだが、私は専門家ではないし、詳しい話はできない。
私が興味をもったのは、「精神というとらえどころないものを特定し、
改善してゆくプロセスの本質的なところ」である。
何度もいうが、私は専門家ではないし、たぶんに独断的、個人的印象を
述べているにすぎないので、ここらで語り口をかえよう(笑)。
ぶっちゃけていえば(いきなりくだけすぎじゃい!)それは、
「心の解放」
だと思う。そう考えると世に出まわる様々な「癒し系の本」のプロセスと
符合する(あくまで私の印象だよん。)
だから「本質的なところ」と書いた。
人は様々なレベルで「判断」する。
正しいとか間違っているとか、
こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない(同じことやろ!)
なんかムカつくとか、あれが好きだ、これが嫌いだ、
どうも苦手だ…、とか。
そうした概念が心のタガとなり、自分をしめつけ、自分を観念の牢獄に
とじこめ、時には良心の呵責をうみだす。
それらをひとつひとつ取り払っていく。決して自分の心の奥底にしまい
込んでしまうのではなく、受け入れ、リリースするのだ。

『すべての望みを引き寄せる法則―夢を叶えるタッピング』(ブレンダ)
この本は、上記のEFTの技法と願望実現(引き寄せ)をミックスした本だ。
非常に欲張りな本ではあるがこれらのミックスは私にはうなづける。
願望は固執すればするほど叶わない、というのが私の持論だからである。
願望への固執はいうなれば精神的(感情的)な病気のようなものだ。
上記の本では、
ネガティブからポジティブへのリマインダー・フレーズというのが用いられる
のだが、そのネガポジ変換プロセスのキーワードが「ネガな自分(感情)を受け入れる」
だと思う。
これまた、ぶっちゃけトークで、「いいじゃん」ってこと。
あいつがゆるせない(いいじゃん)
あいつがゆるせないという自分がゆるせない(いいじゃん)
あいつがゆるせないという自分がゆるせないという自分がゆるせない(……笑)
まあ、様々な技法があっておもしろい。
というわけで今日は最近のマイ・ブーム(「いいじゃんゲーム」)について
書いてみた。
翻訳会社オー・エム・ティの公式ウェブサイト