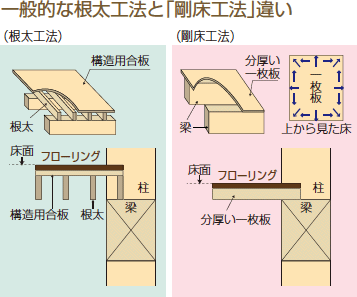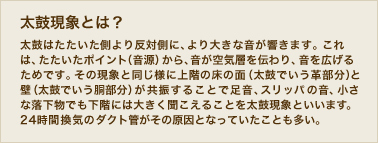7.2.4chのマルチチャネルにもなると、配線も多く長くなるし、無計画にはできない。
屋内工事はまだまだ先だが、施主支給品をそろそろ調達しておきたいと思い、施主セレクトのケーブルを購入した。

業務用スピーカーケーブルのカナレ4S8の100m巻き。150円/mの低価格品だが、長尺使うのでコスパ重視のものにした。70円/mの4S6にしなかったのは、少しだけ贅沢したいという気持ちの表れ。ゾノトーンとかホームオーディオ用のケーブルを使いたい気もしたけど、過剰なコストはつぎ込まないことにした。
長尺のRCAケーブルを使うので、これは引き渡し後が終わってからの使用だが、送料節約の関係で一緒に注文した。カナレのGS-6(同軸ケーブル)とF-09(RCAプラグ)。既製品は5mを越えるとちょうど良い長さが売っていなかったりするので自作することにした。
ステレオシステムはグレード重視だけど、シアターは主要コンポーネント以外はコストパフォーマンス重視の方向がコンセプトになりつつあります。
屋内工事はまだまだ先だが、施主支給品をそろそろ調達しておきたいと思い、施主セレクトのケーブルを購入した。

業務用スピーカーケーブルのカナレ4S8の100m巻き。150円/mの低価格品だが、長尺使うのでコスパ重視のものにした。70円/mの4S6にしなかったのは、少しだけ贅沢したいという気持ちの表れ。ゾノトーンとかホームオーディオ用のケーブルを使いたい気もしたけど、過剰なコストはつぎ込まないことにした。
長尺のRCAケーブルを使うので、これは引き渡し後が終わってからの使用だが、送料節約の関係で一緒に注文した。カナレのGS-6(同軸ケーブル)とF-09(RCAプラグ)。既製品は5mを越えるとちょうど良い長さが売っていなかったりするので自作することにした。
ステレオシステムはグレード重視だけど、シアターは主要コンポーネント以外はコストパフォーマンス重視の方向がコンセプトになりつつあります。