石井式リスニングルームで推奨されている床構造は
ベタ基礎の土間コンクリート床に直接コンパネを敷き、フローリングを貼る構造である。

これはフローリングがコンクリート床と完全に連結することで共振を起こりにくくすることを目的としたものであるようだ。
確かにこういう構造にすることで床は強固になるし、根太や束などを使わないのでローコストでもある。
ただ、コンクリートは硬化後長期間にわたり空気中に湿気を放出する性質があり、この構造だと土間コンクリート床とコンパネの間の湿気の逃げ場がなく、結露とカビの原因になってしまう。現に同じ構造の床がカビ臭くなったという報告もネットで見かける。
音質的に好ましいことを追求したいところではあるが、他のすべてを犠牲にして音質を追求するほどの熱心さは自分にはない。あえて欠陥になりそうな構造を採用するわけにもいかないのが本心だ。
また、床下に配管ができないのも不便である。
サーロジックでは半間間隔で布基礎を作り、根太-コンパネ-根太-フローリングと載せていく方法を推奨している。

これだと床の強さがある程度保たれ、床下を通気させることはできるが、正直大がかりすぎて、ここまでやるのは個人的には厳しい。
ハウスメーカーとも相談して、結局ベタ基礎にプラ束を間隔狭めに配置して、床下に吸音材を充填させた乾式二重床にしようと考えている。プラ束は遮音性能の低い、安物の方がいい。遮音を備えた製品は防音ゴムが介在されており、床が軟らかくなってしまう。間隔を狭く配置することで共振が起きにくい高域に共振周波数を追いやることができるだろうと考えている。
湿気対策としてはコンパネとコンパネの間にあえて隙間を作り、部屋の空気と床下の空気が交通するようにすることで床下だけ湿度が高い状態を作らないようにする。
根太は木製だから結露やカビ、白アリに弱く、スチール束は結露に弱いのでプラスチックがコストや耐食性の面でベターとは考えている。
サーロジックではプラ束は緩い床でブーミーになるとの記載があるが、束を多めに配置し、床下にグラスウールを充填した床構造は石井式リスニングルームの壁構造に開口部をなくした状態と似ており、壁構造と同程度の硬さの床と考えれば、そんなに悪影響があるように思えない。

実際に石井先生が直接設計したリスニングルームにもプラ束の使用実績があり、コストとの兼ね合いも考えると、間違った選択はしていないのだと思いたい。
http://www.tsukasa-sk.com/tadaimasinkoutyu/tadaima_08AS/tadaima_08AS_09.html
そんな感じで下から、土間コン-プラ木レン10cm丈30cm間隔配置(隙間にグラスウール32K充填)-コンパネ-フローリングで構成された床構造にする予定でいる。音響的にうまくいってくれるかは実際やってみないとわからないが、良い結果になることを願っている。
ベタ基礎の土間コンクリート床に直接コンパネを敷き、フローリングを貼る構造である。

これはフローリングがコンクリート床と完全に連結することで共振を起こりにくくすることを目的としたものであるようだ。
確かにこういう構造にすることで床は強固になるし、根太や束などを使わないのでローコストでもある。
ただ、コンクリートは硬化後長期間にわたり空気中に湿気を放出する性質があり、この構造だと土間コンクリート床とコンパネの間の湿気の逃げ場がなく、結露とカビの原因になってしまう。現に同じ構造の床がカビ臭くなったという報告もネットで見かける。
音質的に好ましいことを追求したいところではあるが、他のすべてを犠牲にして音質を追求するほどの熱心さは自分にはない。あえて欠陥になりそうな構造を採用するわけにもいかないのが本心だ。
また、床下に配管ができないのも不便である。
サーロジックでは半間間隔で布基礎を作り、根太-コンパネ-根太-フローリングと載せていく方法を推奨している。
これだと床の強さがある程度保たれ、床下を通気させることはできるが、正直大がかりすぎて、ここまでやるのは個人的には厳しい。
ハウスメーカーとも相談して、結局ベタ基礎にプラ束を間隔狭めに配置して、床下に吸音材を充填させた乾式二重床にしようと考えている。プラ束は遮音性能の低い、安物の方がいい。遮音を備えた製品は防音ゴムが介在されており、床が軟らかくなってしまう。間隔を狭く配置することで共振が起きにくい高域に共振周波数を追いやることができるだろうと考えている。
湿気対策としてはコンパネとコンパネの間にあえて隙間を作り、部屋の空気と床下の空気が交通するようにすることで床下だけ湿度が高い状態を作らないようにする。
根太は木製だから結露やカビ、白アリに弱く、スチール束は結露に弱いのでプラスチックがコストや耐食性の面でベターとは考えている。
サーロジックではプラ束は緩い床でブーミーになるとの記載があるが、束を多めに配置し、床下にグラスウールを充填した床構造は石井式リスニングルームの壁構造に開口部をなくした状態と似ており、壁構造と同程度の硬さの床と考えれば、そんなに悪影響があるように思えない。

実際に石井先生が直接設計したリスニングルームにもプラ束の使用実績があり、コストとの兼ね合いも考えると、間違った選択はしていないのだと思いたい。
http://www.tsukasa-sk.com/tadaimasinkoutyu/tadaima_08AS/tadaima_08AS_09.html
そんな感じで下から、土間コン-プラ木レン10cm丈30cm間隔配置(隙間にグラスウール32K充填)-コンパネ-フローリングで構成された床構造にする予定でいる。音響的にうまくいってくれるかは実際やってみないとわからないが、良い結果になることを願っている。

















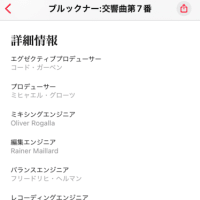

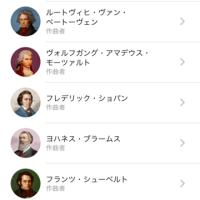







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます