
https://www.star-ch.jp/starchannel-movies/detail_048.php

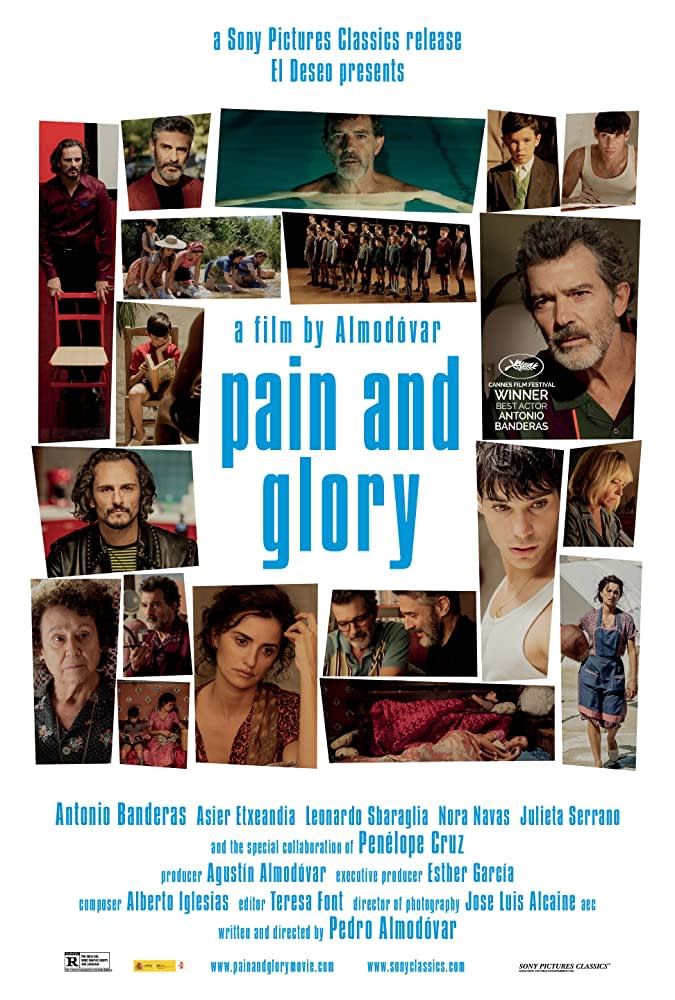
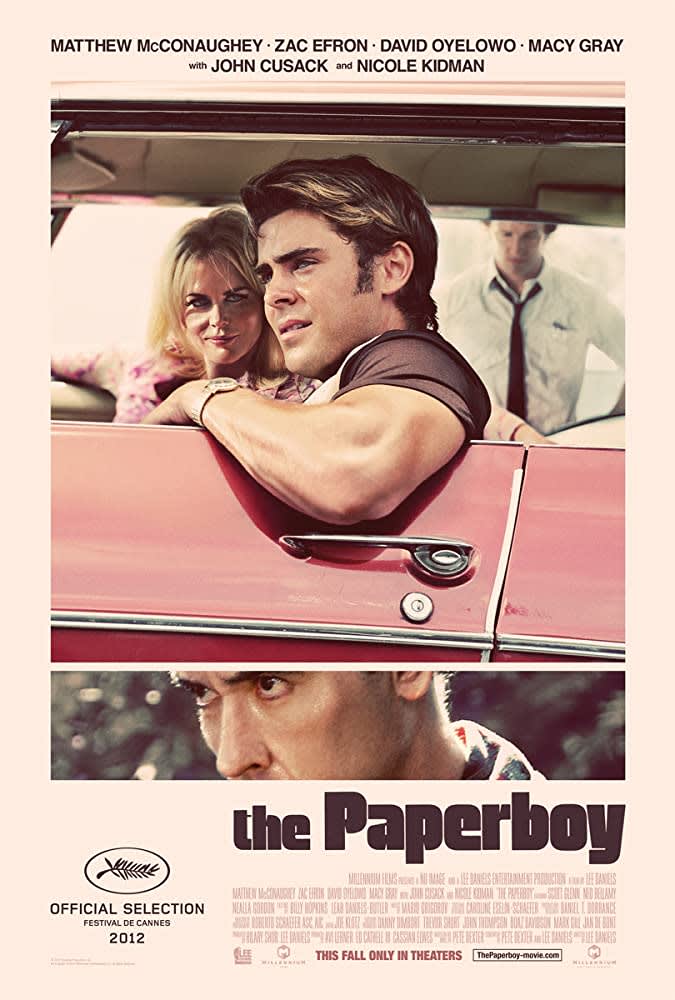

珠玉の名作『ギルバート・グレイプ』脚本や『エイプリルの七面鳥』監督で知られるピーター・ヘッジズの最新作。突然の息子の帰還によるクリスマスの騒動が描かれる。前述2作のイメージが強いせいかハートウォーミングな映画を想像していたが、テーマに見合った過酷な映画であった。
長男ベンが帰ってきた。薬物中毒の更生施設に入って3か月弱、予定にない帰宅だった。家族は戸惑いと嫌悪を隠せない。ヘッジズは名脚本家らしく多くの説明を排し、ディテールの積み重ねで背景を描き出していく。医療用の準麻薬から薬物中毒に陥ったこと、ドラッグディーラーになったこと、そして恋人をオーバードーズで殺したこと…ベンの帰還は家族に負の歴史を思い出させる。彼を支えるのは母ただ一人だ。
母親役はジュリア・ロバーツ。息子から薬物を断つためならあらゆる手段を取る優しさと厳しさをパワフルに演じる。年齢のもたらす深みと作品選択眼が近年『ワンダー』『ホームカミング』という秀作に結実し、若い頃にはなかった充実期にあると言っていいだろう。ベンを演じるルーカス・ヘッジズも好演。なんとピーター・ヘッジズ監督の実息というではないか。
映画は薬物問題が家庭内に留まらず、コミュニティの問題である事に目を向けている。舞台となる田舎町の大きさに対して薬物依存症の数は多く(この実態についてはドキュメンタリー『ヘロイン×ヒロイン』がサブテキストになるだろう)、一度町外れに足を運べばスラムがあり、ホームレスがいて、ジャンキーの溜まり場がある。この映画もまた辺境からアメリカを描いた映画であり、ヘッジズの筆致がこれまでになく厳しいのも困難な時代を見据えた覚悟ゆえなのだ。そして母子の本当の闘いは映画が終わってから始まるのである。
『ベン・イズ・バック』18・米
監督 ピーター・ヘッジズ
出演 ジュリア・ロバーツ、ルーカス・ヘッジズ、キャスリン・ニュートン、コートニー・B・ヴァンス

古今東西、ホラー映画は異性、セックス、出産、子育て、ネグレクト等々あらゆる恐怖のメタファーとなってきた。本作のそれはズバリ“家族であること”だ。逃れようのない血縁という呪いに悩まされた事がある人はこの映画がもたらすストレスは耐え難いかも知れない。そんな不和がなかったとしても新鋭アリ・アスター監督の洗練された演出によって神経衰弱ぎりぎりの恐怖を味わわされる事は必至だ。不穏なコリン・ステットソンの前衛的スコアを背に、ミヒャエル・ハネケの冷徹さとロマン・ポランスキーの厭世、強迫観念を併せ持ったかのようなアスターの演出力は並外れている。
祖母の葬儀から映画は始まる。生前、多くを語る事がなかった彼女だが、娘のアニー(トニ・コレット)はそんな母の“人を操る”気質に気付いており、夫や子供たちに干渉しないよう細心の注意を払っていた。だが、唯一のおばあちゃん子だった末娘チャーリーの様子がおかしい。やがて一家を怖ろしい事件が襲う…。
おっと、ここまで。
『ヘレディタリー』はぜひ一切の事前情報を断って見てもらいたい。前半約20分地点で起きるショックをきっかけに映画は全く先の読めない奈落へと転がり出す。アスター監督はこけおどしの恐怖演出を徹底排除し、俳優のリアクションを重視した演出で観客の想像力を煽って恐怖感を高めている。それに応えて俳優陣は皆、素晴らしい演技だ。コレットの神経症演技はいわゆるジャンル映画の域を超えた名演。長男役アレックス・ウォルフは同世代俳優とは一線を画すブレイクスルーであり、妹ミリー・シャピロは映画史に残るホラーアイコンとなった。アン・ダウドが手練れた怪演を見せるおせっかいな隣人ジョーンが出てくれば、僕らの脳裏にはポランスキーの初期傑作『ローズマリーの赤ちゃん』がよぎり…これくらいにしておこう。昨年、同じくA24からデビューした『ウィッチ』ロバート・エガース監督同様、アスターも抜群に耳が良く、右後方から聞こえてくる“ある音”には身の毛がよだった。この抜群の音響設定はぜひとも劇場で確かめてもらいたい。
興味深い事に本作はアスター監督の身に起きたある実体験が基になっているという。劇中、アニーが行うミニチュア作りの“箱庭療法”は本作撮影と同義だったのかも知れない。そんな視点から見るとしがらみから解放されたかのようなラストシーンにはハッピーエンドとも思える祝祭感があった。
『ヘレディタリー 継承』18・米
監督 アリ・アスター
出演 トニ・コレット、ガブリエル・バーン、アレックス・ウォルフ、ミリー・シャピロ、アン・ダウド