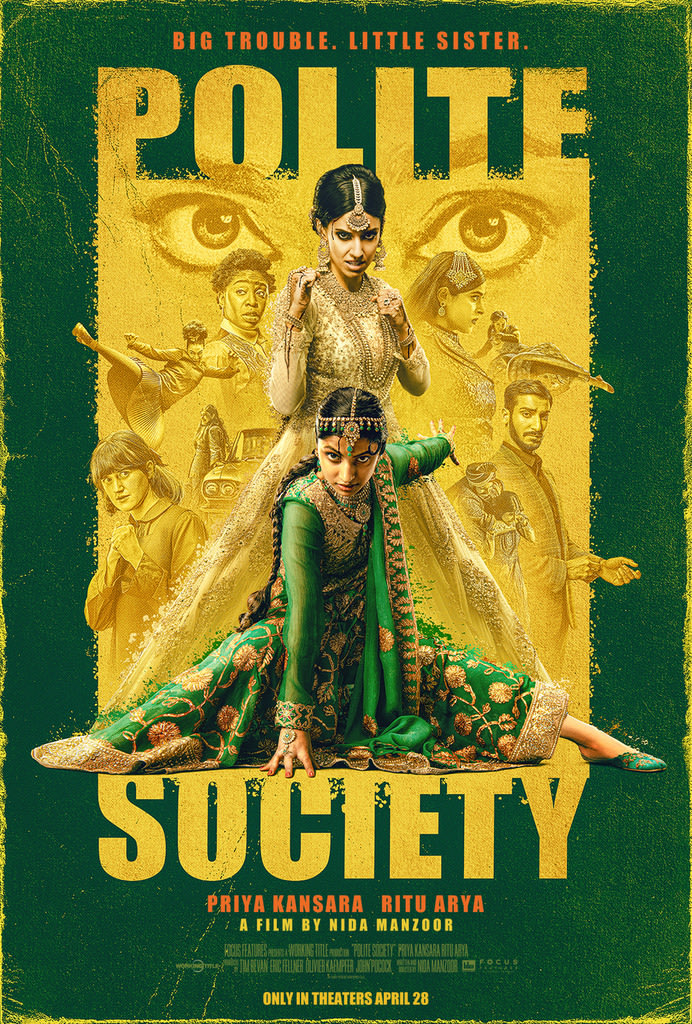「過去が現在(いま)を作る」とは歴史教師ポール・ハナムの言葉だ。慇懃でウンチクが大好きな彼はおまけに体臭もキツく、同僚からも生徒からも嫌われている。そして演じるのはポール・ジアマッティだ。こんな人物が映画の主人公になり得るのか?スーパーヒーローばかりが立ち並ぶ現在のハリウッドでは難しいかも知れないが、本作の舞台となる1970〜71年は複雑な人物を描いた映画ばかりだった。『BIRDSHIT』『ハズバンズ』『ラスト・ショー』『ダーティ・ハリー』『わらの犬』…アレクサンダー・ペイン監督は冒頭、70年当時のユニバーサルのロゴやオープニングクレジットを出し、画面にスクラッチまで付ける手の込みようだが、これは単なる懐古趣味ではない。アメリカ映画が見失いかけている人間洞察への回帰だ。
クリスマス、全寮制の名門校では多くの生徒が家族のもとへ戻る中、様々な理由から帰省が叶わない子供たちが校内に残る。今年の監督役はハナム先生で、居残り組には犬猿の仲とも言うべき問題児アンガスの姿もある。それにベトナム戦争で息子を亡くしたばかりの料理長メアリーも一緒だ。
安易な共感を呼ばない人物ばかりである。ハナム先生はじめ、アンガスもメアリーも複雑な人生を送ってきたが、常に人間への興味を失っておらず、憎まれ口を叩きながら他者との繋がりを求めている節がある。ジアマッティの名人級の人格造形、オスカー受賞のダヴァイン・ジョイ・ランドルフに加え、実質上の主演である新人ドミニク・セッサの軽妙かつ繊細な演技が光る。2023〜2024年は『パストライブス』『チャレンジャーズ』『ツイスターズ』と三すくみを成すことで調和する人間の姿が描かれてきたが、本作もまたその系譜に連なり、アンサンブルは2023年最高のそれである。
2週間のホリデイを共にするうちに、ハナムはアンガスにかつての自分の姿を見出す。怒りを覚え、しかし脆い心を抱えていたあの頃だ。いかなる歴史も現在(いま)を形作っているのなら、アンガスとの対話はかつての自分との邂逅であり、ハナムもまた自身の現在を知るのである。2人は「またな」と言葉を交わして別れるが、おそらく再会することはないだろう。だが30年、40年を経てアンガスはかつての自分のような少年に出会った時、ハナム先生から得た生きる術を伝えるのだ。その時、2人は“再会”を果たすことだろう。
『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』23・米
監督 アレクサンダー・ペイン
出演 ポール・ジアマッティ、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ、ドミニク・セッサ、キャリー・プレストン