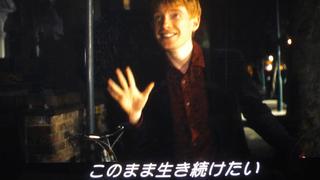2012年:米。 監督:ノア・バームバック。 WOWOWからの録画。
HIVI誌上(堀切日出晴氏)にて推されていたようなので観てみました。
通常娯楽要素の強いアメリカ映画には似ず、ちょっと文芸の匂いのする作品でした。

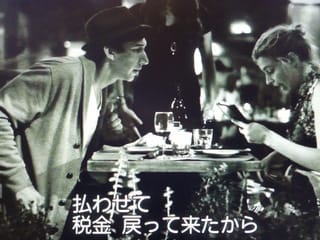
大親友のソフィー㊧と。 臨時収入で気が大きくなるフランシス。
これはプロダンサーを目指す一人の若い女性の”悪戦苦闘”の物語。
ダンス学校を卒業して、今は某ダンスカンパニーの実習生として毎日を送っているフランシス。
目下のところダンスは収入にはならず、アルバイトで生活している。
ルームメイトのソフィーとは大親友。他にも若者らしく色々と友人知人は多い。
近くカンパニーでは大きなツァーが行われるが、何とかそのスタッフとして選ばれたいと思っている。


当てにしていたツァーには参加できずガッカリ。 ソフィーには婚約者ができたようだ。
しかし現実は厳しい。フランシスはツァーには参加できず無収入の身となってしまう。
大親友ソフィーとの仲も、彼女にフィアンセができて以来、微妙な空気が漂いはじめる。
アパート代もなく知人の部屋に転がり込むが、そこはやはり他人。そうそう好意には甘えられない。
考えた結果、一時的に郷里に戻ることにする。


金も住む所もなく一時郷里に帰る。 パリにやってきたが夕方まで眠りこける。
なけなしのお金で気まぐれにやってきたパリ。大半はベッドで眠りこけていただけだった(^^;
なんというお金のムダ使い。いまさら後悔しても仕方がないが。


劇団の事務員に空きがあると言われ....。 母校のスタジオでの練習を断られる。
カンパニーからは事務員の空きがあるからやってみないかと誘われるが、
さすがに今さら事務員に甘んじるのは屈辱感が大きすぎる。
断ってしまうのだが、さりとて生活はしていかなければならない。
見つけた働き口は、母校のダンススクールの学生寮の管理人。
どっちにしても大差はないようだが、これは気持ちの問題だろう。
まさにこれはフランシスの悪戦苦闘の記。
最後は、彼女の思わぬ方向でのハーフ・ハッピーエンド。
まあこのくらいでストーリーが収束するならば、現実には上々の部類なんじゃないかなと。
人生なかなか思い通りにはならないが、そんなに捨てたものでもない。
そんなメッセージがこめられた映画のようです。
HIVI誌上(堀切日出晴氏)にて推されていたようなので観てみました。
通常娯楽要素の強いアメリカ映画には似ず、ちょっと文芸の匂いのする作品でした。

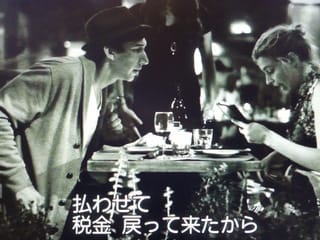
大親友のソフィー㊧と。 臨時収入で気が大きくなるフランシス。
これはプロダンサーを目指す一人の若い女性の”悪戦苦闘”の物語。
ダンス学校を卒業して、今は某ダンスカンパニーの実習生として毎日を送っているフランシス。
目下のところダンスは収入にはならず、アルバイトで生活している。
ルームメイトのソフィーとは大親友。他にも若者らしく色々と友人知人は多い。
近くカンパニーでは大きなツァーが行われるが、何とかそのスタッフとして選ばれたいと思っている。


当てにしていたツァーには参加できずガッカリ。 ソフィーには婚約者ができたようだ。
しかし現実は厳しい。フランシスはツァーには参加できず無収入の身となってしまう。
大親友ソフィーとの仲も、彼女にフィアンセができて以来、微妙な空気が漂いはじめる。
アパート代もなく知人の部屋に転がり込むが、そこはやはり他人。そうそう好意には甘えられない。
考えた結果、一時的に郷里に戻ることにする。


金も住む所もなく一時郷里に帰る。 パリにやってきたが夕方まで眠りこける。
なけなしのお金で気まぐれにやってきたパリ。大半はベッドで眠りこけていただけだった(^^;
なんというお金のムダ使い。いまさら後悔しても仕方がないが。


劇団の事務員に空きがあると言われ....。 母校のスタジオでの練習を断られる。
カンパニーからは事務員の空きがあるからやってみないかと誘われるが、
さすがに今さら事務員に甘んじるのは屈辱感が大きすぎる。
断ってしまうのだが、さりとて生活はしていかなければならない。
見つけた働き口は、母校のダンススクールの学生寮の管理人。
どっちにしても大差はないようだが、これは気持ちの問題だろう。
まさにこれはフランシスの悪戦苦闘の記。
最後は、彼女の思わぬ方向でのハーフ・ハッピーエンド。
まあこのくらいでストーリーが収束するならば、現実には上々の部類なんじゃないかなと。
人生なかなか思い通りにはならないが、そんなに捨てたものでもない。
そんなメッセージがこめられた映画のようです。