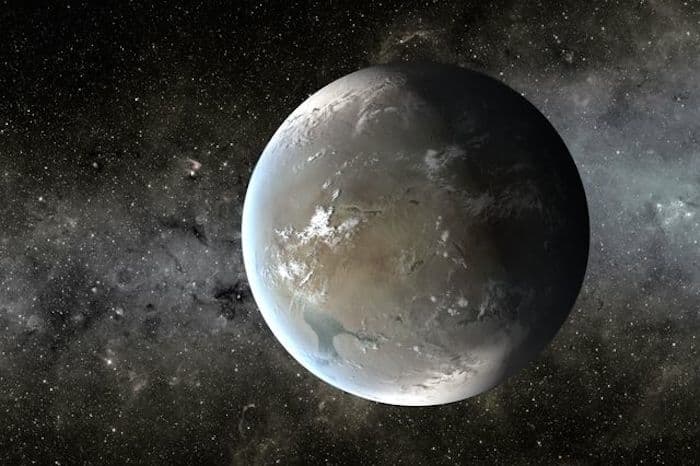星形成が行われておらず、
中心部の超大質量ブラックホールから時おり風が吹き出している銀河。
こういう特徴を持つ“レッドガイザー”と呼ばれる銀河の観測から、
星形成を妨げる原因になっている銀河内でのガスの加熱が、
超大質量ブラックホールからの風によって、
引き起こされていることが明らかになりました。
材料はあるのに星を作らない銀河
近傍の宇宙では、
若い青い星が少ないため赤く見える、星形成が行われていない銀河が、
大半を占めています。
でも、こうした星形成が不活発な銀河の中には、
星形成に必要なガスは十分存在しているのに、星形成が行われていない銀河もあります。
いったい、どのようなメカニズムで星形成が停止しているのか?
が天文学者を長年悩ませてきた謎なんですねー
今回の研究では、銀河観測を行うプロジェクト“MaNGA”で、
“Akira”というニックネームの銀河を観測。
アパッチポイント天文台にある、
口径2.5メートルのスローン財団望遠鏡に取り付けた新型の分光装置を用いています。
“Akira”は“レッドガイザー”と呼ばれる、
新しく発見されたタイプの銀河の典型例にあたります。
若い星が少ないため赤く、
銀河中心の超大質量ブラックホールから時おり風が吹き出すという、
特徴を持っています。
ブラックホールから吹く温かい風
観測の結果とらえられたのが、
“アウトフロー”と呼ばれる風により銀河内のガスが温められる様子でした。
“アウトフロー”とは、
超大質量ブラックホールに物質が落ち込む際に解放されたエネルギーによって、
周囲のガスが高速で外向きに広がって吹く風です。
“Akira”の超大質量ブラックホールからの“アウトフロー”は、
“Tetsuo”というニックネームのさらに小さい銀河との相互作用によって、
生み出されているようです。
“アウトフロー”によってガスが高温になると、
ガスが収縮できないので、新たな星が作れなくなるんですねー
今回の研究結果は、星形成に必要な材料となるガスが銀河に十分あっても、
中心の超大質量ブラックホールからの“アウトフロー”によって、
銀河内のガスが温められ、星形成が妨げられるという説を示すことになりました。
今後、観測データの解析を引き続き行うことで、
“レッドガイザー”自体の性質や、“レッドガイザー”が銀河の進化全般に、
どのように関係するのを明らかにするそうです。
こちらの記事もどうぞ
銀河団の形成に関わる? ブラックホールのアウトフロー
星形成を終わらせたブラックホールの「げっぷ」
中心部の超大質量ブラックホールから時おり風が吹き出している銀河。
こういう特徴を持つ“レッドガイザー”と呼ばれる銀河の観測から、
星形成を妨げる原因になっている銀河内でのガスの加熱が、
超大質量ブラックホールからの風によって、
引き起こされていることが明らかになりました。
材料はあるのに星を作らない銀河
近傍の宇宙では、
若い青い星が少ないため赤く見える、星形成が行われていない銀河が、
大半を占めています。
でも、こうした星形成が不活発な銀河の中には、
星形成に必要なガスは十分存在しているのに、星形成が行われていない銀河もあります。
いったい、どのようなメカニズムで星形成が停止しているのか?
が天文学者を長年悩ませてきた謎なんですねー
今回の研究では、銀河観測を行うプロジェクト“MaNGA”で、
“Akira”というニックネームの銀河を観測。
アパッチポイント天文台にある、
口径2.5メートルのスローン財団望遠鏡に取り付けた新型の分光装置を用いています。
“Akira”は“レッドガイザー”と呼ばれる、
新しく発見されたタイプの銀河の典型例にあたります。
若い星が少ないため赤く、
銀河中心の超大質量ブラックホールから時おり風が吹き出すという、
特徴を持っています。
 |
| 銀河“Akira”(右)と“Tetsuo”(左)のイメージ図。 “Akira”の重力により“Tetsuo”のガスが“Akira”の超大質量ブラックホールに引き込まれる。 これによりブラックホールからの“アウトフロー”が生み出されて“Akira”のガスを温め、 新たな星形成が妨げられている。 |
ブラックホールから吹く温かい風
観測の結果とらえられたのが、
“アウトフロー”と呼ばれる風により銀河内のガスが温められる様子でした。
“アウトフロー”とは、
超大質量ブラックホールに物質が落ち込む際に解放されたエネルギーによって、
周囲のガスが高速で外向きに広がって吹く風です。
“Akira”の超大質量ブラックホールからの“アウトフロー”は、
“Tetsuo”というニックネームのさらに小さい銀河との相互作用によって、
生み出されているようです。
“アウトフロー”によってガスが高温になると、
ガスが収縮できないので、新たな星が作れなくなるんですねー
今回の研究結果は、星形成に必要な材料となるガスが銀河に十分あっても、
中心の超大質量ブラックホールからの“アウトフロー”によって、
銀河内のガスが温められ、星形成が妨げられるという説を示すことになりました。
今後、観測データの解析を引き続き行うことで、
“レッドガイザー”自体の性質や、“レッドガイザー”が銀河の進化全般に、
どのように関係するのを明らかにするそうです。
こちらの記事もどうぞ
銀河団の形成に関わる? ブラックホールのアウトフロー
星形成を終わらせたブラックホールの「げっぷ」