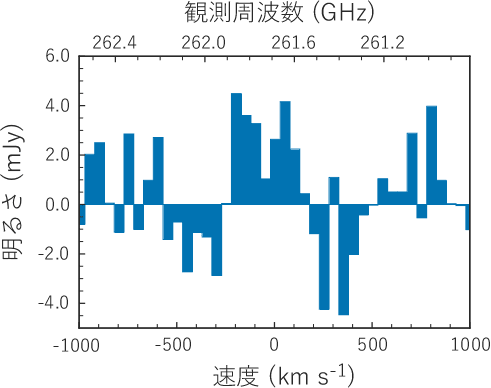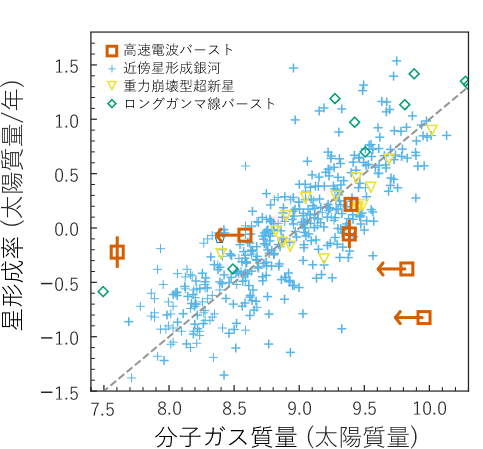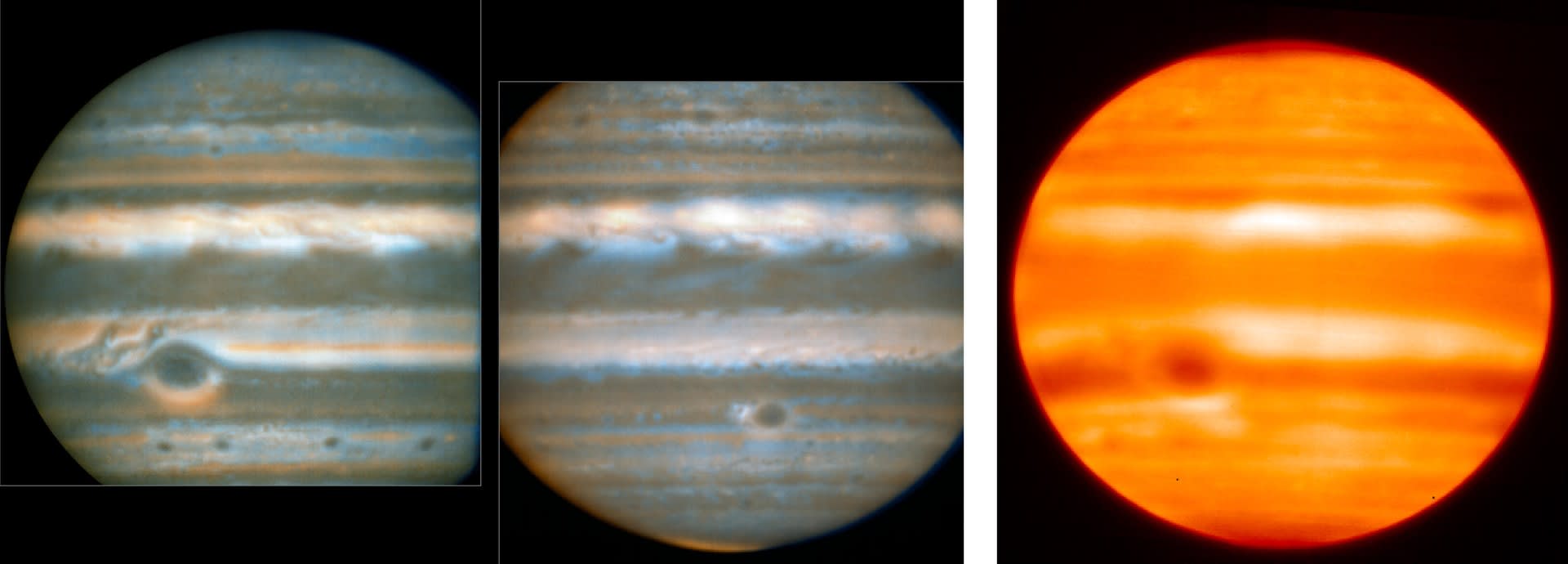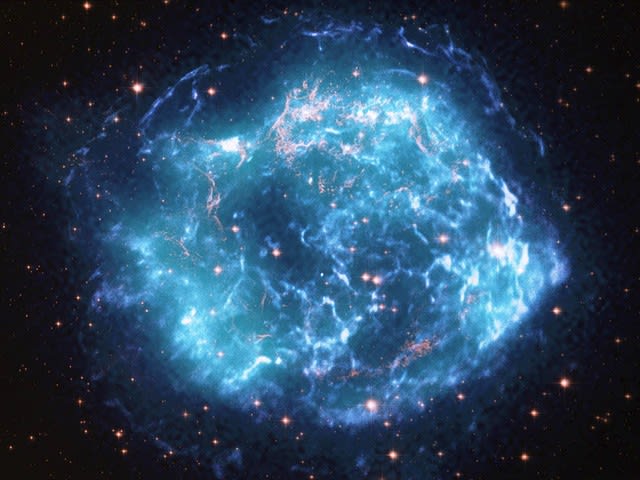今回の研究では、銀河系内にあるブラックホールと恒星の連星系“はくちょう座X-1”の観測から、ブラックホール近傍から放射されるX線がわずかに偏光していることを発見。
ブラックホール近傍にある高温のプラズマ(コロナ)の位置と形状を明らかにしています。
ブラックホール連星系のブラックホールの周辺には、恒星からの物質がブラックホールの強い重力に引かれてできる渦巻き状の高温の円盤“降着円盤”と、円盤よりも高温の“コロナ”と呼ばれるプラズマが存在しています。
今回、共同研究グループはX線偏光観測衛星“IXPE”を用いて、ブラックホール連星系“はくちょう座X-1”を観測。
すると、X線の振動方向がブラックホールから放出されるジェットと呼ばれるプラズマ噴出流の方向にわずかに偏っている(偏光している)ことが分かります。
このX線の偏りとその強さから考えられるのは、コロナはジェットの方向に存在せず、円盤の両面を覆っているか、もしくは円盤の内縁とブラックホールとの間に位置していること。
このようなブラックホール近傍の物質の位置関係は、これまでのX線望遠鏡では遠すぎて分解できないんですねー
偏光を観測することで初めて明らかになったことでした。
さらに、高エネルギーX線の観測から、コロナと呼ばれる約10億℃に達する高温プラズマの存在も示唆されています。
それぞれのX線の電場はある方向を向いていますが、多数のX線の電場が特定の同じ方向を向いている場合は「直線的に偏光している」と表現します。
2021年12月8日、世界で初めてX線偏光観測に特化した望遠鏡を搭載した衛星“IXPE”が打ち上げられます。
はくちょう座の方向約7000光年の彼方に位置する“はくちょう座X-1”は、太陽質量の21倍のブラックホールと太陽質量の41倍の青色超巨星からなるブラックホール連星系です。(図1)
ブラックホール連星系は、その状態が観測時期によって変化することが知られています。
測定されたX線スペクトルから判明したのは、今回観測した“はくちょう座X-1”はコロナから放射されたX線で明るく輝いている状態にあること。
そう、この時期のX線偏光を測定することで、X線放射源であるコロナと、それを反射する物質である円盤との位置関係が知ることができるんですねー
データ解析の結果から明らかになったのは、X線はわずかに偏光していて、その方向はブラックホールからのジェットと呼ばれるプラズマ噴出流の方向(円盤の垂直方向)と揃っていること。
今回の研究では、X線の偏光を測定するという新しい天体観測手法を用いて、ブラックホール近傍のコロナの形状および場所を初めて明らかにしています。
同様の手法は、中性子星と恒星などのブラックホール以外の連星系にも応用でき、さらなる発見が期待できます。
この場合、X線を放射する円盤はブラックホールのより近傍まで引き込まれるので、その強力な重力場により生じた時空の歪みにより、X線偏光が変化すると予想されてます。
この変化を“IXPE”で観測することで、近い将来、ブラックホール近傍における強重力下の物理の検証や、ブラックホールの自転速度の測定が可能になると期待出ます。
こちらの記事もどうぞ
ブラックホール近傍にある高温のプラズマ(コロナ)の位置と形状を明らかにしています。
この研究を進めているのは、理化学研究所 開拓研究本部 玉川高エネルギー宇宙物理研究室の北口 貴雄 研究員、玉川 徹 主任研究員、広島大学大学院 先進理工系科学研究科の张 思轩 大学院生、同宇宙科学センターの水野 恒史 准教授らの共同研究グループです。
研究成果は、今後のブラックホール近傍における強重力場下の物理の検証や、ブラックホールの自転速度の測定につながると期待できます。ブラックホール連星系のブラックホールの周辺には、恒星からの物質がブラックホールの強い重力に引かれてできる渦巻き状の高温の円盤“降着円盤”と、円盤よりも高温の“コロナ”と呼ばれるプラズマが存在しています。
今回、共同研究グループはX線偏光観測衛星“IXPE”を用いて、ブラックホール連星系“はくちょう座X-1”を観測。
すると、X線の振動方向がブラックホールから放出されるジェットと呼ばれるプラズマ噴出流の方向にわずかに偏っている(偏光している)ことが分かります。
このX線の偏りとその強さから考えられるのは、コロナはジェットの方向に存在せず、円盤の両面を覆っているか、もしくは円盤の内縁とブラックホールとの間に位置していること。
このようなブラックホール近傍の物質の位置関係は、これまでのX線望遠鏡では遠すぎて分解できないんですねー
偏光を観測することで初めて明らかになったことでした。
ブラックホール近傍にあるコロナと呼ばれる高温プラズマ
宇宙空間には、ブラックホールと恒星が互いの周りを回っている連星系“ブラックホール連星系”が存在しています。太陽の30倍以上重い恒星が、一生の最期に爆発した後に残される高密度な天体がブラックホール。強い重力のために光さえも逃げ出すことができない。
ブラックホールの連星系では、恒星から放出される物質がブラックホールの強い重力に引き寄せられて、ブラックホールの周りには100万℃程度の高温のプラズマからなる薄い円盤が形成され、円盤は強いX線を放射しています。さらに、高エネルギーX線の観測から、コロナと呼ばれる約10億℃に達する高温プラズマの存在も示唆されています。
プラズマは、原子が電離して陽イオンと自由電子に分かれた状態のこと。コロナは中心ブラックホール近傍に存在するX線放射源のこと。正体は高温プラズマであり、低エネルギーの紫外線・X線と相互作用することで高エネルギーのX線を放射すると考えられている。
でも、コロナがどのような形状で、ブラックホール近傍のどこに位置しているのかは、これまでのX線望遠鏡では分離して観測することができませんでした。世界で初めてX線偏光観測に特化した衛星
X線は波長の短い電磁波であり、電磁波は電場と磁場が交互に振動して空間を伝わります。それぞれのX線の電場はある方向を向いていますが、多数のX線の電場が特定の同じ方向を向いている場合は「直線的に偏光している」と表現します。
偏光は電磁波の持つ性質の一つ。電磁波は電場と磁場が交互に波打ち空間を伝わる波であり、その電場がある方向を向いている状態を偏光という。
電磁波の偏光は、波の電場がどのくらい偏っているのかの度合いを表す“偏光度”と、偏りの方向を表す“偏向角”の二つの情報からなる。例えば、電球などから放射される電磁波は、電場があらゆる方向を向いて偏っていないので無偏光になる。X線も目で見える光(可視光)と同じ電磁波なので偏光という性質持つ。多くの天体から放射されるX線は、波の振動する面がほとんど偏らない無偏光であるが、特殊な状況で放射されたX線は振動面が偏り偏向したX線となる。偏光度は0%(無偏光)から100%までの値をとり、偏向角は-90度から+90度までの値をとる。
このような偏向はX線が物質を通過し、ある確率で反射するときに生じることから、偏光の強さを測定すると、観測者から見たX線の放射源と反射物質の位置関係が分かります。電磁波の偏光は、波の電場がどのくらい偏っているのかの度合いを表す“偏光度”と、偏りの方向を表す“偏向角”の二つの情報からなる。例えば、電球などから放射される電磁波は、電場があらゆる方向を向いて偏っていないので無偏光になる。X線も目で見える光(可視光)と同じ電磁波なので偏光という性質持つ。多くの天体から放射されるX線は、波の振動する面がほとんど偏らない無偏光であるが、特殊な状況で放射されたX線は振動面が偏り偏向したX線となる。偏光度は0%(無偏光)から100%までの値をとり、偏向角は-90度から+90度までの値をとる。
2021年12月8日、世界で初めてX線偏光観測に特化した望遠鏡を搭載した衛星“IXPE”が打ち上げられます。
2021年12月9日にNASAとイタリア宇宙機関によって打ち上げられたのが、世界初の高感度X線偏光観測衛星“IXPE(Imaging X-ray Polarimetry Explorer)”。日本グループは、主要観測装置の一部を提供するとともに、マグネターをはじめとする様々な天体のX線偏光観測とデータ解析に参加している。
NASAとイタリア宇宙機関の共同ミッションで、理化学研究所を含む日本グループも主要観測装置の一部を提供するとともに、X線偏光観測とデータ解析に参加しています。研究手法と成果
研究では“IXPE”を用いて非常に強いX線を発する、つまりX線で最も明るく輝く天体の一つであるブラックホール連星系“はくちょう座X-1”を、2022年5月15日から21日まで観測しています。はくちょう座の方向約7000光年の彼方に位置する“はくちょう座X-1”は、太陽質量の21倍のブラックホールと太陽質量の41倍の青色超巨星からなるブラックホール連星系です。(図1)
青色超巨星とは直径が太陽の数十倍あり、太陽よりも重く高温のため青色で明るく輝く恒星。
ブラックホールと青色超巨星から成るブラックホール連星系“はくちょう座X-1”では、青色超巨星からの物質がブラックホールへ落下していく。落下する物質はブラックホール近傍に約100万℃の円盤を形成し強いX線を発する。
ブラックホールと青色超巨星から成るブラックホール連星系“はくちょう座X-1”では、青色超巨星からの物質がブラックホールへ落下していく。落下する物質はブラックホール近傍に約100万℃の円盤を形成し強いX線を発する。
 |
| 図1.ブラックホール連星系“はくちょう座X-1”のイメージ図 中央に位置するブラックホールは、左に見える青色超巨星から物質を重力で引き寄せ、ブラックホール近傍で渦巻く円盤を形成する。引き寄せられた物質の一部は、ジェットとして円盤の垂直方向に細く射出される。(Credit: John Paice) |
ブラックホール連星系は、その状態が観測時期によって変化することが知られています。
測定されたX線スペクトルから判明したのは、今回観測した“はくちょう座X-1”はコロナから放射されたX線で明るく輝いている状態にあること。
そう、この時期のX線偏光を測定することで、X線放射源であるコロナと、それを反射する物質である円盤との位置関係が知ることができるんですねー
データ解析の結果から明らかになったのは、X線はわずかに偏光していて、その方向はブラックホールからのジェットと呼ばれるプラズマ噴出流の方向(円盤の垂直方向)と揃っていること。
ブラックホールへ落下する物質は角運動を持つため、降着円盤と呼ばれるへんぺいな円盤をブラックホールの周囲に作る。降着円盤内のガスの摩擦熱によって落下するガスは電離してプラズマ状態へ、この電離したガスは回転することで強力な磁場が作られ、降着円盤からは荷電粒子のジェットが噴射し降着円盤の半径に応じて、可視光線、紫外線、X線と幅広い電磁波が観測される。
このX線偏光の強さから、コロナはジェット方向には存在せず、円盤の両面を覆っているか、もしくは円盤の内縁とブラックホールとの間に位置していると考えられます。(図2) |
| 図2.ブラックホール周辺のコロナの位置と形状の可能性 黒丸はブラックホール、赤の帯が円盤、水色がコロナを表す。左はコロナが円盤の両面を覆っているモデル、右はコロナが円盤とブラックホールの間に位置するモデルを示している。(Credit: 理化学研究所) |
今回の研究では、X線の偏光を測定するという新しい天体観測手法を用いて、ブラックホール近傍のコロナの形状および場所を初めて明らかにしています。
同様の手法は、中性子星と恒星などのブラックホール以外の連星系にも応用でき、さらなる発見が期待できます。
中性子星は、太陽の10~30倍程度の恒星が、一生の最期に大爆発した後に残される宇宙で最も高密度な天体。主に中性子からなる天体で、ブラックホールと異なり半径10キロ程度の表面が存在し、そこに地球の約50万倍の質量が詰まっていている。一般に強い磁場を持つものが多い。
また、今回の“はくちょう座X-1”の観測はコロナからのX線が明るい時期に行いましたが、コロナがほとんど見られず、円盤からのX線が非常に明るくなる時期もあります。この場合、X線を放射する円盤はブラックホールのより近傍まで引き込まれるので、その強力な重力場により生じた時空の歪みにより、X線偏光が変化すると予想されてます。
この変化を“IXPE”で観測することで、近い将来、ブラックホール近傍における強重力下の物理の検証や、ブラックホールの自転速度の測定が可能になると期待出ます。
こちらの記事もどうぞ