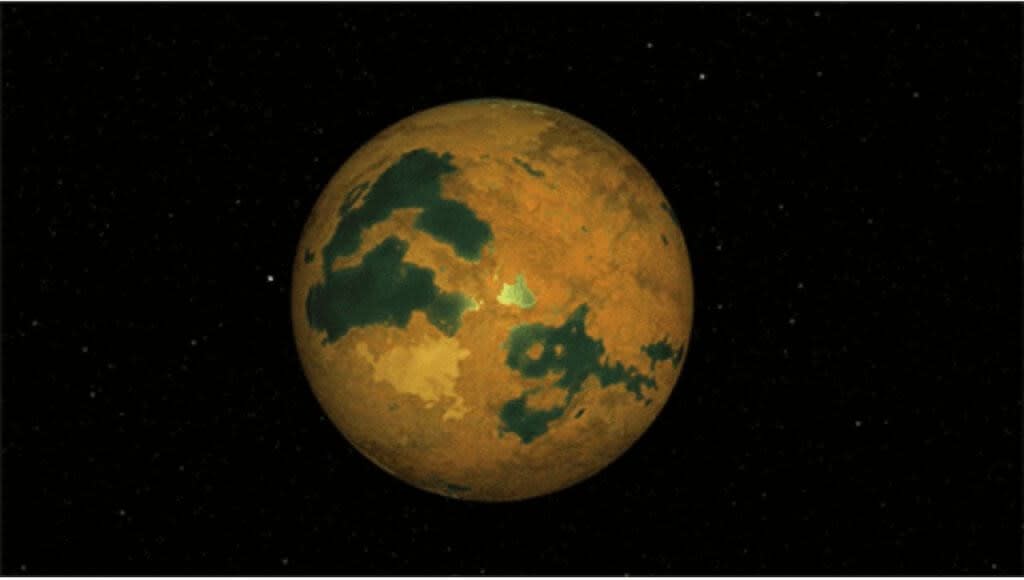今回の研究では、系外惑星“HD 149026 b”の大気中に水蒸気(H2O)が存在する証拠を発見しています。
この系外惑星は、地球から約250光年彼方のヘルクレス座に位置し、土星とほぼ同じ大きさの高温ガス惑星なので“ホットサターン”に分類されています。
さらに興味深いのは、“HD 149026 b”が地球の約110倍という異常に大きなコアを持っていること。
いくつかの理論的なシナリオが提唱されていますが、この惑星の大気の観測を続けることで、これらの理論のいずれかを支持する、あるいは新た理論を示唆する可能性もあります。
土星とほぼ同じ大きさの高温ガス惑星
“HD 149026 b”は、地球から約250光年彼方のヘルクレス座に位置する系外惑星です。
この系外惑星は、土星とほぼ同じ大きさを持つ巨大なガス惑星でありながら、主星“HD 149026”の極めて近くの軌道を公転しているので、“ホットサターン”に分類されます。
主星“HD 149026”の質量は太陽の約1.34倍で、金属が豊富な恒星です。
“HD 149026 b”は、この恒星の周りを、わずか2.9日という短い周期で公転。
この軌道は、太陽から水星までの距離の約10分の1という、非常に近いものとなります。
“HD 149026 b”の最大の特徴は、その高温な環境にあります。
主星に極めて近い距離を公転しているので、推定される“HD 149026 b”の表面温度は約1700ケルビンに達しているようです。
これは、最強の鉄鋼でさえも溶かしてしまうほどの高温で、“HD 149026 b”が過酷な環境にあることを示しています。
さらに、“HD 149026 b”は、その高温な環境に加え、異常に大きなコアを持つことでも知られています。
そのコアの質量は、地球質量の約110倍にも達すると推定されていて、これは従来の惑星形成モデルでは説明が難しい現象と言えます。
透過光分光法と相互相関法で系外惑星の大気を探る
“HD 149026 b”の大気中における水蒸気の発見は、透過光分光法と呼ばれる観測手法を用いて行われたものです。
この手法は、地球から見て系外惑星“HD 149026 b”が、主星“HD 149026”の手前を通過している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星の光を利用します。
分光器により、光の波長ごとの強度分布“スペクトル”を得ることができます。
惑星の大気中には様々な分子が存在し、個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、系外惑星の大気を通過してきた光“透過スペクトル”には、大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。
この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定する訳です。
でも、系外惑星の大気を観測する場合、明るい恒星の光に対して惑星からの光は非常に弱いので、検出が困難になることが多くあるんですねー
そこで用いられるのが、相互相関法と呼ばれる微弱な信号を増幅する手法です。
相互相関法では、高分解能分光法で個別に分解される数百から数千の弱いスペクトル吸収線の情報を組み合わせることで、系外惑星からの信号を高めることができます。
相互相関法を用いることで、高分解能分光データから、微弱な吸収線の情報を統合し、系外惑星からの信号を増幅することが可能となります。
水蒸気は大気全体に広がっている
今回の研究では、スペインのカラー・アルト天文台に設置された分光器“CARMENES”を用いて、“HD 149026 b”の近赤外線波長域(0.97~1.7μm)のスペクトルを観測しています。
研究チームは、この観測データに対して相互相関法を適用。
その結果、“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が存在する証拠を発見しました。
この信号の信号対雑音比(S/N)は約4.8でした。
興味深いことに、2023年に行われたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた“HD 149026 b”の観測でも、大気中に水蒸気を検出したとする報告がされています。
この時、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が観測していたのは惑星の昼側でした。
これに対して、本研究では惑星の夜側を観測しているので、両方の観測結果が水蒸気の存在を示していることになります。
このことは、“HD 149026 b”の大気全体に水蒸気が広がっている可能性を示唆していました。
研究チームでは、“HD 149026 b”の大気にシアン化水素(HCN)も探索しましたが、検出には至らず…
これは、観測データのS/N比が低いためだと考えられています。
“HD 149026 b”の大気は酸素が豊富な環境かも
“HD 149026 b”のような高温のガス惑星の大気では、炭素と酸素の比(C/O)が惑星の形成過程や進化の歴史を理解する上で、重要な指標となります。
C/Oひが1より小さい場合(酸素が炭素より豊富であることを示す)、水(H2O)と一酸化炭素(CO)が最も豊富な酸素と炭素を含む分子となります。
一方、C/O比が1より大きい場合、水は少なくなり、シアン化水素が多くなります。
今回の観測では、“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が検出された一方で、シアン化水素は検出されませんでした。
これは、“HD 149026 b”の大気のC/O比が1より小さい、すなわち酸素が豊富な環境であることを示唆しています。
どうやって異常に大きなコアを持つ惑星が形成されたのか
“HD 149026 b”は、これまでの惑星形成モデルでは説明が難しい、異常に大きなコアを持つことが知られています。
この巨大なコアを説明するために、いくつかのシナリオが提案されています。
1.巨大惑星同士の衝突
Ikoma et al.(2006)は、“HD 149026 b”が、2つ以上の巨大惑星が衝突した結果形成された可能性を指摘しています。
2.微惑星の異常な供給
Broeg & Wuchterl(2007)は、“HD 149026 b”の形成時に、他の惑星からの重力摂動によって、微惑星が異常なほど大量に供給された可a能性を提案しています。
3.標準的なコア集積モデル
Dodson-Robinson & Bodenheimer(2009)は、固体表面密度が高く、初期軌道が大きい場合には、標準コア集積モデルでも“HD 149026 b”のような巨大コアを持つ惑星が形成される可能性を示しています。
これらのシナリオのうち、どのシナリオが正しいのか、あるいは全く新しいシナリオが必要となるのかは、今後の詳細な観測によって明らかになっていくと考えられます。
“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が検出されたことは、この惑星の形成過程や進化の歴史を理解する上で重要な手掛かりとなります。
“HD 149026 b”は、巨大なコア以外にも、高温環境、短い公転周期など、多くの興味深い特徴を持っています。
今後の詳細な観測により、“HD 149026 b”の大気の組成や温度構造、そしてその形成過程について、より詳しい情報が得られることが期待されます。
こちらの記事もどうぞ
この系外惑星は、地球から約250光年彼方のヘルクレス座に位置し、土星とほぼ同じ大きさの高温ガス惑星なので“ホットサターン”に分類されています。
さらに興味深いのは、“HD 149026 b”が地球の約110倍という異常に大きなコアを持っていること。
いくつかの理論的なシナリオが提唱されていますが、この惑星の大気の観測を続けることで、これらの理論のいずれかを支持する、あるいは新た理論を示唆する可能性もあります。
この研究は、東京大学の大学院生Sayyed Ali Rafiさんを中心とする研究チームが進めています。
本研究の成果は、2024年7月付でアメリカの科学雑誌“The Astronomical Journal”に“Evidence of Water Vapor in the Atmosphere of a Metal-Rich Hot Saturn with High-Resolution Transmission Spectroscopy”として掲載されました。DOI: 10.3847/1538-3881/ad5be9
本研究の成果は、2024年7月付でアメリカの科学雑誌“The Astronomical Journal”に“Evidence of Water Vapor in the Atmosphere of a Metal-Rich Hot Saturn with High-Resolution Transmission Spectroscopy”として掲載されました。DOI: 10.3847/1538-3881/ad5be9
 |
| 図1.系外惑星“HD 149026 b”のイメージ図。木星よりも少し小さい“ホットサターン”に分類される。本研究では、この惑星の大気中に水蒸気が存在する証拠を発見している。(Credit: アストロバイオロジーセンター) |
土星とほぼ同じ大きさの高温ガス惑星
“HD 149026 b”は、地球から約250光年彼方のヘルクレス座に位置する系外惑星です。
この系外惑星は、土星とほぼ同じ大きさを持つ巨大なガス惑星でありながら、主星“HD 149026”の極めて近くの軌道を公転しているので、“ホットサターン”に分類されます。
主星“HD 149026”の質量は太陽の約1.34倍で、金属が豊富な恒星です。
“HD 149026 b”は、この恒星の周りを、わずか2.9日という短い周期で公転。
この軌道は、太陽から水星までの距離の約10分の1という、非常に近いものとなります。
“HD 149026 b”の最大の特徴は、その高温な環境にあります。
主星に極めて近い距離を公転しているので、推定される“HD 149026 b”の表面温度は約1700ケルビンに達しているようです。
これは、最強の鉄鋼でさえも溶かしてしまうほどの高温で、“HD 149026 b”が過酷な環境にあることを示しています。
さらに、“HD 149026 b”は、その高温な環境に加え、異常に大きなコアを持つことでも知られています。
そのコアの質量は、地球質量の約110倍にも達すると推定されていて、これは従来の惑星形成モデルでは説明が難しい現象と言えます。
透過光分光法と相互相関法で系外惑星の大気を探る
“HD 149026 b”の大気中における水蒸気の発見は、透過光分光法と呼ばれる観測手法を用いて行われたものです。
この手法は、地球から見て系外惑星“HD 149026 b”が、主星“HD 149026”の手前を通過している時に、系外惑星の大気を通過してきた主星の光を利用します。
分光器により、光の波長ごとの強度分布“スペクトル”を得ることができます。
惑星の大気中には様々な分子が存在し、個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、系外惑星の大気を通過してきた光“透過スペクトル”には、大気に含まれる元素に対応した波長で光の強度が弱まる箇所“吸収線”が現れることになります。
この“透過スペクトル”と“主星から直接届いた光のスペクトル”を比較することで吸収線を調べることができ、その波長から元素の種類を直接特定する訳です。
でも、系外惑星の大気を観測する場合、明るい恒星の光に対して惑星からの光は非常に弱いので、検出が困難になることが多くあるんですねー
そこで用いられるのが、相互相関法と呼ばれる微弱な信号を増幅する手法です。
相互相関法では、高分解能分光法で個別に分解される数百から数千の弱いスペクトル吸収線の情報を組み合わせることで、系外惑星からの信号を高めることができます。
相互相関法を用いることで、高分解能分光データから、微弱な吸収線の情報を統合し、系外惑星からの信号を増幅することが可能となります。
水蒸気は大気全体に広がっている
今回の研究では、スペインのカラー・アルト天文台に設置された分光器“CARMENES”を用いて、“HD 149026 b”の近赤外線波長域(0.97~1.7μm)のスペクトルを観測しています。
研究チームは、この観測データに対して相互相関法を適用。
その結果、“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が存在する証拠を発見しました。
この信号の信号対雑音比(S/N)は約4.8でした。
 |
| 図2.検出されたH2Oシグナル。赤い×印は実際に検出された位置を、シアン色の十字記号は予測されるシグナルの位置を示している。右下の数時4.8は、検出されたシグナルのS/N比。KpとVrestは、それぞれ惑星の視差速度の半値幅と静止系の速度。(Credit: アストロバイオロジーセンター) |
この時、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が観測していたのは惑星の昼側でした。
これに対して、本研究では惑星の夜側を観測しているので、両方の観測結果が水蒸気の存在を示していることになります。
このことは、“HD 149026 b”の大気全体に水蒸気が広がっている可能性を示唆していました。
研究チームでは、“HD 149026 b”の大気にシアン化水素(HCN)も探索しましたが、検出には至らず…
これは、観測データのS/N比が低いためだと考えられています。
“HD 149026 b”の大気は酸素が豊富な環境かも
“HD 149026 b”のような高温のガス惑星の大気では、炭素と酸素の比(C/O)が惑星の形成過程や進化の歴史を理解する上で、重要な指標となります。
C/Oひが1より小さい場合(酸素が炭素より豊富であることを示す)、水(H2O)と一酸化炭素(CO)が最も豊富な酸素と炭素を含む分子となります。
一方、C/O比が1より大きい場合、水は少なくなり、シアン化水素が多くなります。
今回の観測では、“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が検出された一方で、シアン化水素は検出されませんでした。
これは、“HD 149026 b”の大気のC/O比が1より小さい、すなわち酸素が豊富な環境であることを示唆しています。
どうやって異常に大きなコアを持つ惑星が形成されたのか
“HD 149026 b”は、これまでの惑星形成モデルでは説明が難しい、異常に大きなコアを持つことが知られています。
この巨大なコアを説明するために、いくつかのシナリオが提案されています。
1.巨大惑星同士の衝突
Ikoma et al.(2006)は、“HD 149026 b”が、2つ以上の巨大惑星が衝突した結果形成された可能性を指摘しています。
2.微惑星の異常な供給
Broeg & Wuchterl(2007)は、“HD 149026 b”の形成時に、他の惑星からの重力摂動によって、微惑星が異常なほど大量に供給された可a能性を提案しています。
3.標準的なコア集積モデル
Dodson-Robinson & Bodenheimer(2009)は、固体表面密度が高く、初期軌道が大きい場合には、標準コア集積モデルでも“HD 149026 b”のような巨大コアを持つ惑星が形成される可能性を示しています。
これらのシナリオのうち、どのシナリオが正しいのか、あるいは全く新しいシナリオが必要となるのかは、今後の詳細な観測によって明らかになっていくと考えられます。
“HD 149026 b”の大気中に水蒸気が検出されたことは、この惑星の形成過程や進化の歴史を理解する上で重要な手掛かりとなります。
“HD 149026 b”は、巨大なコア以外にも、高温環境、短い公転周期など、多くの興味深い特徴を持っています。
今後の詳細な観測により、“HD 149026 b”の大気の組成や温度構造、そしてその形成過程について、より詳しい情報が得られることが期待されます。
こちらの記事もどうぞ