16日のYahoo!トピックで見かけたニュース記事からです。これを夜中にもう一度読んでみようとしたら、Yahoo!JAPANがダウンしていたわけで。
東日本大震災では宮城県、岩手県の海岸沿いの集落が巨大津波の惨事となり、人々を震撼しております。海岸沿いは津波のリスクがある宿命ゆえに、集落の高台移転を検討していますが、yomiuri onlineの記事では、その移転したいという高台には、かつて縄文時代の遺跡が多数あり、それが復興への道におおきな難題を与えているといいます。
私もあの津波の一報に接した際、海岸沿いは趣がありますけど、やっぱり津波のことを考えれば高台への移転しか無いな、と思っておりました。しかしその高台には遺跡。
そう、縄文時代の遺跡があるということは、かつてそこで人々が暮らしていたということです。縄文人がどんな暮らしをしていたのかは分かりませんが、かつて教わったことでは主に木の芽など植物や、野生の動物を追っていたと聞きます。それでも海洋生物(つまり魚)も捕っていたでしょうが、古人も神話として大津波の伝承があり、そこで高台に住んでいたのではないかと思います。
三陸海岸は明治以降も何度か津波に襲われています。近海の三陸沖の地震の他、遠く南米で起きた地震の津波も、地球の丸さがここで集束する格好となり、大きな津波になります。そこで過去の津波でも何度か高台移転が検討されてきましたし、実際に移転しております。でも漁業を考えると、やっぱり浜に近い方が便利ですね。そこで移転したものの、徐々に元の浜に近い集落に戻ったというところもあります。
津波の恐ろしさ、悲惨さは、なかなか伝承されないものなのだそうです。いや津波に限らず、自然災害はどうも伝承されにくいものだそうで、その災害の当時者は悲惨さゆえに口をつぐみ、一方で新しい世代は先人の教えを賜わる機会が少ないままに、利便性の方へ行ってしまう。
そこで漁業に不便な高台から浜に移転したり、広い土地だからと言って元河道の地に家を建てたりして、再びの災害となってしまいます。
今回の大津波は、貞観11年(869年)の貞観地震以来のものだと言われています。貞観地震以前にもこんな規模の地震と津波はあったはずです。縄文人もこの地震津波に遭遇したことでしょう。後代への言い伝えに加わり、そして畏怖の念として神格化、そして祭礼とつながっただろうと思います。
防災に、古からの言い伝えは無視出来ないと思います。なにやら神話的なものと捉えられ、科学的根拠が無いとされてしまいますが、三陸地方の高台移転で、多数ある遺跡があったという記事を見て、やっぱり古人の知恵は大切だと思います













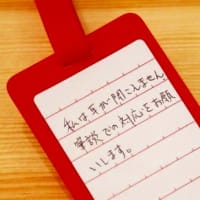
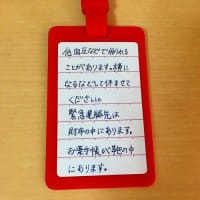





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます