京都新聞web版9月29日付配信記事及び、先ほど(10月1日22:50)配信記事からです。京都市内のタクシー事業者と京都駅前の大家であるJR西日本が共同で、JR京都駅烏丸口のタクシー乗り場へ空車タクシーの乗り入れ規制を10月1日から10日までの10日間実施するとし、その初日が始まりました。
この社会実験は、空車タクシーの乗り入れを規制するという、他地域の方から見ればこの規制「???」でしょうが、京都駅烏丸口(京都タワーの前)の交差点をよく知る方ならお分かりですよね。客待ちの空車タクシーが構内へ入りきらず交差点にはみ出して、周囲凄い渋滞。ハッキリ迷惑と思っている方も多いはずです。
そんなわけで、何らかの厳しい規制が必要ということで、社会実験を行うことにしたもので、10月1日から10日までの午前8時から午後8時までは、空車タクシーは構内に乗り入れさせない。11日から20日までは構内のタクシースペースに入れる車両を、登録番号(ナンバープレート)の数字ごとに三つのグループに分け、客待ちタクシーを分散させるという思い切ったものです。
上手くいくやろか?アカンやろな・・・。そもそもこの期間中は空車ではないタクシーのみが構内へ入れるわけで、乗り場から乗せられるタクシーは、京都駅までお客さんを乗せてきた車両に限るというものです。つまりお客を降ろし乗り場に着けて新たにお客さんを乗せて発車・・・。
これ、机上の論理ですね。そんな京都駅への到着客と乗車客とが常に一定となるわけは無い。時間帯ごとに到着客が多かったり、逆に乗車客が多かったりするものです。概ね、朝の早い時間を過ぎてからの午前中は概して乗車客が多い。しかし空車タクシーは構内の乗り場に入ってこられない・・・。乗り場はどうなるか・・・。想像がつきます。
◇ ◇ ◇
その想像通りのことが起こっていました。午前9時過ぎ、乗車タクシー(つまり駅で降りる客が乗ったタクシー)がなかなか入ってこず、結果乗り場にはタクシーが一台もなくなってしまい、10時頃にはお客さんが100人以上も待ち行列となったのだそうだ。つまり大混乱。
そのため急遽、午前10時45分頃から11時半頃と、午後0時45分頃から2時10分分頃に乗り入れ規制を解除したとのこと。その後は午後5時半頃にお客さんが40人ほど並んだものの、その時間になると京都駅までの実車タクシーも増え、お客さんを降ろした後のタクシーが30台ほど並ぶようになったとのことです。
しかし午後8時でこの規制が終了すると、サッと空車タクシーが殺到。駅前交差点はもちろん塩小路通は200mの行列で渋滞と、今迄どおりの光景となりました。
◆ ◆ ◆
なかなか上手くいかないものですね。私は普段はタクシー乗りませんし、あの加減速と日頃の行動でタクシーそのものに否定的なので、京都駅前に限らず名古屋駅でも凄い待ち行列に迷惑を被っていると感じている一人です。しかしタクシーも必要な交通機関であることは確かなので、ただ空車を理由に一律に駅前に乗り入れを禁止するのは行き過ぎだと思います。
乗り場で待つ人数に応じて入構させるというのは出来ないものでしょうか。或いは乗車待ちタクシーの数に応じて、スペースがある場合に限り入構させるとか。単に運転手の仲間内ルールだけで、並んだ順にお客を乗せるというそのやりかたに固執するあまり、駅前の交通を塞ぎ延々タクシー行列が出来てしまうわけで、根本的にはタクシー業界の改革、ひいては地域交通でのタクシーのあり方を考えるところまで、問題の根は深いと思います。
***10月5日追記
10月4日京都新聞によれば、構内タクシー空車乗り入れ全面禁止は中止とし、利用客の多い時間帯は適宜空車を入れることとなりました。













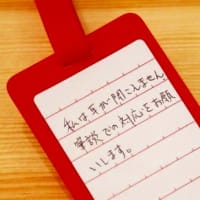
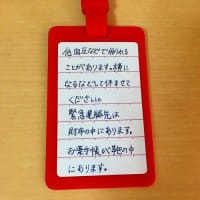





「京都ネタ」という事で、釣られてみました。
タクシーの規制というのも、難しいものですね。
また、業界にも色々な問題が起きており、賃金もあまりよくないということもお聞きします。
観光地などでは、たまに利用しますが、それなりに助かっては、いますが・・・。
インフラ全体で、考えていかなければいけない問題でしょうね。
この空車タクシー構内乗り入れ規制の社会実験は、10日から登録ナンバーにより3区分に分ける第二段階に入りました。
新聞報道ではスムーズにいっているということです。
なんかねぇ、タクシーの業界はどうも理知的とは言えない感じがします。
乗り入れの社会実験でも、それを行う前に、時間帯毎の乗車・降車の数をデータベースにして数値化していれば、一律の空車はダメという発想には至らなかったと思います。
タクシーは一つの運送ごとに、乗車地と降車地、それに人数を記録しているのですけどね。