前記JR北海道の軌道狂いについて記事を書いた際、ふとあるやり取りを思い出しました。
鉄道の通称「線路」と呼ばれている部分、すなわち車輪が載り転がる部分の鋼材「レール」とそれを支える構造の部分を「軌道」と言います。一方で、路面電車などの準拠法の法律名が「軌道法」と言い、同じ「軌道」という文字が使われています。
この鉄道の軌道と軌道法の軌道とはどう違うのか。今回は言葉尻を取るような記事ですいません。
まず「線路」とは、日本工業規格によれば、「列車又は車両を走らせるための通路であって、軌道およびこれらを支持するために必要な路盤、構造物を包含する地帯。」だそうです。また工学的一般に線路とは、ある意図を持ったもを目的の場所に伝送する経路一般のことだそうで、現実的な構造物でなくとも「線路」というは存在します。その一つが郵便線路。かつては鉄道線路がそのまま郵便線路でしたが、自動車便のところも郵便線路です。この郵便線路を締切便などの逓送が行なわれることで郵便の機能が実現されています。なので、路線バスでも一部で線路と呼ばれている他、今ここでこのパソコンを使っていますけど、ネットのケーブルも線路です。
通常の地ベタに敷設されている鉄道線路はレールがあって、その下に「枕木」があり、枕木を隠し埋めるように砂利が敷かれています。その砂利の下はそのまま元の地球の地ベタではなく、平らに均し(ならし)かつ何度もローラーをかけて平滑に固めてあります。最近ではアスファルト舗装する場合もあるようです。この部分を「路盤」といい、路盤から上の部分、すなわち、砂利、枕木、レールの部分を軌道といいます。
鉄道線路の軌道の例(中央本線奈良井駅付近)
・軌道(物理的な)の役割
そしてレールの役割は、車輪を載せ、その車輪が転がる道筋であり、そして曲線では滑らかにガイドもする、そのために正確な位置を保持せねばならず、レールを地ベタに直接並べては左右の間隔が保持できないばかりか、車両の重量で地面にのめりこんでしまいます。
そこで、重量を分散する構造と共に、レールの位置をきちんと保持するために枕木で左右の間隔を正確に保ち、枕木を介して車両の重量を砂利(バラスト)に伝えます。バラストは枕木の位置をしっかりと支え、上からの重力を砂利同士の結びつきがばねのように反発して、車両の重量を地球上の路盤に伝えます。
これが軌道の役割で、軌道法の「軌道」とは、まさにこの電車(電車とは限りませんが)道の軌道のことです。
つまりうこうしたレールによる交通のレールたらしめる重要な部分を「軌道」といい、その軌道を道路に敷設し、事業を営むと軌道法の対象となるわけです。
あまり知られていませんが、軌道法という法律は道路の法律です。道路では様々な交通があり、その一形態が自動車を含む車両ではなくレールによる軌道によるもので、これが軌道法の原点です。建設省と運輸省が別組織だった当時は、軌道法所管官庁は主に建設省でした。運輸事業を営む点で運輸省も所管に入っていただけです。
というわけで、道路上に敷設された「軌道」なので、軌道法。
軌道法による軌道の例(廃止された名鉄美濃町線旧白金~旧赤土坂間)
軌道法では軌道は道路上に敷設するのが原則ですが、道路外の事業者自身の土地に専用の軌道敷きととして敷設する事も可能でした。上の写真はまさにその境界で、専用の軌道部分を「新設軌道」、道路面と同一の平面で他の交通と供用空間にある軌道を「併用軌道」といいます。
ちなみに鉄道模型で売っているようなレールと枕木で、梯子状になっているものは軌道とは呼ばずに、「軌框」(ききょう)と言います。
なお、国土交通省での運輸統計では、鉄道事業法による「鉄道」と軌道法による軌道とは、明確に分けられており、この両者併せた言葉が「鉄軌道」といいます。















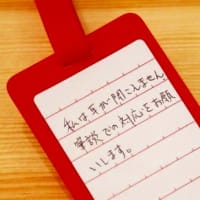
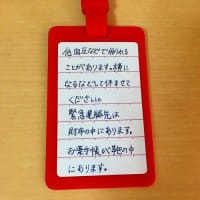





名鉄豊川線がそうだし、大阪市営地下鉄も。
昔の本で読んだことがありますが、阪神や阪急神戸線も最初は軌道特許だったとか。
よくある、軌道法による軌道線なのに実体は高速鉄道と変わりが無い線はなぜ?という問題があります。
そもそも軌道法による軌道線なのに高速電車の嚆矢をつけたのは、阪神電気鉄道と伺っています。
・阪神間で高速電車による鉄道事業を行ないたい。
・しかし並行して省線(鉄道省の線路)が通っている
・よって、私設鉄道法(開業当時の鉄道敷設にかかわる法律)による鉄道敷設免許は下りない。
・そこで考えたのは軌道法による軌道線で、線路のどこかで(具体的には神戸市内の一部で)道路上にあればクリアできる
・・・・という抜け道を考案。
それを真似たのが現在の阪急の創始者小林一三の箕面有馬電鉄。
で、阪急神戸線と宝塚線は軌道でスタートしています。
名鉄豊川線は、元々が軌道線の豊川市内線が発祥で、現在も軌道線のままです。
しかし、運転取り扱いなどの準拠法は鉄道のものを適用しています。
大阪市営地下鉄が軌道線なのは、政治的な話になりますが、建設省の権限を及ばせるために軌道線として特許をとらせ、トンネルのなどのインフラ部分を道路構造物として道路予算から出す便法だと伺っています。
同様に、東京のゆりかもめ、大阪市のニュートラムの新交通システムは、道路部分と港湾施設部分とに分けられ、前者の部分は軌道法、後者の部分は鉄道事業法による線路敷設となっています。
小牧市の旧ピーチライナーは軌道線で高架の橋脚を道路施設とみなし、その建設費用を国庫補助で賄っていますので、おいそれと撤去出来ないでいます。撤去するには、国庫補助分を返還しなければなりません。