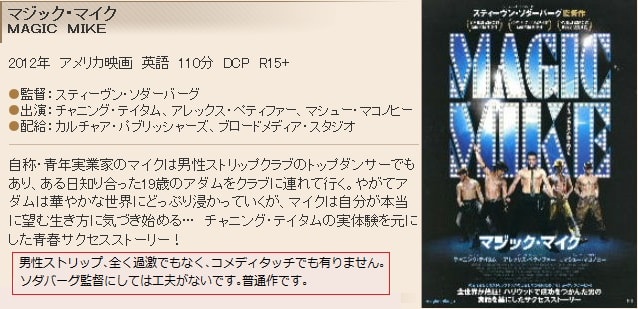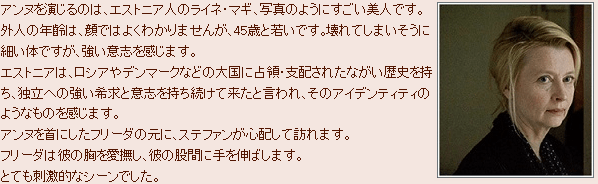2012念東京国際映画祭、グランプリ&最優秀監督賞受賞
秀作です。
ストリーは、シンプルです。
湾岸戦争勃発時生まれた男の赤ん坊が、病院で入れ替わってしまいます。
一人はユダヤ人、一人はパレスチナ人。思秋期を迎えた二人の青年とその二つの家族のドラマです。

写真上・右は、入れ替わった二人の青年ですが、どちらがユダヤ人かパレスチナ人かは区別がつきません。
左の男性は、サイモンとガーファンクルのガーファンクルのような風貌、右の男性はアフリカ系の男性の感じです。
ユダヤ人もアラブ人も人種ではなく、言語・文化・宗教などによるので外見からは見分けることはできないと言われています。
肌・髪・目の色なども様々、使う言語も様々で、ユダヤ人の定義は単純では無く、「誰がユダヤ人か」は複雑と言われます。
また、パレスチナ・イスラエル問題も単純では無く、複雑です。
私の考えでは、一番責任があるのは、第二次世界大戦処理を巡る、二枚舌・三枚舌のイギリス帝国主義とアメリカ帝国主義です。
しかし、この映画のテーマは、いわゆるパレスチナ・イスラエル問題ではありません。
人々の「アイデンティティとは?」 が投げかけられていると私は思います。
「アイデンティティ」と言う言葉・概念は日本語にはなじみが無いのですが、様々なもので説明される「私」の総体とでもしておきましょう。
そう、それは決して一つの概念では無く、ステレオタイプの概念では断じてありません。
日本人、アジア人、男、団塊の世代、……と無限と思える修飾語が連なり、それらの総体まさに"社会的歴史的諸関係の総和"で、
考え出すとキリがありません。
だいぶ脱線気味したついでに、最近の日本の歴史認識の問題について。
日本政府は、安重根(アン・ジュングン)をテロリストと言いますが、当時日本は紛れもなく朝鮮を併合し、朝鮮では、
合法的独立運動など許されない状況下でした。今日の尺度で「テロリスト云々」で非難するのは全くおかしいのです。
従軍慰安婦問題も同様です。官憲が関係した確固とした証拠は無いと日本政府は言いますが、敗戦時、多く資料などを焼却したのです。
官憲は一切関係しなかったという証拠を日本政府がまず挙証しなければならないので、被害を受けた人々に挙証責任があるなどとは
本末転倒・逆立ちしています。
南京虐殺問題もそうです。60万人虐殺の証拠は無いと日本政府は言います。
ナチスが何人のユダヤ人虐殺したかの証拠が必要というのでしょうか。
私は、これらの問題は今の私と私たち日本人のアイデンティティに関わる問題だと思うのです。
さて、映画に戻りましょう。2時間でこうした問題への解決などはあり得ません。
また、パレスチナとイスラエルの市民レベルの交流が問題の解決の糸口だ、と軽々に言っているのでもありません。
私がこの映画で感じたのは、ユダヤ・アラブに対するステレオタイプの見方・感じ方を捨てよう、と言うこと、
それは先に述べたキャスティングにも現れていますし、この映画はフランス映画ですが、多くの言葉が飛び交い、
たくさんの「ナショナリティ」の人々が携わったのだろうな、との思いでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

秀作です。
ストーリーはシンプルです。
サウジアラビアは、アラブ諸国のなかでも、イスラームの宗教的慣習が強いと言われています。
私を含め多くの日本人は、サウジアラビアとそこの人々の生活をほとんど知りません。映画に描かれている日常生活が、
現実を反映しているのかも私にはわかりませんが、その一端を知ることは出来るのでは無いでしょうか。
原題のWadjda は、主人公の10歳の女の子の名前です。
サウジアラビアでは、女性・女の子がしてはならないしきたりが多くあるようです。

禁じられているスニーカーを履き、ヒジャブ(スカーフ)を被らず、「お転婆」、「問題児」と言われるワジダは、
自転車がほしくてたまりません。塀の上を走るような自転車、車の上に積まれて店に運ばれるあこがれの緑の自転車です。

彼女は、一念発起して、自転車を手に入れようとします。一等賞金1000リヤル(3万円弱)のコーランの暗唱大会が開かれることになりました。
彼女は、見事優勝するのですが、自転車を買うなどとはとんもないと、賞金はパレスチナへの寄付を強制されるのでした。
落胆するワジダに彼女の母親は、緑の自転車を用意していました。
ワジダの父親は、他の女性も妻に迎えます。ワジダの母親も、自立の道を選ぼうとします。
監督はサウジアラビア初の女性監督となったハイファ・アル=マンスールさん。
------------------------------------
アラブ・ユダヤの世界を描いた今日の二本の映画は、私たちには珍しい映画でした。
「二人の息子」はちょっとヘビィだったので、「少女は自転車に乗って」は少し軽快に見ました。
「自転車」は自由の"象徴"と言うのは大げさで言い過ぎですが、すがすがしさは十分に伝わってきました。 【3月31日鑑賞】
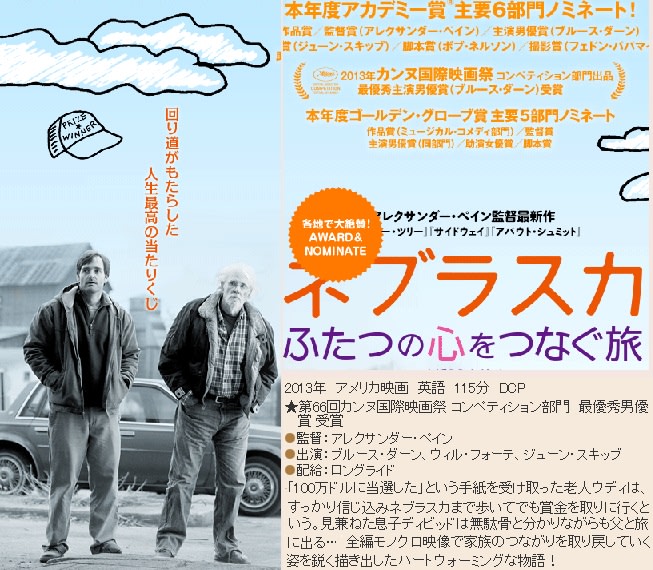
















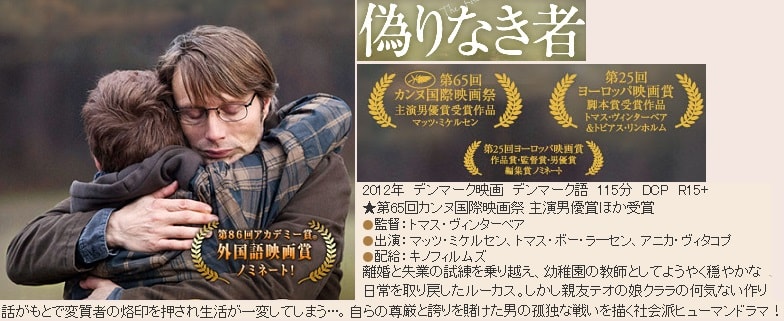












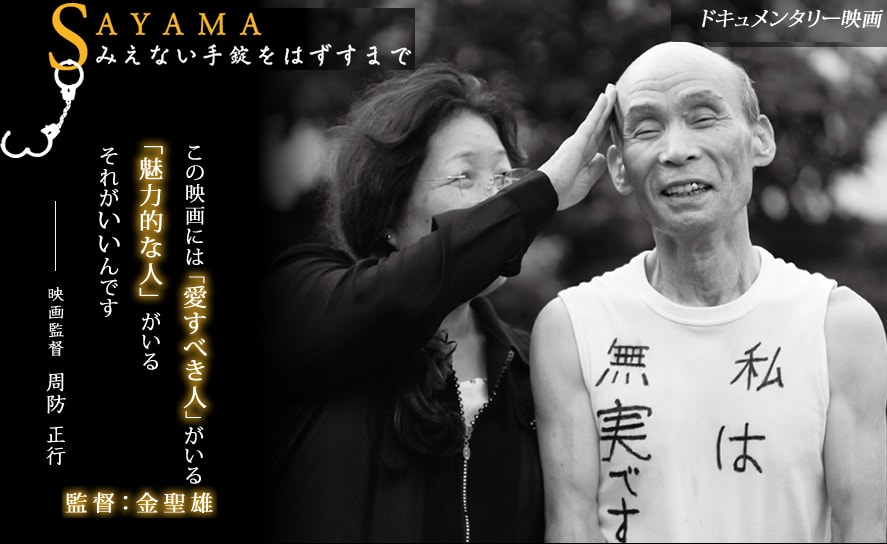








 【終わり】
【終わり】