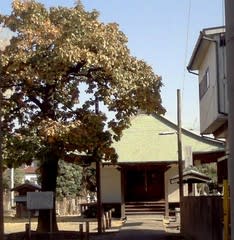南浦和~東浦和を歩く
12月29日、師走の南浦和を歩いた。
JR南浦和→
・曹洞宗守光院

・熊野神社

小さな神社であった。
・普門寺

住職のいない小さな寺で、50mほど先は河川敷で、そこは浦和競馬場であった。
入り口は鍵がかかり入れなかった。周囲は民家である。
・行弘寺

景観がちょっと変わった寺であった。右は住職宅。
・太田窪(だいたくぼ)氷川神社

・大谷口氷川神社

・福聚院観音堂

・善應院

住職のいない、とても小さな寺で、写真は隣接する神社。
・熊野神社権現神社

小さな神社で、ス-パー「サミット」の一角にあった。
・明神社

小さな神社で、これが全部だが、明神・稲荷・神明の三神社である。
・大北釋迦堂(写真なし)
門と墓地と住職と思われる民家であった。
・井沼方霊廟・薬師堂(かなり広い墓地で立派本堂が建っているのだが、入り口には頑丈な鍵がかかり、入れなかった)
・柳崎氷川神社

かなり広い境内で、小高い丘の上にある。
・天台宗観音院(子安観世音霊場)

・伏見稲荷大明神

気温は低く寒かったが、天気が良かったので、南浦和東側を初めて降り歩いた。
30分もすると暖かくなった。
たくさんの寺・神社を見たが、住職・神主がいないと思われる小さなものだった。
しかし、正月を迎える準備がされていた。
産業道路を過ぎると、とたんに風景が変わる。
昔は農村地帯だったのだろう。
今でも畑は結構あるが、農地よりは住宅地の方が多い感じだ。
大きな川はないが、小さな用水路がいくつかあった。
起伏もかなりあり、低地では谷津田、深田で大変だったろう。
大きな道から脇にはいるとそこはかつての農道のように狭く、曲がりくねっている。
お城のような立派な屋敷や一軒分もあるような門のある家などは昔の地主であろうか。
寺はそんなに多いとは思わなかった。農道沿いに墓地もなかった。
歩くだけでは、昔ここがどんな村・町であったかという想像はむずかしい。
東浦和に近づくと急に巨大な高層マンションが出現する。
武蔵野線は低地を走る。
電車が走る前は、何だったのだろう。
武蔵野線からせいぜい500mしか離れていないところを歩いた。
1km離れたら、感じはまた大きく変わるのだろう。
有名な寺社はなかったが、道もあまり迷わず、楽しいウォーキングであった。
2時間半、10キロ。
腹がすき、東浦和駅構内で立ち食いの“もりそば”を食べたが、おいしかった。
冷凍麺のようだが、それが良いのか、はわからない。
12月29日、師走の南浦和を歩いた。
JR南浦和→
・曹洞宗守光院

・熊野神社

小さな神社であった。
・普門寺

住職のいない小さな寺で、50mほど先は河川敷で、そこは浦和競馬場であった。
入り口は鍵がかかり入れなかった。周囲は民家である。
・行弘寺

景観がちょっと変わった寺であった。右は住職宅。
・太田窪(だいたくぼ)氷川神社

・大谷口氷川神社

・福聚院観音堂

・善應院

住職のいない、とても小さな寺で、写真は隣接する神社。
・熊野神社権現神社

小さな神社で、ス-パー「サミット」の一角にあった。
・明神社

小さな神社で、これが全部だが、明神・稲荷・神明の三神社である。
・大北釋迦堂(写真なし)
門と墓地と住職と思われる民家であった。
・井沼方霊廟・薬師堂(かなり広い墓地で立派本堂が建っているのだが、入り口には頑丈な鍵がかかり、入れなかった)
・柳崎氷川神社

かなり広い境内で、小高い丘の上にある。
・天台宗観音院(子安観世音霊場)

・伏見稲荷大明神

気温は低く寒かったが、天気が良かったので、南浦和東側を初めて降り歩いた。
30分もすると暖かくなった。
たくさんの寺・神社を見たが、住職・神主がいないと思われる小さなものだった。
しかし、正月を迎える準備がされていた。
産業道路を過ぎると、とたんに風景が変わる。
昔は農村地帯だったのだろう。
今でも畑は結構あるが、農地よりは住宅地の方が多い感じだ。
大きな川はないが、小さな用水路がいくつかあった。
起伏もかなりあり、低地では谷津田、深田で大変だったろう。
大きな道から脇にはいるとそこはかつての農道のように狭く、曲がりくねっている。
お城のような立派な屋敷や一軒分もあるような門のある家などは昔の地主であろうか。
寺はそんなに多いとは思わなかった。農道沿いに墓地もなかった。
歩くだけでは、昔ここがどんな村・町であったかという想像はむずかしい。
東浦和に近づくと急に巨大な高層マンションが出現する。
武蔵野線は低地を走る。
電車が走る前は、何だったのだろう。
武蔵野線からせいぜい500mしか離れていないところを歩いた。
1km離れたら、感じはまた大きく変わるのだろう。
有名な寺社はなかったが、道もあまり迷わず、楽しいウォーキングであった。
2時間半、10キロ。
腹がすき、東浦和駅構内で立ち食いの“もりそば”を食べたが、おいしかった。
冷凍麺のようだが、それが良いのか、はわからない。